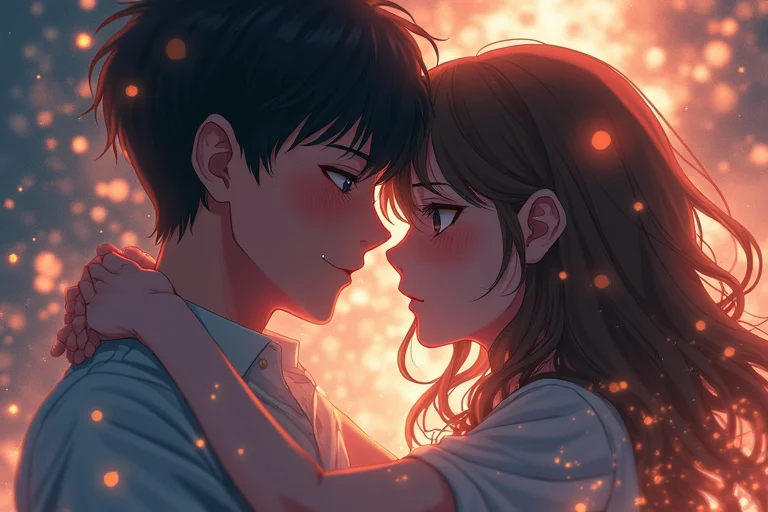第一章 星屑の暗号
歴史とは、乾いたインクの染みであり、脆くなった紙の束だ。古文書修復士である俺、相沢樹(あいざわ いつき)にとって、それは感傷を排した修復対象でしかなかった。過去は過去。俺たちが触れるのは、その物質的な残骸に過ぎない。その信条は、祖父の書斎で埃をかぶった桐の小箱を見つけるまで、揺らぐことはなかった。
先月、祖父は九十年の生涯を静かに閉じた。厳格で、口数の少ない人だった。遺品整理を淡々と進める中で見つけたその箱には、古風な真鍮の留め金がついていた。蓋を開けると、樟脳の匂いとともに、一枚のセピア色の写真と、黒い革表紙の手帳が現れた。
写真には、まだ若々しい祖父と、見知らぬ一人の女性が写っていた。柔らかそうな着物を着た、儚げな印象の女性だ。二人は寄り添い、その表情には親密な空気が漂っている。もちろん、俺の祖母ではない。
胸の内に小さな棘が刺さったような違和感を覚えながら、手帳を手に取った。ずしりと重い。ページをめくると、そこにはおよそ文字とは思えぬものがびっしりと書き連ねられていた。規則性があるようでないような、奇妙な起伏を持つ記号の羅列。まるで未知の言語か、複雑な暗号のようだ。何かの研究記録だろうか。しかし、天文学者だった祖父が、こんな不可解な記録を残すだろうか。
インクの染みは濃く、紙に深く食い込んでいるように見える。指先でそっとなぞると、微かな凹凸を感じた。まるで、書かれたもの自体が立体的な意味を持っているかのようだ。何十ページにもわたって続くその暗号をめくり続け、最後のページにたどり着いた時、俺は息を呑んだ。
そこには唯一、見慣れた日本語が、祖父の確かな筆跡で記されていた。
『星屑を掬う者へ』
乾いていたはずの歴史が、突如として湿り気を帯び、生々しい謎として俺の目の前に立ち塞がった。この女性は誰だ? この暗号の意味は? そして、祖父が未来の誰かに託した「星屑」とは、一体何なのだろうか。俺の日常は、その日を境に、静かに、しかし確実に軋み始めた。
第二章 沈黙の湖底
俺は仕事場の修復室に、祖父の手帳を持ち込んだ。最新鋭のマイクロスコープとX線分析装置が並ぶ、いわば古文書の集中治療室だ。歴史への感傷はないが、プロとしての知的好奇心はあった。この謎を、科学のメスで切り刻んでやろうと思ったのだ。
まず、紙とインクの分析から始めた。紙は戦後間もない頃に作られた和紙。インクは、当時の国産インクに含まれる鉄の成分比率と一致した。やはり、昭和二十年代前半の記録だろう。問題は、あの奇妙な記号だった。
拡大して観察すると、その「暗号」は、筆圧が異様に強いだけでなく、インクに微細な砂粒のようなものが混ぜられていることが判明した。それが、指で触れた時の独特な凹凸を生み出していた。意図的に、触覚に訴えるように作られている。点字の一種だろうか。しかし、どの点字体系とも一致しない。
手帳を丹念に調べていくと、いくつかのページに、ごく微かに地名のようなものが鉛筆で書き込まれているのを見つけた。その一つが「三日月村(みかづきむら)」。だが、現在の地図にそんな地名は存在しない。古い地図を何枚も照合し、ようやく俺はその名を見つけ出した。五十年前、巨大なダムの建設によって、湖の底へと沈んだ村だった。
途端に、ダムの冷たい水が足元に満ちてくるような感覚に襲われた。沈められた村。忘れられた歴史。手帳の謎は、さらに深い場所へと俺を誘っているようだった。
いてもたってもいられなくなり、俺は疎遠だった父に電話をかけた。
「親父、三日月村って知ってるか? じいちゃんが昔、その辺りにいたみたいなんだが」
受話器の向こうで、父が息を呑む気配がした。しばらくの沈黙の後、絞り出すような声が返ってきた。
「……どこでそれを」
「じいちゃんの遺品から。手帳が出てきてな。何か知ってるのか?」
「樹。詮索するな。過ぎたことだ」
父はそれきり、頑なに口を閉ざしてしまった。幼い頃から父との間には、見えない壁があった。祖父の話をすると、父はいつも不機悔になり、その壁は一層厚くなるのだった。父もまた、この歴史の当事者なのかもしれない。だとしたら、俺は一体、何に触れようとしているのだろう。
第三章 まなこに映る空
父の拒絶は、逆に俺の探求心に火をつけた。俺は最後の手段として、文化財解析用の多次元分光イメージング装置を手帳にかけることにした。これは、異なる波長の光を当てることで、肉眼では見えないインクの層や、消された文字を浮かび上がらせる技術だ。
モニターに、解析データがゆっくりと表示されていく。ノイズが除去され、画像が鮮明になるにつれて、俺は自分の目を疑った。あの奇妙な「暗号」のインク層の下に、全く別の、もう一つのインク層が存在したのだ。パリンプセストだ。古い羊皮紙に書かれた文字を消し、その上に新しい文字を書き重ねる手法。だが、これは紙だ。なぜ、わざわざこんなことを。
そして、モニターに浮かび上がった文字を見て、俺は完全に言葉を失った。
それは、暗号ではなかった。流れるように美しい、万葉仮名を交えた和歌だった。何首も、何首も。星の輝き、風の音、花の香り。五感を揺さぶる言葉が、そこに封じ込められていた。
『くらき夜に まなこ閉ざせば 降りそそぐ 君が言葉の 星月夜かな』
胸が締め付けられるような、切ない恋の歌。だが、腑に落ちない。祖父はこんな歌を詠むような人ではなかった。それに、この筆跡は、祖父のそれとは明らかに違う。しなやかで、どこか繊細な、女性的な筆致だ。
その瞬間、雷に打たれたように、全てのピースがはまった。写真の女性。触覚に訴えるインク。ダムの底の村。そして、和歌。
俺は震える手で、国立国会図書館のデジタルアーカイブを検索した。キーワードは「三日月村」「歌人」。そして、一つの記事に行き着いた。ダム建設前の三日月村の特集記事。そこには、村にひっそりと暮らした、一人の盲目の歌人の話が載っていた。
月村(つきむら)しずく。戦争で家族も光も失った彼女は、類稀なる才能を持ちながら、世に出ることなく、その村で詩歌を詠んで暮らしたという。若くして病で亡くなった、と記事は結ばれていた。
記事に添えられた小さな写真に写っていたのは、紛れもなく、祖父の手帳にあったあの女性だった。
もう一度、手帳に目を落とす。そうだ、これは暗号などではなかったのだ。これは、光を失った彼女のために、祖父が発明した「文字」だった。
若き日の祖父は、村の小さな天文台で働いていた。星を愛する祖父は、星を見ることができない彼女に、夜ごと空の美しさを語って聞かせた。こと座のベガの瞬き、天の川の淡い光。しずくは、祖父の言葉を道標に、心で星空を見上げ、それを和歌に詠んだ。
そして祖父は、彼女が指で触れて自分の歌を読むことができるように、砂を混ぜた特殊なインクで、彼女の和歌を一首一首、この手帳に書き留めていったのだ。俺が「暗号」だと思った奇妙な記号は、彼女の歌そのものだった。二人は、それぞれの方法で、一つの星空を共有していたのだ。
父が口を閉ざした理由も、痛いほどにわかった。祖父は、祖母と出会う前に、これほどまでに深く、一人の女性を愛していた。しかし、その恋は彼女の死によって、永遠に叶わぬものとなった。父は、母への気遣いと、父自身が抱えるであろう複雑な感情から、この物語をずっと胸の内に封印してきたに違いない。
第四章 掬われた言葉
全ての謎が解けた時、俺はただ、呆然と手帳を見つめていた。乾いたインクの染みだと思っていたそれは、誰にも知られなかった愛と、喪失の物語の結晶だった。歴史とは、決して過去の遺物などではない。それは、時を超えて誰かの心を揺さぶり、今を生きる我々の内に流れ込んでくる、熱い血潮のようなものなのだ。
数日後、俺は車を走らせ、三日月村が沈んだダム湖を訪れた。広大な湖面が、夕陽を浴びて静かにきらめいている。この静寂の水の下に、かつて祖父としずくが空を見上げた村が眠っている。
日が落ち、空には満天の星が輝き始めた。都会では決して見ることのできない、圧倒的な光の粒。祖父は、この星空を、愛する人にどう伝えたのだろう。
俺は、いつの間にか暗記してしまった歌を、静かに口ずさんだ。
「くらき夜に まなこ閉ざせば 降りそそぐ 君が言葉の 星月夜かな」
風が湖面を渡り、俺の頬を撫でた。それはまるで、遠い過去からの返事のようだった。ドライだったはずの俺の心は、祖父たちの生きた証に触れ、知らなかった温かい感情で満たされていた。
仕事場に戻った俺は、持てる技術のすべてを注ぎ込み、祖父の手帳を修復した。そして、浮かび上がった和歌の数々を、美しい和綴じの本に仕立て直した。本のタイトルは、迷わず『星月夜の歌』とした。
完成した本を、父に手渡した。父は無言でページをめくり、そこに記された和歌を一つ一つ、指でなぞるように読んでいた。やがて、その肩が小さく震え始め、父の目から一筋の涙がこぼれ落ちた。
「親父が…こんな歌を遺していたとはな…」
それは、俺が初めて見る、父の涙だった。その日、俺と父は、初めて祖父の本当の心について語り合った。長年、俺たちを隔てていた厚い氷が、静かに溶けていくのを感じた。
俺は今も、古文書修復士として働いている。だが、もう歴史を乾いたインクの染みだとは思わない。一枚一枚の紙の向こうには、名もなき人々の、掬われるのを待っている無数の想い―星屑―が眠っている。
『星屑を掬う者へ』
祖父のメッセージは、俺の仕事そのものへの、そして生き方そのものへの道標となった。夜空を見上げるたび、俺は思う。歴史とは、死者のための記録ではない。未来へと何かを伝えようとする、生者たちの切なる願いなのだと。そして俺は、その声なき声を掬い上げる者として、ここにいる。