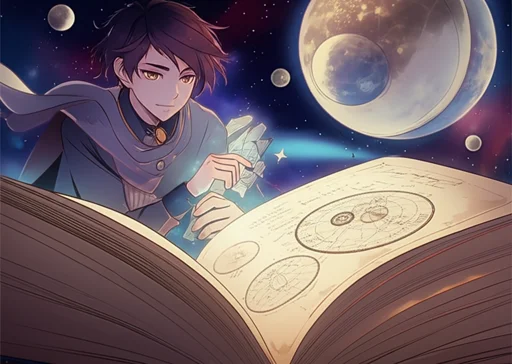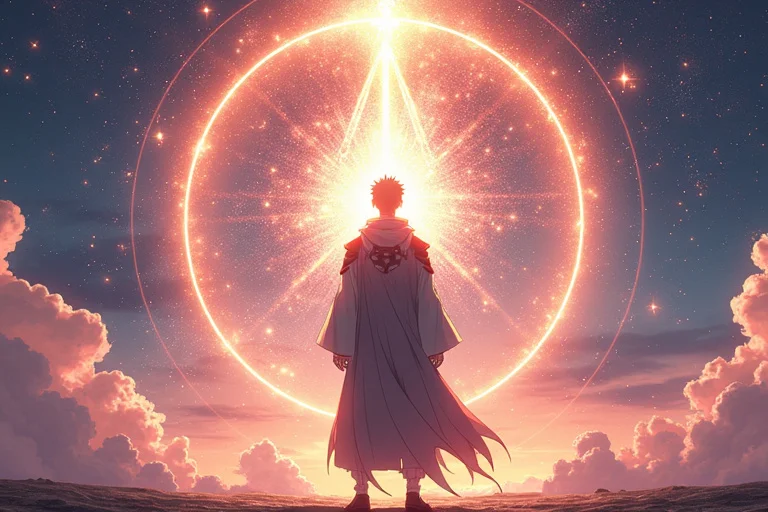古書修補室の空気は、百年物の墨と和紙の匂いで満ちている。埃の一つ一つにさえ、過ぎ去った時間の重みが宿っているようだった。ここで働く僕、柏木伊織(かしわぎいおり)にとって、この静謐な空間こそが世界のすべてだった。僕の仕事は、歴史の波間で砕け散った紙片を拾い集め、元の姿に繋ぎ合わせること。指先に全神経を集中させ、失われた物語の声を聴く、気の遠くなるような作業だ。
ある雨の日、古びた桐の箱が持ち込まれた。依頼主は、山深い寺の老いた住職だった。箱の中には、黒い炭の塊にしか見えない紙の束が、かろうじて形を保って横たわっていた。
「『星詠みの航海日誌』の、唯一の断簡にございます」
住職の声は、雨音に溶け入りそうなくらいにか細かった。室町時代、幕府の命に背き、未知の大海へ漕ぎ出したとされる異端の船乗り、月人(つきひと)の記録。歴史の闇に焼失したはずの幻の書物だった。
「どうか、この魂を救っていただきたい」
住職は深く頭を下げた。不可能に近い挑戦だ。だが、僕の心は燃え立つような期待に震えていた。歴史の空白を、この手で埋められるかもしれない。それが僕の課題であり、目的となった。
修復作業は困難を極めた。ピンセットでつまむだけで崩れ落ちそうなほど脆い断簡。僕は息を殺し、特殊な薬品で紙の繊維を一つ一つ強化していく。数週間が経ち、ようやく数枚の紙片が繋ぎ合わされた時、そこに浮かび上がった文字を見て、僕は息を呑んだ。
『――空ニ双月(そうげつ)カカル夜、我ラノ舟ハ進ム。星ノ羅針盤ノミガ頼リ』
双月? 星の羅針盤? それはまるで御伽噺だ。さらに修復を進めると、『人魚(うおびと)の歌を聞きし島』『天より降り注ぐ光の魚』といった、荒唐無稽な記述が次々と現れた。同僚たちは「長旅で正気を失った船乗りの妄想だろう」と笑った。だが、僕にはそうは思えなかった。その墨痕には、嘘や創作では決して生まれ得ない、鬼気迫るほどの切実さが宿っていたからだ。なぜ彼は、こんな記録を残したのか。この文字の向こうに広がる真実の景色が見たい。僕は寝食を忘れて、墨が滲む紙の海に深く深く潜っていった。
作業が佳境に入った、月が冴え渡る夜だった。最後の一片を繋ぎ合わせようとしたその瞬間、工房の窓から差し込む月光が、修復された日誌の上に一条の光の帯を描いた。次の刹那、信じられないことが起きた。日誌に使われた特殊な墨が、月光に呼応するように青白い光を放ち始めたのだ。
文字が揺らめき、僕の目の前で渦を巻く。和紙の匂いが潮の香りに変わり、インクの黒が深い海の藍へと溶けていく。僕は立っているはずなのに、足元がおぼつかない。気づけば、僕は満天の星が降り注ぐ、夜の甲板に立っていた。
そして、空を見上げて絶句した。そこには本当に、大小二つの月が、静かな光を湛えて浮かんでいたのだ。
「……ようやく、ここまで辿り着いたか」
振り返ると、風に髪をなびかせた男が立っていた。日誌の主、月人だ。彼の瞳は、幾多の星を映した夜空のように澄み切っていた。
「驚くことはない。お主が紡いだのは紙ではない。我らの魂の航路そのものだ」
幻影のはずの彼の声が、僕の魂を直接揺さぶる。
「我らの見た真実は、お主らの歴史では物語になったと聞く。それでいい。それでこそ、我らの旅は意味を持つ。だが、忘れないでくれ。我らは確かにここに在り、この空を見ていた。この星の海を、舟で渡っていたのだと」
彼の姿が、星屑のようにきらめきながら薄れていく。双月の光が、僕の頬に涙の跡を優しく照らした。
意識が戻ると、僕は工房の椅子に座っていた。日誌の光は消え、それはただの古びた和紙の束に戻っていた。しかし、僕にはもう分かっていた。歴史とは、教科書に記された事実の連なりだけではない。それは、時代を超えて受け継がれる魂の記憶なのだと。
翌日、僕は報告書を提出した。そこにはこう記した。「損傷が激しく、記述の多くは航海中の過酷な環境が生んだ船乗りの創作、もしくは寓話と推察される」と。
日誌を住職に返すと、彼はそれを大切そうに胸に抱き、「これで、月人の魂もようやく還るべき場所へ還れます」と静かに微笑んだ。
工房に戻り、窓の外に広がる夕暮れの空を見上げる。もちろん、月は一つしか昇らない。だが、僕の瞼の裏には、あの夜見た双月と、星の海を駆ける一艘の舟の姿が、今も鮮やかに焼き付いている。
僕の仕事は、歴史を修復すること。それは、忘れられた人々の魂の声を拾い上げ、未来へとそっと手渡すことなのだ。新たな誇りを胸に、僕は次の「声なき声」が収められた桐箱へと、静かに手を伸ばした。