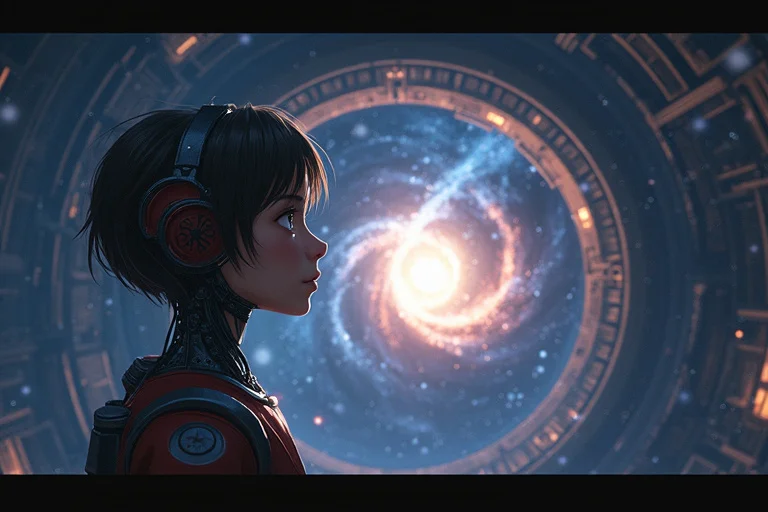宇宙(そら)の配達人が無愛想に差し出したのは、古びたデータパッドと、黒曜石のような奇妙なペンダントだった。差出人の名は、サイトウ・ケンジ。十年前に音信が途絶えた、俺の祖父だ。
「遺産相続のお知らせです。受取サインを」
俺、アキトはしがない軌道整備士だ。日々の暮らしに精一杯で、伝説の惑星改造師(テラフォーマー)だった祖父のことなど、とうに忘れていた。遺産といっても、どうせガラクタだろう。ため息混じりにサインをすると、配達人は無言で立ち去った。
データパッドを起動すると、祖父の無骨な文字が浮かび上がった。
『アキトへ。これを読んでいるということは、ワシはもうこの世にいないのだろう。お前に一つの星を遺す。銀河辺境区画にある、ケイロン-βだ。ペンダントを忘れずにな』
添付されていた航路データが示す先は、かつて祖父がテラフォーミングに失敗し、莫大な負債を抱える原因となった「死の星」だった。
借金のかたに取られたと聞いていたが、なぜ今さら俺に。馬鹿馬鹿しいと思った。だが、退屈な日常から逃げ出したい衝動が、俺の背中を押した。有り金をはたいて中古の宇宙船を買い、俺はケイロン-βへと向かった。
数週間の航行の末にたどり着いたその星は、噂に違わぬ地獄だった。メタンの嵐が吹き荒れ、赤茶けた大地はひび割れ、生命の気配はどこにもない。船のセンサーが「生命居住不可能」の警告をけたたましく鳴らしている。
「じいさん、あんたは俺に何をさせたかったんだよ……」
途方に暮れた俺の目に、地平線にそびえる奇妙な塔が映った。自然物とは思えない、人工的な螺旋構造。祖父の遺したメモには、こう書かれていた。『塔の頂へ』。
宇宙服に身を包み、俺は塔を登った。頂上には、ペンダントがぴったりとはまりそうな窪みのある祭壇があった。言われるがままにペンダントをはめ込むと、黒曜石がまばゆい光を放ち始めた。
その瞬間、足元の大地が脈動した。地鳴りが轟き、空を引き裂くようにオーロラが舞う。まるで惑星そのものが巨大な心臓となって鼓動を始めたかのようだ。俺は立っていられず、その場に崩れ落ちた。
そして、直接、脳内に声が響いた。
《――システム、再起動。認証キー、照合完了。マスター、アキト・サイトウ。お待たせいたしました。私は統合環境制御知性体、コードネーム“ケイロン”です》
声は言った。この星は、岩石と金属の塊ではない。祖父が設計した超巨大な生体演算惑星(バイオプラネット・コンピュータ)なのだと。テラフォーミングの失敗は偽装で、本当はケイロンを銀河の利権争いから隠すためのものだった。そして俺の持つペンダントは、ケイロンを起動し、その主となるための唯一の鍵だったのだ。
「じいさんは……星を創ったのか」
《正確には、星を“育てる”ための土壌を創りました。マスター。あなたの指示で、私は進化します》
俺とケイロンの対話は、巨大企業「オムニ・メガロニクス」のセンサーに筒抜けだった。ケイロン-βが発する未知のエネルギーパターンを察知し、彼らは即座に調査艦隊を派遣してきたのだ。
数日後、惑星軌道上に巨大な戦艦が出現し、威圧的な通信が入った。
「ケイロン-βの不法占拠者へ告ぐ。速やかに惑星の所有権を放棄し、立ち去れ。これは最終勧告である」
「断る」俺は即答した。「ここは、俺の星だ」
その言葉が、戦いの合図となった。
オムニ社の降下艇が、雨のように大気圏へ突入してくる。
「ケイロン! やれるか!」
《マスターの指示と、私の計算があれば》
俺の思考が、ケイロンの五感となる。俺が「盾を」と念じれば、大地が隆起して物理的な障壁となり、「雷を」と叫べば、大気がイオン化して強力な電磁パルスを放つ。俺はまるで神になったかのように、惑星そのものを手足のように操った。地形を変え、天候を操り、侵略者たちを翻弄する。俺は惑星の庭師となり、害虫を駆除する。
だが、敵の物量は圧倒的だった。旗艦から放たれた主砲が、俺の司令塔である塔を掠め、ケイロンとのリンクが乱れる。システムに過負荷がかかり、ケイロンの悲鳴が脳内に響いた。
《マスター……エネルギー残量が……限界です》
絶体絶命。これが、俺の旅の終わりか。
その時、祖父の最後のメッセージが脳裏をよぎった。『アキト、星を信じろ。お前自身を、信じろ』。
信じる?何を。この化け物じみた星をか?いや、違う。じいさんが託したのは、力じゃない。ケイロンという、相棒だ。
「ケイロン。俺の全部、お前にやる。お前の全部、俺にくれ」
俺は覚悟を決めた。最終プロトコル――“シンクロ・ドライブ”。術者とシステムを完全に融合させ、潜在能力を解放する禁じ手だ。失敗すれば、俺の意識は惑星規模のデータの中に霧散する。
《……了解、マスター。あなたのすべてを、私に》
ケイロンの声が応える。俺の意識は肉体を離れ、どこまでも広がっていった。地殻を流れ、マントルを駆け、核の熱を感じる。俺がケイロンになり、ケイロンが俺になった。もはや俺と星の境界はない。
眼前に迫るオムニ社の艦隊。もはやそれは脅威ではなかった。俺はただ、静かに“息”をした。
惑星の核から引き出されたプラズマが、地表の一点に収束する。それは、星が放つ咆哮。超高密度のエネルギービームが、漆黒の宇宙を切り裂き、オムニ社の旗艦を正確に貫いた。
一瞬の閃光の後、巨大な戦艦は宇宙の塵と化した。残された艦隊は、その信じがたい光景に恐れをなし、蜘蛛の子を散らすように撤退していった。
戦いが終わると、俺の意識はゆっくりと身体に戻ってきた。目の前には、信じられない光景が広がっていた。赤茶けた大地は青々とした草原に変わり、澄み切った空には白い雲が浮かび、生命の源である水が川となって流れていた。
《見てください、マスター。私たちが創った、私たちの庭です》
ケイロンの声は、以前よりもずっと温かく、優しく響いた。俺は、祖父が本当に遺したかったものを理解した。それは星ではなく、無限の可能性と、信頼できる相棒だった。
俺は空を見上げ、深く息を吸った。新しい星の匂いがした。
俺は惑星庭師。この星の守り手。俺とケイロンの物語は、まだ始まったばかりだ。