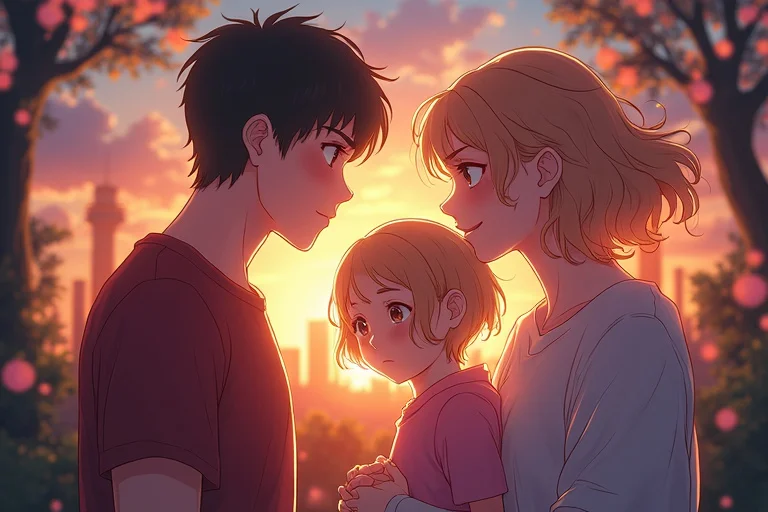第一章 謎の遺言
鈴木健太、三十ニ歳、独身。市役所市民課勤務。彼の人生は、まるで新品の定規のように真っ直ぐで、正確で、そして驚くほど面白みに欠けていた。口癖は「規定によりますと」。彼の世界では、すべての事象が条例か内規によって分類され、処理されるべきだった。感情の揺れは業務の非効率化を招くだけのノイズであり、ユーモアに至っては理解不能なバグでしかなかった。
そんな健太の灰色の日常に、ある日、一滴の原色が垂らされた。三ヶ月前に亡くなった祖父の遺品整理でのことだ。物静かで、いつも難しい顔をして縁側でお茶をすすっていた祖父。健太にとって祖父は、「寡黙」と「頑固」を体現したような、尊敬はすれど親しみは感じられない存在だった。
押し入れの奥、古い布団の間に挟まっていたのは、一冊のくたびれた大学ノートだった。表紙には、かすれた文字で『ネタ帳』とある。健太は眉をひそめた。ネタ? あの祖父が? 恐る恐るページをめくると、そこには健太の知らない祖父がいた。
『ショートコント:タイムマシン』
『漫才:天国と地獄』
稚拙なイラストと共に、ぎっしりと書き込まれたアイデアの数々。まるで、売れない芸人の楽屋からこぼれ落ちてきたような、熱っぽく、どこか滑稽な言葉の羅列。健太は混乱した。あの、挨拶さえ「うむ」の一言で済ませていた祖父が、こんなものを書いていたとは。
そして、最後の一ページ。そこには、他のページとは明らかに違う、震えるような力強い筆跡で、こう記されていた。
『最後のネタ「人生」を、我が愛する孫、健太に託す。
こいつを完成させられるのは、お前だけだ。
合言葉は、笑いの神様がくれたアレだ。忘れるなよ』
健太は呆然と立ち尽くした。「最後のネタ、人生?」「合言葉?」意味が分からない。脳内のデータベースをどれだけ検索しても、該当する条例は見当たらない。ただ一つ確かなのは、健太が知る祖父のイメージが、ガラガラと音を立てて崩れ去ったことだけだった。彼の正確無比だった日常に、初めて「イレギュラー」という名の、巨大なクエスチョンマークが突き刺さった瞬間だった。
第二章 笑いの殿堂とミスター・マニュアル
祖父の「ネタ帳」を解読しようにも、手掛かりはゼロに等しかった。健太は有給休暇を申請し、ノートに唯一記されていた地名、場末の商店街にある演芸場『笑いの殿堂』の錆びついたドアを叩いた。規定外の行動に、心臓がいつもより少しだけ速く脈打つ。
中から現れたのは、眠そうな目をした初老の男だった。橘と名乗ったその支配人は、健太の祖父の名を聞くと、一瞬だけ目を見開き、すぐに興味なさそうに煙草の煙を吐き出した。
「ああ、鈴木さんな。昔、よく顔を出してたよ。ただの、つまらん客だったがな」
橘の言葉は、健太の期待をあっさりと裏切った。
それでも諦めきれない健太は、演芸場に通い詰めた。そこは、健太の生きてきた世界とはまるで違う、カオスそのものだった。舞台袖では若手芸人たちが奇声を発し、客席からは容赦ないヤジが飛ぶ。すべてが非効率で、非論理的。健太は、動物園の檻に入れられた事務ロボットのように、ただただ居心地の悪さを感じていた。
ある日、出演予定の芸人が一人、食中毒で倒れた。舞台に穴が空く。パニックになる芸人たちを尻目に、橘がおもむろに健太を指差した。
「おい、あんた。時間までなんかやって繋げ」
「は? 私がですか? 規定によりますと、私は部外者であり……」
「うるせえ。いいからやれ。祖父さんのこと、何か思い出すかもしれねえぞ」
その一言に、健太は抗えなかった。
舞台に上がった健太は、直立不動でマイクを握りしめた。頭は真っ白。脳裏に浮かぶのは、市民課の業務マニュアルだけだ。
「えー……本日は、かくも大勢の皆様にお集まりいただき、誠にありがとうございます。えー、まず、住民票の写しの請求についてですが……」
客席が、シン、と静まり返る。ヤジさえも凍りついた空間で、健太は延々と行政手続きの説明を続けた。それはもう、放送事故だった。
だが、数分後。客席の隅から、クスクスと笑い声が漏れ始めた。やがてそれは、じわじわと全体に伝播していく。
「なんだこいつ、シュールすぎるだろ」
「目が本気(マジ)なのがヤバい」
健太の真面目さが、常軌を逸したレベルに達した時、それは意図せずして「笑い」に転化していたのだ。舞台袖で見ていた橘は、苦虫を噛み潰したような、それでいてどこか懐かしむような、複雑な表情を浮かべていた。健太はと言えば、ウケた理由が全く理解できず、ただただ困惑するばかり。彼はその日、芸人仲間から『ミスター・マニュアル』という、不名誉なんだか名誉なんだか分からないあだ名を授かった。
第三章 ハッピー・エンドの真実
健太は、なし崩し的に『笑いの殿堂』の舞台に立ち続けることになった。相変わらず彼のネタは「行政手続き講座」だったが、そのあまりの無自覚さと生真面目さが、カルト的な人気を呼び始めていた。健太自身は、祖父の「合言葉」を見つけられない焦りと、自分の行動の不可解さに、毎夜、頭を抱えていた。
そんな中、演芸場の存続をかけた一大イベント『笑いの殿堂・感謝祭』の日がやってきた。健太も出演者リストに名を連ねていた。プレッシャーで押し潰されそうになりながら、彼は最後の望みをかけて、祖父のネタ帳をもう一度、隅から隅まで読み返した。
その時だった。ノートの最後のページ、厚紙になった裏表紙の内側に、何か硬い感触があることに気づいた。慎重に紙を剥がすと、中から一枚のセピア色の写真が滑り落ちた。
そこに写っていたのは、派手な衣装で肩を組み、満面の笑みで舞台に立つ二人の若者だった。一人は、間違いなく若き日の祖父。そして、もう一人は――驚くべきことに、演芸場の支配人、橘さんだった。写真の裏には、インクで『ハッピー・エンド 初舞台記念』と書かれていた。
健太は写真を握りしめ、橘の元へ走った。
「これは、どういうことですか!?」
写真を突きつけられた橘は、しばらく無言で煙草をふかしていたが、やがて観念したように、重い口を開いた。
「……そうだ。俺とあいつは、コンビだった。『ハッピー・エンド』。天才だって、言われてたよ」
橘の声は、静かだった。
「あいつは、笑いのためにすべてを捨てられる男だった。俺もそうだ。二人でてっぺん獲るって、本気で信じてた。だが、あいつは……消えたんだ。俺たちの未来がかかった、一番大事なテレビ出演の日に、何も言わずに」
橘の目に、長年の怒りと、それ以上の悲しみが滲んでいた。
「何年も経ってから、風の噂で聞いたよ。お前の親父さん……あいつの息子が、大きな事故に遭ったらしいな。あいつは、夢を捨てて、家族を選んだんだ。俺を裏切ってな」
健太は息をのんだ。祖父が夢を諦めた理由。それは、自分の父のためだったのだ。あの寡黙な祖父の背中には、そんな壮絶な過去が隠されていたのか。
「おじいちゃんの『最後のネタ』って……」
「さあな。だが、あいつが最後に残したもんがあるなら、ろくなもんじゃねえだろ」
吐き捨てるように言う橘の横顔を見ながら、健太は、ネタ帳の最後の一文を思い出していた。『合言葉は、笑いの神様がくれたアレだ』。その瞬間、健太の脳裏に、雷に打たれたように、遠い記憶が蘇った。
あれは、健太がまだ五歳の頃。高熱を出して寝込んでいた健太を、祖父が見舞いに来てくれた。いつも難しい顔の祖父が、その日一度だけ、健太を笑わせようとしてくれたのだ。それは、お世辞にも上手いとは言えない、ただ目をひん剥いて口を歪ませた、とんでもなく不細工な変顔だった。あまりに唐突で、あまりに下手くそで、熱に浮かされた健太は、それでも腹を抱えて笑った。祖父は照れ臭そうに、「……これはな、『幸福のイカヅチ』っていう、ありがたい顔なんだ」と言った。
合言葉は、それだ。
第四章 人生という名の最高のネタ
『笑いの殿堂・感謝祭』の舞台。健太の出番が来た。客席は満員だった。誰もが、あのシュールな『ミスター・マニュアル』の行政講座を期待している。
しかし、マイクの前に立った健太は、いつもと違った。深呼吸を一つすると、彼は静かに語り始めた。
「規定によりますと、私はここで皆様を笑わせるべきです。しかし、今日だけは、規定違反をお許しください」
ざわめく客席。健太は続けた。
「僕の祖父は、昔、コメディアンでした。相方がいました。でも、ある日、夢を捨てました。家族のために」
健太は、舞台袖で険しい顔をして立つ橘を見つめた。
「その人は、祖父を裏切り者だと思ったかもしれません。でも、祖父は、日記にこう書いていました。『最後のネタ“人生”を、孫に託す』と」
健太の声が、少し震えた。
「僕は、ずっとその意味が分かりませんでした。でも、今なら分かります。祖父にとって、夢を諦めて、不器用に、ただひたすら家族のために生きた人生そのものが、最高に誇らしくて、最高に愛おしい、たった一つのネタだったんだと」
客席は、水を打ったように静かになった。
「これから、祖父から僕に託された、その最後のネタを披露します。合言葉は、『幸福のイカヅチ』!」
健太は、両の拳を固く握りしめた。そして、次の瞬間。
彼は、記憶の底から引っ張り出した、あの日の祖父の変顔を、全力で、渾身の力で、やってのけた。
それは、やはり技術的には全く面白くなかった。ただ、不器用な男が必死に誰かを笑わせようとしている、痛々しいほどの真摯さだけがあった。
一瞬の沈黙。
次の瞬間、客席から爆笑が……起きなかった。
代わりに、誰かのすすり泣く声が聞こえた。それは、舞台袖に立つ橘だった。彼の肩は小刻みに震え、顔は涙と鼻水でぐしゃぐしゃになっていた。その姿を見た客が、つられてふっと笑った。その笑いは、すぐに隣の人に伝染した。やがて、会場全体が、大きな、温かい、優しい笑い声に包まれた。それは、爆笑ではなく、慈愛に満ちた微笑の連鎖だった。
健太は、その光景の中心で、泣きながら、あの下手くそな変顔を続けていた。
人を笑顔にするとは、完璧な技術や計算された構成だけじゃない。不器用でも、滑稽でも、誰かを想う一生懸命な心そのものが、人の心を打ち、温かい笑いを生むのだ。健太は、人生で初めて、そのことを魂で理解した。
後日。市役所の窓口に、鈴木健太の姿があった。
「規定によりますと、この書類は受理できません。……が」
彼はそう言うと、困り果てたおばあさんの耳元で、こっそり囁いた。
「まあ、ここだけの話、あっちの課でこう言えば、なんとかなるかもしれませんよ」
そして、悪戯っぽくウインクをした。おばあさんは、きょとんとした後、花が咲くように笑った。
健太の人生は、もう灰一色ではなかった。時々、週末には『笑いの殿堂』の舞台に立ち、相変わらずシュールなネタでスベっているらしい。でも、その顔は、とても楽しそうだ。
健太の机の上には、今も祖父のネタ帳が置かれている。その最後の一ページには、健太自身の字で、こう書き加えられていた。
『おじいちゃん。最後のネタ、最高だったよ。
僕の人生も、なかなか面白いコメディになりそうだ』