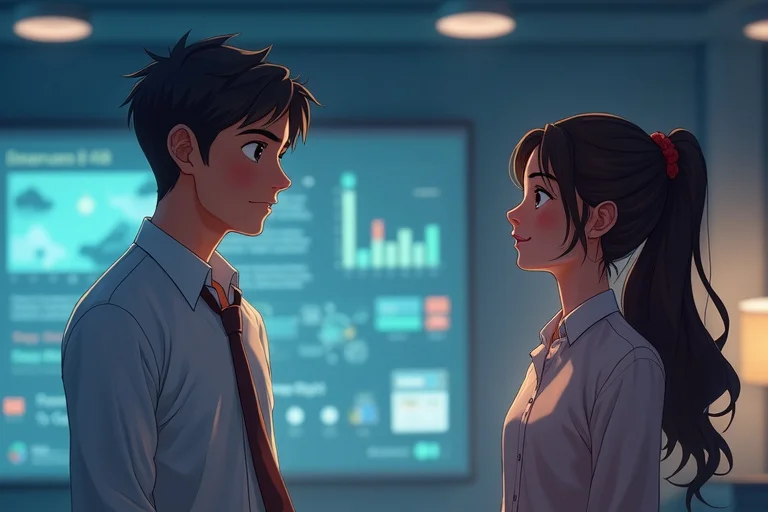第一章 天災は忘れた頃にやってくる(というボケ)
佐藤誠、三十五歳、市役所防災課勤務。彼の人生は、几帳面という言葉をコンクリートで固めたような、真面目さと誠実さだけで構成されていた。彼のデスクは常に完璧に整頓され、カバンの中にはミニサイズの防災キットと栄養補助食品が常備されている。趣味は、過去の災害事例に関する論文を読むこと。そんな彼が、ここ数週間、夜も眠れないほどの深刻な懸念を抱えていた。
「課長、やはりこれは異常です」
月曜の朝一番、佐藤は血走った目で防災課の島田課長に詰め寄った。手には、彼が不眠不休でまとめた分厚い資料が握られている。
「市内各所に設置した微小振動計のデータです。先々週から、人間の体には感じられないレベルの群発的な地盤振動が観測されています。これは、プレート境界で巨大なエネルギーが蓄積されている兆候の可能性があります。過去の巨大地震の前にも、同様の事例が……」
佐藤の言葉は、切迫感と純粋な危機感に満ちていた。しかし、眼鏡の奥で真剣に眉をひそめる彼の表情を見た島田課長は、ぷっと吹き出し、肩を叩いた。
「はっはっは、佐藤くん、朝からキレッキレだなぁ!その真顔で言うのがまた面白いんだよ。『プレート境界で巨大なエネルギー』だって?新しいネタか?いいねぇ、スケールがでかい!」
「いえ、ネタでは……本気です!」
「わかってる、わかってる。その『本気です!』ってツッコミ待ちのフリだろ?俺もまだまだだな、すぐ乗っちまう」
佐藤は愕然とした。なぜ、通じないのか。彼の真剣な警告は、ここ最近、常に高度なジョークとして解釈されていた。きっかけは些細なことだった。先月、防災訓練の講評で、彼が真顔で「津波から逃げるとき、百メートル走で十秒を切れる方以外は、決して振り返らないでください。ちなみに私は十二秒フラットです」と注意喚起したところ、会場がドッと沸いたのだ。それ以来、佐藤誠の真面目な言動はすべて、「シュールな防災コント」として消費されるようになってしまった。
同僚たちは、彼を親しみを込めて「師匠」と呼ぶようになった。
「師匠、おはようございます!今日のネタ、楽しみにしてます!」
「師匠、この前の『土砂災害の危険区域に住む者は、常に自分の体重以上の土嚢を背負う覚悟を持つべき』ってやつ、最高でしたよ!」
佐藤は違うのだと、これは命に関わる真剣な話なのだと、何度も説明しようとした。だが、説明すればするほど、「フリが丁寧すぎる」「設定が細かい」「さすが師匠、芸が細かい」と、事態は悪化の一途をたどるばかりだった。彼の額に浮かぶ冷や汗は情熱の証と見なされ、こわばる表情は絶妙な「間」だと絶賛された。
今日もまた、彼の魂の叫びは、朝のオフィスに快活な笑い声となって吸収されていく。デスクに戻った佐藤は、窓の外に広がる平和な街並みを見ながら、誰にも理解されない巨大な孤独と、日に日に大きくなる不気味な地鳴りの幻聴に、ただ一人、震えるしかなかった。
第二章 災厄のエンターテイナー
佐藤誠の意図しない「芸」の噂は、風に乗ったタンポポの綿毛のように、市役所の壁を軽々と越えていった。地元のケーブルテレビ局のディレクターが、その評判を耳にするまでに時間はかからなかった。
「防災課に、とんでもない逸材がいるらしいじゃないですか!」
ディレクターの灰田は、興奮を隠せない様子で島田課長にまくし立てた。
「その名も『マコト師匠』!真顔で壮大な防災フリをかまし、日常に潜む危機を笑いに変えるという、新しいジャンルのコメディアン!ぜひ、うちの地域情報番組に出ていただきたい!」
話が自分のデスクに届いたとき、佐藤は血の気が引くのを感じた。冗談ではない。テレビに出て、あの誤解を公共の電波に乗せて拡散させるなど、悪夢以外の何物でもない。
「お断りします。私はお笑い芸人ではありません。市民の安全を守るのが仕事です」
彼はきっぱりと、しかし声の震えを抑えきれずに断った。すると、灰田はポンと膝を打って満面の笑みを見せた。
「素晴らしい!その謙虚さ!『芸人ではない』と言い切ることで、逆に芸のリアリティを高める高等テクニック!ますます惚れ込みましたよ、師匠!」
「ですから、師匠では……」
「わかってますって!そういう照れ隠しも芸のうち!さあ、行きましょう、最高の舞台をご用意しますから!」
有無を言わさず、佐藤はスタジオに連行された。スポットライトの熱が、彼の不安をじりじりと炙る。目の前には、人の良さそうな笑顔を浮かべた司会者と、期待に満ちた目でこちらを見る観覧客。もう後戻りはできなかった。
「さあ、今、巷で話題のニューヒーロー!防災課の星、マコト師匠にご登場いただきましょう!」
割れんばかりの拍手に迎えられ、佐藤は硬い足取りでステージ中央に進んだ。彼の脳裏には、ただ一つの使命感だけが燃えていた。この機会を借りて、本当の危険を、一人でも多くの市民に伝えるのだ。
「皆さん、こんにちは。市役所防災課の、佐藤誠です」
彼のあまりに普通で、あまりに真面目な自己紹介に、スタジオは一瞬静まりかえる。そして、誰かがくすりと笑ったのを皮切りに、大きな笑いの波が押し寄せた。
「まずは完璧な『無』の表情から入る!すごい掴みだ!」と司会者が興奮気味に叫ぶ。
佐藤は構わず続けた。彼はフリップボードを使い、ハザードマップを指し示しながら、この街に潜むリアルな危険性を、学術的なデータに基づいて、必死に、真剣に、訴えた。
「この活断層が動いた場合、市街地の約六割が震度六強に見舞われ、液状化現象により、このエリアの木造家屋は九割以上が倒壊するとのシミュレーション結果が……」
彼の説明は、パニック映画の冒頭シーンさながらに鬼気迫るものだった。だが、彼の真剣さが頂点に達するほど、観客の笑いは大きくなっていく。彼のこめかみを伝う一筋の汗は、計算され尽くしたパフォーマンスの小道具に見えた。彼の震える声は、恐怖を煽るための絶妙な演出だと思われた。
「この緊迫感!このディテール!からの、一体どんな『オチ』が待っているんだー!?」
司会者の煽りに、スタジオのボルテージは最高潮に達した。佐藤は、もはや自分が何を話しているのかわからなくなっていた。ただ、目の前の人々が、腹を抱えて笑っている。その光景が、悪夢のように目に焼き付いた。
番組は大成功を収めた。佐藤誠は、本人の絶望とは裏腹に、一夜にして「災厄のエンターテイナー」として、地域にその名を知らしめることになった。彼は自分の無力さに打ちひしがれた。だが同時に、心の片隅で、奇妙な感情が芽生えていることにも気づいていた。あれほど楽しそうに笑う人々の顔を、彼はこれまで見たことがなかった。自分の言葉が、たとえ誤解された形であれ、誰かを笑顔にしている。その事実は、彼の凝り固まった心に、小さな、しかし無視できない波紋を広げていた。
第三章 笑えない冗談
マコト師匠の人気は、もはや誰にも止められなかった。ケーブルテレビの出演はシリーズ化され、彼の「防災ネタ」は子供からお年寄りまで、誰もが口ずさむフレーズになった。「タンスは凶器、ヘルメットは親友」「エレベーターは信じるな、信じるべきは自分の足」といった彼の真剣な警告は、キャッチーな迷言として人々の記憶に刻み込まれていった。
そしてついに、市の文化振興課とテレビ局の共催で、市民ホールを貸し切った大規模な「マコト師匠・防災ライブショー」が開催されることになった。佐藤は、これが最後のチャンスだと覚悟を決めた。この舞台で、すべてを終わらせる。誤解を解き、本当の危機を伝え、そして自分はただの心配性な市役所職員に戻るのだ。
当日、千人収容のホールは満員御礼だった。ステージ袖から客席を見渡した佐藤は、ごくりと唾を飲んだ。老若男女、誰もが期待に満ちた笑顔で、彼の登場を待っている。スポットライトを浴びて舞台に上がると、地鳴りのような拍手と歓声が彼を包んだ。
「師匠ー!」
「待ってましたー!」
佐藤はマイクを握りしめ、深く息を吸った。
「皆さん……今夜は、本当に大事な話をします」
静まり返る会場。観客は固唾を飲んで、師匠の壮大な「フリ」が始まるのを待っている。
「これは、笑い事ではありません」
彼の声は、決意に満ちていた。
「この街は、本当に危険な状態にあります!今すぐにでも、巨大な災害が我々を襲う可能性があります!お願いです、私の話を信じてください!今すぐ備えを!家族と避難場所を確認し、非常持ち出し袋を……!」
彼の魂からの絶叫。それは、これまでのどのスピーチよりも真に迫っていた。その瞬間、観客は今日一番の爆笑に包まれた。
「出たー!師匠の十八番、『ガチ説教』ネタ!」
「この迫真の演技!もはや芸術だ!」
「フリが長えよ師匠!」
ヤジと笑い声がホールに響き渡る。佐藤は膝から崩れ落ちそうになった。もう、だめだ。自分の言葉は、永遠に届かない――。
その、瞬間だった。
ゴゴゴゴゴゴッ……!
地獄の底から響くような、低く、重い轟音。そして、突き上げるような激しい揺れ。照明が大きく揺れ、天井からパラパラと埃が舞い落ちる。観客の笑い声が、一瞬にして悲鳴に変わった。
巨大地震。佐藤がずっと警告し続けてきた、そのものが、最悪のタイミングで現実となったのだ。
ホールはパニックの坩堝と化した。人々は我先にと出口に殺到し、将棋倒しが起きかける。佐藤自身も、あまりの恐怖に足がすくみ、その場に立ち尽くすことしかできなかった。
だが、その混沌の中で、奇妙なことが起こり始めた。
「ま、待て!師匠が言ってた!パニックになったら深呼吸だ!」
誰かが叫んだ。その声に、我に返る者が何人もいた。
「そうだ、『机の下は基本だけど、柱の多いトイレも意外と安全』って!」
「『出口に殺到するな、頭を守って揺れが収まるのを待て』!師匠のネタにあったぞ!」
「『押さない、駆けない、喋らない』!お・か・し!これ、小学校で習ったけど、師匠の言い方だと絶対忘れないよな!」
パニックに陥った人々の脳裏に、不思議なことに、マコト師匠がテレビで、職場で、真顔で語っていた「防災ネタ」が、鮮明に蘇ってきたのだ。彼のシュールで、どこかおかしい警告は、皮肉にも、どんな真面目なパンフレットよりも強く、人々の記憶にこびりついていた。
人々は、まるで示し合わせたかのように、彼の「ネタ」を実践し始めた。机の下に潜り、柱の影に身を寄せ、冷静さを取り戻していく。佐藤は、目の前で繰り広げられる光景が信じられなかった。自分が絶望の中で放った言葉たちが、今、確かに人々の命を救っている。恐怖で震える彼の目に、涙が滲んだ。それは、絶望の色ではなかった。
第四章 最高のフリ
長く、恐ろしい揺れがようやく収まった時、市民ホールは奇跡的に静けさを取り戻していた。幸いにも建物の倒壊は免れ、そして何より、あれだけのパニックにもかかわらず、死傷者は一人も出なかった。消防隊員や救護班が駆けつける頃には、人々は互いに助け合い、負傷者がいないか確認し合っていた。その中心には、呆然と立ち尽くす佐藤誠がいた。
「師匠のおかげだ……」
初老の女性が、震える声で言った。
「あなたの番組を見てなかったら、どうなっていたか。あの面白いネタが、まさか本当に役に立つなんて……ありがとう、本当にありがとう」
その言葉を皮切りに、あちこちから感謝の声が上がった。「ありがとう、師匠!」「命の恩人だ!」人々は、英雄を見るような目で佐藤を見つめていた。
佐藤は、その時、はっきりと理解した。
自分が必死に伝えようとしてきた「真実」は、それが「コメディ」という衣をまとったからこそ、最も効果的に、最も深く、人々の心に届いたのだ。真面目一辺倒だった彼の価値観が、ガラガラと音を立てて崩れ、そして新しい形で再構築されていくのを感じた。正しさを伝える方法は、一つだけではなかった。人を笑わせることもまた、人を救うための、尊い力になり得るのだ。
彼は、初めて、心からの笑顔で人々の賞賛を受け入れた。その笑顔は、少しぎこちなかったが、彼の人生で最も晴れやかなものだった。
数ヶ月後、街は少しずつ日常を取り戻し始めていた。復興イベントが開かれた公園の一角で、佐藤は小さなステージに立っていた。彼の前には、目を輝かせた子供たちが座っている。
彼は、手作りの防災紙芝居をめくっていた。その口調は穏やかで、優しく、そしてどこかユーモラスだった。
「いいかい?もし、地面が『わー!びっくりした!』って言いながら揺れたら、みんなはこのカメさんの真似をするんだ」
紙芝居に描かれた、ヘルメットを被って手足を引っ込めたコミカルなカメを指差す。
「そう、頭を隠して、ダンゴムシのポーズ!これが、世界で一番面白くて、一番大事なポーズだからね!さあ、みんなでやってみよう!」
「はーい!」
子供たちの元気な返事と、屈託のない笑い声が青空に響き渡る。それを見守る大人たちの顔にも、温かい笑みが浮かんでいた。
佐藤誠は、もはや自分の言葉がどう受け取られるかを気にしていなかった。彼はもう、孤高の「師匠」ではない。真実と笑いを両立させ、人々を笑顔で救う、ただの一人の男になっていた。
彼の人生は、壮大で、あまりにも優しい「フリ」に満ちていた。そしてそれは、彼自身が経験した中で、間違いなく最高のコメディだった。