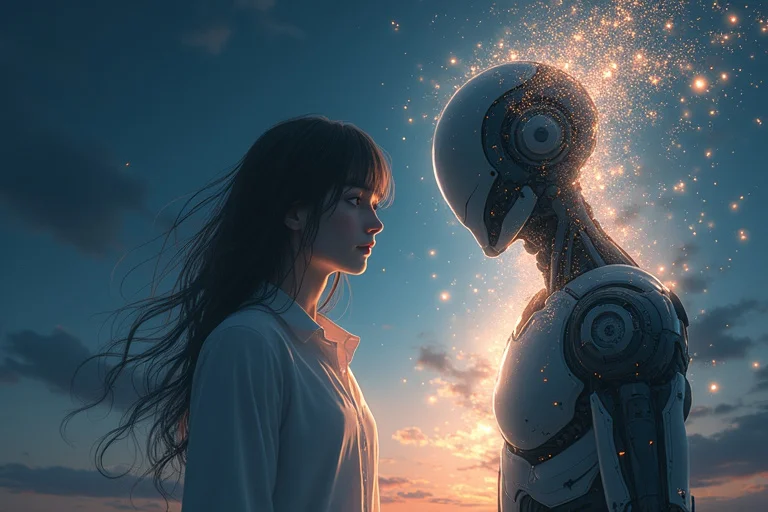第一章 静寂のディスコード
アスファルトの隙間から顔を出す雑草が、ほんの一瞬、真紫の結晶体のようにきらめいた。その刹那の変容に気づく者は、この公園にいる誰一人としていない。人々はスマホの画面に視線を落とし、あるいは子供の甲高い声に笑い、噴水の縁で眠る猫の寝息にすら気づかない。だが、僕、相沢リクの目には、その異常が網膜を焼くように映っていた。
「時間震クラスC-3。発生座標、北緯35度41分、東経139度46分。歪み率0.0012%。軽微な物理法則の非整合性を確認」
耳に装着したインカムから、冷静なAIの合成音声が響く。僕はベンチから静かに立ち上がると、コートのポケットに隠した「チューナー」と呼ばれる銀色の円筒を握りしめた。それは一見、古風な万華鏡のようにも見えるが、その実態は、狂い始めた時間流を正常なリズムへと強制的に引き戻すための、精密極まりない時空調律装置だ。
僕の仕事は「時間の調律師」。この世界で頻発するようになった微細な時間流の乱れ――時間震――を、誰にも知られず修正する存在だ。原因は不明。ある日を境に、世界のいたるところで、過去や未来の事象が現在に染み出すようになった。噴水が逆流したり、咲くはずのない花が一瞬だけ満開になったり。そのほとんどは取るに足らないディスコード(不協和音)だが、放置すればやがて世界の存在そのものを揺るがすシンフォニー・オブ・カオスへと発展しかねない。
チューナーを例の雑草にかざす。レンズの奥で、光の粒子が複雑な幾何学模様を描き、対象の時空座標をロックオンする。僕の指がデバイスの側面を滑ると、心地よい低周波の振動が空気を震わせた。世界がほんの僅かにたわみ、そして元に戻る。目の前の雑草は、もうどこにでもある平凡な緑色をしていた。
「調律完了。当該座標の時間流、安定を確認」
任務は完了した。しかし、僕の心はいつも、この瞬間に鉛のような重さを感じる。物理的な事象は修正された。だが、僕の仕事には一つ、致命的な欠陥がある。それは、人々の「記憶」までは修正できない、ということだ。
公園で遊んでいた子供が、ふと母親に尋ねる。
「ねえママ、さっきのお花、きれいだったね。紫色のキラキラしたやつ」
「お花? どこにも咲いてないじゃない。変なこと言う子ね」
母親は笑って取り合わない。子供は首を傾げ、やがてその「偽りの記憶」を忘れていくだろう。だが、その残滓はデジャヴや予知夢といった形で、人々の無意識の底に澱のように溜まっていく。僕が世界を調律すればするほど、人々の記憶と現実との乖離は広がっていくのだ。
僕はポケットから一枚の古い写真を取り出した。色褪せた写真の中では、ショートカットの快活な少女が、満面の笑みで僕の隣に立っている。星空を背景にした、古い天文台の前で撮ったものだ。
彼女の名前は、水瀬エマ。僕の幼馴染で、唯一の理解者だった。
「リクの目には、世界はどんな風に見えてるの?」
子供の頃、彼女はよくそう尋ねた。僕が人には見えない時空の歪みを「光の染み」として認識できることを、彼女だけが知っていた。その特殊な知覚能力を買われ、僕は調律師になった。
エマは今、どうしているだろうか。僕がこの孤独な仕事に就いてから、もう何年も会っていない。彼女を、僕が作り出す「記憶の迷子」の一人にしたくなかったからだ。彼女だけは、偽りのない世界で生きていてほしかった。
僕は写真をコートの内ポケットにしまい、空を見上げた。灰色に濁った空は、まるでこの世界の歪みを映しているかのようで、僕は静かにため息をついた。
第二章 天文台の残響
その警報が鳴り響いたのは、三日後の深夜だった。鳴り慣れたインカムからの警告音とは明らかに違う、けたたましいアラートが司令部から直接僕の脳に叩きつけられる。
「緊急事態! 時間震クラスA! クラスAを確認! 相沢調律師、直ちに出動せよ!」
クラスA。それは理論上存在しうる最大級の時間災害を意味する。都市が丸ごと過去の風景と入れ替わったり、そこに住む人間の存在そのものが時間軸から消去されたりするレベルの、破局的なディスコードだ。そんなものが現実に発生するなど、悪夢でしかない。
僕はベッドから跳ね起き、凍りつくような声で座標を問い返した。
「発生座標は!?」
「北緯35度38分、東経139度32分……丘の上の、古い天文台だ!」
その言葉に、僕の心臓は氷の楔を打ち込まれたように軋んだ。あの天文台。エマと二人で、飽きもせず星を眺めた、僕たちの聖域。
現場に転送ゲートで到着すると、目の前の光景に息を呑んだ。天文台を中心に、空間がゼリーのように揺らめいている。数秒おきに、現代の風景と、蔦に覆われた廃墟のような過去の風景が、激しく明滅を繰り返していた。空にはオーロラのような時空の裂け目が走り、そこから存在しないはずの星座が覗いている。これが、クラスAの時間震……。
「原因を特定しろ! このままでは半径数十キロが時空の渦に飲み込まれるぞ!」
司令官の怒声が飛ぶ。僕はチューナーを構え、震える指で解析モードを起動した。レンズの奥で、無数の光の糸が渦を巻いている。それはまるで、巨大な嵐の中心そのものだった。
「ひどい歪みだ……。自然発生的じゃない。何かが、過去のある一点に強力なアンカーを打ち込んで、無理やり現在を引っ張っている……!」
解析を進める僕の脳裏に、一つの可能性が浮かび上がった。これは事故ではない。テロだ。時間流のメカニズムを熟知した何者かが、意図的にこの災害を引き起こしている。
僕は歪みの中心――時間震の震源となっている過去の時点――を探った。チューナーが示した座標は、僕の全身の血の気を引かせるには十分だった。
『10年前。8月22日。午後9時15分』
忘れるはずがない。あの日、あの時間。それは、僕とエマの運命が、永遠に変わってしまった日だ。あの夜、この天文台で、エマは事故に遭った。そして、星を追うという彼女の夢は、その夜に砕け散ったのだ。
なぜ、あの瞬間が? 偶然のはずがない。僕は司令部の制止を振り切り、チューナーのモードを切り替えた。
「時空ダイブを敢行する。震源に直接介入し、アンカーを破壊する」
「馬鹿を言え! クラスAの中心に飛び込むなど、自殺行為だ!」
だが、僕には分かっていた。この事件の背後には、僕自身が関わっている。僕が知らなくてはならない真実が、10年前のあの夜に隠されている。僕は唇を噛みしめ、10年前の自分自身と対峙する覚悟を決めた。
第三章 忘却のフーガ
時空ダイブの衝撃は、全身の骨が軋むようだった。光の奔流が僕の体を通り過ぎ、意識が再構築されたとき、僕は10年前の天文台のドームに立っていた。空気は夏の夜特有の湿った匂いがし、窓の外からは虫の声が聞こえる。そして目の前には――若き日の僕と、エマがいた。
「すごい! リク、これ本当にあなたが作ったの?」
10年前のエマが、興奮した様子で僕の手の中にある不格好な銀色の装置を覗き込んでいる。それは、僕が調律師の見習いとして自作した、未完成のチューナーのプロトタイプだった。
「まあね。ほんの少しだけ、時間の流れを遅くできるんだ。ほら、あそこの時計を見てて」
若き日の僕は、得意げにそう言って、装置のスイッチを入れた。壁の古時計の秒針が、ほんのわずかに動きを鈍らせる。
「わあ……!」
エマが目を輝かせる。その無邪気な笑顔が見たくて、僕はいつも無茶をした。そして、その日、僕は決して越えてはならない一線を越えた。
「もっとすごいものを見せてあげる。一瞬だけ、未来の星空をここに映し出すんだ」
「未来の星空?」
「エマが宇宙飛行士になった頃に見える星だよ」
僕は禁じられていた出力制限を解除し、チューナーのエネルギーを高めた。エマを喜ばせたい。その一心だけが、僕を突き動かしていた。
その光景を、現在の僕は透明なゴーストのように、ただ見つめていることしかできなかった。そして、恐れていた瞬間が訪れる。暴走したエネルギーがプロトタイプから溢れ出し、空間に亀裂を走らせた。閃光。衝撃。機材がなだれのように崩れ落ち、エマの悲鳴がドームに響き渡った。
これが、僕がずっと目を背けてきた真実。エマの事故は、僕の未熟さと傲慢さが引き起こした悲劇だったのだ。
だが、驚くべき事実はそこからだった。僕が知っている歴史では、この事故でエマは足を負傷し、宇宙飛行士への道を断念した。しかし、僕の目の前で起きている「本当の過去」は違った。崩れた機材がエマを直撃する寸前、彼女の体が淡い光に包まれ、機材はまるで見えない壁に阻まれたかのように弾かれたのだ。彼女は無傷だった。
「……どういうことだ?」
呆然とする僕の隣に、静かな気配が立った。振り返ると、そこにいたのは、白髪の老人だった。見覚えのない顔。だが、その目は、僕と全く同じ色をしていた。
「やっと来たか、若き日の私よ」
老人は、僕が持っているものと同じ、しかし遥かに洗練されたチューナーを手にしていた。
「あなたは……未来の僕……?」
「そうだ。そして、この時間震を引き起こした張本人でもある」
老いた僕は、悲しげに微笑んだ。「私は、過ちを犯した。あの日、エマを救うために、私は未来から干渉し、事故の物理的結果だけを書き換えたのだ。彼女は怪我をせず、夢を叶え、偉大な宇宙飛行士になった」
老人の言葉に、僕は愕然とした。では、僕が知っている「エマが怪我をした記憶」は、一体何なんだ?
「忘れたのか? 我々の仕事の、最も残酷なルールを。事象は変えられても、記憶は変わらない。エマは無傷だった。だが、彼女の『記憶』の中では、事故は確かに起こり、彼女は重傷を負った。そして、その絶望の中で、君に支えられ、二人で困難を乗り越え、新しい夢を見つけた……。その10年間の記憶が、彼女の中には刻み込まれている」
未来の僕は続けた。
「彼女は、夢を叶えた幸福な現実と、君と共に苦しんだ悲痛な記憶との間で、精神の均衡を失い始めた。その矛盾が生み出した巨大なエネルギーの歪みこそが、この時間震の正体なのだ。彼女の魂が、世界そのものを引き裂こうとしている」
僕の価値観が、足元から崩れ落ちていく。世界を救うこと。それが僕の正義だった。だが、その正義が、愛する人を最も深く傷つけていた。
「どうすれば……どうすれば、エマを救える?」
「方法は一つしかない」
老いた僕は、決然と言い放った。
「事故を、本当に『起こす』のだ。私が介入する前の、本来の歴史に戻す。彼女が怪我をし、夢を諦める世界線に、すべてを戻す。そうすれば、彼女の記憶と現実は再び一致し、世界の歪みは消える。……しかし、それは、君が彼女と共に歩んだあの10年間の絆の記憶を、ただの『事実』として確定させることを意味する。君が彼女の支えであったという、その記憶の温もりを、彼女の中から永遠に奪い去ることになる」
それは、究極の選択だった。世界を救うか、エマとの絆の記憶を守るか。いや、違う。これは、エマの魂を救うための、唯一の道なのだ。僕は、老いた自分自身を見つめ返した。その瞳の奥にある、計り知れないほどの後悔と悲しみを、はっきりと理解した。
第四章 星空のレクイエム
僕は、決断した。
10年前の事故現場で、僕は自分のチューナーを構えた。未来の僕が作り出した防御フィールドを、僕自身の手で打ち消す。それは、エマを傷つけるための行為であり、同時に、彼女の魂を救うための、唯一の儀式だった。
鈍い音と共に、鉄の機材がエマの足に落ちる。悲鳴。そして、10年前の僕が、血の気の引いた顔で彼女に駆け寄る。僕がずっと記憶してきた、あの悲劇の光景が、ついに「真実」となった瞬間だった。
時空の渦が、急速に収束していく。世界の悲鳴が止み、静寂が戻った。僕の隣にいた老人の姿は、陽炎のように消えていた。彼は、役目を終え、本来いるべき時間へと還っていったのだろう。
僕は、現代の天文台へと帰還した。空の裂け目は消え、都市は平穏を取り戻している。僕のインカムには、司令部からの称賛と安堵の声が届いていたが、それはひどく遠い世界の音のように聞こえた。
僕は、ふらつく足で天文台の展望室へ向かった。そこにはもう、宇宙飛行士エマの華々しいポスターはない。代わりに、壁には地元のプラネタリウム解説員として、子供たちに囲まれて穏やかに微笑むエマの写真が飾られていた。彼女は、新しい夢を見つけていたのだ。僕との、あの10年間の中で。
ガラス戸が開き、誰かが入ってくる気配がした。振り返ると、そこにエマがいた。彼女は少し足を引きずっていたが、その表情は驚くほど晴れやかだった。
「リク……? どうしてここに?」
「……君の顔を見に」
僕がそう言うと、彼女は柔らかく微笑んだ。
「そっか。ありがとう。ねえ、リク。私、最近思うんだ。あの事故があって、宇宙には行けなくなったけど、あなたがあの時そばにいてくれたから、今の私がいるんだって。あの10年間は、私の宝物だよ」
その言葉に、僕の胸は張り裂けそうになった。彼女は、事故の記憶を、苦難を乗り越えた証として、誇りに思ってくれている。僕が消し去ろうとした絆の記憶は、今、彼女の中で確かな輝きを放っていた。
僕は世界を救ったのではない。僕はただ、愛する人の記憶と現実が、これ以上引き裂かれないように、その調律をしただけだ。そのために、彼女に怪我を負わせるという、決して許されない罪を犯した。
「元気そうで、良かった」
僕は、それだけを言うのが精一杯だった。彼女に背を向け、展望室を出る。もう、彼女の前に立つ資格は僕にはない。
一人、天文台の丘から夜空を見上げる。無数の星が、何も語らずに瞬いていた。
僕だけが知っている。この平穏な世界が、一人の女性の幸福な可能性を犠牲にして成り立っていることを。そして、彼女が「宝物」だと言ってくれたあの10年間が、僕が彼女から未来を奪った罪の証でもあることを。
この記憶こそが、僕がこれからも「忘却の調律師」として生きていくための、唯一の道標であり、そして、永遠に背負い続けるべき十字架なのだ。僕は星空に誓う。二度と、誰の記憶も、世界も、僕の傲慢さで傷つけはしない、と。
夜空の静寂が、まるで鎮魂歌(レクイエム)のように、僕の心を優しく、そして容赦なく包み込んでいた。