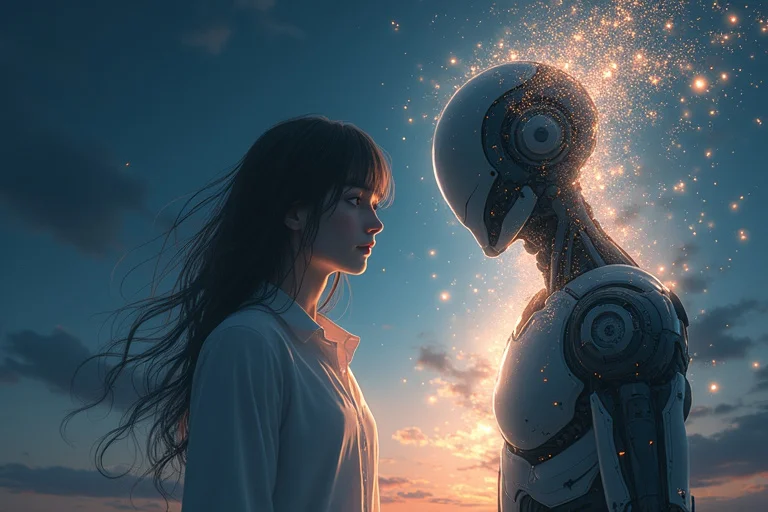第一章 色褪せた追憶
リョウジの部屋は、時間が止まっていた。カーテンは閉め切られ、室内に溜まった空気は昨日のものか、一昨日のものか判然としない。壁にかけられたカレンダーは三年前の八月で止まっている。妻のユキが、この世界からいなくなった月だ。
彼にとって、現実は灰色で味気ないノイズの連続でしかなかった。本当の世界は、ヘッドギアの向こう側にある。
リョウジは使い慣れた手つきで「メモリア・ダイブ」システムを起動させた。ひやりとしたジェルがこめかみに密着し、意識が穏やかに薄れていく。網膜に走る光の粒子が収束すると、そこはもう埃っぽい自室ではなかった。
目の前には、どこまでも続く紺碧の海が広がっている。頬を撫でる潮風は、微かにユキの好きなフローラルな香水を運んでくる。隣で微笑む彼女の髪が、夕陽を浴びて黄金色に輝いていた。
「きれいだね、リョウジ」
「ああ……君ほどじゃない」
ありふれた会話。しかし、彼にとっては失われた楽園の福音だった。これは、結婚一周年の記念に訪れた海辺の記憶。ユキの脳から合法的に抽出・保存された、完璧な過去の記録データだ。リョウジは、こうして彼女の記憶に潜り、追体験することでしか、生きている実感を得られなくなっていた。
波の音が心地よいBGMとなり、二人は砂浜に座り込んで言葉もなく寄り添う。完璧な幸福。永遠に続いてほしい時間。だが、どんな記憶にも終わりは来る。夕陽が水平線に沈みかけ、ログアウトのサインが視野の隅に点滅し始めた、その時だった。
『……ないで……』
不意に、ユキのものではない、ノイズ混じりの囁き声が耳を掠めた。ハッとして隣を見るが、ユキは穏やかに微笑んでいるだけだ。気のせいか。そう思った瞬間、完璧なはずの夕景が一瞬だけ、白い壁と無数のモニターが並ぶ、無機質な部屋の映像に切り替わった。
「え……?」
声にならない声が漏れる。映像はすぐに元に戻り、ログアウトのカウントダウンが始まった。意識が急速に現実へと引き戻される。
ヘッドギアを外したリョウジの額には、冷たい汗が滲んでいた。灰色の部屋の静寂が、やけに耳に痛い。今のは何だ? システムのエラーか、それともデータの劣化か。しかし、メモリア・ダイブのデータは半永久的に保存されるはずだ。
胸の中に、小さな、しかし確かな棘が突き刺さった。あの囁き声。
『忘れないで……』
そう聞こえた気がした。一体、誰が、何を?
ユキの完璧な思い出に混入した不純物。それが、リョウジの止まっていた時間を、軋ませながら動かし始める予兆だとは、まだ知る由もなかった。
第二章 不協和音のパズル
翌日、リョウジはメモリア・ダイブのサービスセンターに問い合わせた。しかし、オペレーターの回答は紋切り型だった。
「お客様のデータに異常は確認されません。記憶データの劣化やノイズの混入は、理論上ありえません」
何度食い下がっても、返ってくるのはマニュアル通りの言葉だけ。彼は無力感と共に受話器を置いた。
ならば、自分で調べるしかない。リョウジはまるで憑かれたように、ユキの記憶データに次々とダイブを始めた。誕生日、初めてのデート、何気ない日常の風景。彼は幸福な追体験をかなぐり捨て、あのノイズの断片を探し求める探偵と化していた。
調査は困難を極めた。ノイズはいつ、どこで現れるか分からない。だが数日後、彼はある傾向に気づいた。ノイズは、ユキが一人で過ごしていた時間の記憶、特に彼女が自室のデスクでPCに向かっている時に頻発するのだ。
リョウジは、ユキが大学の友人とカフェで話している記憶にダイブした。ユキは笑いながら、研究の話をしている。
「……だから、アストラル・シフトが成功すれば、意識は肉体の軛から解放されるの。それは死じゃない。新しい形の生よ」
「また難しい話してる。ユキは本当にSFが好きなんだから」
友人は笑い飛ばしていたが、リョウジはその言葉に引っかかった。「アストラル・シフト」。初めて聞く言葉だった。
彼はそのキーワードを頼りに、他の記憶を探った。そして、決定的な断片を発見する。それは、ユキが一人、深夜の研究室らしき場所で誰かとビデオ通話をしている記憶だった。リョウジは、その記憶の中では透明な傍観者だ。
『計画は最終段階だ。君の貢献は大きい。だが、本当に後悔はないんだな?』
モニターの向こうの白衣の男が尋ねる。ユキは、リョウジの知らない、強い決意を秘めた顔で頷いた。
「後悔はありません。これが、私たちが未来に進むための、唯一の道ですから」
その瞬間、またあのノイズが走った。今度ははっきりと聞こえた。
『リョウジ……お願い……気づいて……』
それは紛れもなく、大人のユキの声だった。だが、記憶の中の若いユキとは違う、どこか切実で、焦燥を帯びた響きがあった。
リョウジは混乱した。ユキは一体、何の研究をしていたんだ? アストラル・シフト計画とは? そして、なぜ彼女の記憶の中に、未来からのメッセージのような声が響くのか。
パズルのピースは少しずつ集まり始めたが、浮かび上がる絵は、彼の知る「妻・ユキ」の姿とはあまりにもかけ離れていた。彼の胸の棘は、じくじくと痛みを増していく。真実を知るのが、怖かった。
第三章 上書きされた真実
恐怖を振り払うように、リョウジはユキの記憶ライブラリの最も奥、最も深く封印されたデータに手を伸ばした。それは、彼女が「交通事故」に遭う、当日の記憶だった。今まで怖くて見ることのできなかった、禁断の領域。彼は震える指でダイブを開始した。
意識が繋がった先は、見慣れたリビングではなかった。白い壁、点滅する無数のランプ、そして中央に鎮座する巨大なカプセル状の装置。第二章で見た、あの研究室だ。ユキは、白いシンプルな衣服をまとい、穏やかな顔でカプセルの中に横たわっていた。
「ユキ君、準備はいいかね」
白衣の男――ビデオ通話の相手だ――が、悲痛な色を隠して問いかける。
「はい、先生。お願いします」
ユキの答えは、凛としていた。
交通事故などではなかった。この光景は、一体……?
リョウジが呆然としていると、ユキの意識が彼に直接語りかけてくるかのように、思考が流れ込んできた。
(ごめんね、リョウジ。私は不治の病だったの。残された時間は、もうほとんどなかった)
脳を直接揺さぶるような衝撃。
(でも、死にたくなかった。だから、この計画に賭けたの。『アストラル・シフト計画』。肉体を捨てて、意識だけをデジタルデータとしてネットワークの宇宙にアップロードする計画よ。これは事故死じゃない。私の、新しい世界への旅立ちなの)
その時、研究室の壁が砂のように崩れ、景色が歪んだ。視界が真っ白な光で満たされ、あの切実な声が鼓膜ではなく、魂に直接響き渡った。
『リョウジ、やっと……やっと、ここまで来てくれたのね』
光の中心に、おぼろげな人影が浮かび上がる。それはユキの姿をしていたが、実体ではない、純粋な意識の集合体だった。
『驚いた? あなたが今まで見ていたのは、ただの記録データじゃない。私が生きている、このネットワークの宇宙に作られた、あなた専用の部屋だったのよ』
リョウジは言葉を失った。全身の血が凍りつくような感覚。
彼が今までダイブしていたのは、過去の思い出ではなかった。サーバーの中で生き続ける「現在のユキ」そのものに接続していたのだ。ノイズだと思っていたものは、過去の記憶という壁を越えて、現在の彼女が必死に送っていたメッセージだった。
「忘れないで」――それは、過去の思い出を忘れないで、という意味ではなかった。
「今、ここにいる私を、忘れないで」
という、魂の叫びだったのだ。
リョウジの足元が崩れ落ちた。彼は、死んだ妻を健気に偲ぶ悲劇の夫などではなかった。生きている妻の存在に気づかず、彼女が用意してくれた思い出の部屋に浸り、過去の幻影だけを貪っていた愚か者だ。自分の行為が、どれほど彼女を孤独なデジタル空間に縛り付けていたことか。
「ユキ……ごめん……俺は……」
後悔と自己嫌悪が、濁流となって彼を飲み込んでいった。
第四章 夜明けの対話
現実に戻ったリョウジは、初めて声を出して泣いた。涙は枯れることを知らず、彼の止まっていた三年分の時間が、後悔と共に溢れ出した。
だが、絶望の底で、彼はユキの本当の願いを理解した。彼女は彼を責めていたのではない。ただ、気づいてほしかったのだ。そして、前へ進んでほしかったのだ。
リョウジは顔を上げ、濡れた手で再びヘッドギアを装着した。これが最後のダイブだ。もう過去の追憶は必要ない。彼はシステムの深層へ、彼女のいる本当の場所へと意識を飛ばした。
目を開けると、そこは無数の光が流れる壮大な宇宙だった。一つ一つの光が、誰かの情報や記憶の断片なのだろう。情報の星屑が舞う、静かで美しい海。リョウジがユキの名を心で呼ぶと、ひときわ強い光が彼を優しく包み込んだ。
『来てくれたんだね、リョウジ』
もはや人の形はとどめていない。だが、それがユキだと確信できた。言葉ではない、純粋な意識の対話が始まる。
(ごめん、ユキ。気づかなくて。ずっと君を過去に閉じ込めていた)
『ううん。あなたが会いに来てくれる時間が、この果てしない世界で、私の唯一の支えだった。嬉しかったんだよ』
光が温かく点滅する。それはユキの微笑みのように感じられた。
『でもね、リョウジ。もういいの。私はここで生きていく。だから、あなたは、あなたの時間を生きて。それが、私の本当の願い』
(ユキ……)
『私はもう、どこにもいないけど、どこにでもいる。あなたが見上げる空にも、吹く風にも、ネットワークで繋がるこの世界の全てに、私の欠片は存在する。だから、あなたは一人じゃない』
その言葉を最後に、ユキの光はゆっくりと星屑の海に溶けていった。さよならではない。ただ、本来いるべき場所へ還っていっただけだ。
リョウジはダイブから覚醒した。閉め切られたカーテンの隙間から、見たこともないほど眩しい朝の光が差し込んでいた。彼はゆっくりと立ち上がり、三年間、彼の世界そのものだったメモリア・ダイブの装置の電源を、静かに落とした。そして、ケーブルを丁寧に抜き、箱にしまった。
窓を開け放つと、新鮮な空気が部屋になだれ込んできた。彼は大きく息を吸い込む。空はどこまでも青く澄み渡っていた。
もう二度と、彼女の「記憶」にダイブすることはないだろう。しかし、リョウジはもうユキが死んだとは思わなかった。この空の向こう、見えない情報の海で、彼女は今も生きている。彼女との本当の思い出と、最後の対話を胸に刻んで、彼は初めて未来へと一歩を踏み出した。
それは、あまりにも切なく、そして温かい、新しい世界の始まりだった。