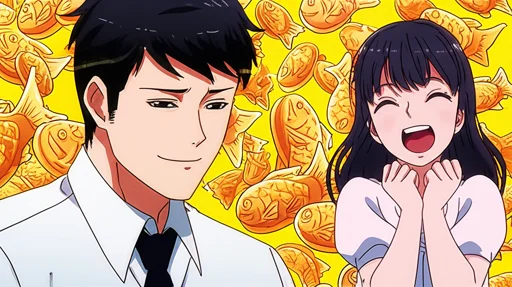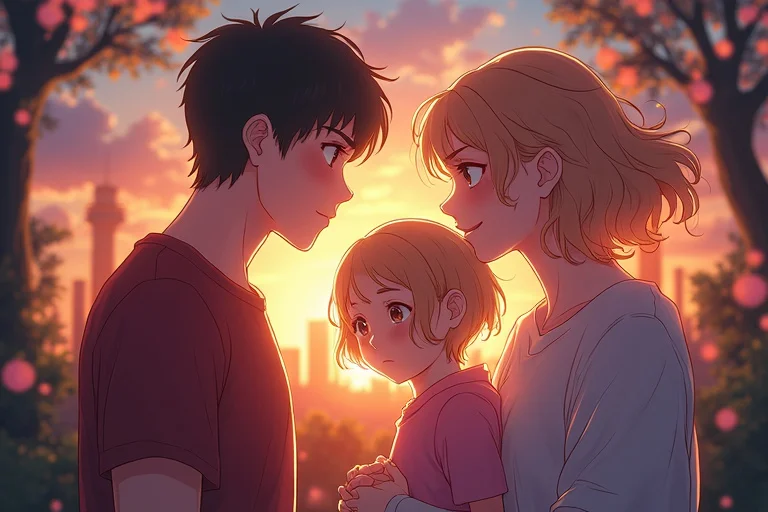第一章 公園の鳩に謝罪せよ
佐藤健太、三十五歳、市役所市民課勤務。彼の人生は、定規で引かれた線のように正確で、寸分の狂いもなかった。毎朝六時半に起床し、きっちり七分間で朝食を済ませ、アイロンの効いたシャツに袖を通す。通勤電車ではいつも最後尾車両のドア横に立ち、職場では窓口業務を淡々とこなす。彼の信条は「規則は秩序の母である」。そのあまりの四角四面ぶりに、同僚からは密かに「ミスター・コンパス」と呼ばれていたが、本人は知る由もなかった。
そんな健太の平坦な日常に、小石が投げ込まれたのは、初夏の気配が漂い始めたある週末のことだった。三ヶ月前に亡くなった祖父の遺品を整理するため、埃っぽい実家の屋根裏部屋に足を踏み入れた。祖父は健太とは正反対の、豪放磊落でユーモアを愛する人だった。健太が幼い頃、「人生は壮大なコントだ。オチを恐れるな」とよく言っていたのを思い出す。
段ボールの山の中から、健太はひときわ古びた桐の小箱を見つけた。蓋を開けると、ふわりと白檀の香りが立ち上る。中には、黄ばんだ封筒が一通だけ。表には、祖父の震えるような筆跡でこう書かれていた。
『未来の健太より、過去の健太へ』
健太は眉をひそめた。祖父の最後の悪ふざけか。しかし、好奇心には勝てず、封を破った。便箋には、見慣れない、しかしどこか自分の筆跡に似た文字が並んでいた。
『拝啓、三十五歳の俺。驚くなよ。俺は四十五歳の君、つまり未来の君だ。信じられないだろうが、これは事実だ。タイムパラドックスがどうとか、難しいことは言うな。とにかく、君の人生は、このままでは取り返しのつかないほど退屈なまま終わる。だから、俺がテコ入れすることにした。
まずは最初の指令だ。明日、近所の公園へ行き、そこにいる鳩の群れに向かって、心から謝罪しろ。理由は問うな。これは、君が世界を救う偉大なコメディアンになるための、第一歩なのだから。
追伸:鳩に謝る際は、腹の底から大声で叫ぶこと。誠意が大事だ。』
「……馬鹿げている」
健太は手紙をくしゃりと握りつぶそうとして、寸前で思いとどまった。コメディアン? 世界を救う? 公園の鳩に謝罪? 荒唐無稽にもほどがある。頭のおかしくなった人間の戯言だ。だが、その手紙から目が離せない。祖父の悪ふざけにしては、手が込みすぎている。それに、この筆跡は……。
翌日、日曜日。健太は気づけば、公園のベンチに座っていた。手には、昨日の手紙。心臓が妙に高鳴る。周囲では、子供たちの笑い声が響き、恋人たちが寄り添い、平和な時間が流れている。その中で、自分だけがとんでもないミッションを抱えている。
足元では、十数羽の鳩がのんきに首を振りながら歩き回っていた。
「規則違反だ。公衆の面前で奇声を上げるなど、条例に抵触する可能性がある」
健太は自分に言い聞かせた。しかし、手紙の『君の人生は、このままでは取り返しのつかないほど退屈なまま終わる』という一文が、脳内でリフレインする。
退屈。その言葉が、彼の胸に小さな棘のように刺さった。
健太は立ち上がった。スーツの埃を払い、ネクタイを締め直す。そして、鳩の群れの中心に向かって、ゆっくりと歩き出した。彼の額には、脂汗が滲んでいた。これは、彼の人生で最も大きな規則違反になるかもしれなかった。
第二章 不本意なインフルエンサー
「先日! 私が落としたパンくずを! 横取りするような形になってしまった件について! 誠に、申し訳ありませんでしたぁっ!」
健太は、鳩に向かって九十度の完璧な角度で頭を下げた。腹の底から絞り出した声は、日曜の長閑な公園に、場違いなほど大きく響き渡った。鳩たちは一斉に飛び立ち、周囲の人々の視線が突き刺さる。犬の散歩をしていた老婦人は目を丸くし、砂場で遊んでいた子供は母親のスカートの後ろに隠れた。健太の顔は、羞恥心でトマトのように真っ赤に染まっていた。
「……あなた、最高に面白いですね」
背後から声をかけられ、健太はビクッと肩を揺らした。振り返ると、ショートカットがよく似合う、快活そうな女性が立っていた。手にはスマートフォン。どうやら一部始終を撮影していたらしい。
「私はフリーでディレクターをやっている田中美咲と申します。今の、何かのパフォーマンスですか? アート? それとも罰ゲーム?」
「い、いえ、これはその、個人的な事情で……」
しどろもどろになる健太に、美咲は目を輝かせた。
「その訳の分からなさが良いんですよ! あなた、才能あります! 私が今度企画している深夜番組に出てみませんか?」
「滅相もございません! 私は市役所職員で、そのような柄では……」
健太は丁重に、しかし断固として断り、逃げるように公園を後にした。とんでもない一日だった。もう二度と、あんな手紙の言うことなど聞くものか。
しかし、その夜。健太が桐の小箱を恐る恐る開けると、そこには新たな封筒が置かれていた。昨日までは、確かに一通しかなかったはずなのに。
『指令その二:明日の朝、君の直属の上司である鈴木課長の、その不自然なまでに黒々とした髪型を、渾身の力で褒め称えよ。ポイントは「地毛のようですね」と付け加えることだ。』
鈴木課長のカツラ疑惑は、市民課の公然の秘密だった。それに触れるなど、自殺行為に等しい。しかし、健太は昨日の鳩への謝罪が、不思議な高揚感を伴っていたことを思い出していた。規則を破るスリルと、それをやり遂げた後の奇妙な解放感。
翌朝、健太は意を決して課長のデスクへ向かった。
「課長、おはようございます。本日のヘアスタイルも、実に精悍でいらっしゃいますね。まるで、ご自身の地毛のように自然で、素晴らしいです」
時が止まった。フロア中の職員が息を呑むのが分かった。鈴木課長はピクリと眉を動かし、健太を睨みつけた。終わった。左遷だ。健太が覚悟を決めた、その時。
「……佐藤くん。君は、正直な男だな」
課長はふっと表情を緩めると、誰にも聞こえないような小声で囁いた。「実は昨日、新しいのに替えたんだ。気づいてくれたのは君だけだよ」。
その日以降、なぜか課長は健太に優しくなった。面倒な仕事をさりげなく他の職員に回し、健太には「君はもっとクリエイティブな仕事が向いているかもしれんな」などと謎の言葉をかけるようになった。
それからというもの、健太は半信半疑ながらも「未来からの指令」を実行し続けた。「駅前で大根をマイク代わりに演説しろ」「デパ地下の試食コーナーを全制覇しろ」。その奇行の数々は、いつの間にか美咲によって隠し撮りされ、編集された動画が『謎のスーツ男、サトケン』としてネット上で拡散され始めていた。健太は、自分のあずかり知らぬところで、不本意なインフルエンサーになっていたのである。
第三章 祖父のラストジョーク
「サトケンさん、ついにこの日が来ましたよ!」
美咲の熱意と、ネットでの妙な盛り上がりに押し切られる形で、健太は小さなライブハウスのステージに立つことになった。観客は約五十人。好奇の目に晒されながら、彼はガチガチに震える足でマイクの前に立った。
「えー、どうも。サトケン、です」
声が裏返る。客席からクスクスと笑いが漏れた。もはや、まな板の上の鯉だ。健太は、今朝届いたばかりの「最終指令」を思い出した。
『指令その十:これまでの指令を、すべて正直に語れ。そして最後に、高らかに宣言しろ。「これが、俺の生きる道だ!」と。』
健太は覚悟を決めた。公園の鳩への謝罪から始まった、この一ヶ月の奇行の数々を、訥々と、しかし正直に語り始めた。市役所職員としての自分。未来からの手紙。上司のカツラ。大根での演説。彼のあまりに真面目な語り口と、行動の馬鹿馬鹿しさのギャップが、奇妙な化学反応を起こした。最初はクスクス笑いだった客席が、やがてどっと沸き、最後には腹を抱えての大爆笑に変わっていた。
健太は、人生で初めて、人を笑わせるという快感を知った。スポットライトの熱が心地いい。観客の笑顔が、胸の奥を温かくする。彼は最後に、指令通りに叫んだ。
「これが! 俺の生きる道だぁっ!」
割れんばかりの拍手。健太は、自分が生まれ変わったような気がした。
ライブ後、高揚感に包まれて楽屋に戻ると、美咲が目を潤ませて待っていた。
「最高でした、サトケンさん! 絶対にスターになれます!」
「はは、大げさですよ。でも、ありがとう。未来の俺に感謝しないと」
健太がそう言って笑った時、美咲は少し寂しそうな顔で、自分のスマートフォンを差し出した。
「サトケンさん……これ、見てください」
画面に表示されていたのは、一枚の古い写真だった。そこには、車椅子に座った健太の祖父と、若き日の美咲が、満面の笑みで写っていた。
「これ、は……」
「私、以前、介護施設でヘルパーをしていたんです。佐藤さんのおじいさま、担当でした」
健太の頭が、真っ白になった。
「おじいさん、昔、売れないコメディアンだったんですって。夢を諦めて、堅実な仕事に就いたことを、ずっと少しだけ後悔していました。そして、孫の健太くんが、自分とそっくりで、真面目すぎて人生を楽しめていないんじゃないかって、いつも心配していました」
美咲は、ゆっくりと続けた。
「あの手紙は……未来からなんかじゃ、ありません。おじいさんが亡くなる直前に、私と一緒に考えたんです。『健太の未来を変えるための脚本』です。あの子は、規則や指令には真面目に従うはずだからって……。あの桐の小箱には、私がこっそり次の手紙を補充していたんです」
未来からの手紙。それは、未来の自分からではなく、過去に逝った祖父からのものだった。健太の性格を知り尽くした祖父が、彼を退屈な日常から救い出すために仕掛けた、壮大で、あまりにも優しい「最後のいたずら」。
健太は、その場に崩れ落ちそうになった。信じていたものが、音を立てて崩れていく。怒りなのか、悲しみなのか、それとも感謝なのか。分からない感情の奔流が、彼の心をめちゃくちゃにかき混ぜていた。ただ一つ分かったのは、頬を熱いものが伝っているということだけだった。
第四章 自分で作る未来
数日間、健太は抜け殻のようになった。市役所の仕事に戻ったが、書類の文字は頭に入ってこない。祖父に騙されていた。あの優しい嘘に、まんまと乗せられていたのだ。しかし、胸の奥底では、自分を想う祖父の深い愛情を感じずにはいられなかった。あの破天荒な指令の一つ一つが、祖父からのエールだったのだ。
週末、健太は再びあの公園のベンチに座っていた。鳩たちが、何事もなかったかのように足元を歩いている。あの謝罪の日が、遠い昔のことのようだ。
「やっぱり、ここにいましたか」
美咲が隣に腰を下ろした。
「すみません、黙っていて……」
「……いいえ」健太は首を振った。「おじいちゃんは、俺に何を伝えたかったんでしょうか」
「たぶん」美咲は空を見上げて言った。「人生は、もっと馬鹿げてて、もっと笑っていいんだってこと。規則通りじゃなくても、道は作れるんだって、伝えたかったんだと思います」
その言葉に背中を押され、健太は家に帰ると、埃をかぶった桐の小箱をもう一度開けた。その底に、今まで気づかなかった一枚の便箋が張り付いているのを見つけた。それは、間違いなく祖父の筆跡だった。
『健太へ。
もしこの手紙を読んでいるなら、俺の最後のジョークに気づいた頃だろう。驚いたか?
未来は決まってなんかない。手紙に書かれた指令でも、誰かの脚本でもない。お前が、お前の足で歩いて、作るもんだ。
だから、思いっきり笑える未来を作れ。それが、じいちゃんへの最高のオチってもんさ。
じいちゃんより』
涙が、便箋の上にぽたりと落ちた。健太は嗚咽を堪えながら、何度も何度もその手紙を読み返した。そして、顔を上げると、彼の目には確かな光が宿っていた。
一ヶ月後。週末のライブハウスは、満員の客で熱気に満ちていた。ステージに上がったのは、スーツ姿の佐藤健太。客席には、美咲や、なぜかカツラを新調した鈴木課長、そして市役所の同僚たちの顔も見える。
健太はマイクを握り、少しはにかみながら、観客に語りかけた。
「えー、つい最近まで、僕、未来の自分から手紙が届いてるって、本気で信じてましてね……」
彼は、祖父が仕掛けた壮大なコントのすべてを、愛情とユーモアを込めて語り始めた。それは、天国にいる一人の不器用なコメディアンに捧げる、最高のアンサーソングだった。客席は、笑いと、そして温かい涙に包まれた。
スポットライトの中心で、健太は人生で一番の笑顔を見せた。それは、誰かの指令によって作られた笑顔ではない。彼自身が、自分の意志で見つけ出した、本物の笑顔だった。
未来は、まだ白紙の便箋だ。そこにどんな物語を書くかは、自分次第。健太は、これからたくさんの笑いと、少しの涙で、その余白を埋めていくのだろう。天国の祖父に、「最高のオチだったぜ」と胸を張って言えるように。