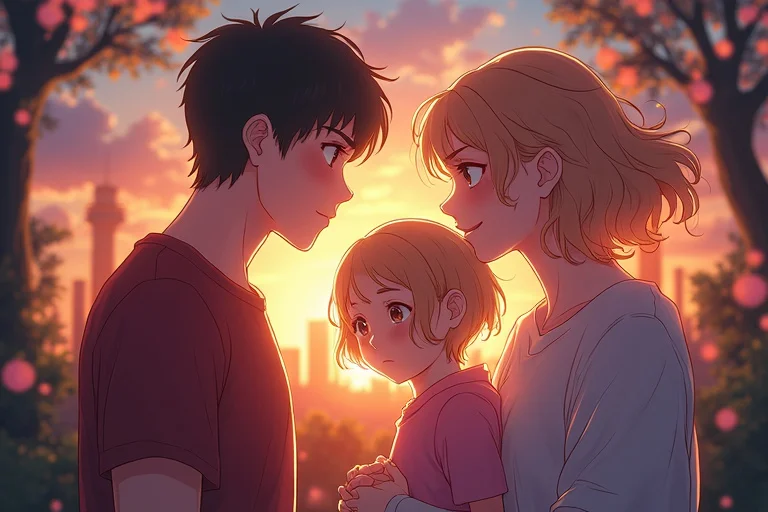第一章 恐怖はゼリー状
小鳥遊誠(たかなしまこと)の人生は、常に異物誤飲の危険と隣り合わせだった。いや、正確には「異物吐出」の危険、と言うべきか。
月曜の朝、企画三部のエースとしての彼の未来がかかったプレゼンの真っ最中、それは訪れた。目の前には役員たちがずらりと並び、その鋭い視線がレーザーのように誠の背中を焼いている。手元のレーザーポインターが、緊張で生まれた手汗のせいでぬるりと滑る。まずい、心拍数が上がる。喉の奥が奇妙にひきつり、胃のあたりから何かがせり上がってくる感覚。来た。来るな。今だけは、頼むから。
「…つきましては、このCプランこそが、我が社の次なる百年を築く礎となると、私は確信しており…ます…っ!」
最後の「ます」が妙に上擦った瞬間、誠の口から「ぽとり」と、何かが足元に落ちた。それは、手のひらサイズの、半透明でぷるぷると震える立方体。蛍光灯の光を鈍く反射するそれは、どう見ても無味無臭のコーヒーゼリー、ただしコーヒー抜きバージョン、といった代物だった。
『極度の緊張と恐怖』が具現化した物体だ。
血の気が引く。役員の一人が怪訝な顔で眉をひそめたのが見えた。「小鳥遊くん、何か落としたかね?」。その声に、誠は脊髄反射でプレゼン用の資料をわざとらしく床にぶちまけた。
「も、申し訳ありません!手が滑りました!」
散らばった紙を拾い集めるふりをしながら、素早く革靴のつま先でゼリー状の恐怖を蹴飛ばす。それは無音で滑り、隣の部長の椅子の脚に当たって、ぶるんと震えて止まった。セーフ。いや、全くセーフではない。
これが、物心ついた頃からの僕の呪い。強い感情が昂ると、その感情を象徴する意味不明な物体を、まるでカエルが虫を吐き出すかのように口から排出してしまうのだ。怒りは熱い小石に、悲しみは冷たいガラス玉に、そして喜びは、なぜかフワフワしたタンポポの綿毛になって現れる。
おかげで、僕の感情表現は極端に乏しくなった。ポーカーフェイスを貫き、何事にも動じないクールな男を演じる。それが、この厄介な体質を隠し、社会で平穏に生きていくための唯一の術だった。感情を殺せ。心を無にしろ。そう自分に言い聞かせ、僕は他者との間に分厚い壁を築いてきた。
プレゼンは何とか乗り切ったものの、自席に戻った誠はぐったりと椅子に沈んだ。隣のデスクの佐藤さんが、心配そうに声をかけてくる。
「小鳥遊さん、お疲れ様でした。顔色、悪いですよ? 大丈夫ですか?」
彼女の笑顔は、澱んだオフィスの中に咲く一輪のひまわりのようだ。その屈託のない優しさに、誠の胸の奥がきゅっと音を立てる。まずい。喉の奥に、直径一センチほどの硬い感触が生まれた。これは『ときめき』が具現化した、小さなビー玉だ。これ以上彼女と話していると、口からキラキラのビー玉を吐き出してしまう。
「…問題ない」
誠は短くそう言うと、ごくり、と喉の奥のビー玉を無理やり飲み込んだ。カラン、と胃の中に落ちる小さな音が聞こえた気がした。佐藤さんは少し寂しそうな顔をしたが、「そっか。無理しないでくださいね」と微笑んで自分の仕事に戻った。
胸が痛んだ。本当は、君と笑い合いたい。君の優しさに、ありがとうと伝えたい。でも、それができない。僕が感情を表に出せば、奇妙なガラクタを吐き出すだけなのだから。飲み込んだビー玉が、胃の底で重く、冷たく、僕の孤独を告げていた。
第二章 炭と綿毛のバーベキュー
「週末、部のみんなでバーベキューに行きませんか!?」
佐藤さんのその一言で、誠の平穏な週末は木っ端微塵に打ち砕かれた。断る理由も思いつかず、彼は半ば強制的に、感情の地雷原とも言うべきイベントへ引きずり出されることになった。
案の定、バーベキュー会場は感情の坩堝だった。肉が焼ける香ばしい匂い、同僚たちの弾けるような笑い声、川のせせらぎ。五感が刺激され、誠の体内の「異物生成工場」はフル稼働の兆しを見せていた。
「小鳥遊は相変わらず付き合い悪いなー。もっと楽しめよ」
ビールで顔を赤らめた営業部の鈴木が、馴れ馴れしく肩を叩いてきた。彼は何かと誠をライバル視している男だ。
「ほら、これでも食えよ」
鈴木がトングで寄越したのは、見るからに焦げ付いたピーマンだった。その挑発的な笑みに、誠の腹の底でカッと熱が生まれた。喉元までせり上がってきたのは、指先ほどの大きさの、チリチリと熱を帯びた『怒り』の石炭。
まずい、こんなものを吐き出したら大騒ぎになる。誠はとっさにくしゃみをするふりをして顔を覆い、手のひらに「ぽとっ」と石炭を産み落とした。熱い。火傷しそうだ。彼は何食わぬ顔でコンロに近づき、自分が持ってきた肉を焼くふりをしながら、手のひらの石炭をそっと炭火の中へ投じた。ジュッ、と小さな音がして、僕の怒りは本物の炭の中に紛れていった。完璧な隠蔽工作だった。
冷や汗を拭い、ふと視線を上げると、少し離れた場所で佐藤さんが子供たちとシャボン玉を飛ばして遊んでいた。風に乗って飛んでくる虹色のシャボン玉が、彼女の髪や肩ではじける。その光景は、まるで一枚の絵画のように美しかった。
太陽の光を浴びて楽しそうに笑う彼女を見ていると、胸の奥からふわりと温かいものがこみ上げてきた。それは、さっきの石炭とは全く違う、柔らかくて優しい感触。誠は慌ててポケットに手を突っ込み、その中でそっとそれを吐き出した。
ポケットの中で生まれたのは、陽だまりのように温かい光を放つ、小さなタンポポの綿毛だった。『幸福感』の結晶だ。指先でそっと触れると、じんわりと心が温かくなる。
しかし、誠にとって、これもまた処理すべき「ゴミ」でしかなかった。彼は周囲に気づかれないよう、そっとその場を離れ、綿毛を川に流そうとした。だが、その温かい光を見つめていると、どうしても捨てることができなかった。まるで、自分の幸せな気持ちそのものを、ゴミ箱に捨てるような気がして。
結局、彼はその綿毛をハンカチにそっと包み、ズボンのポケットの奥深くにしまい込んだ。挙動不審にポケットをまさぐる彼の姿を、遠くからじっと見つめる視線があることにも気づかずに。
第三章 心の葉の秘密
バーベキューが終わり、後片付けをしていた時だった。突然、佐藤さんが「あっ」と小さな声を上げ、その場にふらりと崩れ落ちたのだ。
「佐藤さん!?」
周囲が騒然となる。誠の心臓が氷の塊で殴られたように冷たくなった。彼女の顔は真っ青で、額には脂汗が滲んでいる。どうしよう、どうすれば。パニックと焦りが頭の中を駆け巡り、誠の喉が大きくひきつった。
「が、はっ…!」
こらえきれず、彼の口からバラバラと何かが吐き出された。それは、無数の冷たい氷の欠片だった。『強烈な不安と心配』の具現化だ。カラン、カラン、と乾いた音を立てて地面に散らばる氷片に、同僚たちが息をのむ。
「な、なんだ…? 小鳥遊、お前…」
鈴木の戸惑った声が聞こえる。終わった。僕の秘密が、最悪の形で暴かれてしまった。絶望が誠の心を支配した、その時だった。
「あらあら、派手にやりましたねぇ」
穏やかで、少ししわがれた声が響いた。振り返ると、そこに立っていたのは、いつも物静かで存在感の薄い、経理部の田中さんだった。御年六十を超えるであろう老婆が、なぜここに。
田中さんは少しも驚いた様子を見せず、地面に散らばった氷の欠片を一つ、しわくちゃの手で拾い上げた。そして、苦しむ佐藤さんのそばにしゃがみ込むと、その氷を彼女の額にそっと乗せた。
「これはただの氷じゃありませんよ。彼の純粋な『心配』が結晶になったもんだ。よく冷えるし、不思議と心も落ち着く。ただの氷嚢よりよっぽど効きます」
田中さんの言葉に、誰もが呆気にとられた。誠も、自分の耳を疑った。
「あなた、小鳥遊さん。自分が吐き出すものを、ずっと『ゴミ』だと思ってきたんでしょう」
田中さんは、誠の心を見透かしたように言った。
「それは違う。私たちの一族に稀に伝わる、それは『呪い』なんかじゃない。『心の葉(こころのは)』と言ってね、言葉にならない想いを形にする、尊い力なんですよ」
心の、葉…?
「怒りの石炭は、冷え切った心を温めるカイロになる。悲しみのガラス玉は、磨けばどんな宝石よりも美しく輝き、人の心を慰める。そして、あなたがさっき隠し持っていた幸福の綿毛は、落ち込んでいる誰かのお守りになる。あなたの感情は、決して無価値なゴミなんかじゃない。誰かを助けるための『贈り物』になる力を持っているんです」
価値観が、音を立てて崩壊していく。僕がずっと隠し、捨ててきたものは、ゴミではなかった? 贈り物…?
ポケットの奥で、ハンカチに包んだ綿毛が、かすかに温かい光を放っているような気がした。救急車が到着し、佐藤さんは病院へ運ばれていった。幸い、軽い熱中症ですぐに回復するとのことだった。
誠は、田中さんの前に立ち尽くしていた。彼女は、皺の刻まれた顔で優しく微笑んだ。
「力をどう使うかは、あなた次第。隠し続けるのも一つの生き方。でもね、その素敵な贈り物を、誰かに分けてあげる生き方も、悪くないもんですよ」
その言葉は、誠が長年築いてきた心の壁に、初めて差し込んだ一筋の光だった。
第四章 虹色オルゴールのセレナーデ
あの日以来、小鳥遊誠の世界は少しだけ色を変えた。彼はまだポーカーフェイスを崩せないし、とっさに変なものを吐き出して慌てることもあった。だが、決定的に違ったのは、彼が自分の吐き出すものを「ゴミ」ではなく、「自分の一部」として受け入れ始めたことだった。
数日後、大きなミスをしてデスクで頭を抱えている新人の後輩を見かけた。以前の彼なら、見て見ぬふりをしていただろう。だが、今の誠は違った。
彼はそっと席を立ち、給湯室へ向かうと、後輩への「大丈夫、誰にでもあるさ」という励ましの気持ちを強く念じた。喉の奥に、甘くて温かい塊が生まれる。彼はそれを手のひらに吐き出した。コロン、と現れたのは、小さな太陽のように黄金色に輝く、べっこう飴だった。
誠は後輩のデスクに戻り、その飴を「ほらよ」とぶっきらぼうに置いた。
「疲れてるんだろ。糖分でも摂っとけ」
後輩はきょとんとした顔で飴と誠を見比べたが、「あ、ありがとうございます…!」と受け取った。その飴を口に入れた後輩の表情が、少しだけ和らいだのを誠は見逃さなかった。自分の感情が、誰かの役に立った。その事実は、彼の心に静かで温かい満足感を広げた。
そして、その日の夕方。会社を出ようとした誠を、すっかり元気になった佐藤さんが呼び止めた。
「小鳥遊さん! この間は、ありがとうございました。すごく心配してくれたって、田中さんから聞きました」
彼女ははにかみながら、小さなクッキーの包みを差し出した。「これ、お礼です」。
二人きりの帰り道。夕焼けがビルとビルの間をオレンジ色に染めている。隣を歩く彼女のシャンプーの香りが、風に乗ってふわりと鼻をかすめる。誠の心臓が、今まで経験したことのないほど大きく、そして心地よく高鳴った。
感謝、尊敬、憧れ、そして、確かな恋心。全ての感情が混ざり合い、一つの美しい形になろうとしていた。もう、こらえるのはやめよう。隠すのは、もう終わりだ。
「佐藤さん」
誠が立ち止まって彼女を呼ぶ。佐藤さんが不思議そうに振り返った、その時。
誠の口から、そっと、一つの物体が吐き出された。
それは、クリスタルでできた、手のひらサイズの小さなオルゴールだった。夕日を受けて七色にきらめき、精巧な彫刻が施されている。それは、誠の純粋で、不器用で、けれど真っ直ぐな『恋心』そのものだった。
佐藤さんは目を見開いて驚いていた。しかし、彼女は逃げなかった。気味悪がるそぶりも見せなかった。彼女は、怖々と、けれど優しくそのオルゴールを両手で受け取った。
「きれい…」
彼女がそっと蓋を開ける。すると、澄んだ、それでいてどこか少し間抜けで、愛嬌のあるメロディが流れ出した。それは、誠が彼女を想う、温かくて、少し臆病で、でもキラキラした心の音色だった。
「小鳥遊さんの音、なんだか…すごく安心しますね」
そう言って、彼女は今までで一番美しい笑顔を見せた。
彼の恋がこの先どうなるのか、まだ分からない。けれど、誠はもう自分の感情を隠す必要はなかった。彼は自分の心を、不器用な形のまま、誰かに手渡す方法を知ったのだ。夕焼け空の下、鳴り響くオルゴールの音色は、世界がほんの少しだけ優しく、そしてカラフルになったことを告げているようだった。