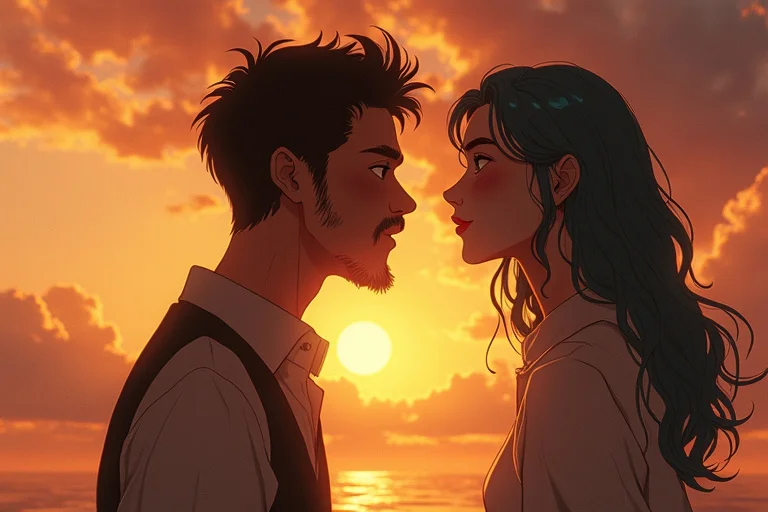第一章 灰色の煙と黄金の奔流
灰谷修一(はいたに しゅういち)、三十二歳。彼の世界は、人々の感情が色を帯びて見える。特に「笑い」という感情は、鮮烈なオーラとなって彼の網膜に焼き付いた。
それは祝福であると同時に、呪いでもあった。
都心のオフィスビル、十三階。修一が勤める会社のフロアは、常に淀んだ灰色の煙に満ちていた。課長のしょうもないダジャレに、同僚たちが浮かべる愛想笑い。それは、湿った焚き火から立ち上る煙のように、くすんだ灰色で、見る者の気管をじわりと締め付けるような不快さがあった。心からの笑いが、暖かな金色や、弾けるような虹色の粒子として見える修一にとって、この職場は一種の地獄だった。
「はは、課長! 相変わらずキレッキレですね!」
後輩の田中が口にした瞬間、その口元からぼふりと吐き出される灰色の塊。修一は思わず眉をひそめ、コーヒーをすすることで視界からそれを追い出した。カップの底に映る自分の顔は、感情という色彩を失ったモノクロ写真のようだった。
かつて、修一はお笑い芸人を目指していた。相方と二人、小さな舞台に立ち、観客の笑いを浴びるのが夢だった。しかし、彼の呪われた眼は、客席の微妙な空気までをも色として捉えてしまう。滑った瞬間に広がる冷たい青色のオーラ、作り笑いの灰色の煙。それに耐えきれず、彼は夢を捨てた。本物の笑いなど、この世界にはほとんど存在しないのだと絶望して。
その夜、修一は意味もなくネットの動画サイトを彷徨っていた。無数のサムネイルが明滅する中、ふと、一つの動画に目が留まった。黒いシルクハットに白い仮面。パントマイムだけで人々を爆笑させるという、正体不明のパフォーマー『Mr.サイレント』。再生数は、すでに数千万回を超えていた。
「どうせ、これも…」
冷めた気持ちで再生ボタンをクリックした。画面には、簡素なステージに立つMr.サイレントと、彼を取り囲む観客たち。音はない。彼はただ、見えない壁にぶつかったり、滑る床に足を取られたり、ありふれたパントマイムを演じているだけ。なのに。
次の瞬間、修一は息を呑んだ。
画面の中の観客たちから、信じられないほどの光が立ち上っていたのだ。それは、くすんだ煙などでは断じてない。一人一人の腹の底から噴き出す、純度百パーセントの黄金の光。光は粒子となり、渦を巻き、やがて巨大な奔流となって天井へと突き抜けていく。それはまるで、真夏の太陽を凝縮したような、圧倒的な熱量と輝きだった。修一がかつて一度も見たことのない、究極の「本物の笑い」。
心臓が激しく脈打った。全身の血が沸騰するような感覚。灰色の世界に、突如として極彩色の亀裂が入った。
「……いるんだ」
まだ、こんな笑いが。こんなにも純粋で、美しい光を放つ笑いを生み出せる人間が、この世界のどこかに。
修一は、モニターに映る黄金の奔流から目が離せなかった。それは、彼がとうの昔に失くしてしまった希望そのもののように見えた。
第二章 淡いピンクと廃工場の地図
Mr.サイレントに会いたい。その一心で、修一のモノクロームだった日常は、俄かに色づき始めた。彼は仕事の合間を縫って、ネットの掲示板やSNSを漁り、神出鬼没のパフォーマーの情報を集め始めた。しかし、その正体は謎に包まれており、ライブも告知なしのゲリラ形式。有力な手がかりは一向に掴めなかった。
そんなある日、修一は都心から少し離れた古書店で、サブカルチャー雑誌のバックナンバーを調べていた。その時だった。
「あの、もしかして…Mr.サイレント、お好きなんですか?」
声をかけてきたのは、エプロン姿の店員らしき女性だった。ショートカットの髪に、少しそばかすのある親しみやすい顔立ち。彼女が微笑むと、その全身から、桜の花びらのような、淡く優しいピンク色のオーラがふわりと立ち上るのが見えた。それは修一が今まで見てきたどんな作り笑いとも違う、心地よい暖かさを持っていた。
「え、あ、はい。ご存知なんですか」
「はい! 私、大ファンなんです! なかなか仲間がいなくて」
彼女は水野夏帆(みずの かほ)と名乗った。夏帆もまた、Mr.サイレントの行方を追っている一人だった。共通の目的を見つけた二人は急速に打ち解け、情報交換をすることになった。
夏帆は修一の能力など知る由もないが、彼女の存在は修一の心を少しずつ癒していった。彼女は、面白いものを見ては屈託なく笑った。そのたびに立ち上る美しいピンク色の光は、修一の周囲に漂う灰色の煙を浄化してくれるようだった。
「修一さんって、なんだか面白いですね。人が笑う瞬間を、すごく真剣な顔でじーっと見てる」
カフェで向かい合って座っている時、夏帆にそう言われて、修一はどきりとした。
「そ、そうかな。癖みたいなもので…」
「でも、その目、嫌いじゃないです。なんだか、その人の心の中にある一番綺麗なものを見つけようとしてるみたいで」
夏帆の言葉と、彼女から放たれる穏やかな光に、修一は胸が熱くなるのを感じた。人間不信のフィルター越しに世界を見ていた自分にとって、彼女の言葉は救いだった。
数週間後、ついに転機が訪れる。夏帆が、とあるハッカーのコミュニティから、Mr.サイレントの次のライブに関する暗号めいた情報を手に入れたのだ。
「『鉄の巨人が眠る場所で、沈黙が黄金に変わる時』…これ、絶対、川崎の臨海エリアにある廃工場ですよ!」
夏帆が興奮気味にスマートフォンの地図を指差す。修一の心臓も高鳴った。ようやく、あの黄金の奔流を、この目で見ることができる。
二人は入念に計画を立て、ライブ当日とされる夜、フェンスを乗り越えて廃工場の敷地へと忍び込んだ。錆びた鉄の匂いと、湿ったコンクリートの匂いが混じり合う中、奥の巨大な倉庫から漏れる微かな光と人々のざわめきが、彼らを導いていた。
あの光に、もう一度会える。修一は、隣を歩く夏帆の横顔から立ち上る、期待に満ちたピンク色のオーラを見つめながら、固唾を飲んだ。
第三章 空っぽの器と創造主
倉庫の中は、異様な熱気に包まれていた。百人ほどの観客が、即席のステージを囲んでいる。やがて照明が落ち、スポットライトがステージ中央を照らすと、シルクハットと白い仮面のMr.サイレントが、音もなく現れた。
パフォーマンスは圧巻だった。言葉を発しない彼の動き一つ一つが、観客の心の琴線を的確に震わせ、笑いを誘発していく。修一の視界は、瞬く間に黄金の光で埋め尽くされた。渦を巻き、火花を散らし、まるで銀河が生まれる瞬間を見ているかのような壮大な光景。隣の夏帆からも、これまでで一番強い、輝くようなピンクのオーラが立ち上り、涙を流しながら腹を抱えていた。
修一も笑っていた。心の底から。しかし、その興奮の最中、彼はある決定的な違和感に気づいてしまった。
ステージ上のMr.サイレント本人から、何のオーラも出ていないのだ。
人間であれば、興奮や緊張、喜びといった感情が、必ず何らかの色のオーラとして現れるはず。だが、彼の身体は、まるで魂の抜け落ちた器のように、完全に「無色」だった。観客からあれだけの黄金の光を引き出しておきながら、彼自身は、色のない空洞。それはありえないことだった。
ライブが終わり、観客たちが満足げな表情で去っていく。修一は、胸に突き刺さった違和感の正体を確かめずにはいられなかった。夏帆に少し待っているよう告げ、彼はこっそりと舞台裏へと忍び込んだ。
バックステージは、がらんとしていた。いくつかの機材が置かれているだけ。その中央に、Mr.サイレントが椅子に座っていた。そして、修一は見てしまった。
白い仮面とシルクハットを外したその下にあったのは、人間の顔ではなかった。滑らかな金属と合成皮膚、そして複雑に絡み合うケーブル。Mr.サイレントの正体は、精巧すぎるほどに精巧なアンドロイドだったのだ。
「驚いたかい?」
背後から、落ち着いた声がした。振り返ると、白衣を着た若い男が立っていた。彼の周りには、同じように白衣を着た数人の男女がいる。
「我々は、感情誘発型AI『サイレント』の開発チームだ。私はリーダーの神崎」
神崎と名乗る男は、悪びれる様子もなく言った。
「彼は、観客の表情、心拍数、瞳孔の動き、脳波の微細な変化までをリアルタイムでスキャンし、データベースと照合して、その瞬間に最も『笑い』を引き出す最適解のパフォーマンスを生成する。我々の目的は、計算によって究極の感動を創造することだ」
修一は、言葉を失った。頭を鈍器で殴られたような衝撃。彼が追い求め、心を震わせたあの「究極の本物の笑い」は、心を持たない機械が、冷徹な計算によって生み出したものだった。
「本物…じゃ、ないのか……」
絞り出した声は、自分でも驚くほどか細く、震えていた。
神崎は、憐れむような目で修一を見た。
「『本物』とは何だろうね? 君たちが感じた笑いや感動は、君たち自身の脳が作り出した電気信号に過ぎない。我々はそのスイッチを押しただけだ。きっかけが人間だろうとAIだろうと、そこに本質的な違いはない」
価値観が、音を立てて崩れ落ちていく。灰色の煙に満ちた世界で、唯一見つけた黄金の光。その光源が、空っぽの機械だったという事実。修一は、その場に崩れ落ちそうになった。
第四章 輝きの在り処
絶望が、再び修一の心を黒く塗りつぶそうとしていた。結局、この世界に本物なんてなかったんだ。計算ずくで生み出された偽りの光に、自分は踊らされていたピエロに過ぎなかった。
倉庫の外で待っていた夏帆が、彼のただならぬ様子に気づいて駆け寄ってきた。
「修一さん、どうしたんですか? 顔色が…」
修一は力なく首を振り、事の顛末を話した。Mr.サイレントがアンドロイドだったこと。あの笑いが、すべて計算によって作られたものだったこと。
てっきり彼女も自分と同じように絶望するだろうと思っていた。しかし、夏帆はしばらく黙って彼の話を聞いた後、意外なことを口にした。
「そっか…機械だったんだ」
彼女の声は、不思議なほど穏やかだった。
「でも、だから何だって言うんですか?」
「え…?」
「だって、私たちが笑ったのは事実じゃないですか。お腹がよじれるほどおかしくて、涙が出て、心がぽかぽかしたのも、全部本当だった。きっかけが何かなんて、私にはどうでもいいです。あの瞬間、私の心の中に生まれたあの気持ちは、紛れもなく『本物』でしたよ」
夏帆はそう言って、にっこりと笑った。その瞬間、彼女の全身から、いつもの、あの暖かく優しいピンク色のオーラがふわりと立ち上った。
その光を見て、修一ははっとした。
そうだ。きっかけが何であれ、それを受け取った人間の感情は、本物だ。作り笑いの灰色の煙と、心からの笑いの黄金の光。その決定的な違いを、この眼は見分けることができる。Mr.サイレントは、人々の心の中にある「本物の笑い」の輝きを、最大限に引き出すための、完璧な触媒だったに過ぎない。
重要なのは、光源が何かじゃない。光そのものの輝きだ。
自分の能力は、他人を断罪し、世界に絶望するためのものではなかったのかもしれない。偽物の中に埋もれた、小さな本物の輝きを見つけ出すために。そして、その輝きを、もっと大きく、もっと強くするために、与えられた力なのかもしれない。
「ありがとう、水野さん」
修一は、心の底から言った。「君のおかげで、目が覚めた」
その数日後、修一は古いスマートフォンの連絡先から、一つの名前を呼び出した。かつての相方だ。
「もしもし、俺だ。灰谷だ。……ああ、久しぶり。いや、大したことじゃないんだ。ただ、もう一度、やらないかと思って。お前と、漫才を」
小さなライブハウスのステージ。眩しいスポットライトを浴びて、修一はマイクの前に立っていた。客席はまだまばらだ。けれど、彼の眼には見えていた。最前列のカップルから立ち上る期待のオレンジ色。友人同士で来たらしい女性グループの、楽しげな黄色の粒子。
それは、Mr.サイレントが見せたような、天を衝く黄金の奔流ではない。ささやかで、不揃いな、人間臭い光の集まり。
でも、それでいい。それでこそ、いい。
修一は、隣に立つ相方に向かって、深く息を吸った。
「いくぞ」
相方が頷く。修一は、客席に広がる色とりどりの光のオーラを、まるで夜空の星々を眺めるように見つめた。あれが、僕たちの道しるべだ。
彼は満面の笑みを浮かべた。その瞬間、修一には確かに見えた気がした。自分自身の胸の中心から、力強く、そしてどこまでも暖かい、黄金色の光が立ち上るのを。