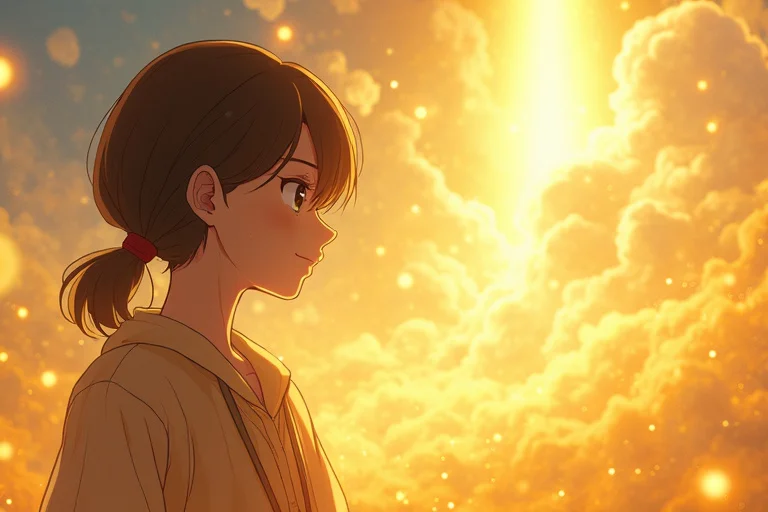第一章 膨らむ男と枯れゆく泉
僕、カミシロ・リクには秘密がある。いや、秘密というには、あまりにも見え透いている。感情が極度に高ぶると、僕の体は古びたゴム風船のように、みしみしと音を立てて膨らんでしまうのだ。そして、喜びや怒り、悲しみの頂点で、パン、と乾いた音を立てて破裂する。後に残るのは、色とりどりの紙吹雪と、しばらくして再生する僕の体だけ。
この体質のせいで、僕はいつも街一番の祭典『爆笑バトル』で優勝を逃してきた。あと一歩、審査員を笑わせれば栄光の『笑いの王冠』が手に入るという瞬間、高ぶる興奮が僕を破裂させてしまう。舞い散る紙吹雪は観客を沸かせるが、それはジョークの面白さとは関係のない、ただの見世物としての喝采だった。
僕が住む街、ワライブルクの生命線は、街の中心に湧き出る『笑いの泉』だ。泉は人々の笑い声をエネルギーに変え、街灯を灯し、家々を温める。しかし、その泉が近頃、明らかに元気をなくしていた。噴き上げる水の勢いは弱まり、夜の街路は頼りなく点滅する光に覆われている。人々の顔から笑顔が減り、市場のざわめきも、どこか乾いた響きを帯びていた。まるで街全体が、深いため息をついているかのようだった。
僕は、この静かになっていく街と、どうにもならない自分の体質が、重苦しい雲のように心にのしかかるのを感じていた。なんとかしなければ。このままでは、街も、僕自身も、しぼんで消えてしまう。
第二章 石化の伝説とパフパフマイク
街の古文書館の奥、埃の匂いが満ちた一角で、僕は答えを探していた。『笑いの泉』を蘇らせる唯一の方法。それは、伝説の『腹筋崩壊ジョーク』を見つけ出すことだった。古びた羊皮紙には、そのジョークが泉に無限の活力を与えると記されている。しかし、その記述には不吉な続きがあった。
『――そのジョークを最後に聞きし者、笑いのあまり体が硬直し、石と化したもうた』
石化の呪い。僕の背筋を冷たい汗が伝う。だが、僕には他の誰にもない切り札があった。もし本当に笑い死にするほどのジョークなら、僕は石になる前に破裂するはずだ。紙吹雪になってしまえば、呪いも効かないかもしれない。それは希望と呼ぶにはあまりに心許ない、藁にもすがるような賭けだった。
文献を読み解くと、ジョークは『沈黙の洞窟』の最奥に封印されているとあった。そして、その洞窟の扉を開けるには、奇妙な鍵が必要らしい。
僕は街外れの古道具屋で、それを見つけ出した。棚の隅で他のガラクタに埋もれていた、色褪せたラッパのようなおもちゃ。『声変わりパフパフマイク』。値札には「たまに音が出ません」とだけ書かれていた。店主の老人は、僕がそれを手に取ると、皺だらけの顔で奇妙な笑みを浮かべた。
「そいつは気まぐれな相棒さ。肝心な時に裏切るかもしれんよ」
僕はなけなしの金を払い、そのおかしなマイクを手に、夕闇が迫る街を後にした。
第三章 沈黙の洞窟
『沈黙の洞窟』は、その名の通り、息が詰まるほどの静寂に支配されていた。僕の足音が壁に反響し、まるで何者かが後をつけてくるような錯覚に陥る。湿った土と苔の匂いが、冷たい空気と混じり合っていた。
洞窟の最深部で、僕は一枚の巨大な石の扉に行き当たった。扉には奇妙な紋様が刻まれ、中央に小さな穴が空いている。古文書の記述によれば、この穴にマイクを差し込み、合言葉を唱えるのだという。
僕はごくりと唾を飲み込み、『声変わりパフパフマイク』を穴に差し込んだ。
「開け、ゴマ!」
僕の口から飛び出したのは、甲高い赤ん坊のような声だった。
「あけー、ごまー!」
扉は微動だにしない。もう一度。
「開け、ゴマ!」
今度は、地の底から響くような、しゃがれた老人の声になった。それでも扉は沈黙を守ったままだ。僕は何度も、何度も試した。媚びるような猫なで声になったり、機械的な音声になったり、マイクは僕の声を好き勝手にもてあそぶ。焦りと苛立ちで、僕の体が少しずつ膨らみ始めるのを感じた。
もうだめかもしれない。諦めかけたその時、僕はふと気づいた。古道具屋の老人の言葉。「たまに音が出ません」。そして、この洞窟の名前。『沈黙の洞窟』。
僕は最後にもう一度、マイクに向かって息を吸い込んだ。
「……」
声は出さなかった。ただ、息を吹き込むだけ。すると、マイクは期待通り、何の音も発さなかった。完全な「沈黙」。その瞬間、ゴゴゴゴ、と地響きのような音を立てて、石の扉がゆっくりと、重々しく開き始めた。
第四章 先代の王
扉の向こうに広がっていた光景は、僕の想像を遥かに超えていた。そこにいたのは、石化した悲劇の人物などではなかった。洞窟の奥にある地底湖で、一人の老人がのんびりと釣り糸を垂れていたのだ。彼は簡素な椅子に腰かけ、鼻歌まで歌っている。
「……あの、あなたが伝説の?」
僕の声に、老人はゆっくりと振り返った。その顔には見覚えがあった。街の広場に立つ銅像、ワライブルクを建国した先代の王、アルベールその人だった。
「おお、久しぶりのお客さんじゃな」
老人は悪びれもせずに言った。
「石化した男を探しておるのかね?残念ながら、あれはワシが流したデマじゃよ」
僕は何が何だか分からず、立ち尽くした。
「デマ…?では、『笑いの泉』が枯れているのは?」
「ああ、それもワシの仕業じゃ」
アルベールはこともなげに、洞窟の壁に取り付けられた巨大なレバーを指さした。それは紛れもなく、泉のエネルギー供給を司るメインスイッチだった。OFFの位置に倒されている。
「もう疲れたんじゃよ」
彼は深いため息をついた。
「『笑いの王冠』は、どんな願いでも叶えてしまう。最初は良かった。だが、人々は際限なく願い事をし始めた。天気を変えろ、宝くじを当てろ、隣の家の犬を黙らせろ…。ワシは、人々の欲望を叶えるための機械ではない。もう、笑えなくなってしまったんじゃ」
第五章 腹筋崩壊の正体
アルベールの言葉は、僕の中で怒りの炎を燃え上がらせた。
「疲れた、だと…?あんた一人の都合で、街中の人々がどれだけ苦しんでいると思ってるんだ!」
僕の声は震えていた。体が急速に熱を帯び、風船のように膨張していくのが分かった。視界の端が歪み、手足がパンパンに張り詰める。もう限界だ。
アルベールは膨れ上がる僕を見ても、慌てる様子はなかった。彼は少し困ったように眉を下げると、真剣な面持ちで口を開いた。
「まあ、待て、若者よ。お主を落ち着かせるために、ワシが命懸けで守ってきた、あの伝説のジョークを教えてやろう」
それが、僕が探し求めていた『腹筋崩壊ジョーク』。緊張が走る。僕は破裂寸前の体で、固唾を飲んで彼の言葉を待った。アルベールは咳払いを一つすると、厳かに告げた。
「ふとんが……ふっとんだ」
しん、と洞窟に静寂が落ちた。
僕の膨らんだ体から、ぷしゅー、と間の抜けた音を立てて、一気に空気が抜けていった。怒りも、恐怖も、使命感も、全てがそのくだらない駄洒落と共に霧散していく。後に残ったのは、計り知れない脱力感だけだった。
街中を巻き込んだ壮大な伝説の正体が、小学生でも言わないような、古典的な駄洒落。
僕はその場にへたり込み、乾いた笑いを漏らすことしかできなかった。
第六章 笑いのない王冠
僕とアルベールが街に戻ると、スイッチを入れられた『笑いの泉』は、以前にも増して勢いよく水を噴き上げていた。街に温かい光が戻り、人々は歓声を上げたが、真実を知ると、その表情は一様に複雑なものに変わった。怒る者、呆れる者。そして、あまりの馬鹿馬鹿しさに、ぷっと吹き出してしまう者もいた。街は、なんとも言えない微妙な空気に包まれた。
次の『爆笑バトル』が開催された日、異変が起きた。誰もが優勝を目指してしのぎを削るはずの舞台は、どこか気の抜けた雰囲気だった。挑戦者たちのジョークは冴えず、観客の笑いも乾いている。結局、その日の王者は決まらなかった。人々は気づき始めていたのだ。どんな願いでも叶う絶対的な権力よりも、隣の席の友人とくだらない駄洒落で笑い合える時間の方が、ずっと価値があるのかもしれない、と。
僕は広場の真ん中に立っていた。僕を取り囲む子供たちの期待に満ちた瞳。僕はわざと、とても面白いことを思いついたフリをして、興奮してみせた。僕の体はゆっくりと、しかし確実に膨らんでいく。子供たちが息を飲む。
そして、パン!
色とりどりの紙吹雪が、青空に舞い上がった。子供たちの甲高い歓声と、純粋な笑い声が広場に響き渡る。僕は再生しながら、初めて自分の体質を誇らしく思った。感情の爆発は、誰かを傷つけるものではない。それはただ、ささやかな祝福のように、空に彩りを添えるだけなのだ。
広場の片隅で、その光景を見ていたアルベールが、本当に久しぶりに、心の底から微笑んだ。
『笑いの王冠』は、もう誰の頭上にもなかった。笑いは、与えられるものでも、求めるものでもなく、ただそこに、人々の心の中に静かに湧き出る泉のように、存在しているのだった。