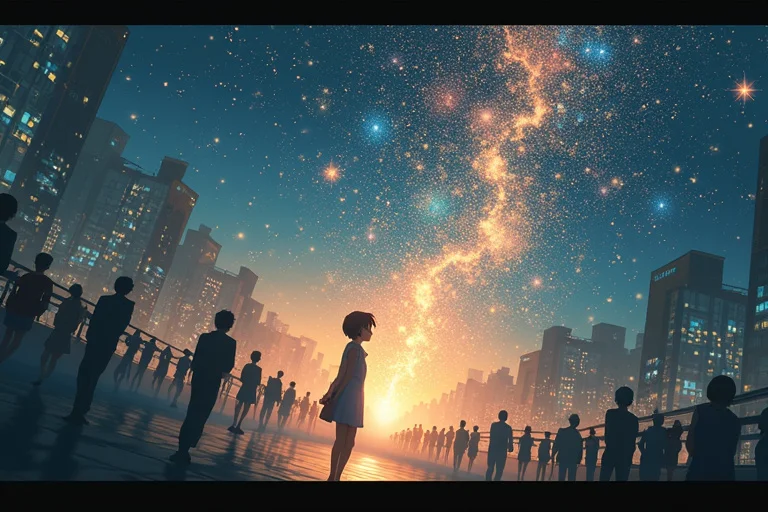第一章 どうでもいい僕と浮遊するトースト
僕、灰田空(はいだそら)には、秘密がある。それは、自分にとって「心底どうでもいいこと」を思考の俎上に載せると、物理法則が気まぐれを起こすという体質だ。具体的に言えば、僕を中心とした半径数メートルの重力が、ランダムな方向へと一時的に反転する。
今朝もそうだ。こんがりと焼けたトーストにバターを塗りながら、ふと思ったのだ。「このバターナイフの柄の部分にある小さな傷、いつ付いたんだろう」。次の瞬間、僕はダイニングチェアからふわりと浮き上がった。天井に向かって。手にしたトーストとバターナイフ、淹れたてのコーヒーが描く優雅な放物線と共に。
「うわっ、とと……!」
慌てて天井に手をつき、体勢を整える。コーヒーは無惨にも壁に茶色い染みを作り、トーストはバターの面を下にして天井に張り付いた。僕の日常とは、常にこんなカオスと隣り合わせだ。どうでもいい思考は、呼吸のように無意識に湧き出てくる。それを止める術を、僕は知らない。
テレビからは、深刻な顔をしたキャスターの声が流れていた。『……依然として、世界各地で動物会議による重要決議の否決が続いており、社会機能の麻痺が懸念されています。昨日承認されるはずだった東西を結ぶ新幹線の建設計画も否決され、関連書類は全て判読不能な状態に……』
この世界では、結婚、転職、企業の合併、果ては国家間の条約に至るまで、全ての「重要な決断」は、世界中からランダムに選ばれた動物たちの会議によって承認されなければならない。もし否決されれば、その決断に関する記憶はなぜか曖昧になり、関連書類はインクが滲んでぐしゃぐしゃになる。それが、この世界の絶対的な法則だった。
僕は天井からゆっくりと床に降り立ちながら、溜め息を吐いた。社会の混乱と、僕個人の混乱。二つのカオスが共鳴しているようで、気分が滅入る。天井に張り付いたトーストを虚ろな目で見上げながら、またどうでもいいことを考えていた。「天井の壁紙の模様、よく見ると小さな星が隠れてるな……」
第二章 連絡官は珈琲の染みを指さした
その日の午後、玄関のチャイムが鳴った。ドアを開けると、そこに立っていたのは、スーツをきっちりと着こなした、涼しげな目元の女性だった。手には分厚いファイルを持っている。
「灰田空さんですね。私、内閣府所属、動物会議連絡調整室の鳩山凛と申します」
彼女はそう言って、一枚の名刺を差し出した。紙の質感から、これが非常に「重要」な書類であることが伝わってくる。
「はあ……」
「単刀直入に申し上げます。最近、あなたの周辺で頻発している突発的な局所重力異常について、お話を伺いに来ました」
鳩山と名乗る女性は、僕を値踏みするように見つめている。その視線は鋭く、まるで僕の思考の隅々まで見透かそうとしているかのようだ。彼女をリビングに通すと、その視線はすぐに壁のコーヒーの染みに吸い寄せられた。
「これも、その……現象の一環ですか?」
「ええ、まあ。今朝のコーヒーが少々、アクロバティックな旅をしまして」
僕は曖昧に笑った。鳩山さんは手にしたファイルをぱらぱらとめくり、一枚のグラフを僕に見せた。「これは、ここ一ヶ月の日本における原因不明の器物損壊および浮遊現象の発生件数です。そして、その震源地のほとんどが、このアパートを中心に同心円状に広がっている」
彼女の言葉は、僕の秘密の核心を正確に撃ち抜いていた。観念して、僕は自分の体質についてぽつりぽつりと話し始めた。どうでもいいことを考えると、重力が反転してしまうこと。それを自分でコントロールできないこと。
鳩山さんは眉一つ動かさずに僕の話を聞いていたが、やがて深く頷いた。「なるほど。あなたのその『どうでもいい思考』が、現在の世界的な混乱と無関係ではないかもしれません」その声は、冗談を言っている響きではなかった。むしろ、藁にもすがるような必死さが滲んでいた。
第三章 空白の承認用紙
鳩山さんに連れられて、僕は薄暗い政府の資料保管室にいた。黴と古い紙の匂いが鼻をつく。彼女が取り出したのは、例の動物会議で否決されたという議案書の数々だった。どれもこれも、まるで水に浸かったかのようにインクが滲み、文字は判読不能。紙自体も奇妙によれて、ぐしゃぐしゃになっていた。
「これが否決された書類です。記憶の曖昧化と共に、物理的にもこうなってしまう」
しかし、と彼女は指をさす。ぐしゃぐしゃになった紙の中央、本来なら議長の承認印が押されるべき場所だけが、不自然なほど真っ白な空白として残っていた。まるでそこだけ聖域であるかのように、インクの滲みも紙の歪みも及んでいない。
「全ての否決された書類に、この『空白』が残されています。まるで、議長がここに何かを描き足されるのを待っているかのように……」
鳩山さんの真剣な横顔を見ながら、僕はまた、どうでもいい思考の渦に囚われていた。「この蛍光灯、チカチカしてるな。寿命かな。LEDに替えた方が電気代も安いんだろうか……」
その瞬間、僕の足が床から離れた。
「わっ!」
「灰田さん!?」
資料室の中を、僕と数冊の古いファイルがゆるやかに舞う。慌てて棚に捕まろうとした拍子に、ポケットからメモ帳とボールペンが滑り落ちた。宙でくるくると回転するメモ帳のページに、ボールペンの先が偶然触れる。カツン、という小さな音と共に、そこには何とも言えない、線の震えた奇妙な図形が走り書きされていた。
第四章 アルパカ議長、沈黙す
「これを持って、議長に会うしかありません」
僕が床に戻ると、鳩山さんは床に落ちたメモ帳を拾い上げ、その奇妙な落書きを真剣な目で見つめていた。彼女の瞳には、狂気とも希望ともつかない光が宿っている。有無を言わさず、僕は彼女に腕を引かれ、動物会議の議場へと続く重々しい扉の前に立たされていた。
議場は、巨大なドーム状の空間だった。古い木の匂いと、様々な動物たちの体臭、そして張り詰めた空気が混じり合っている。中央の最も高い席に、その存在はいた。長い首、柔和そうな瞳、しかしその全身から放たれる威厳は凄まじい。純白の毛に覆われた、アルパカ議長だった。彼の周りには、カピバラの書記官、ナマケモノの法務官、フクロウの顧問などが静かに控えている。
鳩山さんが前に進み出て、事の経緯を説明しようとした。しかし、アルパカ議長はゆっくりと首を横に振るだけ。その琥珀色の瞳は、ただ虚空を見つめている。そして、低く、しかし議場全体に響き渡る声で呟いた。
「まだ、見つからぬか。あの『余白』を満たす、至高の『無意味』が」
その絶望的とも言える雰囲気に、僕は完全に呑まれてしまった。緊張が極限に達すると、僕の思考は安全装置が働くかのように、どうでもいい方向へと逃避を始める。
(アルパカの毛って、一頭からセーター何着分取れるんだろう……)
(あのカピバラ、さっきから瞬き一つしてないな……)
(この床の石畳、一枚だけ模様が逆向きだ……)
思考が連鎖する。そして、僕の体感がふっと軽くなった。次の瞬間、議場全体を巻き込む、これまでで最大規模の重力反転が起こったのだ。
議長の威厳も、書記官の冷静さも、全てが宙に舞った。フクロウが羽ばたき、ナマケモノがゆっくりと天井に向かっていく。荘厳な椅子も、山積みの書類も、そしてアルパカ議長自身さえもが、スローモーションのように浮遊を始めた。カオス。まさに、世界の縮図のような光景だった。
第五章 奇跡のコラボレーション
大混乱の議場で、僕のポケットから再びあのメモ帳が滑り落ちた。それは、重力と慣性の法則が狂った空間を、まるで運命に導かれるかのようにひらひらと舞い、ゆっくりと浮遊するアルパカ議長の目の前で、ぴたりと静止した。
ページは、あの奇妙な落書きが見えるように開かれていた。
線の震えた、猫のようでもあり、雲のようでもある、何とも形容しがたい、しかし間違いなく「心底どうでもいい」と断言できる絵。
アルパカ議長の琥珀色の瞳が、その落書きを捉えた。時間が、止まったように感じられた。やがて、議長はその長い首を、荘厳な仕草でゆっくりと、深く、縦に振った。
「……これだ」
その一言で、議場の重力が元に戻った。僕も、動物たちも、書類も、どさどさと床に落ちる。静まり返った議場に、議長の穏やかで、しかし歓びに満ちた声が響き渡った。
「我は探していたのだ。人間たちの『重要』な決断の重さに拮抗しうる、完璧なまでの『軽やかさ』を。この世界の均衡を保つための、至高の『どうでもよさ』を!この絵には、その全てがある。計算も、意図も、意味もない。ただ、そこにあるだけの、純粋な無意味。なんと美しい……!」
全ての謎が、氷解した。動物会議が決定を否決し続けていたのは、議長が、承認用紙の『余白』を埋めるための、最もアーティスティックで、最も『どうでもいい』落書きを探し求めていたからだったのだ。この世界を揺るがした大混乱の真相は、一頭のアルパカの、極めて個人的で、あまりにくだらない美意識の発露だったのである。
僕のどうでもいい思考が生んだ重力反転。そのカオスの中で生まれた無意識の落書き。それが、議長のどうでもいい芸術的探求の終着点となった。それは、壮大で、馬鹿馬鹿しくて、そして奇跡的なコラボレーションだった。
第六章 どうでもいい世界の片隅で
世界は、あっという間に正常化した。溜まっていた全ての議案は、僕のあの落書きが『承認の印』として印刷され、次々と可決されていった。社会機能は回復し、人々は元の生活を取り戻した。
僕が英雄になることはなかった。そもそも、真相を知っているのはごく一部の人間と動物だけだ。僕はまた、あのアパートの一室で、どうでもいいことを考えては時々宙に浮く、そんな日常に戻った。
けれど、世界は少しだけ、変わった。市役所で発行される婚姻届にも、企業が交わす契約書にも、その片隅には必ず、あの線の震えた猫のような絵が印刷されるようになった。人々はそれを見て、これが何なのかも知らず、ただ「なんだか気の抜けるマークだな」と少しだけ笑うのだ。
ある晴れた午後、僕はベランダでコーヒーを飲んでいた。「このコーヒーカップの取っ手、小指が絶妙に余るな」。そう思った瞬間、僕の体は椅子と共にふわりと浮き上がった。
もう、以前のような自己嫌悪はなかった。
眼下の道で、市役所の袋を持った若いカップルが、幸せそうに書類を眺めているのが見えた。その紙の隅には、僕の落書きがちょこんと印刷されている。
彼らの人生にとって、それはとても「重要」な一枚の紙だ。そして、僕の存在は、この世界にとってきっと「どうでもいい」ものだろう。
でも、それでいいのかもしれない。重要なことと、どうでもいいこと。その二つが寄り添い、互いの重さを打ち消し合うことで、この世界はかろうじてバランスを保っているのかもしれない。僕のどうでもいい浮遊が、世界のどこかで、誰かの重要な一歩を、ほんの少しだけ軽くしているのだとしたら。
そう考えると、この面倒な体質も、ほんの少しだけ、愛せるような気がした。