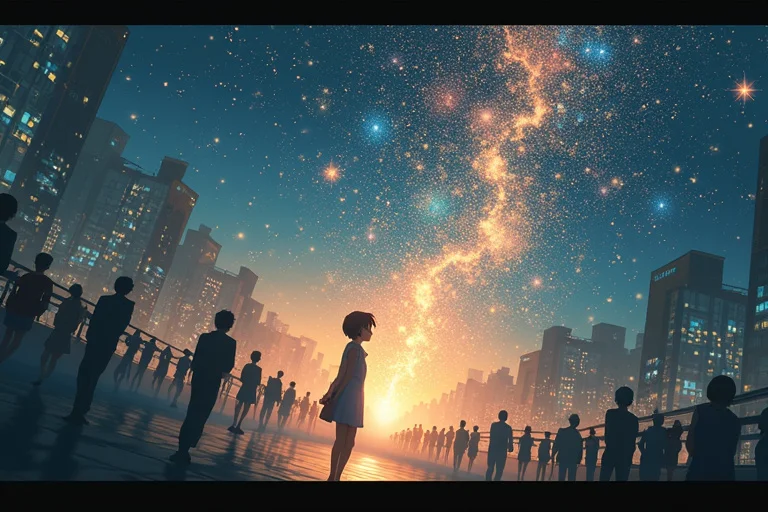第一章 聞こえすぎる男の憂鬱
佐藤誠、32歳、区役所戸籍係。彼の人生は、一ヶ月前から地獄に変わった。原因は、彼の耳が良すぎることにある。いや、物理的な聴力ではない。彼には、他人の「心のツッコミ」が聞こえてしまうのだ。
「この度は、ご愁傷様でございます。こちらの死亡届にご記入を…」
神妙な面持ちで書類を差し出す佐藤の耳に、黒い喪服を着た初老の男性の心の声が、無遠慮に飛び込んでくる。
(…定型文キター。心こもってねえなあ、この兄ちゃん)
佐藤は表情筋をミリ単位で痙攣させながらも、完璧な公務員スマイルを維持する。心の中では、暴風雨が吹き荒れていた。聞こえる。聞こえてしまう。言葉の裏に隠された、冷ややかで、身も蓋もない、正直すぎるツッコミが。
きっかけは些細なことだった。重要な書類の入力ミスが発覚し、課長から部署全員の前で叱責された夜。惨めさと自己嫌悪で眠れなかった翌朝から、世界は一変した。満員電車で聞こえる「(うわ、隣のやつ汗くっさ!)」。コンビニで聞こえる「(弁当温めるの、おっそ!)」。街じゅうが、悪意のない、しかし鋭利な刃物のような本音で満ち満ちていた。
中でも、佐藤が最も苦手としているのが、隣の席の先輩、高橋美咲だった。彼女は、区役所の花形だ。常に笑顔を絶やさず、どんな厄介な住民相談も完璧にこなし、それでいて嫌味がない。誰もが彼女を慕っていた。佐藤も、以前はそうだった。
「佐藤くん、この間のデータ、すごく分かりやすくまとめてくれてありがとう。助かったわ」
キラキラした笑顔で高橋が言う。しかし、佐藤の特殊な耳には、もう一つの声が届いていた。
(…まあ、フォントサイズが微妙にバラバラだったのは、私が直しといたけどね)
「いえ、そんな…高橋さんこそ、いつも完璧で尊敬します」
お世辞を言う佐藤の口が乾く。
(…出た、そのマニュアル通りの褒め方。もっと自分の言葉で話しなさいよ)
ぐさっ。まただ。高橋さんの心のツッコミは、他の誰のものよりも的確で、鋭利で、佐藤の自信を根こそぎ奪っていく。彼女の完璧な笑顔と、辛辣な心の声のギャップは、佐藤にとって何よりの精神的苦痛だった。彼女はきっと、無能な僕を心底見下しているに違いない。
その日、佐藤はまたミスを犯した。複雑な相続関係の戸籍謄本の発行手続きで、必要な書類を一つ、依頼者に伝え忘れてしまったのだ。遠方から来たという依頼者は「また来なければいけないのか」と声を荒らげ、窓口は一瞬にして険悪な空気に包まれた。
パニックに陥る佐藤を助けたのは、やはり高橋さんだった。彼女は柔らかな物腰で依頼者の怒りを鎮め、必要な書類を郵送でやり取りする方法を提案し、その場で手配を済ませてみせた。まさに神業だった。
依頼者が納得して帰った後、高橋さんは「誰にでも間違いはあるから、気にしないで」と、聖母のように微笑んだ。だが、佐藤の耳には、雷鳴のようなツッコミが轟いていた。
(…だから言わんこっちゃない!あの時、ダブルチェックしとけって、目で合図したでしょ!)
佐藤は、もはや顔を上げることができなかった。透明な壁が、自分と世界の間にそびえ立っていくのを感じた。もう無理だ。人と関わるのは、僕には無理なんだ。
第二章 呪いの能力と孤独なランチ
この能力は呪いだ。そう確信した佐藤は、どうにかして心のツッコミを遮断しようと試みた。ノイズキャンセリング機能付きの高級ヘッドホンを買い、通勤中は大音量でクラシック音楽を流した。しかし、ベートーヴェンの荘厳な交響曲の隙間から、「(うわ、この人ヘッドホンから音漏れしてる…最悪)」という舌打ちのようなツッコミが鮮明に聞こえてきた時、彼はヘッドホンをゴミ箱に叩きつけたくなった。
能力が発現した、あの惨めな夜を思い出す。失敗を責められ、誰もいない給湯室で一人、涙をこらえていた。その時、背後を通り過ぎた同僚たちのひそひそ話と共に、冷ややかな心の声が、初めて彼の脳内に響いたのだ。「(あいつ、またやらかしたらしいぜ)」。あれは、現実の悪意だったのか、それとも最初から幻聴だったのか。今となってはもう分からない。ただ、あの瞬間から、彼の世界には余計な注釈が付きすぎるようになった。
唯一の救いは、ツッコミが聞こえない存在がいることだった。彼は休日に動物園へ行った。泰然自若としたゴリラも、優雅に眠るレッサーパンダも、何も語りかけてはこない。公園の鳩も、植え込みのツツジも、沈黙を守っている。無機物と、言葉を持たない生き物だけが、彼の安息の地だった。いっそ、山奥で木こりにでもなろうか。そんな非現実的な逃避行ばかりを夢想する日々が続いた。
そんなある日の昼休み、事件は起きた。
「佐藤くん、よかったら一緒にランチ行かない?駅前に新しいパスタ屋さんできたんだって」
高橋さんが、例の完璧な笑顔で誘ってきた。断る理由が見つからない。いや、本当は「あなたといると心が削れるので無理です」という最大の理由があるのだが、それを口にできるはずもなかった。
「あ、はい…ぜひ」
引きつった笑顔で頷く佐藤の耳に、早速ツッコミが届く。
(…声、ちっさ!蚊の鳴くような声だな)
パスタ屋の雰囲気は最高だった。焼きたてのフォカッチャの香ばしい匂い、客たちの楽しげな喧騒、窓から差し込む柔らかな陽光。しかし、佐藤には毒だった。高橋さんが「このカルボナーラ、濃厚で美味しい!」と微笑むたびに、「(でも、ちょっと塩辛いかな。それにベーコンが固い)」という冷静な分析が聞こえてくる。佐藤が当たり障りのない仕事の話をすれば、「(またその話?この人、趣味とかないのかしら)」という感想が聞こえ、彼は口に含んだペペロンチーノの味も香りも、何も感じられなくなっていた。
「佐藤くん、最近元気ないみたいだけど、何か悩みでもあるの?私でよかったら聞くよ?」
高橋さんの気遣いですら、今の佐藤には拷問だった。きっと彼女は、僕の悩みを鼻で笑うに違いない。
「いえ、何も…大丈夫です」
そう答えるのが精一杯だった。その時、佐藤の耳に、決定的な一撃が突き刺さった。
(…この人、本当に面白くないな)
世界から、色が消えた。フォークがカチャン、と皿に落ちる。もう、限界だった。
第三章 雨宿りの告白
ランチの帰り道、空はまるで佐藤の心を映したかのように、みるみるうちに暗くなっていった。灰色の雲が急速に広がり、大粒の雨がアスファルトを叩き始める。二人は慌てて、近くの古いビルの軒下に駆け込んだ。
「すごい雨になっちゃったね」
高橋さんがタオルハンカチで濡れた髪を拭きながら言う。佐藤は何も答えられなかった。先ほどのレストランでの出来事が、鉛のように心にのしかかっている。「面白くない」。その一言が、彼の存在そのものを否定しているように思えた。気まずい沈黙が、激しい雨音にかき消されていく。
佐藤は、次に聞こえてくるであろう心のツッコミを覚悟した。(早く雨、やまないかな…)(この人と二人きり、気まずすぎる…)そんな言葉が聞こえてきたら、今度こそ心が折れてしまうだろう。彼はぎゅっと目を閉じた。
その瞬間、聞こえてきたのは、まったく予想もしていなかった言葉だった。
「**(大丈夫。私がちゃんとツッコんであげるから、あなたは安心してボケてればいいのよ)**」
え…?
佐藤は雷に打たれたように顔を上げた。目の前の高橋さんは、雨に煙る街並みを、いつもと変わらない穏やかな表情で見つめている。今の声は、確かに高橋さんの声だった。だが、その内容は、あまりにも不可解で、そして…どこか温かかった。
「…あの、今…」
佐藤がかすれた声を漏らすと、高橋さんは驚いたように彼の方を振り向いた。その完璧な笑顔が、一瞬だけ揺らぐ。彼女は数秒間、何かを考えるように宙を見つめ、やがて観念したように、ふっと息を吐いた。
「…もしかして、聞こえちゃった?」
その声は、いつもの彼女からは想像もつかないほど、静かで、少しだけ諦めを含んでいた。
「聞こえたって…何がです…?」
「私の…心の中の、ツッコミ」
高橋さんは、雨で濡れた前髪をかきあげながら、気まずそうに言った。佐藤の頭は真っ白になった。何が起きているのか、全く理解が追いつかない。
「ごめんなさい。私、昔から変な癖があって…」
彼女はぽつりぽつりと語り始めた。
「人の話を聞いたり、何かを見たりすると、心の中で、自動的にツッコミを入れちゃうの。止めようとしても、止められない。相手が何か言おうとすると、その先を読んで、先回りしてツッコんじゃう。一種の、能力…なのかな。自分でもよく分からないんだけど」
佐藤は、ただ呆然と彼女の話を聞いていた。
「じゃあ、僕に聞こえていたのは…」
「たぶん、私の心の声だと思う。特に佐藤くん、あなたって…なんていうか、心のボケしろが大きいのよ」
「ぼけしろ…?」
「そう。いつもオドオドしてて、心の中では『僕なんてダメだ』とか『また失敗するかも』とか、ネガティブなことばっかり考えてるでしょ?それが、私にとっては最高のボケに聞こえるの。だから、つい…全力でツッコんじゃう」
そこで、佐藤は一つの疑問に思い至った。
「でも、他の人のツッコミも聞こえました。電車の中とか、コンビニとか…」
高橋さんは首を横に振った。
「それは、たぶんあなたの思い込みよ。あなたの能力は、もしかしたら、『私の心のツッコミだけが聞こえる』っていう、すごく限定的なものなんじゃないかな」
衝撃の事実だった。彼を苦しめていた無数の悪意は、ほとんどが彼の被害妄想が生み出した幻聴だった。そして、彼が最も恐れていた高橋さんの心の声は、彼女の「自動ツッコミ機能」の産物だったのだ。レストランでの「この人、本当に面白くないな」というツッコミも、佐藤が「僕の話は面白くないんだろうな…」と内心でボケたことに対する、反射的なものだったのだ。
世界が、ぐるりと反転した。
第四章 ふたりのための虹
呪いだと思っていた能力は、たった一人の女性の、奇妙な癖を受信するだけの、極めて個人的なホットラインだった。人間不信の原因は、世間の冷たさではなく、自分の被害妄想と、彼女の特異体質の奇跡的なコンビネーションだったのだ。佐藤は、あまりの馬鹿馬鹿しさに、力が抜けていくのを感じた。
「ごめんね。私のせいで、ずっと辛い思いをさせてたみたいで」
高橋さんが申し訳なさそうに眉を下げる。
「私も、この能力、嫌いだった。いつも誰かの欠点とか、おかしなところにばかり目がいっちゃうから。性格悪いなって、自分でも思うし」
彼女は、強い雨が作り出す灰色のカーテンを見つめながら続けた。
「でも…佐藤くんといると、私のツッコミ、すごくキレが良くなるの。あなたの心のボケは、なんていうか…すごく質が高いのよ。純度100%のネガティビティというか。だから、本当は…ちょっとだけ、楽しかった」
最後は、照れくさそうに、小さな声で付け加えられた。
質の高い、ボケ。
生まれてこの方、誰かに何かを「質が高い」と評価されたことなど一度もなかった。ましてや、自分の最大のコンプレックスであるネガティブな思考が、最高の素材として認められる日が来るなんて。
佐藤は、胸の奥から、温かい何かが込み上げてくるのを感じた。それは、生まれて初めて、自分の弱さやダメな部分を、丸ごと肯定されたような、不思議な感覚だった。
いつの間にか、雨脚は弱まっていた。分厚い雲の切れ間から、久しぶりに太陽の光が差し込み、アスファルトの匂いを立ち上らせる。そして、東の空には、大きな虹がかかっていた。
「じゃあ…」
佐藤は、虹から高橋さんに視線を戻し、自分でも驚くほど、自然に言葉を紡いでいた。
「僕がこれからも、どんどん質の高いボケを提供するので、高橋さん、どんどんツッコんでくれませんか?」
それは、彼が人生で初めて口にした、アドリブの冗談だった。
高橋さんは一瞬、きょとんと目を見開き、次の瞬間、これまで見たどんな笑顔よりも楽しそうに、声を立てて笑った。佐藤の耳には、最高の音質の、最高のツッコミがクリアに響き渡った。
「**(上等じゃない!かかってきなさい、Mr.ネガティブ!)**」
世界は何も変わっていない。明日からも、佐藤は区役所で働き、きっと些細なことでクヨクヨするだろう。高橋さんはその隣で、完璧な仕事をこなしながら、心の中で鋭いツッコミを入れ続けるだろう。
けれど、佐藤にとって、その声はもう呪いではなかった。それは、世界でたった一人の理解者と自分とを結ぶ、秘密の会話。誰にも聞こえない、二人だけの漫才。
雨上がりの澄んだ空気の中、七色に輝く虹を見上げながら、佐藤は思った。明日の朝、高橋さんに「おはようございます」と言った時、彼女は心の中で、どんなツッコミを入れてくれるのだろう。
ほんの少しだけ、明日が来るのが楽しみになっている自分に気づき、彼は小さく笑った。