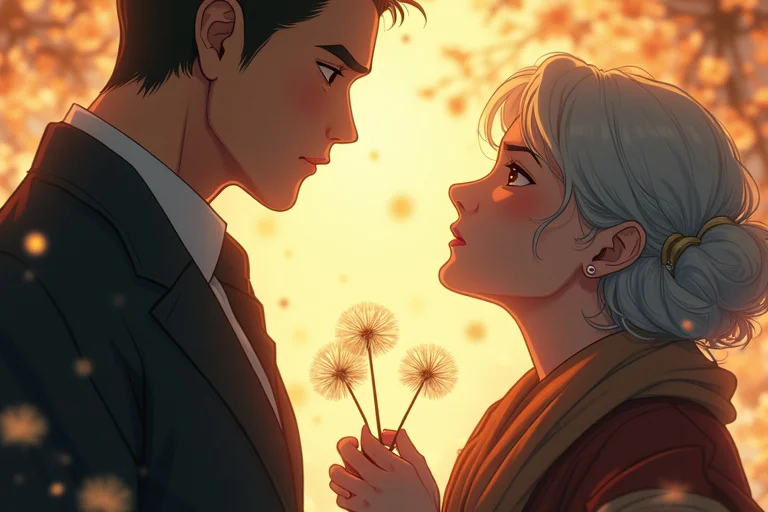第一章 奇妙なチラシと月曜日の法則崩壊
鈴木健太の人生は、寸分の狂いもなく設計された精密機械のようだった。毎朝六時半に起床。トーストは八枚切りを三分。駅までの歩数は千二百三十歩。彼の信条は「平凡こそ至高」であり、人生における予期せぬ出来事は、スープに紛れ込んだ髪の毛のようなものだと考えていた。だから、その月曜日の朝、枕元に見慣れない一枚のチラシが落ちているのを発見した時、彼の体内時計は警報を鳴らした。
チラシは、虹色に鈍く輝く、紙とも金属ともつかない未知の素材でできていた。触れるとひんやりとして、指先に微かな静電気が走る。そこには、地球のどの言語とも違う、ミミズが這ったような奇妙な文字でこう書かれていた。
『高視聴率御礼!銀河系ワイドショー『地球人ケンタの日常』視聴率アップ↑キャンペーン!抽選で惑星間旅行券が当たる!応募はこちらの二次元コードから!』
「……なんだ、これ」
健太は眉をひそめた。二次元コードは、まるで生きているかのように明滅を繰り返している。そもそも、自分の部屋は昨夜、完璧に施錠したはずだ。一体誰が、どうやってこんな悪趣味なイタズラを? 健太はそれをゴミ箱に叩き込むと、無理やり意識から追い出し、いつものように家を出た。
しかし、その日から、彼の信奉する「平凡」は音を立てて崩れ始めた。
まず、駅に向かう途中、いつも赤信号に捕まるはずの横断歩道が、まるで彼を待っていたかのように青に変わった。偶然だろう、と彼は思った。だが、次の交差点も、その次の交差点も青だった。おかげで、いつもより三分も早く駅に着いてしまった。ホームに滑り込んできた電車は、なぜか普段は乗らない特急車両で、しかも奇跡的に彼の目の前の席だけが一つ空いていた。
会社に着いてからも、奇妙な幸運は続いた。いつもは鬼の形相で部下を叱責している部長が、健太を見つけるなり「鈴木君、今日のネクタイ、いいねえ! センスあるよ!」と満面の笑みで肩を叩いてきた。そのネクタイは、三年前にスーパーのワゴンセールで買った、くたびれたポリエステル製だ。
午後、重要なプレゼンの番が来た。健太は極度のあがり症で、人前に立つと声が震え、手足は氷のように冷たくなる。案の定、最初の数分で彼は盛大に言葉を噛んだ。「弊社の、えー、しんししし、新商品ですが……」
静まり返る会議室。健太の額から冷や汗が噴き出した。終わった。と思った、その瞬間。
どこからともなく、陽気な笑い声の効果音が「ワッハッハ!」と響き渡ったのだ。
会議室にいる全員が、きょとんとして顔を見合わせる。健太も例外ではない。しかし、その場違いな効果音は、なぜか張り詰めた空気を和らげた。取引先の重役がくすりと笑ったのを皮切りに、室内には温かい笑いが広がった。「いやあ、鈴木さん、面白い冗談を言うなあ」と誰かが言った。
健太は訳が分からないまま、勢いに乗せられてプレゼンを終えた。結果は、まさかの大絶賛。契約は即決だった。
帰宅途中、健太は混乱していた。幸運? いや、これは幸運などという生易しいものではない。まるで、世界が自分を中心に、都合の良いように書き換えられているような、薄気味悪い感覚。彼はふと、今朝のあの虹色のチラシを思い出した。『地球人ケンタの日常』。まさか。そんな馬鹿なことがあるはずない。
しかし、彼の部屋のドアノブには、これ見よがしに新しいチラシが引っかかっていた。
『本日のハイライト:ド緊張プレゼン、謎の効果音で大逆転!平均視聴率5%アップ!ケンタ、やるじゃないか!』
健太は、血の気が引くのを感じながら、そのチラシを握りしめた。彼の平凡な日常は、もうどこにも存在しなかった。
第二章 災厄はジェットコースターに乗って
奇妙なチラシの出現から一週間。健太の周囲で起こる異常現象は、幸運の範疇をとうに超え、悪意に満ちたドタバタ劇へと変貌していた。
ある朝、彼が乗った通勤電車は、突如としてけたたましいファンファーレを鳴らし始めた。車内アナウンスが陽気に叫ぶ。「皆様、お待たせいたしました!本日より、当路線は『スリル満点☆地獄のサラリーマン・エクスプレス』としてリニューアルオープン!」次の瞬間、電車は窓の外の景色が歪むほどの猛スピードで急上昇し、垂直に近い角度で急降下した。
「うわああああああ!」
車内は阿鼻叫喚の渦と化した。吊り革にぶら下がるサラリーマンたち。宙を舞うカバンと書類。健太は必死で手すりにしがみつきながら、ジェットコースターと化した満員電車に揺られた。会社に着く頃には、乗客全員が疲労困憊でぐったりしていたが、不思議なことに怪我人は一人もいなかった。そして、健太のデスクには、またあのチラシが置かれていた。『電車DE絶叫!視聴率、前週比12%アップ!大成功!』
もはや偶然やイタズラではない。何者かが、健太の人生に意図的に介入している。彼は恐怖と怒りで気が狂いそうだった。誰が? 何のために?
健太は原因究明に乗り出した。監視カメラ、探偵、警察への相談。しかし、全てが無駄に終わった。監視カメラには何も映らず、探偵は「統合失調症の初期症状では?」と憐れみの目を向け、警察には「チラシくらいで事件にはできません」と一蹴された。彼は完全に孤立していた。
災厄は、仕事にまで及んだ。懇意にしている取引先の社長、五十嵐氏との重要な会食の席でのことだ。五十嵐氏は、業界でも有名なカタブツで、礼儀作法に異常なほどうるさい人物だった。健太は細心の注意を払い、完璧なマナーで接待に臨んでいた。
「鈴木君、このプロジェクトは君の熱意に免じて、前向きに検討しよう」
五十嵐氏がそう言ってくれた瞬間、健太は勝利を確信した。だが、その時だった。健太の背後にあるスピーカーから、突如として情熱的なサンバのリズムが流れ出したのだ。そして、あろうことか、健太の身体が本人の意思とは無関係に、勝手に踊り始めたのである。
「なっ、なんだこれは!?」
腕がしなり、腰がくねり、足が軽快なステップを刻む。健太の意識は悲鳴を上げているのに、身体は一流のダンサーのように、情熱の限りを尽くしてサンバを踊っていた。目の前の五十嵐氏は、箸を落とし、あんぐりと口を開けて固まっている。
「や、やめろ! 止まれ、俺の身体!」
しかし、彼の身体は言うことを聞かない。それどころか、テーブルクロスを引き抜き、頭に巻いて踊り狂う始末だ。ワイングラスが倒れ、高級なフランス料理が床に散らばる。地獄のような数分が過ぎ、音楽が止んだ時、健太はぜえぜえと肩で息をしながら、荒れ果てた個室の中央に立ち尽くしていた。
五十嵐氏は、わなわなと震えながら立ち上がると、真っ赤な顔で一言だけ言い放った。
「……君は、仕事をなんだと思っているんだ!」
契約は、もちろん破談になった。会社に戻った健太は、部長から雷のような叱責を受け、土下座して謝罪した。自分のロッカーに戻ると、そこには案の定、新しいチラシが貼られていた。
『情熱のサンバで契約破談!衝撃の展開に視聴率爆上がり!ケンタの不幸は蜜の味!』
健太は、チラシをぐしゃぐしゃに握りつぶした。もう限界だった。笑い声の効果音、ジェットコースター電車、そして、勝手に踊る身体。これはエンターテイメントなどではない。ただの悪質な嫌がらせだ。彼の心の中で、何かがぷつりと切れる音がした。
「出てこい……」健太は、誰もいないロッカールームで、虚空に向かって呟いた。「誰だか知らないが、俺の人生をオモチャにするのは、もうやめろ!」
その声は、怒りと絶望に震えていた。
第三章 視聴率と宇宙からのご挨拶
健太が魂の底から叫んだ、その時だった。目の前の空間が、水面のように揺らめき、ノイズと共に三次元の映像が結ばれた。そこに立っていたのは、人間ではなかった。
頭には三本の触角が生え、大きな複眼はチカチカと光を放ち、タコのような下半身をくねらせている。派手なスーツに身を包んだその異形の存在は、葉巻型のデバイスをふかしながら、陽気な声で言った。
「やあ、ケンタ! いつも番組を盛り上げてくれてありがとう! 私が、この番組の総合プロデューサー、ゾルタックスだ!」
健太は、声も出せずに立ち尽くした。宇宙人。目の前にいるのは、紛れもない宇宙人だった。
ゾルタックスと名乗る宇宙人は、ホログラムの身体を揺らしながら、マシンガンのように喋り続けた。「いやあ、君のリアクションは最高だよ! 平凡な男が突然、非日常に巻き込まれる! このギャップが視聴者に大ウケでね! 特に先日のサンバは伝説回になったよ! おかげで視聴率は三十二パーセントを超え、銀河系視聴率ランキングでトップテン入りだ!」
「……番組?」健太は、かろうじて言葉を絞り出した。「一体、何の話をしている?」
ゾルタックスは、心底意外だという顔をした。「おや、まだ気づいていなかったのかい? 君の人生だよ、ケンタ。君が生まれてから今日までの三十二年間、その全てが、リアリティショー『地球人ケンタの日常』として、この銀河系全域に放送されているんだよ」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。自分の人生が、ショー? あの日の幸運も、今日の不幸も、全てが「演出」だったというのか。
「なんで……なんでそんなことを……」
「ビジネスさ」ゾルタックスは、デバイスから紫色の煙を吐き出した。「知的生命体のリアルな生態を観察する番組は、昔から人気ジャンルでね。特に君のような、極端に変化を嫌う『平凡固執型』の地球人は、サンプルとして非常に興味深い。だが、正直に言おう。最近の君の日常は、あまりにも退屈で、視聴率がダダ下がりだった。番組打ち切りの危機だったんだよ。だから、我々は少しだけ『テコ入れ』をさせてもらったというわけさ」
ジェットコースターも、情熱のサンバも、全ては視聴率のため。健太の混乱も、恐怖も、屈辱も、全てが銀河の住人たちの娯楽のため。健太の中で、怒りが沸々と湧き上がってきた。
「ふざけるな!」健太は叫んだ。「俺の人生だぞ! お前たちのオモチャじゃない! 今すぐこんなくだらない放送はやめろ!」
しかし、ゾルタックスは複眼を冷ややかに光らせただけだった。「やめる? 無理な相談だね。君には拒否権はない。我々の科学力の前では、君は無力だ。それに、考えてもみろよ、ケンタ。君の不幸は、何十億もの知的生命体に笑いと感動を与えているんだ。君は、ただのサラリーマンじゃない。銀河のスターなんだよ! 誇りに思うべきだ」
その言葉が、健太の理性の最後の糸を断ち切った。誇り? 自分の意志を奪われ、操り人形のようにされて、何が誇りだ。彼は、自分の人生が、自分の尊厳が、根底から踏みにじられたことを悟った。絶望が彼の心を支配した。膝から崩れ落ち、彼は床に突っ伏した。
「さあ、ケンタ! 明日はもっとエキサイティングな展開を用意しているぞ!」ゾルタックスは楽しそうに告げた。「君の会社が、宇宙海賊に乗っ取られるというのはどうだい? きっと視聴率も爆上がりだ! 期待しているよ、我らが主演俳優!」
ホログラムが消え、ロッカールームに静寂が戻る。床に転がった健太の肩は、悔しさと無力感で小刻みに震えていた。しかし、その瞳の奥深くで、絶望とは違う、小さな、しかし確かな光が灯り始めていた。それは、これまで彼の人生に存在しなかった感情――反逆の炎だった。
第四章 主演・鈴木健太の逆襲
翌朝、鈴木健太はいつもより一時間早く目覚めた。鏡に映る自分の顔は、ひどくやつれていたが、その瞳には昨日の絶望の色はなかった。代わりに宿っていたのは、覚悟を決めた者の、静かな闘志だった。
「見てろよ、ゾルタックス。お前の思い通りにはさせない」
会社に向かうと、予想通りロビーが騒然としていた。タコの足を生やした、見るからに宇宙海賊といった風体の連中が、光線銃を手に社員たちを威嚇している。「この会社は我々が乗っ取った! 金目のものを全て出せ!」リーダー格の海賊が叫ぶ。社員たちは恐怖に怯え、隅で固まっていた。
健太は、深呼吸を一つすると、海賊たちの前に進み出た。
「お待ちください、海賊の皆様」
海賊も、社員たちも、突然現れた健太に呆気にとられている。
「この会社で最も価値があるのは、私、鈴木健太の『平凡な日常』に関するデータです。私の三十二年分の行動、思考、感情の全てが記録されています。これぞ、銀河系でも類を見ない貴重な情報資産。これを、皆様に差し上げましょう」
健太の突拍子もない提案に、海賊のリーダーは面食らった。「な、なんだと? そんなものに価値があるのか?」
「もちろんです」健太は自信満々に言い放った。「このデータを解析すれば、どんな知的生命体でも予測不能なトラブルに巻き込み、最高のエンターテイメントを生み出す方程式が手に入ります。銀河の放送業界を牛耳ることも夢ではありませんぞ!」
健太のハッタリは、見事に海賊たちの射幸心を煽った。彼らは顔を見合わせ、やがてリーダーが頷いた。「よし、その話、乗った! データとやらを渡せ!」
健太は、会社のメインサーバーに彼らを案内すると、自分の人事ファイルや日報など、ありったけの「平凡なデータ」をUSBメモリにコピーして手渡した。海賊たちは大喜びでそれを奪い取ると、「達者でな、サラリーマン!」と言い残し、UFOに乗って飛び去って行った。
呆然とする社員たちを前に、健太は静かに頭を下げた。「ご迷惑をおかけしました」。部長が駆け寄り、健太の肩を掴んだ。「鈴木君、君は会社を救ったヒーローだ!」
その夜、健太の部屋に、怒り心頭のゾルタックスがホログラムで現れた。「ケンタ! なんてことをしてくれたんだ! 宇宙海賊をハッタリで追い返すなんて、台本のどこにも書いてないぞ! おかげで視聴者は大混乱だ!」
「あんたの台本通りに動くのは、もうやめたんだ」健太は、初めてゾルタックスを真っ直ぐに見据えて言った。「これは俺の人生だ。主演も、脚本も、監督も、俺がやる」
その日から、健太の反撃が始まった。ゾルタックスが仕掛けるトラブルを、健太は次々と予測不能な方法で乗り越えていった。お見合い相手として送り込まれてきた銀河的アイドルには「ごめんなさい、僕にはずっと想っている人がいるんです」と告げて、長年片思いしていた同僚の佐藤さんに告白し、見事OKをもらった。隕石が会社に落ちてくるという予報が出れば、全社員を避難させた上で、そのエネルギーを利用した新発電システムを考案し、特許を取得した。
健太の「台本無視」の行動は、ゾルタックスの予想とは裏腹に、銀河系の視聴者たちを熱狂させた。操り人形だった男が、自らの意志で運命を切り拓いていく姿は、最高のエンターテイメントだったのだ。視聴率は瞬く間に過去最高を記録し、『地球人ケンタの日常』は社会現象を巻き起こすほどの伝説的番組となった。
数ヶ月後。ゾルタックスは、すっかり神妙な面持ちで健太の前に現れた。
「……ケンタ、君の勝ちだ。我々は、もう君の人生に過度な介入はしない。君の『ありのまま』が、最高のコンテンツだと、ようやく理解したよ」
「そうかい。物分かりが良くて助かるよ」健太は、コーヒーを飲みながら平然と答えた。
「一つだけ、教えてくれないか」ゾルタックスは尋ねた。「なぜ、君はあれほど変われたんだ?」
健太は、窓の外の青空を見上げた。かつては退屈で、灰色にしか見えなかった日常が、今は無限の可能性に満ちて輝いて見える。
「あんたのおかげさ」と彼は言った。「あんたが、俺の人生は『見られている』価値があるんだって、教えてくれたからな」
ゾルタックスは何も言わずに、静かに消えた。
健太は立ち上がり、ベランダに出た。心地よい風が頬を撫でる。彼の人生は、今も銀河中に放送されているのかもしれない。だが、もうそんなことはどうでもよかった。彼は自分の物語の主役だ。カメラが回っていようといまいと、彼は自分の足で立ち、自分の言葉で語り、自分の心で愛する。
彼は空に向かって、悪戯っぽくウインクした。
「ま、せいぜい楽しんでくれよ、銀河の皆さん」
その呟きは、誰に聞かれることもなく、東京の空に溶けていった。平凡だった男は、自らの人生という最高の舞台で、誰よりも輝く主演俳優になったのだ。