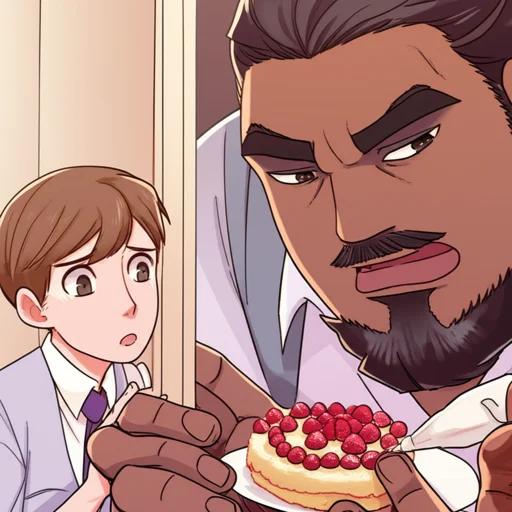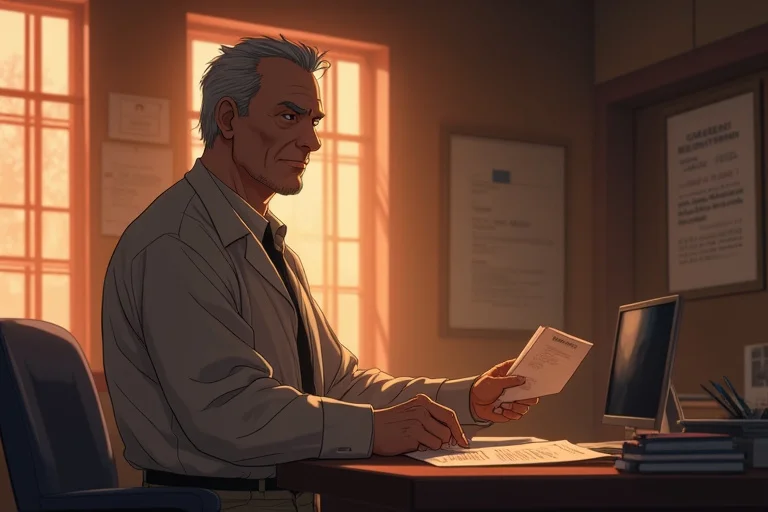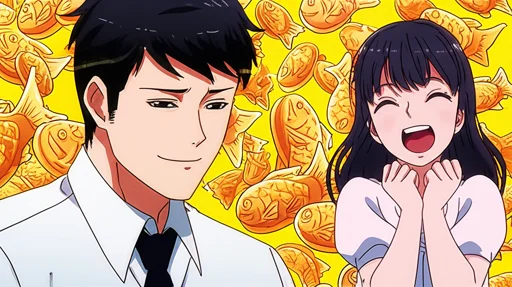第一章 嵐の前のプロレス実況
俺、星野走馬の耳は、どうも普通じゃないらしい。他人の心の声が、なぜか『アテレコされたプロレス実況』として聞こえてくるのだ。
例えば、今。目の前のデスクで山積みの書類と格闘している同僚、天野詩織。彼女は今日の午後に控えた、会社の命運を左右するプレゼンの大役を任されている。傍から見れば、ただ静かに資料をめくる真剣な横顔だが、俺の耳には灼熱のリングサイドが広がっていた。
『ゴングは鳴った! 今、まさに最終調整のリングに立つエンジェル詩織! その瞳には静かなる闘志の炎が燃え盛る! 対するは、冷徹なる絶対王者、部長デビル! 果たして彼女は、必殺のプレゼンテーション・ボムを炸裂させ、勝利のベルトをその手に掴むことができるのかーっ!』
「……うるさっ」
思わず漏れた呟きに、詩織がぱちりと瞬きをしてこちらを向いた。亜麻色の髪がさらりと揺れる。
「何か言った、星野くん?」
「い、いや、なんでもない。独り言」
慌てて首を振る俺に、彼女は少しだけ眉を寄せたが、すぐに資料へと視線を戻した。その仕草だけで、俺の鼓膜には「一瞬の隙も見せない鉄壁のガード! さすがはエンジェル詩織!」という絶叫が響き渡る。
この世界にはもう一つ、奇妙な法則がある。『ボディシェアリング』。人々は人生の重要な決断を下す際、必ず自分以外の誰か、ランダムに選ばれた赤の他人の肉体を一時的に借りなければならない。その間、元の体は意思を失い、まるで彫像のようにフリーズする。交差点で青信号を渡るか否か、そんな些細な決断でさえ、誰かの体を借りるのがこの世界の常識だった。街角で突然固まる人々は、もはや日常の風景と化している。
詩織もまた、プレゼンの最終決断の瞬間、どこかの誰かの体を借りるのだろう。それがどうか、器用な人物でありますように。俺は心の中で、いや、脳内で絶叫する実況を打ち消すように、静かに祈った。
第二章 シェアリング・パニックの開幕
その祈りは、驚くほど無惨に裏切られた。
異変は、まずテレビのニュースから始まった。キャスターが神妙な面持ちで語る。
「……世界各地で報告されている『ボディシェアリング』の異常集中現象ですが、専門家は原因の特定に至っていません。特定の人物、しかも極めて不器用で運が悪いとされる一個人に、世界の重要な決断が集中しているとの情報も……」
その「一個人」が誰なのか、俺が身をもって知ることになるのに、時間はかからなかった。
午後二時。プレゼン開始の五分前。
詩織が深呼吸し、覚悟を決めた表情で立ち上がった、その瞬間だった。俺の体の中で、俺じゃない何かが、ぐにゃり、と主導権を握った。視界が揺れ、手足の感覚が曖昧になる。
「うわっ!」
俺の口から、俺のものではない悲鳴が上がった。次の瞬間、俺の体は勝手に立ち上がり、盛大に足をもつれさせ、デスクの角に脇腹を強打。積んであった資料のタワーをなぎ倒し、床にぶちまけられたコーヒーで派手にスリップした。まるで三文芝居のようなドタバタ劇。
脳内に響き渡る、俺自身の心の声が変換された実況。
『な、なんだぁーっ!? 突如としてリングに乱入したのは、なんとエンジェル詩織だ! 星野走馬の肉体をジャックし、自らのプレゼン資料を相手に無差別大破壊! これは前代未聞の反則攻撃だーっ!』
数秒後、俺の体から詩織の意識が抜け、自分の感覚が戻ってきた。床に大の字で転がる俺。呆然と立ち尽くす同僚たち。そして、自分の席でフリーズしていた詩織が、はっと我に返って目を丸くしている。
「ご、ごめん、星野くん! なぜかあなたの体に……!」
これが始まりだった。その日を境に、ラーメン屋の店主が新メニューの味付けを決めるために、タクシーの運転手が最短ルートを選ぶために、果ては道端の小学生がガチャガチャを回すかどうか決めるために、ありとあらゆる人々の意識が俺の体に乗り移ってきた。俺の日常は、制御不能のドタバタコメディへと変貌した。
第三章 ツッコミ専用メガホン
もはやまともな生活は送れない。俺は会社を休み、街を彷徨っていた。その時、ふと路地裏の古びた骨董品屋が目に入った。埃をかぶったガラクタの中に、手のひらサイズの小さな赤いメガホンが一つ。そこには、震えるような文字でこう書かれていた。
『ツッコミ専用』
馬鹿馬鹿しい。そう思いながらも、何かに引かれるようにそれを手に取った。店主の老人は、ギョロリとした目で俺を一瞥すると、「お代はいいよ。あんたなら、うまく使えるだろう」とだけ言った。
その帰り道だった。けたたましいクラクションが鳴り響き、交差点に差し掛かったトラックが蛇行を始めた。運転席で、男が体を硬直させている。ボディシェアリングだ。そして、その意識は、またしても俺の体に流れ込んできた。
『右か! 左か! 運命の分かれ道! このハンドルさばきが、数多の命運を分ける! だがしかし、乗り移ったこの男の体、絶望的に運動神経が悪いぞーっ!』
俺の体が、ありえない方向に手足を動かし始める。トラックは歩道に乗り上げそうだ。万事休す。その時、俺は無我夢中で、手にした赤いメガホンを口に当てていた。脳内に響く実況に向かって、魂の底から叫ぶ。
「なんでやねん!」
瞬間、メガホンから凄まじい突風が吹き荒れた。それは物理的な衝撃波となり、トラックの運転手を直撃する。運転手の意識が、まるで風で吹き飛ばされるように俺の体から離脱し、元の体へと吸い込まれていった。男ははっと我に返り、急ブレーキを踏む。タイヤが悲鳴を上げ、トラックは歩行者の数センチ手前で停止した。
世界が安堵のため息をついた、まさにその時。
俺の体は、まるで糸の切れた操り人形のように、カクン、と膝から崩れ落ちた。後頭部をアスファルトに打ち付けそうになる寸前、漫画みたいにくるりと一回転し、見事なまでの『ズッコケ』を披露していた。
「……副作用、か」
メガホンには、小さな文字で『※使用後、しばらくズッコケやすくなります』と追記されていた。
第四章 世界の中心でズッコケる
ツッコミ専用メガホン。それは、不条理なシェアリングに対する俺の唯一の対抗手段となった。
フランスの大統領が重要な法案に署名する決断で、俺に乗り移ろうとすれば、「おフランスの事情は知らん!」とツッコんで追い返す。南米のサッカー選手がPKを蹴る方向を決めるために乗り移ろうとすれば、「右か左か自分で決めろ!」と突風を浴びせる。そのたびに俺は、ありとあらゆる場所で、ありとあらゆるズッコケを繰り返した。駅のホームで、スーパーの鮮魚コーナーで、図書館の静寂の中で。
世界は俺を中心に回り、そして、俺のズッコケを中心に救われていた。
そんな狂乱の日々が続いたある夜。事件は起きた。
夜空が突如として巨大なスクリーンのように発光し、そこに映像が映し出されたのだ。それは、世界中でズッコケまくる俺の姿をまとめたダイジェスト映像だった。BGMは軽快なサンバだ。
そして、空から響き渡る、どこかで聞いたことのあるような、陽気なナレーション。
『いやー、素晴らしいリアクション! 今週の地球ドキュメンタリー『ズッコケ救世主』、いかがでしたでしょうか? 主演はもちろん、この男、星野走馬! 彼のズッコケが、視聴率を爆上げしております!』
呆然と空を見上げる俺の前に、いつかの骨董品屋の老人が、いつの間にか立っていた。彼は空を指さし、悪戯っぽく笑う。
「言ったろ、あんたならうまく使えるって。創造主様は退屈してたんだよ。で、地球を舞台にした壮大なコメディドキュメンタリーを撮ることにした。あんたは、その主役に選ばれたのさ。一番面白いリアクションをするからね。あんたにシェアリングが集中するように、全人類の無意識にちょっとだけ干渉してな」
第五章 創造主への逆ツッコミ
これが、真実。
俺の苦悩も、世界の混乱も、全ては神の退屈しのぎ。壮大なテレビ番組の、ただのネタ。俺は、笑われるためだけに選ばれた道化だった。
絶望が、冷たい水のように全身を浸していく。脳内で、最後のプロレス実況が鳴り響いた。
『ああ、なんということだ! 全ての戦いは、壮大な神の掌の上だった! リングの上で踊らされ続けた哀れなピエロ、星野走馬! このまま無様に膝をつき、番組はエンディングを迎えるのかーっ!』
違う。
違うだろ。
俺の人生は、お前らの暇つぶしの道具じゃない。詩織の真剣な眼差しも、トラックの運転手の焦りも、世界中の人々の必死な決断も、全部、全部、笑いものにしていいはずがない。
怒りが、絶望を焼き尽くした。
俺は赤いメガホンを握りしめ、夜空の巨大なスクリーンに向かって、喉が張り裂けんばかりに叫んだ。
「退屈しのぎに世界を巻き込むな! こっちは必死で生きてんだよ! 一番ズッコケなのは、高みの見物してるアンタだろ、神様ァッ!」
それは、もはやツッコミではなかった。魂の咆哮だった。
メガホンから放たれた突風は、これまでとは比較にならない巨大な竜巻となり、天を突いた。空のスクリーンに直撃し、ガラスが割れるような甲高い音と共に、夜空に巨大な亀裂が走る。世界の歪んだ法則が、音を立てて崩れていくのが分かった。
第六章 カーテンコールの後で
世界は、元に戻った。
ボディシェアリングは再び公平なランダム制を取り戻し、街角でフリーズする人々の数も穏やかな日常の範囲に収まった。
そして、俺の耳から、あれだけ騒々しかったプロレス実況が、嘘のように消え去っていた。ただ、静寂だけがそこにあった。副作用だったズッコケ体質も、いつの間にか治っていた。
数日後、オフィスに出社すると、詩織が心配そうな顔で駆け寄ってきた。
「星野くん、大丈夫だった? なんだか大変なことに巻き込まれてたみたいだけど……。あ、そうだ。この前のプレゼン、大成功だったの。ありがとう」
「俺は何も……」
「ううん」と彼女は首を振る。「あの時、なんだか星野くんが背中を押してくれた気がしたの。一番大事な決断の時、あなたの不器用な優しさが、私に乗り移ってきてくれたみたいで」
彼女の心の声は、もう聞こえない。
だが、その穏やかな微笑みと、少しだけ潤んだ瞳を見ていると、実況なんかがなくても、大切なことはちゃんと伝わるのかもしれない、と思えた。
その夜、アパートのベランダから空を見上げると、一筋の流れ星が、まるで盛大にズッコケるように夜空を横切っていった。
その時、俺の心の中にだけ、最後のナレーションが静かに響いた。それはもうプロレス実況ではなく、どこか寂しげで、それでいて温かい響きを持っていた。
『本日のハイライト、主人公のドタバタ劇でした。……いやはや、最高の最終回だった。視聴率は、過去最高を記録したよ。ありがとう、主演男優。またいつか、別の番組で会う日まで。アディオス!』
空は何も語らない。ただ、無数の星が瞬いている。俺は小さく笑って、夜空に向かってそっと、ツッコミを入れた。
「……もうこりごりだよ」
その声は、夜風に溶けて消えていった。