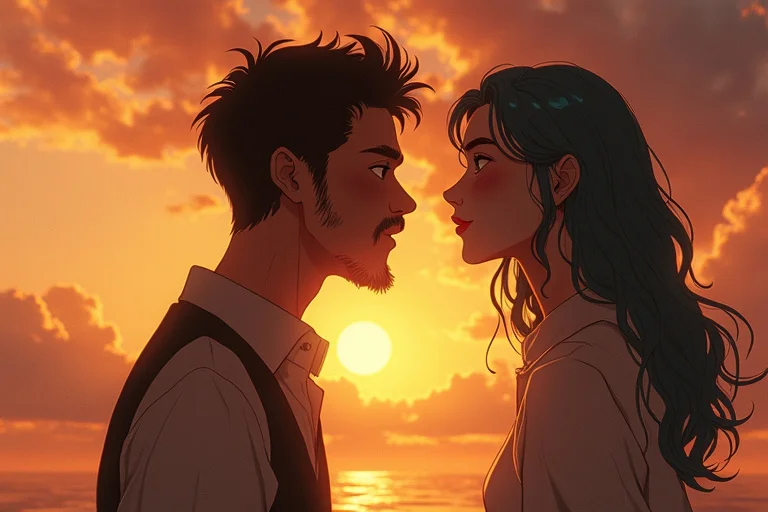第一章 呪いのカウンター
三谷健司の視界の隅には、常に数字がちらついていた。それは幽霊でもなければ、飛蚊症でもない。他人の感情、特に「笑い」を可視化した、彼だけの呪いのカウンターだ。
今夜も、薄暗いライブハウスのステージ上で、健司はその数字に睨まれていた。相方の佐藤が繰り出すシュールなボケに、客席が揺れる。健司の目には、観客一人ひとりの頭上に浮かぶ『WP』、すなわち『ワライ・ポイント』が鮮明に見えた。小さな笑いは10WP、爆笑なら50WP。その合計値が、ステージ後方の集計カウンターのようにリアルタイムで健司の脳内に表示される。
「――というわけで、僕のペットのタピオカ、名前は『権左衛門』って言うんですけど」
「なんでだよ! 粒にそんな厳つい名前つけんな! しかも一匹しか飼ってないみたいな言い方やめろ!」
健司のツッコミが炸裂し、客席からドッと笑いが起きる。脳内のカウンターが勢いよく回る。
『TOTAL WP: 850』
まだいける。健司は額に滲む冷や汗を、スポットライトの熱のせいだと思い込もうとした。この能力が発現してから五年、彼はある法則に気づいていた。ライブ一回あたりの合計WPが1000を超えると、必ず、彼に不幸が降りかかるのだ。
「その権左衛門がですね、最近、反抗期で……」
「タピオカに反抗期はねえだろ! どう反抗すんだよ! ストローに吸われるのを全力で拒否でもすんのか!」
『TOTAL WP: 980』
来た。危険水域だ。健司の心臓が警鐘のように鳴り響く。彼はネタ帳の構成を思い出し、ここで締めるはずだった。なのに、相方の佐藤の目が爛々と輝いている。乗っているのだ、完全に。
「健司、聞いてくれよ。権左衛門が昨日、俺にこう言ったんだ。『父さん、俺、ミルクティーの底に沈んでるだけの一生は嫌だ』って」
それは台本にない、完全なアドリブだった。佐藤の渾身のボケ。健司は刹那、最高のツッコミを閃いた。だが、それを口にすれば、確実に1000の壁を突破してしまう。恐怖が喉を締め付ける。しかし、相方の期待に満ちた瞳を裏切ることはできなかった。
「知るかぁ! 育て方が悪かったんだろ! 親子で話し合え!」
健司がそう叫んだ瞬間、世界がスローモーションになった。客席は今日一番の爆笑に包まれ、観客たちの頭上から金色のWPが噴水のように吹き上がる。
脳内のカウンターが、けたたましい音を立てて臨界点を超える。
『TOTAL WP: 1250』
――ああ、終わった。
そう思った直後。バチン、と天井から鋭い音がした。観客の悲鳴が上がる。スポットライトの一つが、固定器具から外れて落下してきたのだ。それは健司の肩を掠め、床に甲高い音を立てて転がった。幸い、怪我はなかった。しかし、不幸はこれで終わりではない。
楽屋に戻り、安堵のため息をついた健司は、ポケットを探って凍りついた。あるはずの財布が、どこにもなかった。まただ。WPが1000を超えると、いつもこうだ。財布を落とす。スマホの画面が割れる。階段から落ちる。その代償の大きさは、超過したWPに比例するようだった。
「どうした、健司? 顔色悪いぞ」
佐藤が心配そうに声をかける。健司は「なんでもない」と力なく笑うことしかできなかった。この呪いのことは、誰にも言えない。特に、純粋に笑いを愛する相方には。健司は、全力で人を笑わせることを禁じられた、悲劇のコメディアンだった。
第二章 980ポイントの壁
それ以来、健司は意図的に舞台の熱量をコントロールするようになった。佐藤がアドリブを仕掛けてきても、当たり障りのないツッコミで流す。観客のWPが900を超えそうになると、わざと間を外したり、凡庸な返しをしたりして、笑いを失速させる。当然、舞台の評価は下がった。
「なあ、健司。最近どうしたんだよ」
ある日の稽古後、佐藤が缶コーヒーを差し出しながら切り出した。彼の顔には、隠しきれない不満が滲んでいる。
「お前のツッコミ、キレが悪い。守りに入ってるっていうか……なんか、セーブしてないか?」
図星だった。健司は缶を握りしめ、視線を落とす。
「……スランプ、なんだよ。悪い」
嘘をつくたびに、胸の奥がキリキリと痛んだ。佐藤は才能の塊だ。彼のボケは、健司のツッコミという触媒があってこそ、最高の化学反応を起こす。なのに、自分はその爆発を恐れている。
そんな中、若手芸人の誰もが夢見る大型お笑いコンテスト『THE LAUGHING KING』の開催が告知された。優勝すれば、一夜にしてスターダムにのし上がれる。
「これだ、健司! これに俺たちの全部を賭けよう!」
佐藤は子供のようにはしゃいだ。その純粋な情熱が、健司には眩しすぎた。コンテストの舞台でセーブなどできるはずがない。勝ち進めば、WPは天井知らずに跳ね上がるだろう。その先にあるのは、財布をなくす程度では済まない、破滅的な不幸かもしれない。
答えを出せないまま、健司は一人、近所の公園のベンチに座ってため息をついていた。ネタ帳を開いても、浮かんでくるのは破滅のイメージばかりだ。
「面白いことを考えるのは、難しいかい」
不意に、しわがれた声がした。見ると、隣に小柄な老婆が座っていた。手には古びた杖をついている。
「まあ……はい。人を笑わせるって、簡単じゃないですから」
「あんたの漫才、この前ライブハウスで見たよ」
健司は驚いて顔を上げた。
「へえ。どうでした?」
「相方さんは、火の玉みたいだね。あんたは、それを優しく受け止める風のようだ。でも、最近はその風が弱くて、火の玉が燻っちまってる」
老婆の言葉は、すべてを見透かしているようだった。健司の視界には、彼女の頭上に浮かぶWPが見えた。数値は『0』。笑っていない。
「……どうすれば、強い風を吹かせられるんでしょうか」
思わず、本音を漏らしていた。老婆は健司の目をじっと見つめ、ゆっくりと口を開いた。
「風は、誰かのために吹くもんさ。自分のためじゃない」
その言葉の意味を、健司はすぐには理解できなかった。老婆は静かに立ち上がると、杖を頼りにゆっくりと去っていった。その背中を見送りながら、健司は「誰かのために」という言葉を、何度も心の中で反芻していた。
第三章 リミッター解除
『THE LAUGHING KING』一回戦当日。会場の空気は、芸人たちの熱気と野心で張り詰めていた。舞台袖で出番を待つ間も、健司の心は揺れ動いていた。ここで失敗すれば、佐藤とのコンビは終わるかもしれない。だが、本気を出せば、自分の人生が終わるかもしれない。
「次、5番、アップダウンズさん、スタンバイお願いしまーす!」
スタッフの声が響く。佐藤が健司の背中を強く叩いた。
「健司、楽しもうぜ。俺たちの最高のネタで、全員笑わせてやろう」
その瞳には、一点の曇りもなかった。健司は、腹を括るしかなかった。
まばゆいスポットライトを浴びて、二人はマイクの前に立つ。ネタが始まると、佐藤は水を得た魚のように躍動した。彼のボケは、稽古の時よりも遥かに鋭く、奇想天外だった。観客は瞬く間に彼らの世界に引き込まれていく。
健司の脳内カウンターは、恐ろしい勢いで上昇を始めた。『500』、『700』、『900』……。
警報が鳴り響く。指先が冷たくなり、呼吸が浅くなる。佐藤が、勝負のボケを繰り出した。練習では一度もやらなかった、とっておきのアドリブだ。
健司の頭が真っ白になる。ツッコめない。ここでツッコんだら、確実に1000を超える。
「……健司?」
佐藤の声が、マイクを通して会場に響く。それは、戸惑いと、ほんの少しの悲しみが混じった声だった。観客も、不自然な間に首を傾げている。
その瞬間、健司の脳裏に、公園の老婆の言葉が蘇った。
『風は、誰かのために吹くもんさ』
そうだ。俺は今まで、自分の不幸を恐れて、自分のために笑いを制限してきた。でも、違う。今、目の前で最高のボケを放った相方がいる。俺のツッコミを待っている。俺たちの漫才で笑うために、ここに来てくれたお客さんがいる。
自分のことなんて、どうでもいい。
こいつを、佐藤を、最高のボケにしてやりたい。お客さんを、心の底から笑わせたい。
「――ああ、もうどうにでもなれ!」
健司は、心の奥底で自分を縛り付けていた鎖を、自ら引きちぎった。
「そんなわけあるかぁ! お前が言ってるのはな、キリンの首が伸び縮みするくらいあり得ないんだよ! しかもそのキリン、たぶん反抗期だぞ! 親子で話し合え!」
リミッターを解除したツッコミは、もはや技術ではなかった。魂の叫びだった。それは佐藤のボケという火の玉に、最大風速の風を送り込み、舞台上で見たこともないような大爆発を引き起こした。
会場が、揺れた。割れんばかりの拍手と、腹を抱えて涙を流す観客たちの爆笑。
金色のWPが嵐のように吹き荒れ、健司の脳内カウンターは意味不明な記号を羅列した末に、フッと消えた。計測不能。
健司は目を固く閉じた。これで終わりだ。どんな天変地異が俺を襲うのか。
しかし、何も起きなかった。
落下する照明も、失くした財布もない。ただ、鳴り止まない拍手と笑い声が、全身を包んでいるだけだった。
舞台袖に戻っても、異常はなかった。混乱する健司の前に、見覚えのある人影が現れた。公園の老婆だった。彼女はなぜか、関係者パスを首から下げている。
「見事な風だったよ」
老婆は、穏やかに微笑んでいた。
「どうして……何も起きないんです? WPは、とっくに限界を超えたはずなのに」
健司が尋ねると、老婆はゆっくりと首を振った。
「あんたの力は、呪いじゃない。祝福さ」
「……祝福?」
「ワライ・ポイントは、人々から集めた幸福のエネルギーそのもの。それを自分の保身や名声のために使うと、反作用としてあんたに不幸が返ってくる。だがね、今日、あんたは違った。相方のために、観客のために、ただ純粋に笑いを届けようとした。その利他の心で放たれたエネルギーは、あんたに跳ね返らず、世界を少しだけ幸せにするために還元されたのさ」
老婆の言葉が、雷のように健司の心を貫いた。呪いだと思っていたものは、使い方を間違えていただけだった。自分の不幸を恐れていた心こそが、本当の呪いだったのだ。
第四章 祝福のスポットライト
一回戦の結果は、圧倒的な点数での一位通過だった。楽屋に戻る道すがら、健司は佐藤にすべてを打ち明けた。ワライ・ポイントのこと、呪いだと思っていたこと、そしてそれが祝福だったこと。
話を聞き終えた佐藤は、一瞬きょとんとした後、腹を抱えて笑い出した。
「なんだよそれ! 俺、そんな壮大な設定のツッコミ担当とコンビ組んでたのかよ! 最高のボケじゃねえか!」
その屈託のない笑い声に、健司の心に残っていた最後のわだかまりも、きれいに溶けていった。二人の絆は、雨降って地固まるどころか、嵐の後に虹がかかったように、より強く、鮮やかになった。
数週間後、コンテストの二回戦の舞台に、アップダウンズの姿はあった。健司が観客席を見渡すと、そこにいる一人ひとりの頭上に、色とりどりのWPの蕾が見えた。それはもはや、恐怖の時限爆弾のカウンターではない。これから咲き誇る、幸福の花々に見えた。
マイクの前に立ち、深く息を吸う。隣には、最高の相方がいる。目の前には、笑う準備ができている観客がいる。
健司は思う。笑いとは、何かを犠牲にして得るものではない。誰かの不幸の上に成り立つものでもない。それは、ただ分かち合うもの。与えれば与えるほど、世界に満ちていく、温かい光のようなものなのだ。
彼は、最高の笑顔で言った。
「どうもー! アップダウンズです!」
客席から、期待に満ちた温かい笑いが起きる。そのWPが、まるで優しい光の粒子となって、健司の全身に降り注ぐ。もう、不幸は訪れない。彼は、本当の意味で人を笑わせる喜びと、その尊さを知ったのだから。
彼の視界に映る世界は、祝福の光でキラキラと輝いていた。