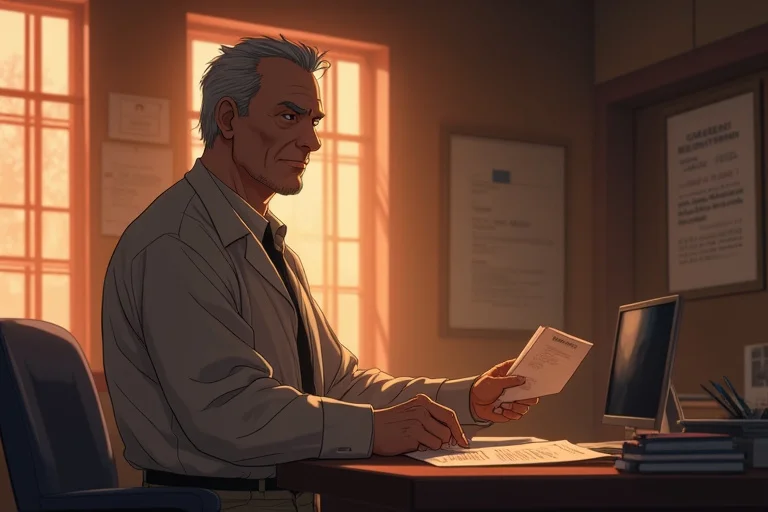第一章 香る街の奇行
僕の住むこの街は、欲望の香りに満ちている。それは比喩ではない。人々が心の底で強く願うものが、ある日を境に物理的な『香り』として具現化し、予告なく大気を満たすようになったのだ。
ある日の午後、街は「一等地の角部屋が欲しい」という不動産業者の強烈な欲望が具現化した、新築の家の木の香りに包まれた。すると、道行く人々は皆、四つん這いになって地面の匂いを嗅ぎ始め、まるで自分が犬にでもなったかのように電柱にマーキングをする真似事を始めた。またある時は、パティシエの「究極のショートケーキを作りたい」という願いが、鼻腔をくすぐる甘いバニラの香りとなり、住民全員がスキップで移動するというメルヘンチックな集団行動を引き起こした。
そんな奇妙な日常にも、人々は次第に慣れていった。香りが消えれば、奇行の記憶は曖昧な夢のように薄れていく。だが、ここ数週間、街には一つの不快な香りが居座り続けていた。それは何の欲望から生まれたのか見当もつかない、『不協和音の香り』だった。錆びた鉄と腐った果実を混ぜ合わせたような、脳の皺に直接やすりをかけるようなその香りは、住民たちにこれまでで最も不可解な奇行を強いていた。
「またか……」
僕はカフェの窓から外を眺め、深く溜め息をついた。不協和音の香りが一段と濃くなった瞬間、歩道を歩いていた人々が一斉に、着ている服を器用に裏返しに着始めたのだ。サラリーマンはワイシャツを、学生は制服を、老婆はカーディガンを。その光景は滑稽であると同時に、底知れぬ不気味さを漂わせている。
その時、僕の目の前で小さな女の子が石につまずいて転んだ。軽い擦り傷。少女が泣き出す。すると、僕の頭皮に微かな、しかし確実な喪失感が走った。そっと頭頂部に手をやると、数本の髪が抜け落ちたのが分かる。僕、鏡見蓮(かがみれん)は、他人の不幸を目の当たりにすると、その規模に応じて髪が増減する特異体質だった。大災害のニュースを見れば一夜にして腰まで伸びる剛毛となり、隣人が爪を割ったと聞けば円形脱毛症の一歩手前まで後退する。実に厄介な体質だ。
この終わらない奇行と、常に漂う不協和音の香りは、街全体を覆う巨大で持続的な不幸の源泉と言えた。そのせいで、僕の頭髪は最近、危険な水域をさまよっている。
「もう、我慢の限界だ」
僕は席を立ち、アパートへと戻った。目的は一つ。埃をかぶった祖父の遺品箱から、古びた鼻眼鏡のような『欲望可視化ゴーグル』を取り出すためだ。香りの発生源を突き止め、この狂った日常に終止符を打つ。それができなければ、僕の頭は近いうちに、つるりとした満月になってしまうだろう。
第二章 逆さまの世界で追うもの
『欲望可視化ゴーグル』をかけると、世界は奇妙な色合いを帯びた。そして、何とも厄介な副作用が僕を襲う。装着者の顔、つまり僕の顔が常に逆さまに見えるのだ。鏡に映る自分の顎から眉が生え、額に口がある光景は、何度見ても慣れそうにない。
しかし、その不便さと引き換えに得られる情報は絶大だった。ゴーグル越しに見る世界では、街を覆う不協和音の香りが、よどんだ紫色の靄として可視化されていた。それはまるで、街全体が病に侵されているかのように、建物の隙間や人々の頭上を気味悪く漂っている。
「こっちか……」
僕は靄が最も濃く、その流れが生まれている方向へと歩き始めた。すれ違う人々の顔が、ゴーグル越しに上下逆さまに見える。逆さまに笑いかける婦人、逆さまに怒鳴りながら自転車を漕ぐ青年。狂った街並みに、さらなる狂気が上乗せされたようだ。
時折、紫色の靄とは異なる、別の色の香りが立ち上るのが見えた。パン屋の前では、焼きたてのパンを渇望する人々の思いが黄金色の湯気となって立ち上り、それに誘われた人々が店に吸い込まれていく。公園では、昼寝をしたいという老人の欲望が、淡い水色の穏やかな霧となってベンチの周りを漂っていた。欲望は、必ずしも悪ではない。それは生命の輝きそのものだ。だが、街を覆うこの紫の靄だけは、明らかに異質だった。それは欲望というより、執念や怨念に近い、歪んだ粘り気を感じさせた。
靄を辿り着いた先は、街で最も格式高いとされる丘の上の高級住宅街だった。そして、紫色の靄は明らかに、その中でも一際大きな屋敷から湧き出している。
鷲尾厳(わしおげん)。この街の市長であり、厳格で威風堂々とした人格者として市民から絶大な支持を得ている男の屋敷だ。
まさか。あの清廉潔白で知られる市長が、こんな不気味な欲望の源だというのか? 疑念と好奇心が、僕の足を屋敷の重厚な鉄門へと向かわせた。
第三章 市長室の秘密
深夜、僕は鷲尾邸の塀を乗り越えていた。僕の髪がこれ以上減るのを防ぐためだ。そう自分に言い聞かせ、一種の正当防衛だと結論付けた。幸い、屋敷の警備は手薄だった。おそらく、この街の奇行騒ぎのせいで、警備員たちも正常な思考を保てていないのだろう。
ゴーグルが示す紫の靄は、二階の書斎と思われる部屋から漏れ出ていた。窓から漏れる明かりを頼りに、壁を伝ってバルコニーにたどり着き、そっとガラス戸の隙間から中を覗く。
そこに広がっていたのは、僕の想像を遥かに超える光景だった。
威厳の象徴であったはずの市長、鷲尾厳が、椅子に腰かけ、汗だくで、顔を真っ赤にしながら、巨大なアコーディオンを必死に演奏していたのだ。その表情は苦悶に満ちており、まるで拷問でも受けているかのようだ。そして、そのアコーディオンから奏でられる音色は、まさに街を包む不協和音そのものだった。猫の断末魔とガラスを爪で引っ掻く音をミキサーにかけたような、おぞましい旋律。
蛇腹が伸縮するたびに、濁った紫色の香りが物理的な靄となって噴き出し、部屋を満たしていた。これだ。これが全ての元凶だ。
『世界一のアコーディオン奏者になりたい』
ゴーグルを通して、彼の欲望が灼熱の文字のように浮かび上がって見えた。あまりにも純粋で、強烈で、しかし、絶望的なまでに才能が伴っていない欲望。その歪みが、街全体を狂わせていたのだ。
僕が息を呑んだ音に、鷲尾が気づいた。彼は演奏を止め、ギョッとした目でこちらを睨みつけた。
「だ、誰だ貴様は!」
「市長…」僕はバルコニーから部屋に足を踏み入れた。「そのアコーディオンが、街の奇行の原因です。今すぐそれをやめてください」
鷲尾の顔が怒りでさらに赤く染まる。「何を言うか!これは私の夢だ!長年、公務に身を捧げてきた私が、唯一、自分のために追い求めている夢なのだ!誰にも邪魔はさせん!」
彼はアコーディオンを抱え直し、再びおぞましい音を奏でようとした。その瞬間、僕は彼に飛びかかっていた。
第四章 不幸と祝福のフーガ
もみ合いは、あっけなく終わった。長年デスクワークに勤しんできた市長と、自分の髪を守るために必死な僕とでは、体力が違いすぎた。アコーディオンは鷲尾の手を離れ、床にゴトンと鈍い音を立てて転がった。
その瞬間、世界から音が消えたかのような静寂が訪れた。いや、違う。おぞましい不協和音が消えたのだ。窓の外を見やると、街を覆っていた紫色の靄が、まるで陽光に溶ける朝霧のように、すうっと消え去っていくのが見えた。
呆然と立ち尽くす鷲尾を残し、僕は屋敷を後にした。
翌朝、街は嘘のような平穏を取り戻していた。人々は昨夜までの奇行を「なんだか変な夢を見ていたようだ」と首を傾げながら、いつも通りの日常を送っている。カフェの窓から見えるのは、ごく普通の、何の変哲もない街の風景だ。不協和音の香りは、もうどこにもない。
僕は安堵のため息をつき、無意識に自分の頭に手をやった。そして、指先に触れた信じられない感触に、凍りついた。
「な……んだ、これ……」
鏡に映った僕の頭は、爆発していた。髪一本一本が異常なまでの生命力で自己主張し、黒々とした巨大なアフロヘアーを形成している。まるで黒い綿菓子だ。
鷲尾市長の『長年追い続けた夢が、目の前で見ず知らずの若者に打ち砕かれた』という、特大の不幸。それを間近で目撃してしまった僕の頭皮は、過去最大級の活性化を果たしたのだ。
その頃、市長室では。鷲尾厳が鏡の前に立ち、愕然としていた。彼のトレードマークであり、威厳の源でもあった豊かな白髪が、一夜にして全て抜け落ち、頭は磨き上げたビリヤードの球のように、つるりとしていた。長年の夢を失った絶望が、彼の毛根にまで追い打ちをかけたのか。もちろん、自分の不幸が、昨夜忍び込んできた侵入者の髪を祝福したなどとは、知る由もなかった。
僕は、手に負えないこの爆発した髪を抱えながら、青空を見上げた。街にはもう、不協和音の香りはしない。代わりに、どこかの家から漂ってくる、朝食の味噌汁の香りが鼻をくすぐる。「ああ、お腹が空いたな」という、誰かのささやかで温かい欲望の香りだ。
平和を取り戻した街と、その代償として得たこの滑稽な頭。僕は乾いた笑いを漏らしながら、とりあえず一番近くの理髪店を探して歩き始めた。この髪をどう説明すればいいのか、見当もつかないままに。