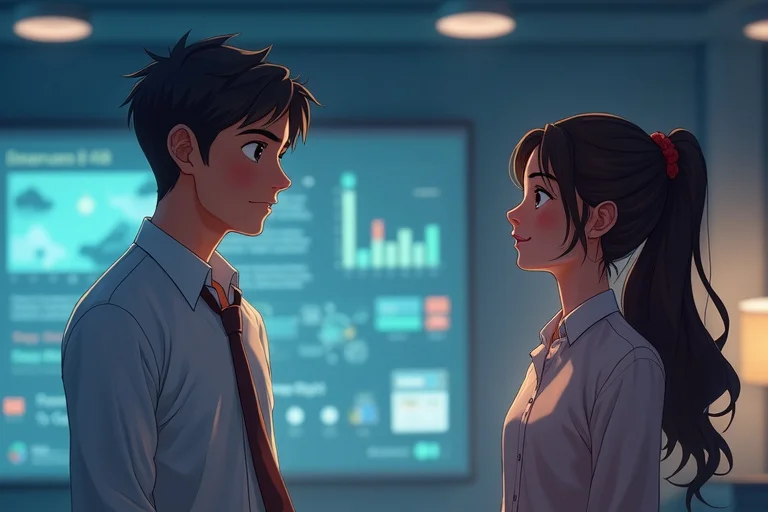第一章 静寂の図書館と、こぼれたインク
天野蒼太は、沈黙を吸って生きているような男だった。彼が司書補として働く市立図書館の古書庫は、まさにうってつけの隠れ家だった。革装丁の背表紙が放つ乾いた匂い、かすかに舞う埃、そしてページをめくる音だけが許された世界。ここでは、複雑なジェスチャーで挨拶を交わす必要も、昼食のメニューを身振り手振りで注文する必要もない。
この世界では、言葉は思考を縁取る額縁に過ぎない。あらゆる合意形成、交渉、果ては愛の告白までが、数万種類にも及ぶ『公式ジェスチャー』によって執り行われる。蒼太は、それが死ぬほど苦手だった。人々の視線が自分の一挙手一投足に集中するのを感じると、心臓が喉元までせり上がり、指先は氷のように冷たくなる。そして決まって、おかしなことが起きるのだ。ペン立てのペンがふわりと宙に浮いたり、足元の床がゼリーのように一瞬だけ揺れたり。もちろん、気のせいだ。彼はいつもそう結論付けた。
その日、古書庫の重い扉が軋む音を立てて開いた。現れたのは、凛と名乗る女性だった。燃えるような瞳と、古代遺跡から発掘された装飾品のように複雑なジェスチャーを淀みなく繰り出す、快活な女性。ジェスチャー考古学者だという彼女は、禁帯出である『世界公式ジェスチャー大全集』の閲覧を求めてきた。
「これですわね」
蒼太は手袋をはめ、台車に乗せた巨大な本を彼女の前の閲覧机に運ぶ。ずしり、と重たい音を立てて本が置かれる。その存在感だけで蒼太の呼吸は浅くなった。
凛が感謝の意を示す複雑なジェスチャー(両手の指を絡め、鳥が羽ばたくように広げる形)を向けた瞬間、蒼太の緊張は頂点に達した。
「い、いえ…」
声にならない声を発し、お辞儀のジェスチャーをしようとした彼の肘が、うっかりインク瓶に当たった。黒い液体が、まるで生き物のように跳ね、大全集のページに見事な染みを作ってしまった。
凛の大きく見開かれた瞳と、蒼太の真っ青な顔。そして、インクの染みがじわりと広がり、肝心なイラストを黒く塗りつぶしていく様を、古書庫の沈黙だけが静かに見守っていた。
第二章 意味の無い身振り
世界がおかしくなり始めたのは、その数日後のことだった。最初は、街角の若者たちの間で流行っている、ただの悪ふざけだと思われていた。両腕を奇妙な角度で交差させ、片方の手のひらを空に向け、もう片方の指先で地面を指す。そんな、どのジェスチャー辞典にも載っていない、意味不明な身振り。
しかし、それは悪性のウィルスのように瞬く間に世界中に伝播した。
交通整理員がそのジェスチャーをしたせいで交差点は大渋滞に陥り、市場の競り人が使えば誰も値をつけられず、取引は不成立。銀行の窓口、役所の申請、レストランの注文に至るまで、あらゆる公式ジェスチャーゲームが機能不全を起こし始めた。まるで、世界のコミュニケーション回路が、根本から焼き切られてしまったかのようだった。
「これは…失われた古代ジェスチャー、『原初の言葉』かもしれないわ」
図書館に日参するようになった凛は、インクの染みがついた大全集のページを睨みながら、興奮気味に言った。蒼太は、彼女の情熱に巻き込まれる形で、半ば強制的に調査の助手にさせられていた。
「ただの、間違いでは…」
「間違いが、世界中で同時に起こるものですか!」
凛は蒼太の弱気なジェスチャーを一蹴する。彼女は、謎のジェスチャーが最初に目撃された場所のリストを作り、地図上にピンを刺していた。蒼太は、その地図に既視感を覚えた。ピンが刺さった場所のいくつかは、自分が最近、極度の緊張を強いられた場所―――大事なプレゼンで失敗した会社のロビー、大勢の前でスピーチをさせられた広場―――と、不気味に一致していたからだ。背筋に冷たい汗が流れたが、まさか、と彼はその考えを振り払った。
第三章 螺旋のパニック
混乱は加速した。東方連合と西方同盟の和平交渉は、大使が挨拶のつもりで謎のジェスチャーを繰り出したことで決裂寸前に陥った。「侮辱」と解釈した相手側が、即座に国交断絶を示唆するジェスチャーで応酬したのだ。世界は、意味の通じない身振りの応酬によって、かつてない緊張状態に包まれた。誰もが互いを信じられなくなり、沈黙と猜疑心が街を覆っていた。
蒼太の日常も、もはや平穏ではなかった。図書館に来る人々は、貸し出し手続きのジェスチャーすらおぼつかない。誰もが苛立ち、誰もが途方に暮れていた。その人々の不安が、蒼太の緊張をさらに煽った。彼の周りでは、ますますおかしなことが頻発した。返却された本がひとりでに書架に戻ったり、閲覧室の椅子が微妙に床から浮き上がったり。
「天野さん、見て。ジェスチャーの発生源には、ある種のパターンがあるみたい」
凛が突きつけてきた資料には、発生現場の共通点が記されていた。「突発的な気圧の低下」「微弱な磁場の乱れ」「原因不明の光の屈折」。それはまるで、その場所でだけ物理法則が僅かに歪んでいることを示唆していた。
蒼太は、自分の心臓が大きく脈打つのを感じた。それは、自分がパニックに陥った時に感じる、世界がぐにゃりと歪むあの感覚と、あまりにもよく似ていた。恐怖が、彼の喉を締め上げた。まさか。自分のせいだとでもいうのか。そんな馬鹿なことが。
第四章 塔の上のジェスチャー
事態を収拾すべく、世界の指導者たちが一堂に会する『世界ジェスチャー評議会』が、街のシンボルである古時計塔の広場で緊急開催されることになった。
「この評議会で、謎のジェスチャーの正体がわかるかもしれない。お願い、天野さん。一緒に来て」
凛の真剣な眼差しに、蒼太は断ることができなかった。彼女は、このジェスチャーが「新しい概念」を人々に提示しているのだと信じていた。蒼太は、ただこの悪夢が終わってくれれば、それでよかった。
広場は、人々の不安と期待でむせ返るようだった。各国の代表が壇上に上がり、議論(もちろんジェスチャーによる)が始まるが、すぐに膠着状態に陥った。誰もが相手の意図を測りかね、そして誰もが、あの忌まわしい謎のジェスチャーをいつ繰り出すかと警戒していた。
その張り詰めた空気、数万の視線、鳴り響く報道ヘリのローター音。そのすべてが巨大な圧となって、蒼太にのしかかった。
息ができない。
世界が、ぐらりと傾ぐ。
その瞬間だった。ゴーン、と厳かに時を告げるはずだった時計塔の鐘が、甲高い金属音を立てて止まった。巨大な長針が、カクカクと不自然に逆回転を始める。広場の中心にある噴水の水が、重力に逆らって巨大な螺旋を描きながら、空へと昇っていく。人々の足元の影が地面から剥がれ、まるで黒い炎のように揺らめき始めた。
悲鳴は上がらなかった。あまりに非現実的な光景に、誰もが声もジェスチャーも失い、ただ立ち尽くしていた。
パニックの絶頂で、蒼太の身体が勝手に動いた。彼は、まるで操り人形のように、奇妙なポーズを取った。両腕を複雑に絡ませ、震える指先を天に突き刺すように向け、片足でふらつきながら立つ。それは、逆回転する時間、螺旋を描いて昇る水、揺らめく影、そのすべてを一つの動きに凝縮したかのような、歪でありながら、恐ろしく美しいジェスチャーだった。
第五章 新しい秩序
広場の沈黙を破ったのは、壇上にいた老練なジェスチャー言語学者だった。彼は蒼白な顔で、震える指で蒼太を指し示した。
「あの動きは…! 今、我々が見ているこの現象そのものを、表現している…!」
その言葉が引き金になった。人々は、目の前で起きている物理法則の崩壊と、蒼太の取った奇妙なポーズが、完璧に一致していることに気づいたのだ。
「『時空の局所的な逆行』を示すジェスチャーだったのか!」
「いや、『重力ベクトルの多次元的展開』だ!」
誰もが理解した。世界を混乱の渦に陥れたあの意味不明なジェスチャーは、間違いでも、古代の言語でもなかった。それは、人類がまだ名前を持たなかった“新しい物理現象”を表現する、生まれたばかりの『言葉』だったのだ。
この発見は、世界を一変させた。謎のジェスチャーは、『予測不能な変化』あるいは『既存の秩序の外側にある可能性』を意味する、極めて高度で哲学的なジェスチャーとして正式に認定された。
それまで「はい」か「いいえ」の二択でしかなかった交渉の場に、「予測不能な変化を受け入れ、第三の道を探る」という新しい選択肢が生まれたのだ。国家間の対立は融和へと向かい、停滞していた経済は新しいアイデアで活気づき、世界はかつてないほどの調和と創造性に満ちた時代を迎えた。
混乱は、新しい秩序の産声だったのだ。
第六章 逆さまに落ちた林檎
蒼太は、自分が気を失っている間に何が起きたのか、全く理解していなかった。気がついた時には広場は歓声に包まれており、人々が涙ながらに未知のジェスチャーを交わし合っていた。
「すごい人混みで緊張して、変な体勢で固まっちゃっただけなんだけどな…」
彼は、歴史の教科書に「蒼太のポーズ」として掲載されることになる、あのジェスチャーのことを、ただの醜態だと思っていた。
数日後、凛が英雄として世界中から賞賛を浴びる中、彼女はひっそりと蒼太の図書館を訪れた。
「天野さん、あなたがあの世界を救ったのよ! あのポーズが、新しい時代の扉を開いたんだわ!」
凛は興奮してまくし立てるが、蒼太には何のことやらさっぱりだった。彼はただ、彼女の笑顔を前にして、また心臓が早鐘を打つのを感じていた。
「これ、お礼。ほんの気持ちだけど」
凛が感謝のジェスチャーと共に差し出したのは、真っ赤な一個の林檎だった。蒼太が「ありがとう」のジェスチャーを返し、おずおずとそれを受け取ろうと手を伸ばした、その瞬間。
また、少しだけ緊張してしまった。
つるり、と凛の指から滑り落ちた林檎は、しかし、床には向かわなかった。まるでスローモーション映像のように、ふわりと宙に浮かび上がると、そのままゆっくりと、天井に向かって「落ちて」いった。
コツン、と軽い音を立てて、林檎は天井に張り付いた。
「うわっ!」と素っ頓狂な声を上げる蒼太。
その隣で、凛は天井の林檎を見上げ、発見者の瞳をきらきらと輝かせていた。
「すごい…! また新しい物理現象! ねぇ天野さん、これを表すジェスチャーは、一体どんな形になるのかしら!?」
自分の平穏な日常が、また一つ、遠ざかっていく。蒼太は、天井に逆さまに実った赤い果実を呆然と見上げながら、これから始まるであろう新たな厄介事に、深いため息をつくことしかできなかった。