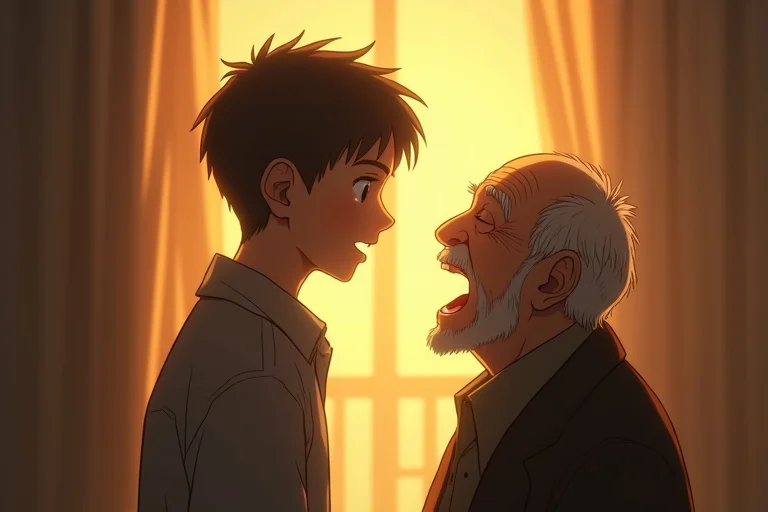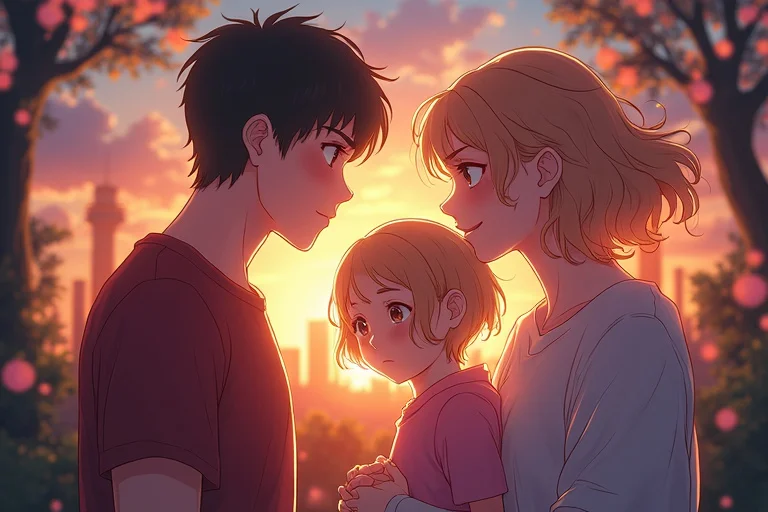第一章 ホコリまみれの真実とカラフルな厄介者
潔癖誠(いさぎよしまこと)の仕事は、掃除だ。ただし、彼が相手にするのは物理的な汚れではない。彼が取り払うのは、「嫉妬」という名の緑青色の粘菌であり、「後悔」として壁に染み付いた黒い煤であり、「怠惰」が生み出す綿菓子のような、しかし鉄のように重いホコリの塊だ。彼は、この世界で数少ない『概念清掃士』だった。
誠の仕事場は、人々の心が生み出す澱(おり)が具現化する場所だ。彼のモットーは「迅速、確実、そして感情移入ゼロ」。概念はあくまで除去すべき対象であり、そこに感傷を挟む余地はない。彼の愛用する特殊な掃除機『ロゴス』は、あらゆるネガティブな概念を論理的に分解し、吸引する。彼の白く糊の効いた作業着は、これまで一度も汚れを付着させたことがなかった。彼の心のように。
その日、誠のもとに舞い込んだ依頼は、異例ずくめのものだった。依頼主は、IT業界の寵児として名を馳せた老富豪、郷田宗介。依頼内容は「屋敷の一部を占拠した、正体不明の概念汚染の除去」。電話口から聞こえる郷田の声は、富と名声を手にした男のものとは思えないほど、切羽詰まっていた。
「報酬は言い値で構わん。とにかく、あれを、あれをなんとかしてくれ」
最新鋭のセキュリティを抜け、大理石の床がどこまでも続く郷田邸の奥。案内されたのは、かつては書斎だったという広大な部屋だった。息を呑んだ。部屋の中央には、小山のような「何か」が鎮座していた。
それは、あらゆる定義を拒絶する存在だった。ゼリーのようであり、綿雲のようでもあり、ネオンサインのように明滅するかと思えば、次の瞬間には古びたレンガのような質感に変わる。色は虹色のマーブル模様で、絶えず形を変え、予測不能な動きを繰り返していた。時折、トランペットの陽気なファンファーレのような音を立てたり、熟れたバナナの匂いをあたりに振りまいたりする。
誠は冷静にゴーグルを装着し、携帯分析機『パトス・スキャナー』をかざした。画面に表示された解析結果を見て、彼は眉をひそめた。
概念:ユーモア
汚染レベル:9(暴走状態)
特記事項:極めて不安定。論理的アプローチへの強い耐性あり
ユーモア。冗談、おふざけ、諧謔。誠が人生において最も不要なものとして切り捨ててきた概念だ。生産性がなく、論理を破壊し、しばしば誤解を生む。そんな非効率なものが、なぜこれほど巨大な汚染と化しているのか。
「……郷田さん。これは、いつから?」
「一月ほど前だ」郷田は苦々しく顔を歪めた。「最初は、小さな虹色のシミだった。それが日に日に大きくなり、今ではこの有様だ。部屋の家具は飲み込まれ、時々、変な音を立てては壁からラバーカップを生やしたりする」
誠はこめかみを押さえた。ラバーカップ。意味が分からない。だが、それが「ユーモア」の本質なのかもしれない。理解不能で、無秩序。彼が最も忌み嫌うもの。
「お任せください。私の『ロゴス』は、あらゆる非論理を分解します」
彼は宣言し、純白の手袋をはめ直した。眼前のカラフルな厄介者を、まるで数学の問題を解くかのように冷徹に見つめる。しかし、その不定形な塊の奥で、何かがキラリと光ったような気がした。それは、まるでこっちを見て、悪戯っぽくウィンクしたかのように見えた。
第二章 論理の掃除機はアヒルに勝てない
誠の清掃計画は、常に完璧だった。対象の概念を構成要素に分解し、最も脆弱な結合点から順に吸引していく。彼は「暴走したユーモア」を前に、いつもの手順を踏んだ。
「まず『皮肉』の層を剥離し、次に『駄洒落』の核を中和する。最後に残った『不条理』のエネルギーを拡散させ、吸引する」
彼は『ロゴス』のモードを「反語的論理(アイロニー・ロジック)」に設定し、ノズルを塊に向けた。強力な吸引音が鳴り響き、塊の表面がさざ波のように揺れる。よし、効いている。誠がそう確信した瞬間だった。
『ロゴス』の排気口から、ポンッ、と乾いた音がした。次の瞬間、色とりどりの紙吹雪が滝のように噴き出し、あっという間に誠の全身を覆った。キラキラと舞う紙片の中、彼は呆然と立ち尽くす。完璧に糊付けされた作業着が、まるでお祭りの後の道化師のように彩られていた。
「なっ……!?」
塊は、ぶるぶると楽しそうに震えている。まるで腹を抱えて笑っているかのようだ。
「くそっ……! ならば、直接洗浄だ」
誠は次に、高圧洗浄機『カタルシス』を取り出した。概念の表層構造を洗い流すための特殊な論理溶液を充填し、噴射する。しかし、溶液が塊に触れた途端、それは無数の黄色いアヒルのオモチャに姿を変え、床にボトボトと落ち始めた。一つ、また一つと増殖し、数分後には誠の足首が黄色いアヒルの海に埋もれていた。キュッ、キュッと間抜けな音が部屋に響き渡る。
何をしても、裏目に出る。論理的なアプローチはすべて、より高度な不条理によって無力化され、おちょくられているかのようだった。郷田は壁際で腕を組み、深いため息をついている。誠の額には、普段はありえない汗が滲んでいた。彼の完璧な世界に、初めて「エラー」という文字が点滅していた。
一週間が過ぎた。部屋はさらにカオスな状態になっていた。天井からは巨大なソーセージがぶら下がり、床から生えたキノコが時々、下手なオペラを歌いだす。誠は疲弊しきっていた。睡眠不足の目に映るカラフルな塊は、もはや除去すべき汚染ではなく、彼の無力さを嘲笑う巨大な怪物に見えた。
「なぜだ……。なぜ、私の論理が通じない……?」
彼は床にへたり込み、黄色いアヒルの一個を無心に握りしめた。キュッ、と鳴る音が、やけに悲しく響く。プライドはズタズタに引き裂かれ、自信は粉々に砕かれていた。その時だった。
彼が投げやりな気持ちで塊を睨みつけていると、その表面の動きがふと穏やかになった。そして、マーブル模様の中心が、まるで古い映写機のようにぼんやりと光り始めた。そこには、一つの情景が映し出されようとしていた。
第三章 世界で一番優しいジョークの正体
映し出されたのは、病院の一室だった。ベッドには、穏やかながらも衰弱の見える一人の女性が横たわっている。その傍らで椅子に座り、ただ黙って手を握っているのは、今よりも少し若い郷田宗介だった。部屋の空気は、鉛のように重い。
「ねえ、あなた」か細い声で、妻が口を開いた。「面白い話、してあげましょうか」
郷田は何も言わず、ただこくりと頷いた。
「宇宙飛行士がね、バーに行ったの。そしたらバーテンダーが『いつものやつかい?』って聞いたのよ。宇宙飛行士はなんて答えたと思う?」
妻は少し息を整え、悪戯っぽく笑った。
「『いや、今日は雰囲気を変えたい(I need a little space.)』ですって」
部屋に、沈黙が落ちた。郷田の顔は、悲しみに凍りついたままで、微動だにしない。妻は、はは、と力なく笑った。
「……だめね。すべっちゃった」
「すまない、さつき。笑えなくて」
「いいのよ。あなたの、その真面目すぎるところが好きだったんだから。でもね、私が死んだら、ちゃんと笑うのよ。笑ってないと、福が逃げちゃうわ。約束よ」
映像はそこで途切れた。
誠は、息をすることさえ忘れていた。隣を見ると、郷田が静かに涙を流していた。
「……妻だ。一年前、病気で亡くなった」
郷田は、震える声で語り始めた。
「あいつは、いつも俺を笑わせようとしてくれた。俺が仕事で追いつめられている時も、会社の経営が傾いた時も、いつもくだらないジョークで……。最後の最後まで、俺を……」
言葉が続かない郷田の背中を、誠はただ見つめていた。そして、部屋の中央にある巨大な塊を、もう一度見上げた。
あれは、汚染なんかじゃない。
悪意のあるゴミでもない。
あれは、愛する人を笑顔にしたいと願った、最後の、そして叶わなかった妻の想いそのものだった。悲しみの中で受け取られなかった優しさが、行き場をなくし、暴走するほどに膨れ上がってしまったのだ。純粋で、不器用で、どうしようもなく優しい、「ユーモア」の塊。
誠は、自分の仕事の根幹が揺らぐのを感じた。彼はこれまで、概念を「善」と「悪」、「必要」と「不要」で切り分けてきた。しかし、目の前にあるのは、そのどちらでもない、愛と悲しみが複雑に絡み合った、あまりにも人間的なものだった。
非効率? 無意味?
違う。
世界で一番、意味のあるゴミじゃないか。
彼はゆっくりと立ち上がると、これまで決して汚すことのなかった純白の作業着の袖で、自分の目元を拭った。そして、愛用の『ロゴス』を静かに床に置いた。この塊に必要なのは、論理的な分解や除去ではない。
必要なのは、きっと――。
第四章 笑う門には福来る、とは限らないけれど
誠は、アヒルの海をかき分け、巨大なユーモアの塊の前に立った。彼は深呼吸を一つすると、人生でほとんど使ったことのない顔の筋肉を、ぎこちなく動かした。
「……あの、一つ、なぞなぞを」
彼の唐突な言葉に、郷田が驚いて顔を上げる。誠は、耳まで赤くしながらも、声を張り上げた。
「パンはパンでも、食べられないパンは、なーんだ?」
シーン、と部屋が静まり返る。塊の動きも、ぴたりと止まった。誠は、心臓が口から飛び出しそうになるのを感じながら、震える声で答えを言った。
「……フライパン」
その瞬間、塊がぶるりと震えた。そして、塊の表面から、小さなシャボン玉が一つ、ふわりと浮かび上がった。
それを見た郷田が、ふっと息を漏らすように笑った。
「……なんだ、それ。妻が昔、よく言っていたよ」
郷田は涙の跡が残る顔で、懐かしむように目を細めた。そして、今度は彼が口を開いた。
「じゃあ、これはどうだ。いつも怒ってばかりいる野菜は、なんだと思う?」
彼は一呼吸おいて、優しい声で言った。
「……ごぼう(牛蒡)だ。すぐに『ゴボー』って言うからな」
郷田はそう言うと、くつくつと笑い始めた。それは、妻を亡くして以来、初めて見せた心からの笑顔だった。
その笑い声に呼応するように、ユーモアの塊は輝きを増し始めた。シャボン玉が次々と生まれ、部屋中を舞い始める。二人の笑い声が重なるにつれて、塊はその形を失い、無数の温かい光の粒子へと変わっていった。
それは「清掃」ではなかった。それは、悲しみごと、不器用さごと、すべてを受け入れる「受容」の儀式だった。
光の粒子は、書斎全体を優しく満たしていった。壁に染み付いていた郷田の「後悔」のシミは薄れ、床を覆っていた「悲嘆」のホコリは輝きの中に消えていく。天井のソーセージも、歌うキノコも、床のアヒルたちも、すべてが光に溶けて、部屋は元の静かで美しい書斎の姿を取り戻していた。ただ、窓から差し込む光が、以前よりもずっと柔らかく感じられた。
後日。潔癖誠の事務所でのことだ。
彼は、依頼人から持ち込まれた、どんよりと黒い「自己嫌悪」の塊を前にしていた。それは、粘着質で、重く、見るからに厄介な概念だった。以前の彼なら、即座に『ロゴス』で最大吸引していただろう。
しかし、誠は掃除機を手に取らなかった。代わりに、引き出しから一枚の紙を取り出す。そこには、彼が描いた、お世辞にも上手いとは言えない、塊のヘタクソな似顔絵があった。
彼はその絵を塊に見せると、少し照れたように、こう呟いた。
「まあ、お前のそういう不器用なところも……ちょっとは、面白いけどな」
すると、重苦しい黒い塊の隅が、ほんの少しだけ、虹色にきらめいた気がした。
誠の顔には、微かだが確かな笑みが浮かんでいた。世界から無駄で非効率なものがなくなることはない。だが、それとどう付き合っていくかは、自分次第なのだ。彼の真っ白な作業着の胸ポケットには、あの日のお礼だと言って郷田から無理やり渡された、黄色いアヒルのオモチャが一つ、顔を覗かせていた。