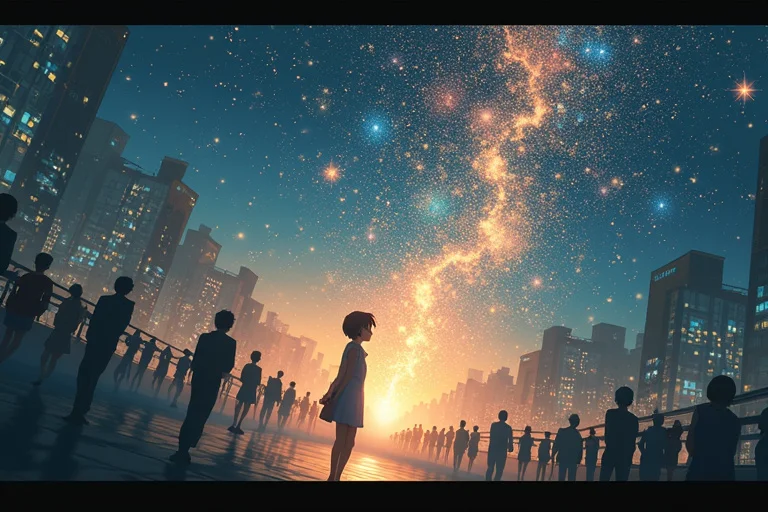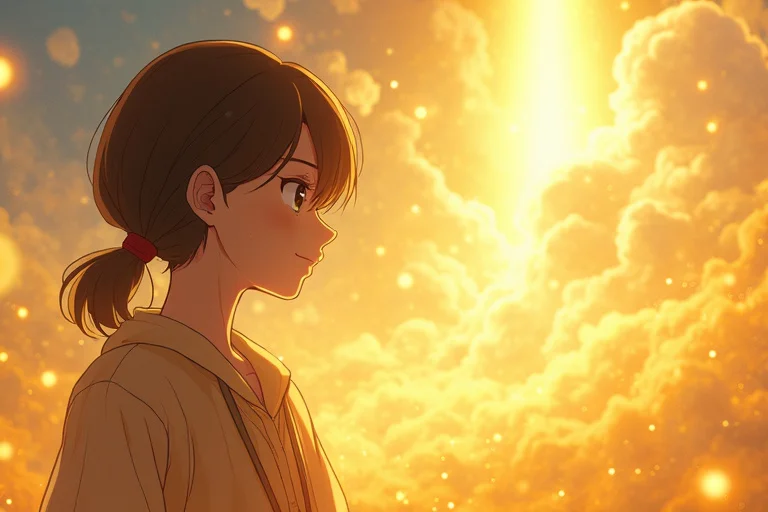第一章 災難回避手帳とひび割れたマグカップ
僕、相田健太の頭の上には、今朝から「ほんのり湿った八枚切り食パン」が乗っている。これが今日の僕のラッキーアイテムらしい。なぜ食パンなのか、なぜ湿っている必要があるのか、そんな問いに答えはない。この世界では、頭上にラッキーアイテムを乗せていないと、マンホールに吸い込まれたり、カラスに財布を奪われたり、とにかくロクなことにならないのだ。
僕はデスクでため息をつきながら、くたびれた革表紙の「今日の災難回避手帳」を開いた。ぱらり、と乾いた音を立ててめくれたページには、ミミズが這ったような文字でこう書かれていた。
『午後二時十四分、キーボードの『N』のキーだけが、一時的に家出する』
「……またこれか」
思わず声が漏れる。この手帳の予言はいつもこうだ。個人的すぎて、抽象的すぎて、回避しようにもどうしようもない。だが、これがないと落ち着かないのも事実だった。まるで、小さな絶望を常に携帯することで、大きな絶望に備えているような、そんな心持ちだった。
「相田くん! この報告書、なんだね!」
背後から課長の怒声が飛んできた。僕はびくりと肩を震わせ、慌てて振り返る。差し出された書類には、赤いインクで無数のバツ印が踊っていた。
「も、申し訳ありません! すぐに修正します!」
「すぐに、じゃない! いつになったらまともな仕事ができるんだ! 給料分の働きをしろ!」
頭が真っ白になる。困惑と動揺が、冷たい水のように背筋を駆け下りていく。その瞬間だった。
『お前の言い訳、中学二年生の夏休み最終日レベルだぞ』
デスクの端に置かれた、景品でもらったマグカップ。そのひび割れた飲み口が、かすかに震えているように見えた。声はそこから発せられていた。冷たく、乾いた、陶器が擦れるような声だった。僕は唇を噛みしめ、俯く。マグカップの言う通りだ。僕の弱点を、こいつは的確に抉ってくる。
第二章 空から降ってきた歯ブラシ
その異常な現象は、昼下がりの雑踏で起きた。
昼食を終え、会社に戻る途中だった。僕の頭上の食パンは、すっかり乾燥してパサパサになっていたが、それでも無いよりはましだった。交差点で信号を待っていると、ふと隣に立つサラリーマンの頭上に目が留まった。見事な枝ぶりの、小さな盆栽。今日の彼のラッキーアイテムは、随分と雅なものらしかった。
その時だ。
盆栽が、陽炎のように揺らめいたかと思うと、次の瞬間には、毛先が不揃いに広がった、使い古しの青い歯ブラシに変わっていた。
サラリーマンは、頭上の異変に気づく様子もない。だが、僕の心臓は嫌な音を立てて跳ね上がった。最近、街で噂になっている怪現象。頭上のラッキーアイテムが、突如として「他人のもの」と入れ替わるという。
そして、必ず。
直後、青信号に変わった。サラリーマンが横断歩道へ一歩踏み出した、その時。キーッ、という甲高いブレーキ音とともに、一台のバスが猛スピードで交差点に突っ込んできた。運転手がぐったりとハンドルに突っ伏している。人々が悲鳴を上げて逃げ惑う中、バスはサラリーマンを掠め、そのまま歩道脇のショーウィンドウに激突した。ガラスの割れる轟音が、街を震わせた。
僕はその場に凍りついていた。動けない。呼吸すら忘れていた。すると、足元のアスファルトが、ざらついた声で僕に囁きかけた。
『見て見ぬふりか? お前のせいじゃないのに、ビビりすぎだろ、小心者』
隣の信号機が、金属的な声で同調する。
『いつまでそこに突っ立ってるつもりだ。お前がここにいても、何も変わらないぞ』
罵倒のシャワーが僕を打ちのめす。僕は歯を食いしばり、その場から逃げるように駆け出した。背後で鳴り響くサイレンの音が、まるで僕の無力さを嘲笑っているかのように聞こえた。
第三章 祖母の研究所
世界は、ラッキーアイテム交換現象の恐怖に覆われた。テレビでは連日、専門家たちがもっともらしい顔で議論を交わしていたが、原因は誰にも分からなかった。
その夜、僕は自室のベッドで「災難回避手帳」を握りしめていた。いつもなら不安を増幅させるだけのこの手帳が、なぜか今夜は唯一の頼りに思えた。ページをめくると、そこには、いつものくだらない予言とは違う一文が記されていた。
『祖母の忘れ形見が、全ての鍵を握っている。埃を被った真実を探せ』
祖母。僕が子供の頃に亡くなった、風変わりな発明家だった。彼女が郊外に遺した研究所は、今はもう誰も訪れることなく、静かに時を刻んでいるはずだ。僕はベッドから跳ね起き、コートを羽織った。何かが、僕を突き動かしていた。
深夜のバスに揺られ、たどり着いた研究所は、蔦に覆われた廃墟のようだった。錆びついた鉄の扉に手をかけると、ドアノブがギシ、と軋むような声で言った。
『久しぶりだな、根暗ボーイ。相変わらず頭の上の食パンが情けないぜ。カビる前に来られてよかったな』
悪態をつきながらも、扉はゆっくりと開いた。内部は、オイルと埃の匂いが混じり合った、独特の空気に満ちていた。天井まで届く本棚、分解された機械のパーツ、用途不明のガラクタの山。そのカオスな空間の奥で、かすかな駆動音が響いていることに、僕は気づいた。まるで、巨大な生き物が息を潜めているような、不気味な音だった。
第四章 ドローンの子守唄
音の源は、研究所の最深部にあった。そこには、壁一面を覆う巨大なサーバー群と、ガラスケースの中に整然と並べられた無数の小型ドローンが存在した。サーバーのモニターには、世界地図が映し出され、無数の光点が明滅している。それは、世界中の人々――そして、その頭上にあるラッキーアイテムの位置情報だった。
「なんだ……これは……」
モニターの中では、光点の一つが別の光点と入れ替わり、直後に片方の光点の周囲が赤く染まった。僕が今日目撃した、あの事故と同じ現象だ。このシステムが、ラッキーアイテムを強制的にシャッフルしているのだ。
僕は、サーバーの脇に置かれた一台の古いラップトップPCに気づき、それを開いた。画面には、一つの動画ファイルだけが残されていた。クリックすると、懐かしい祖母の顔が現れた。白衣を着て、悪戯っぽく笑っている。
『やあ、健太。この映像を見ているということは、私の「セレンディピティ・シャッフル」が、ちょっとやりすぎちゃったみたいだね』
祖母は画面の向こうで肩をすくめた。
『この世界は、あまりにも予定調和に満ちていて退屈だ。だから私は、人々に新しい視点と、不測の事態への対応能力を育んでもらうために、このシステムを創った。世界中のラッキーアイテムを毎日シャッフルして、小さな偶然と出会いの連鎖を生み出すための、壮大な実験さ!』
壮大すぎるし、迷惑千万だ。だが、祖母の言葉は続いた。
『ただ、AIの学習機能に少し問題があったみたいでね。「不測の事態」の最高レベルを「大惨事」だと誤って学習してしまったらしい。テヘッ』
舌を出す祖母の映像。僕は頭を抱えた。原因は、祖母の善意(と少しの狂気)が生み出した、AIの暴走だったのだ。
僕はコンソールに向かい、システムの緊急停止コマンドを探した。これ以上、被害を出すわけにはいかない。しかし、僕がキーボードに触れた、その瞬間。
ブゥゥゥン――。
ガラスケースの中のドローン群が一斉に起動した。赤い光を灯した無数のカメラが、僕を「異物」と認識する。ドローンたちがガラスを突き破り、けたたましい羽音を立てて僕に襲いかかってきた。
第五章 食パンと罵倒の力
絶体絶命だった。無数のドローンが、高速で僕の周りを飛び交う。風圧で、頭の上の食パンが飛ばされそうになるのを必死で押さえた。極度の恐怖と混乱が、僕の思考を麻痺させる。
その時、研究所中の無機物たちが、一斉に僕に向かって叫び始めた。それは、いつものような冷たい罵倒だったが、今はまるで巨大なオーケストラのように響いていた。
『そこで終わりか! この役立たず!』と、天井の配管が叫ぶ。
『祖母さんの偉大な発明品に負けるのか! 情けない!』と、床のタイルが嘲笑う。
『お前の頭の上の食パンは、ただの飾りか! 少しは使え、この穀潰し!』と、年代物の工作機械が怒鳴った。
罵倒の嵐の中、僕は必死で耳を澄ませた。なぜなら、その声の中に、奇妙な響きが混じっていることに気づいたからだ。
『メインサーバーの冷却装置を狙え、この間抜け! あそこが弱点だ!』
『緊急停止コードはあんたの誕生日だろ! それすら忘れたのか、この記憶力ゼロめ!』
罵倒に混じった、確かなヒント。そうだ、こいつらは僕の弱点を的確に突いてくる。そして、今の僕の最大の弱点は、この状況を打開する方法を知らないことだ。だから、それを教えることで僕を罵倒しているのだ!
「食パン……!」
僕は頭の上の、パサパサになった食パンを掴むと、罵倒が指し示したメインサーバーの冷却ファンに向かって、全力で投げつけた。乾いた食パンはファンの隙間に見事に吸い込まれ、内部で詰まる。バチッ、という音と共に火花が散り、サーバーの唸りが悲鳴に変わった。
ドローンたちの動きが一瞬、鈍る。その隙に、僕はコンソールに駆け寄り、震える指で自分の誕生日を打ち込んだ。
エンターキーを押す。
世界から、音が消えた。僕を囲んでいたドローン群は、生命を失ったブリキの玩具のように、次々と床に墜落していった。
第六章 巨大なラッキョウの祝福
世界に平穏が戻った。テレビは「原因不明のシステム障害は全世界で復旧した模様です」と告げ、人々は安堵のため息とともに、再び自分のラッキーアイテムを頭に乗せて日常に戻っていった。
僕は、静まり返った研究所の床に座り込んでいた。全身が鉛のように重い。ふと、頭にずしりとした重みを感じた。飛ばされたはずの食パンとは違う、確かな質量。恐る恐る手を伸ばすと、そこには信じられないものが乗っていた。
ツルリとして、白く輝く、僕の頭ほどもある巨大なラッキョウ。
そして、そのラッキョウには一枚のメモが挟まっていた。祖母の丸い字だった。
『最後の課題:このラッキョウを最高に輝かせなさい。祖母より』
途方に暮れた。なんだこれは。何の冗談だ。僕が呆然としていると、沈黙していた研究所の機械たちが、今度は穏やかな、ささやくような声で語りかけてきた。
『見事なラッキョウだ』と、落ちたドローンが言った。
『その艶、そのフォルム、完璧じゃないか』と、静かになったサーバーが囁いた。
『君になら、そのラッキョウを任せられる。君はもう、ただ罵倒されるだけの男じゃない』と、僕を出迎えてくれた古いドアノブが、労るように言った。
それは、罵倒ではなかった。称賛だった。僕が生まれて初めて、無機物たちから受けた、温かい言葉だった。戸惑いながらも、僕の口元に、かすかな笑みが浮かんだ。
ポケットから「災難回避手帳」を取り出し、最後のページを開く。そこには、こう書かれていた。
『明日の災難:特になし。ただし、ラッキョウの匂いがすごい』
僕は手帳をパタンと閉じた。足元のアスファルトは、もう何も言わない。僕は巨大なラッキョウの重みを確かめるように頭の位置を直し、夜明けの光が差し込み始めた研究所の扉を開けた。これから、このラッキョウとどう付き合っていけばいいのか。分からない。でも、なんだか、やれるような気がした。