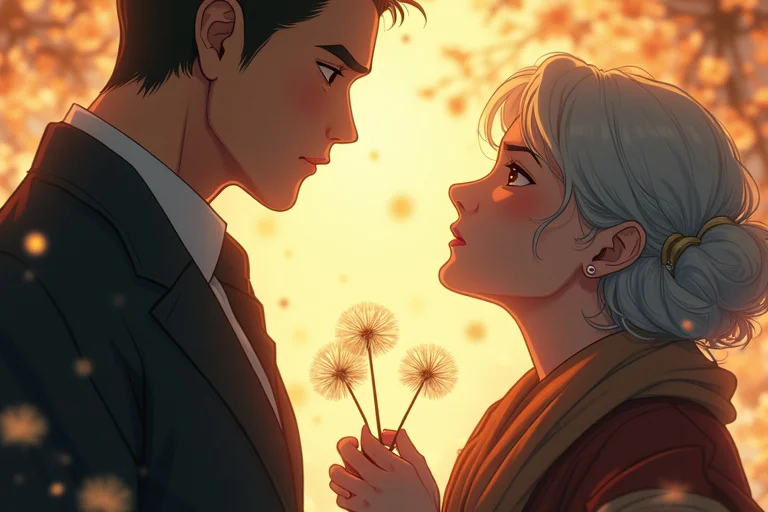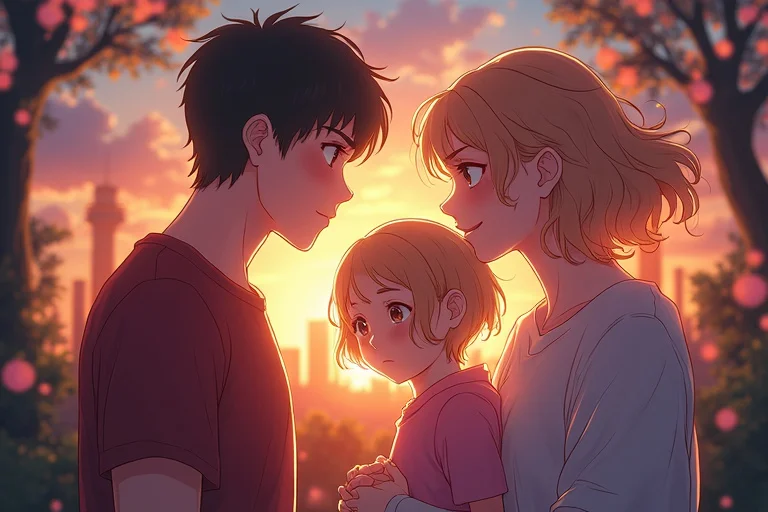第一章 呪いの朝はトーストの香りがしない
月曜の朝。間宮聡(まみや さとし)、三十二歳。彼の世界は、正確な数字と揺るぎないルーティンで構築されていた。目覚ましは六時ジャスト。トーストの焼き時間は三分十五秒。ネクタイの結び目は、鏡の中の自分と寸分違わぬウィンザーノット。感情の起伏という名のバグを、聡は人生のプログラムから徹底的に排除してきた。
その完璧な朝が、隣室から聞こえてきた妙な独り言によって粉々に砕け散った。
「あらやだ、どうしましょう。テレビのリモコンでご飯を炊こうとしてたわ……」
佐藤さん、七十二歳、一人暮らし。彼女の天然ボケは今に始まったことではない。いつもなら聡は、無感動にその声をやり過ごし、バターを塗る作業に戻るはずだった。
しかし、その日の聡の口は、脳の指令を完全に無視した。
「なんでやねん! それ炊飯器ちゃう、文明の利器の墓場や!」
静寂な自室に、我ながら驚くほどキレのあるツッコミが響き渡った。声変わりしたての少年のような、裏返った大声。聡はバターナイフを握りしめたまま、硬直した。なんだ、今の。俺は今、何を言った?
脳が混乱でショートする。まるで自分の身体に、見知らぬ誰かが乗り移ったかのようだ。その「誰か」は、明らかに大阪出身だった。
その異常は、一度きりでは終わらなかった。家を出て、駅へと向かう道すがら、聡の世界は突如としてツッコミ待ちのボケで溢れかえった。散歩中の犬がリードを咥え、飼い主の老婆の手を引いている。「逆やろ! 主従関係が逆転しとるがな!」。電柱に貼られた「猫探してます」の張り紙。描かれた猫の絵が、どう見てもタヌキ。「これじゃあ見つからんわ! ポンポコリンな珍獣として保護されるのがオチや!」。
聡の口は、彼の意思とは無関係に、的確かつ大声で状況を訂正し続けた。道行く人々がぎょっとして彼を振り返る。普段、人にジロジロ見られることなど皆無だった聡は、羞恥心で顔から火が出そうだった。これは呪いだ。間違いなく、何かの呪いにかけられている。
満員電車という名の密室劇空間をどうにか乗り切り、やつれた顔でオフィスにたどり着く。ここなら大丈夫だろう。聡の所属する経理部は、静寂と秩序を愛する人間たちの聖域なのだから。
安堵のため息をついた、その時だった。
「間宮さーん! おはようございます!」
太陽のような笑顔で駆け寄ってくる、天野ひかり。彼女こそが、この会社の、いや、聡の人生における最大のバグであり、歩く天然ボケ発生装置だった。
「見てください! 昨日、パソコンのキーボードを丸洗いしたら、すっごくキレイになったんですよ!」
ひかりは、びしょ濡れのキーボードを誇らしげに掲げた。水滴が床にポタポタと落ちている。
聡の脳が警報を鳴らす。言うな。絶対に言うな。頼むから黙っててくれ、俺の口。
だが、その願いは虚しく、呪いは無慈悲に発動した。
「アホか! それ、ただの電子部品の漬物やないか! 精密機械の常識、お母さんのお腹の中に忘れてきたんか!」
オフィスに響き渡る、魂の絶叫。
経理部の静寂は破られた。そして、間宮聡の平穏な日常は、この日、完全に終わりを告げた。
第二章 天然記念物は絶滅しない
呪いが始まって一週間。聡はすっかり「オフィスのお笑い担当」という不名誉な称号を手にしていた。彼の意思とは裏腹に、口から飛び出すキレ味抜群のツッコミは、なぜか周囲に好評だった。
「間宮さん、この企画書、ヤギに食べさせたら良い評価もらえると思うんです」
ひかりが真顔で言う。
「ヤギは紙食うけど評価はせんわ! 胃液で溶かされてプロジェクトごと反芻されるだけや!」
聡のツッコミに、周りの同僚たちがどっと笑う。以前は「鉄仮面の間宮」と影で呼ばれていたのが嘘のようだ。しかし、聡の心は疲弊の一途をたどっていた。自分の言葉を奪われ、見知らぬ関西人のような何かに身体を乗っ取られている感覚。それは、静かな自己喪失だった。
特に、天野ひかりの存在は致命的だった。彼女の思考回路は予測不可能で、その一挙手一投足がボケの塊だった。
「ホチキスの芯って、サプリメントの代わりになりませんかね? 鉄分摂れそうですし」
「ならんわ! 亜鉛の過剰摂取で病院送りや! 身体の中から書類綴じたいんか!」
「この観葉植物に、毎日コーヒーあげたら、カフェインで元気になったりしませんかね?」
「根腐れするだけや! 植物に徹夜させようとすな!」
聡はツッコミ続ける。不思議なことに、この呪いには妙なルールがあった。中途半端なツッコミをすると、頭の奥がキーンと痛むのだ。まるで、最高のパフォーマンスを要求されているかのようだった。おかげで彼のツッコミスキルは日進月歩で向上し、もはや職人芸の域に達していた。
だが、奇妙な変化もあった。ツッコミという強制的なコミュニケーションを通じて、聡はひかりのことを以前よりずっと知ることになった。彼女が突拍子もないことを言うのは、ただの天然ではなく、凝り固まった物事を違う角度から見ようとする、彼女なりの純粋な探究心から来ていること。そして、彼女が時折見せる、不安げな表情。
ある日、ひかりが大きな契約でミスをし、部長に厳しく叱責されて落ち込んでいた。聡の席の近くで、彼女は小さな声で呟いた。
「私のミスなんて、地球四十六億年の歴史から見たら、ほんの塵みたいなものですよね……」
それは、自分を慰めるための、痛々しいボケだった。聡の呪いが、静かに発動する。
「スケールでかくして問題すり替えるな! …けどな」
聡は続けた。その先の言葉は、呪いではなかった。彼の心の奥底から、自然に湧き出てきた言葉だった。
「まあ、その塵は、俺が半分持ったるわ。次は手伝うから、そんな顔すんな」
それはツッコミのようで、ツッコミではない、不器用な優しさだった。
驚いたように顔を上げたひかりが、やがて、ふわりと花が咲くように笑った。その笑顔を見た時、聡の胸に、今まで感じたことのない温かい感情がじんわりと広がった。
呪いは、まだ解けない。けれど、ほんの少しだけ。ほんの少しだけ、この呪いも悪くないかもしれない、と。そんなことを、思ってしまった。
第三章 バナナはマイクで、君は魔法使い
運命の日がやってきた。社運を賭けた大型コンペのプレゼンテーション。担当に抜擢されたのは、聡だった。几帳面な彼が何日もかけて準備した資料は完璧。勝利は目前のはずだった。しかし、彼の心臓は、破裂しそうなほど激しく脈打っていた。
プレゼン開始五分前。聡が控室で深呼吸を繰り返していると、ひかりがそっと入ってきた。その手には、なぜか一本のバナナが握られていた。
「間宮さん、緊張をほぐすために、これをマイク代わりにして十八番を歌いませんか?」
真剣な瞳だった。彼女は本気で言っている。
聡の頭の中で、何かがぷつりと切れた。この土壇場で、最大のボケをかましてくるのか。呪いが、過去最大出力で発動する。
「歌えるかァ! ていうか何で今バナナやねん! その出どころ不明の黄色い果実を、なんで俺が神聖なプレゼン前に握らなあかんねん! 衛生観念どうなっとんねん!」
渾身のツッコミが、マイクのスイッチがオンになっていたせいで、会場全体に響き渡った。静まり返っていた会場から、どっと爆笑が起こる。審査員であるクライアント企業の役員たちも、腹を抱えて笑っていた。場の空気は、一瞬にして和やかなものに変わった。
呆然とする聡をよそに、プレゼンは始まった。そして、驚くべきことに、それは大成功に終わった。笑いから始まったプレゼンは、クライアントの心をがっちりと掴んだのだ。
会社に戻ると、聡はヒーロー扱いだった。部長は彼の肩を叩き、「あのツッコミが勝因だ!」と絶賛した。
だが、聡の心は晴れなかった。自分の努力ではなく、呪いによって得た成功。それは虚しいだけだった。
彼は、祝賀ムードのオフィスを抜け出し、屋上へ向かった。追いかけてきたひかりに、溜まりに溜まった感情をぶつける。
「いい加減にしてくれ! 君のせいで、俺は! 俺はもう、自分が何なのか分からなくなっていくんだ!」
初めて、ツッコミではない、剥き出しの感情を叫んだ。その瞬間、聡は立っていられないほどの激しい頭痛に襲われ、その場に膝をついた。ガンガンと、内側から頭蓋骨を殴られるような痛み。
「ごめんなさい……」
涙声が聞こえた。見上げると、ひかりが泣きそうな顔で、唇を震わせていた。
「私が…私が、かけたんです。その…呪い」
聡は耳を疑った。ひかりは続けた。彼女の一族は「言祝ぎ(ことほぎ)」と呼ばれ、古来から言葉の力で人々の心を繋いできたこと。感情を押し殺し、いつも孤独だった聡を心配し、彼が他者と繋がるきっかけになればと、「ツッコミ」という形でコミュニケーションの橋を架けようとしたこと。
「でも、私の力はまだ未熟で……ただの強制的な呪いになっちゃったんです。間宮さんの心が、本当に言いたいことと違うツッコミをした時、拒絶反応で頭が痛むように…」
それは、あまりにも突拍子もない、信じがたい告白だった。
だが聡は、それが真実だと直感で理解した。
目の前の天然記念物は、ただの同僚ではなかった。
彼女は、不器用で、おせっかいな、魔法使いだったのだ。
第四章 ボケとツッコミのハーモニー
呪いの真相。それは、聡が想像しうるどんな結末よりも奇想天外で、そして、どうしようもなく優しいものだった。ひかりは、ただ心配してくれていただけだったのだ。孤独な彼の世界に、無理やり窓を開けようとしてくれたのだ。
聡は、これまでの日々を思い返した。地獄だと思っていた。自分の言葉を奪われたと思っていた。だが、本当にそうだっただろうか。
ひかりの突拍子もないボケ。それに返す、自分のツッコミ。いつからか、彼女のボケを心待ちにしている自分がいた。どう返せば、彼女が一番楽しそうに笑うだろうかと、必死に言葉を探している自分がいた。
それは呪いなんかじゃなかった。生まれて初めての、不器用で、回りくどい「対話」だったのだ。
数日後、オフィスはいつもの空気に戻っていた。だが、聡とひかりの間には、以前とは違う、少しだけ甘くて気恥ずかしい空気が流れていた。
昼休み、給湯室でコーヒーを淹れている聡に、ひかりがおずおずと話しかけてきた。
「あの、間宮さん」
彼女は真剣な眼差しで、聡をまっすぐに見つめた。
「私と、ツッコミのない平穏な人生と、どっちが好きですか?」
それは、究極のボケだった。そして同時に、震える声にのせられた、紛れもない告白だった。
聡は一瞬、息を呑んだ。呪いは、まだ彼の身体に宿っている。ここでツッコまなければ、激しい頭痛が襲うだろう。だが、どんなツッコミが正解なんだ?
彼は考えた。そして、ゆっくりと息を吐き出すと、今まで見せたことのない、最高に優しい顔で、少しだけ照れながら、こう言った。
「そんな究極の選択みたいな顔して言うな。…選べるか、アホ。君がおらん人生に、意味なんかないやろ」
それは、完璧なツッコミだった。そして、完璧な愛の告白だった。
不思議なことに、頭は全く痛まなかった。彼の心と、口から出た言葉が、初めて完全に一致した瞬間だった。
ひかりの瞳から、大粒の涙がぽろりと零れた。でも、その口元は、満開の花のようにほころんでいた。
呪いは、きっともう解けないだろう。
でも、それでいいと聡は思った。
これはもう、呪いではない。世界でたった二人だけの、特別なコミュニケーションの形だ。
世界は相変わらず、大小さまざまなボケで満ち溢れている。だが、聡にとって、その世界はもう灰色ではなかった。隣でとんでもないボケをかまそうとしている愛しい魔法使いがいる限り、どんな理不尽なボケが来たって、最高の愛で、ツッコんでやろう。
間宮聡、三十二歳。彼の人生のプログラムには、新たに「愛」と「笑い」という名の、温かくて、少しだけ騒がしい変数が追加された。そしてそれは、彼の人生を、これまでで最も豊かで素晴らしいものにしていくのだった。