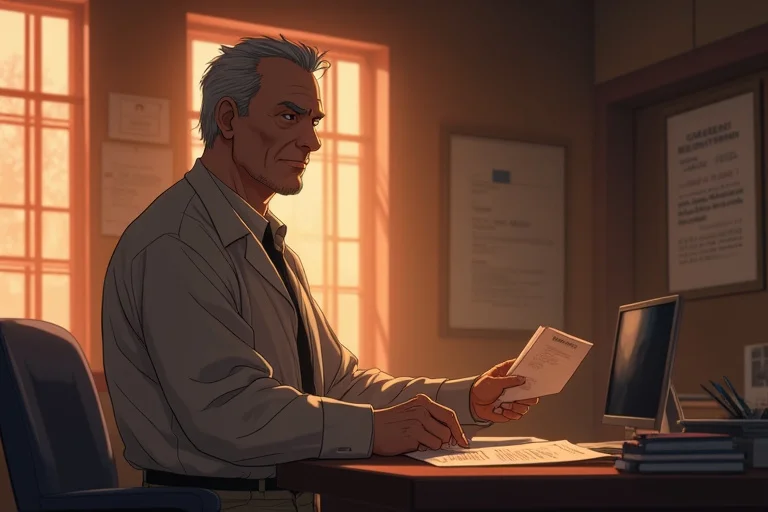第一章 緑色のユートピア
街は、静かな熱狂に満ちていた。カフェのテラス席、高級レストランのテーブル、家庭の食卓。あらゆる場所で、人々は同じものを一心不乱に口へ運んでいる。粘液状の緑色シチュー『グリューネ・シュライム』。カチャリ、とスプーンが陶器を打つ音だけが、まるで神聖な儀式のように繰り返される。誰もが恍惚の表情を浮かべ、その沼のような緑色に世界の真理を見出したかのように瞳を輝かせていた。
僕、佐倉湊は、その光景に背を向けて息を殺していた。ポケットの中で、先ほどコンビニで買ったミントタブレットの箱が、かすかに温かい。ダメだ、考えるな。上司の理不尽な叱責、鳴りやまないクレーム電話、世界の異様さ。ストレスの波が押し寄せるたび、指先が痺れるような奇妙な感覚に襲われる。深呼吸。大丈夫。ポケットの中身はまだ、清涼感のある白い粒のはずだ。
だが、好奇心には勝てなかった。指先でそっと探ると、硬く、ごつごつとした感触が返ってきた。角張ったミントタブレットではない。骨付き肉の、あの忌まわしい形。僕は冷や汗をかきながら、慌ててポケットに蓋をするように手を押し込んだ。この世界で、フライドチキンは禁忌の食べ物。そして僕は、ストレスを感じると、最も近くにある食べ物を完璧なフライドチキンに変えてしまう、呪われた能力の持ち主だった。
第二章 黄金色の罪
世界が緑色に染まる前、僕の隣にはいつも彼がいた。高遠彰。聡明で、いつも少しだけ寂しそうな瞳をした、たった一人の親友。
高校の文化祭、あのむせ返るような熱気と、わたあめの甘い匂いが立ち込める喧騒を今でも覚えている。僕はクラスの出し物から逃げ出し、誰もいない屋上へと彰を連れ出した。手には、能力で作ってしまったフライドチキン。緊張で震える手で、それを彰に差し出した。
「これ…何?」
「い、いいから。食べてみてくれ」
彰は訝しげにそれを受け取ると、意を決したように一口かじった。
その瞬間、時間が止まった。彰の瞳が、見たこともないほど大きく見開かれる。カリッ、と衣が砕ける軽やかな音が、やけに大きく鼓膜を震わせた。彼の喉が上下し、肉汁が飲み込まれていく。沈黙。傾きかけた夕日が、彰の横顔を黄金色に染めていた。やがて彼は、手の中のチキンと僕の顔を交互に見つめ、絞り出すような声で言った。
「湊…これは、罪だ」
その言葉の意味を、当時の僕が理解することはできなかった。ただ、生まれて初めて誰かに自分の能力を肯定されたような気がして、胸が熱くなったことだけを覚えている。彰が、その日から少しずつ笑顔を失っていくことにも気づかずに。
第三章 チキン撲滅委員会
街角の大型ビジョンが、ヒステリックな警告を発している。『チキン撲滅委員会』と名乗る組織の広報官が、鶏肉がいかに人類の味覚を破壊し、思考を鈍らせる毒物であるかを熱弁していた。スーパーの精肉コーナーからは鶏肉が消え、黒い制服に身を包んだ委員会のメンバーが、街を巡回し、「違法チキン」の所持者を厳しく取り締まっている。
僕は息を潜め、アパートの部屋でカーテンの隙間から外を窺っていた。彼らの目的は、おそらく僕だ。この世界の異変も、僕の能力が何らかの形で関わっているに違いない。逃げなければ。しかし、どこへ?この緑色の世界に、僕の居場所などない。
ドアが激しくノックされた。
心臓が喉から飛び出しそうになる。息を殺す。
「佐倉湊君。話がある」
冷静で、しかし有無を言わせぬ声。聞き覚えのある声だった。ドアの向こうの気配に、僕は抗うことができなかった。ゆっくりとドアノブに手をかける。ドアを開けた先には、黒服の男たち、そしてその中心に、見違えるほど冷徹な表情を浮かべた、懐かしい面影の男が立っていた。
第四章 虚構の食卓
連れてこられたのは、壁も床もテーブルも、すべてが純白で統一された無機質な部屋だった。目の前の椅子に、高遠彰が静かに腰掛けている。高校時代よりも幾分か鋭くなった輪郭。しかし、あの寂しそうな瞳の色だけは変わっていなかった。彼は『チキン撲滅委員会』の総帥なのだという。
「久しぶりだな、湊」
テーブルの上には、二皿の『グリューネ・シュライム』が置かれていた。彰は顔色一つ変えず、ごく自然にそれを口に運ぶ。そして、自分の顔から、黒縁のメガネを外してテーブルに置いた。
「これが、世界の真実だ。『世界味覚強制メガネ』。これをかければ、どんな食べ物も『グリューネ・シュライム』の味になる」
彼の言葉が、うまく頭に入ってこない。
「なんで…彰が、こんなことを…」
「世界を救うためさ」
彰は僕をまっすぐに見つめた。彼の瞳の奥には、狂信的なまでの善意が、暗い炎のように揺らめいていた。「君が作った、あの罪の味からね」
第五章 美食の孤独
彰は静かに語り始めた。あの日、屋上で食べたフライドチキンの衝撃。脳髄を焼き尽くすような旨味の奔流。それは彼にとって、祝福であると同時に、取り返しのつかない呪いの始まりだった。
「あの日から、世界から味が消えたんだ」
最高級のステーキも、三ツ星レストランのデザートも、母親が作る温かい味噌汁でさえ、すべてが砂を噛むように無味乾燥に感じられた。あまりに高すぎる基準を知ってしまったが故に、他のすべてが色褪せてしまう。『美食鬱病』。彼は、たった一人、味のない世界に取り残されたのだ。
「最初は君を憎んだよ。僕の世界を壊した君を。でも、すぐに気づいた。悪いのは君じゃない。人間に過ぎた『美食』そのものなんだ」
彼は立ち上がり、部屋をゆっくりと歩き始めた。
「だから、僕は決めた。すべての人々を、この苦しみから解放しようと。誰もが同じものを食べ、同じように満足できる世界。味覚の絶対基準を、この『グリューネ・シュライム』まで引き下げることで、誰も美食に苦しめられることのない、平等なユートピアを創造するんだ」
彼の歪んだ理想。その根底にあるのは、僕への友情と、あの日のチキンが与えた、あまりに深すぎる孤独だった。
第六章 最後の一ピース
「間違ってるよ、彰!」
僕は拘束された椅子の上で叫んだ。「そんなのは救いじゃない!ただの偽りだ!」
「偽りでもいい。人は、その中で幸せになれる」
彰は冷ややかに言い放つと、部下に目配せした。黒服の男たちが僕に近づいてくる。絶望的な状況。極度のストレス。だが、僕の心の中には、恐怖とは別の感情が燃え上がっていた。彰を救いたい。あの日の笑顔を取り戻したい。その強い想いが、僕の能力をこれまで経験したことのないレベルまで引き上げた。
狙うは一つ。彰が再びかけようとしている、テーブルの上の『世界味覚強制メガネ』。
僕の指先から、金色の火花が散った。メガネのフレームがぐにゃりと歪み、レンズに亀裂が走る。次の瞬間、甲高い音と共に、それは完璧なフライドチキンへと姿を変えた。黄金色の衣をまとった、手羽先のチキン。それはまるで生きているかのようにテーブルから跳ね上がると、彰の驚く顔の目の前でぴたりと静止した。部屋中に、抗いがたいスパイスの香りが充満する。彰の瞳が、大きく揺れていた。
第七章 味覚の夜明け
彰は、まるで引力に引き寄せられるかのように、そのチキンに手を伸ばした。忘れようとしても忘れられなかった、あの日の香り。震える指でそれを掴み、無意識に口へと運ぶ。
カリッ。
時が、再び動き出した。彰の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちる。彼の味覚を縛り付けていた、長く、暗い呪いが解けていくのがわかった。
「……おいしい」
その呟きは、誰に言うでもない、魂からの叫びだった。彼は子供のように嗚咽を漏らし、その場に崩れ落ちた。
『チキン撲滅委員会』は解散し、世界はゆっくりと元の色彩を取り戻していった。理由も分からぬまま味覚が戻った人々は、あれほど熱狂した『グリューネ・シュライム』を、「たまに食べたくなる不思議な健康食」として、奇妙な食文化の中に残した。
数週間後、僕と彰は、川辺のベンチに並んで座っていた。手には、コンビニで買った、ごく普通のフライドチキン。僕が作るそれには到底及ばない、ありふれた味だ。
「普通の味も、悪くないだろ?」
僕が言うと、彰は小さく頷いて、照れくさそうに笑った。
「ああ。悪くない」
その笑顔は、高校時代に僕が見た、少しだけ寂しそうで、でも、とても優しい笑顔だった。僕たちは言葉少なにチキンを頬張りながら、美食という名の甘美で切ない呪いが解けた、この穏やかな世界の空気を、ただ静かに味わっていた。