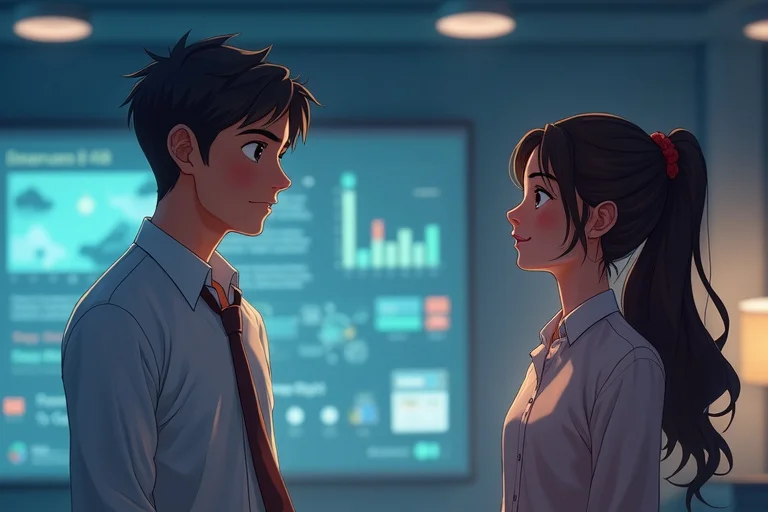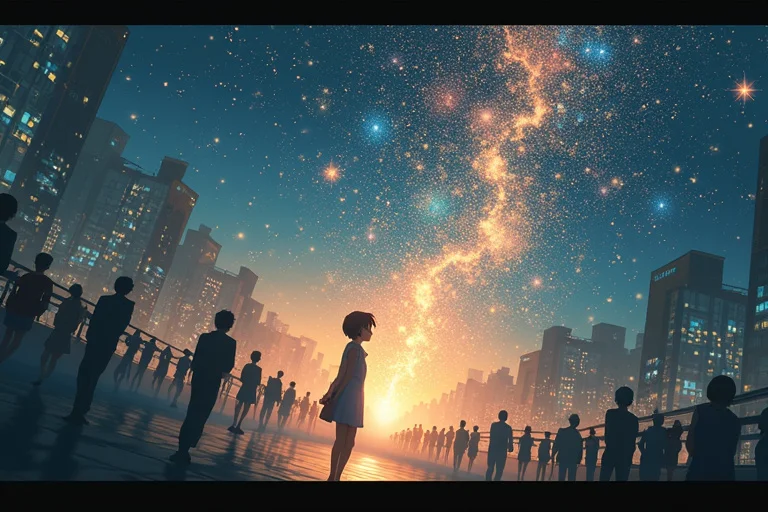第一章 未来からの訪問者
須田正(すだ ただし)の人生は、定規で引かれた線のように正確だった。朝六時起床、三十品目の朝食、七時十五分の電車。ワイシャツの襟の角度から、デスクに置かれた付箋の向きに至るまで、全てが完璧にコントロールされている。市役所の資産税課に勤める彼の信条は「曖昧さの排除」。冗談や比喩表現を、世界のバグであるかのように憎んでいた。
そんな彼の完璧な日常に、ある火曜日の夜、致命的なエラーが発生した。
仕事から帰宅し、いつものように玄関で靴を寸分違わず揃え、リビングのドアを開けた瞬間、須田は呼吸を忘れた。見慣れたソファに、汚れたジャンパーを着た見知らぬ老人がどっかりと腰を下ろし、我が物顔でテレビのリモコンをいじっていたのだ。床にはコンビニ弁当の空き容器が転がっている。須田の世界を構成する精密な歯車が、けたたましい音を立てて砕け散った。
「ど、どちら様でしょうか。不法侵入ですよ。警察を呼びます」
喉から絞り出した声は、自分でも驚くほど震えていた。老人はゆっくりとこちらを振り返る。皺だらけの顔に、悪戯っぽい光が宿った瞳。無精髭の間から、黄ばんだ歯がのぞいた。
「おお、おかえり、おじいちゃん」
「……はい?」
「わしは未来から来たんじゃ。あんたの孫の、トキオじゃよ」
須田は絶句した。孫? おじいちゃん? そもそも自分は三十五歳、独身、彼女いない歴イコール年齢だ。何かの詐欺か、あるいはたちの悪いドッキリか。須田がスマートフォンに手を伸ばした、その時。
「警察はよさんか。それより、小学校の卒業文集、覚えてるか?『僕の将来の夢は、日本の法律をすべて暗記することです』。あれ、書いた日の晩、お母さんに『正は面白いわねえ』って言われて、本気で褒められたと思って喜んでたじゃろ。本当は、あまりの堅物ぶりに呆れられてただけなのに」
須田の動きが止まる。そのエピソードは、母と自分しか知らない、心の奥底に封印した記憶だった。
「な、なぜそれを……」
「だから言うたじゃろ。わしは、あんたの孫なんじゃって」
トキオと名乗る老人は、けらけらと笑った。
「このままだと、おじいちゃんは誰にも看取られず、たった一人で孤独死する。その強烈な無念のエネルギーが時空の歪みを引き起こし、未来で大変なことになるんじゃ。だからわしが、おじいちゃんに『ユーモア』というやつを教えに来てやった。感謝せい」
あまりに荒唐無稽な話に、須田の脳の処理能力は完全に追いつかなかった。しかし、子供の頃の秘密を知られているという事実が、警察を呼ぶという選択肢を奪っていく。
こうして、須田正の定規で引かれたような人生に、「未来から来たと自称する孫(推定年齢七十歳)」という、規格外の存在が割り込んできたのだった。
第二章 スベる男の養成講座
奇妙な同居生活が始まって一週間。須田の精神は限界に達していた。トキオは須田の生活ルールを片っ端から破壊した。醤油のボトルはキャップが開けっ放し、トイレットペーパーは逆向き、須田が几帳面に並べた蔵書は、なぜか五十音順から作者の血液型順(推定)に並べ替えられていた。
そして何より耐え難いのが、トキオが課す「ユーモア養成講座」だった。
「今日の課題じゃ。職場で、一番偉い部長のオヤジギャグに、腹を抱えて笑ってみせい」
「無理です! 課長のダジャレでさえ、僕は真顔で『その発言に生産性はありますか?』と聞き返してしまうんですよ!」
「だからやるんじゃ! ユーモアの第一歩は、他人のスベり芸を温かく受け止めることからじゃ!」
須田は嫌々ながらも、昼休みに部長が放った「このカレー、かれー(辛い)なあ!」という古典的なギャグに、必死で笑ってみせた。引きつった頬、ワハハという乾いた声。周囲の同僚たちは、須田がとうとう猛暑で頭がおかしくなったのだと、憐れむような視線を送ってきた。須田は羞恥で死にそうだった。
またある時は、「合コンで自己紹介ギャグを言え」という指令も出た。友人に無理やり誘われた合コンで、須田は震える声でこう言った。
「す、須田正です。趣味は、間違い探しです。僕の人生も、間違いだらけですが……」
地獄のような沈黙が流れた。正面に座っていた女性は、あからさまに眉をひそめた。その夜、須田は帰宅するなりトキオに掴みかかった。
「あなたのせいで、僕の人生はめちゃくちゃだ! 評判も信頼もガタ落ちですよ!」
「それでええんじゃ」
トキオは、須田の剣幕にもどこ吹く風で、縁側で月を見上げていた。「完璧な人間なんかつまらん。失敗して、恥をかいて、それでも笑い飛ばすのが人間じゃ。お前の人生には、その『余白』が足りんのじゃよ」
その横顔は、いつものふざけた表情とは違い、どこか遠くを見ているようで、不思議な寂しさを帯びていた。その時、須田は初めて、この老人の奔放さの奥にある何かに、ほんの少しだけ触れたような気がした。
変化は、本当に少しずつ訪れた。部長への愛想笑いがきっかけで、なぜか「あいつ、意外と面白いところあるな」と飲みに誘われたり、合コンで大スベりしたことを自虐ネタにした同僚が、意外にも周囲の笑いを誘ったりした。須田の完璧な世界にできた綻びから、これまで見たことのなかった光が差し込んでいるようだった。
第三章 三文芝居のカーテンコール
ある雨の日の午後、須田は風邪で会社を休んでいた。薬を探して棚を漁っていると、トキオがいつも枕元に置いている、古びたがま口が目に留まった。ほんの出来心だった。中を覗くと、数枚の千円札と共に、一枚の古い写真が折り畳まれて入っていた。
須田は、その写真を広げて息を呑んだ。
色褪せた写真には、自分とよく似た目元を持つ若い男と、優しそうに微笑む女性、そしてその二人に抱かれた赤ん坊が写っていた。見覚えのない家族写真。だが、須田の心を鷲掴みにしたのは、写真の裏に書かれたインクの文字だった。
『正へ。君が笑うと、世界が輝く。愛を込めて。美咲より』
正(ただし)。それは自分の名前だ。美咲。それは、自分が生まれてすぐに病気で亡くなったと聞かされていた、母親の名前だった。
では、この若い男は誰だ?
心臓が嫌な音を立てる。頭の中で、バラバラだったパズルのピースが、恐ろしい形に組み合わさっていく。トキオが知っていた子供の頃の秘密。時折見せる、寂しげな眼差し。そして、この写真――。
夕方、帰宅したトキオに、須田は震える手で写真を突きつけた。
「トキオさん……いや、あなたは、一体誰なんですか」
観念したように、トキオは深く息を吐いた。そして、いつもの悪戯っぽい笑みを消し、静かな声で語り始めた。
「……わしは、未来からなんぞ来とらん」
その一言で、須田の足元が崩れ落ちる感覚がした。
「わしは……あんたの親父じゃよ」
須田の父親。それは、須田が物心つく前に家を出て行った、売れないコメディアンだった。母親は須田に「お父さんは事故で死んだ」と教え、夫への当てつけのように、息子を冗談の通じない、真面目で堅実な人間に育て上げた。須田自身も、顔も知らない父親を、家族を捨てた無責任な人間として、心のどこかでずっと軽蔑してきた。
「ずっと、遠くから見とった。お前が真面目に、まっすぐに育っていくのを。……じゃが、あまりにまっすぐすぎて、見ていて苦しかった。お前は、ちっとも笑っとらんかった」
父親は、末期のガンで余命宣告を受けたのだという。死ぬ前に、息子にもう一度笑ってほしかった。だが、今さら父親だと名乗って現れても、拒絶されるだけだろう。
「じゃから、最後の三文芝居を打つことにしたんじゃ。『未来から来た孫』。そんな大嘘なら、お前も仕方なく付き合ってくれるかもしれん、とな。わしにできる、最初で最後の、親父らしいことだったんじゃよ」
それは、あまりにも不器用で、壮大で、そして途方もなく愛情深い、たった一人の観客に向けたコメディだった。須田の価値観が、音を立てて崩壊した。自分が忌み嫌っていた「曖昧さ」や「不真面目さ」の塊のような父親が、命を懸けて自分を笑わせようとしていた。その事実が、須田の胸を激しく揺さぶった。頬を伝う熱い雫が、父親から教わった「ユーモア」の本当の意味を、須田に教えていた。
第四章 最高のコメディ
それからの日々は、まるで夢のようだった。須田は初めて、父親と「息子」として向き合った。病院のベッドに横たわる父親に、須田は覚えたてのユーモアを、必死で届けようとした。
「お父さん、聞いて。この間、僕が合コンで言った自己紹介ギャグなんだけど…」
ぎこちない口調で語る失敗談。完成度の低いモノマネ。意味不明なダジャレ。そのどれもが、プロのコメディアンだった父親からすれば、落第点だっただろう。だが、父親はしゃがれた声で、腹を抱えて笑った。涙を流しながら、何度も「面白いぞ、正。お前は、最高のコメディアンじゃ」と繰り返した。
それは、須田正の人生で、最もスベったけれど、最も温かいステージだった。
数週間後、父親は須田の腕の中で、満足そうに微笑みながら静かに息を引き取った。まるで、最高の舞台を終えた役者のように、安らかな顔だった。
半年が過ぎた。須田は今も、市役所の資産税課で働いている。定規で引かれたような日常は、基本的には変わらない。しかし、彼の世界には、父親が遺してくれた確かな「余白」が生まれていた。
ある日の午後、新人の女性職員が大きなミスをして、デスクで泣き出しそうになっていた。周囲は見て見ぬふりをしている。須田は静かに彼女の隣に立つと、少しだけ首を傾げて、こう言った。
「大丈夫。僕なんか、人生そのものが壮大な打ち間違いみたいなものだから」
一瞬、きょとんとした彼女の顔が、やがて、ふっと綻んだ。小さく、でも確かな笑い声が、静かなオフィスに響いた。
その音を聞きながら、須田は窓の外に広がる青空を見上げた。空はどこまでも青く、まるでこれから始まる最高のコメディの幕開けを告げているようだった。
須田は、誰にも聞こえない声で、そっと呟いた。
「……お父さん。今の、結構ウケたよ」
その口元には、父親によく似た、少しだけ悪戯っぽい笑みが浮かんでいた。