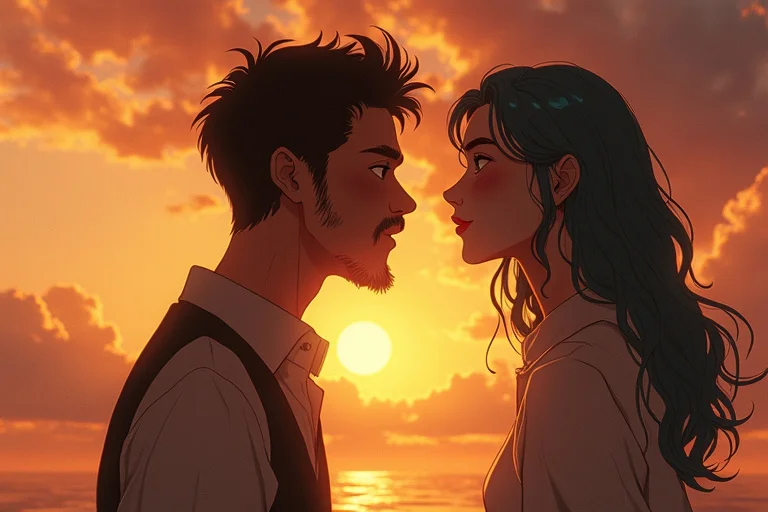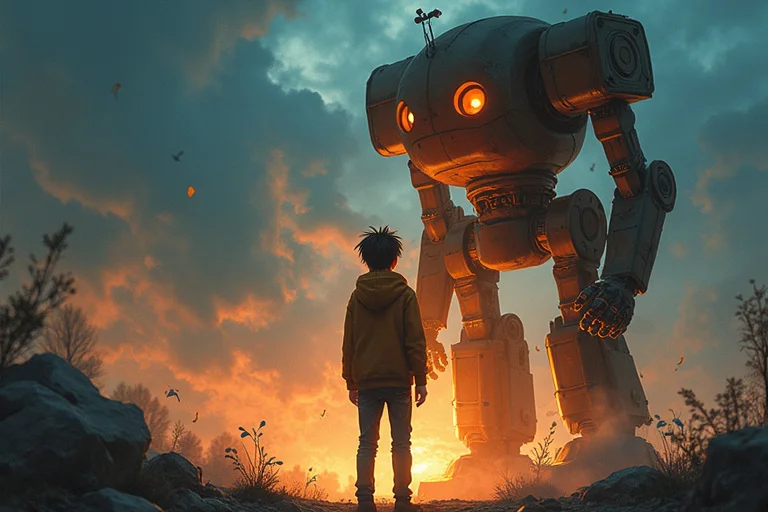第一章 言霊はダジャレに宿る
山田健二、四十二歳、独身。市役所市民課に勤めて十五年。彼の人生は、正確に折り畳まれたハンカチのように、皺一つなく、しかし面白みにも欠けていた。定規で引かれた線の上を歩くように日々を過ごし、感情の起伏は、せいぜい自動販売機で当たりが出た時くらいのもの。それが、彼の信条であり、処世術だった。
しかし、山田の整然とした内面には、誰にも言えない混沌が渦巻いていた。それは、時と場所を選ばずに湧き出してくる、致命的にくだらない「ダジャレ」の衝動だ。ストレスが臨界点に達すると、脳内でオヤジギャグの神が降臨し、彼の意思とは無関係に、陳腐な言葉遊びが口をついて出そうになる。彼はそれを、必死に喉の奥に押し込めて生きてきた。ダジャレは、彼の完璧な世界の唯一のバグだった。
その日、事件は起きた。
窓口に現れたのは、頭頂部が綺麗に磨き上げられた、血圧の高そうな男だった。書類の不備を指摘された男は、火山のように怒りを噴出させた。
「何度来させる気だ! この税金泥棒が!」
男の唾がアクリル板に飛び散る。山田はいつものように、能面のような無表情で頭を下げた。だが、連日の残業と寝不足で、彼の精神のダムは決壊寸前だった。男の怒声が、頭の中で不快なエコーを響かせる。
(ああ、もう、うるさいな……そんなに怒鳴ると、頭に血が上りますよ……)
そう思った瞬間、彼の脳内でギャグの神が囁いた。
(頭に……血がのボール……なんちゃって……)
まずい。口から漏れる。山田は唇を固く噛みしめた。しかし、ダムの亀裂から水が染み出すように、その言葉は微かな吐息と共に外の世界へ漏れ出してしまった。
「……ちが、のぼーる……」
その刹那、信じられない光景が目の前で繰り広げられた。
怒り狂っていた男の、つるりとした頭頂部から、ピンポン玉ほどの大きさの、真っ赤な球体がぽこんと生まれ出たのだ。それはまるで生き物のように、ぷるぷると震え、男の頭の上をバスケットボールのようにポヨン、ポヨンと跳ね始めた。
窓口の喧騒が、水を打ったように静まり返る。誰もが、男の頭上で陽気に弾む「血のボール」に釘付けになっていた。当の男自身も、周囲の視線に気づき、恐る恐る頭に手をやる。指先に、ゼリーのような奇妙な感触が伝わったのだろう。
「ひっ……! な、なんだこれはぁっ!」
男は悲鳴を上げ、自分の頭の上で跳ねる赤い球体をパニック状態で振り払おうとするが、ボールは彼の動きに合わせて、より一層楽しげに踊るだけだった。
山田は、自分がしでかしたことの意味も分からぬまま、ただ目の前の超常現象を呆然と見つめていた。彼の整然とした世界に、あまりにもくだらなく、そして巨大な亀裂が入った瞬間だった。
第二章 暴走するオヤジギャグ
あの日以来、山田健二の世界は一変した。彼は、自分の口からこぼれるダジャレが、現実を歪める力を持つことに気づいてしまったのだ。それはまるで、コメディの神様から押し付けられた、迷惑千万なギフトだった。
彼は過去の奇妙な出来事を必死に思い返した。締め切りに追われ、「猫の手も借りたい」と呟いた翌日、アパートの周りに町中の野良猫が集結していたこと。風の強い日に「このままじゃ布団が吹っ飛ぶな」と口走ったら、ベランダの布団が本当に凧のように空へ舞い上がっていったこと。全ては、彼の無意識のダジャレが引き起こした惨事だったのだ。
「どうすれば……。この力をコントロールするには、どうすればいいんだ……」
山田は自室で頭を抱えた。まずは、ポジティブなダジャレで実験してみよう。彼は、昼食のレトルトカレーを温めながら、意を決して呟いた。
「このカレーは、実に……華麗だ!」
すると、湯気を立てるカレー皿から、後光のような眩い光が放たれた。黄金色のオーラが立ち上り、部屋中にスパイシーかつ荘厳な香りが満ちる。一口食べると、まるで高級レストランのシェフが丹精込めて作り上げたかのような、複雑で深遠な味わいが口の中に広がった。ただの三百円のレトルトカレーが、奇跡の料理へと変貌を遂げたのだ。
力は本物だ。しかし、その制御は絶望的に難しい。くだらない思いつきが、そのまま世界に影響を与えてしまう。山田は、ダジャレを封印するため、人と話すことを極力避けるようになった。彼の態度は「無口」から「不気味」へとランクダウンし、市役所内での孤立はさらに深まった。
そんな彼を、遠巻きながらも気にしている人物がいた。隣の席の鈴木さんだ。彼女は、太陽のような笑顔が似合う、快活な女性だった。
「山田さん、最近元気ないですね。何か悩み事ですか? 私でよければ、相談に乗りますよ。なんたって、私は皆のそうだん相手(ソーダ水)ですから!」
彼女は屈託なく笑いながら、下手なダジャレを飛ばした。山田はぎょっとした。この人のダジャレは現実化しないのか? 世界の法則はどうなっているんだ?
「い、いえ、何でもありませんので……」
山田が慌てて席を立つと、足がコードに引っかかった。バランスを崩し、彼は派手に転倒する。
「うわっ!……こ、これは、見事なまでに……転倒(てんとう)虫……」
しまった、と口を覆ったが、もう遅い。彼の背中から、忽然と、赤地に七つの黒い斑点を持つ、巨大なテントウムシの翅が「ばさっ」と生えたのだ。
「……え?」
鈴木さんは目を丸くして、山田の背中でパタパタと虚しく動く、立派な昆虫の翅を見つめていた。
「や、山田さん……その……背中……すごいコスプレですね……」
「ち、違います! これは……その……」
山田は顔を真っ赤にして、翅を隠そうと身をよじるが、翅は彼の意思に反して存在を主張し続ける。彼は半泣きになりながら、トイレへと逃げ込んだ。暴走するオヤジギャグは、彼の社会的な生命をも脅かし始めていた。
第三章 氷点下のヒーロー
ダジャレ能力は、山田にとって呪いでしかなかった。彼は言葉を失い、ただ息を潜めるように日々を過ごした。自分の存在が、いつ世界にくだらないバグを発生させるか分からない。その恐怖が、彼の心を蝕んでいた。
その日は、よく晴れた午後だった。市役所の窓から見える駅前の再開発エリアでは、巨大なクレーンが新しいビルの鉄骨を吊り上げている。昼休み、弁当を買いに出た山田が広場を横切ろうとした、その時だった。
甲高い金属音と、人々の悲鳴が響き渡った。
見上げると、クレーンに吊られていた巨大な鉄骨の塊が、ワイヤーが切れたのか、ゆっくりと傾き、地上に向かって落下を始めていた。その真下には、数人の作業員と、しゃがみ込んで泣いている小さな女の子がいる。
誰もが、次の瞬間に起こるであろう惨劇を悟り、凍り付いていた。逃げることすらできない。山田の足も、恐怖で地面に縫い付けられたように動かなかった。
(だめだ……間に合わない……!)
死の影が、コンクリートの地面に急速に広がっていく。女の子の泣き顔が、スローモーションのように見えた。山田の心臓が、破裂しそうなほど激しく脈打つ。
(誰か……誰か、助けてくれ……! あんな鉄の塊……あんなもの……!)
彼の脳内で、恐怖と焦りが渦を巻き、一つの切実な願いへと収束していく。それは祈りであり、叫びだった。そして、彼の口から、ほとんど無意識に、その言葉が飛び出した。
「鉄骨なんて……凍って(こおって)しまえぇっ!」
その絶叫が広場に響き渡った瞬間、世界の音が消えた。
落下していた巨大な鉄骨が、まるで神の見えざる手によって掴まれたかのように、空中でぴたりと静止した。それだけではない。鈍色の鉄骨の表面を、白い霜が瞬く間に覆い尽くし、太陽の光を浴びてキラキラと輝く、巨大な氷の彫刻へと変貌させたのだ。カキン、という硬質な音が、静寂の中でやけに大きく聞こえた。
人々は、何が起きたのか理解できずに、ただ空中の氷塊を見上げていた。やがて、我に返った作業員たちが、女の子を抱きかかえて安全な場所へと走り出す。広場は、安堵と賞賛のどよめきに包まれた。
「すごい!」「何が起きたんだ?」「助かった……!」
山田は、ぜえぜえと肩で息をしながら、その光景を見ていた。やった。自分の力が、初めて、人を救った。くだらないダジャレが、命を救ったんだ。安堵と、これまで感じたことのない高揚感が、彼の全身を駆け巡る。彼は震える声で、誰に言うでもなく呟いた。
「いやあ……肝が……冷えた……」
次の瞬間、山田の体に激痛が走った。
自分の指先から、急速に体温が失われていくのが分かった。見れば、腕に、足に、霜が降り始めている。彼の呟いたダジャレが、今度は彼自身をターゲットにしたのだ。
「う……あ……」
体が急速に凍りつき、動かなくなる。呼吸が苦しい。意識が遠のいていく。人々が助かったことへの安堵と、自らが招いた絶体絶命の危機。そのあまりに皮肉な状況の中で、山田の視界は、ゆっくりと白く閉ざされていった。
第四章 世界を温める言葉
氷のように冷たい闇に沈みかけた山田の意識を、必死に呼び戻す声がした。
「山田さん! しっかりしてください、山田さん!」
薄目を開けると、心配そうに顔を覗き込む鈴木さんの姿があった。彼女は自分のコートを山田の体にかけ、震える手でその肩をさすっている。
「山田さん、こんなところで凍えてちゃだめです! 温かいお茶でも飲んで、体も心も、あったかく(温かく)しましょう!」
鈴木さんが叫んだ、その素朴で、心のこもった言葉。それはダジャレですらなかったかもしれない。だが、その言葉が山田の耳に届いた瞬間、彼の体を蝕んでいた氷が、陽光に溶ける雪のように、すうっと消えていくのを感じた。体の芯から、じんわりとした温かさが広がっていく。
「すずき……さん……?」
「よかった……! 本当に、よかった……!」
鈴木さんは、涙を浮かべながら、心から安堵したように微笑んだ。
救急隊が到着する頃には、山田の体はすっかり元に戻っていた。鉄骨事件は「原因不明の突発的な凍結現象」として処理され、山田の絶叫を聞いた者はほとんどいなかった。だが、鈴木さんだけは、全てを見ていた。
後日、市役所の給湯室で、鈴木さんは山田にそっと缶コーヒーを差し出した。
「あの時……山田さんがやったんですよね?」
山田は観念して、こくりと頷いた。自分のくだらない能力の全てを、正直に打ち明けた。笑われるか、気味悪がられるか、どちらかだと思った。
しかし、鈴木さんの反応は、彼の予想とは全く違っていた。
「すごいじゃないですか! 山田さん! それは、呪いなんかじゃなくて……人を笑顔にできる、素敵な力ですよ!」
彼女は、まるで自分のことのように、目を輝かせて言った。
「たしかに、ちょっと不便かもしれないですけど……。でも、使い方次第で、ヒーローにだってなれる力です。私は、あの時の山田さん、最高にカッコいいと思いました」
その言葉は、山田が四十二年間、誰からも言われたことのない種類の賛辞だった。自分の最大のコンプレックスであり、隠し続けてきた欠陥。それが、初めて誰かに肯定された。山田の心の中で、固く凍りついていた何かが、ゆっくりと溶け始めるのを感じた。
それからの山田は、少しだけ変わった。
相変わらず市民課の窓口で、真面目に、淡々と仕事をしている。しかし、彼の表情には、以前にはなかった微かな自信と、優しさが宿っていた。
書類の書き方が分からず、不安そうな顔をしているお年寄りがいる。山田は、その背中に向かって、誰にも聞こえないくらいの声でそっと呟く。
「大丈夫。その問題は、きっと……かいけつ(貝、ケツ)しますよ」
すると、お年寄りの顔から不安の色が消え、何かを思い出したように、スラスラとペンを走らせ始める。
落ち込んで窓口に来た若者には、こうだ。
「あなたの未来は、きっと……明るい(ア・カルイ)でしょう」
若者は、ふと顔を上げ、何か吹っ切れたような晴れやかな表情で、深く頭を下げて帰っていく。
彼のダジャレは、もう世界を混乱させるだけのバグではなかった。それは、人々の心を少しだけ軽くし、世界をほんの少しだけ温かくする、ささやかな魔法になった。完璧なコントロールはまだできない。時々、「トイレが……遠いれ(トイレ)」と呟いて、トイレまでの廊下が物理的に伸びてしまうこともある。だが、もう彼は自分の力を恐れてはいなかった。
ある晴れた日の午後、山田は公園のベンチに座って、子供たちが遊ぶのを眺めていた。一人の男の子が転んで、膝をすりむいて泣き出した。山田は、その子に向かって、優しく微笑みかけた。
「大丈夫。その痛みは、すぐに……去っていった(サー、手、言った)から」
男の子は、きょとんとした顔で涙を拭うと、すぐに痛みを忘れたかのように、また友達の輪へと駆け出していった。
心地よい風が、公園の木々を揺らす。山田は、空を見上げた。青い空は、どこまでも澄み渡っていた。自分のくだらない言葉が、世界を少しだけ良くできるかもしれない。そう思うと、なんだか無性に可笑しくて、そして誇らしかった。彼は、誰に聞かせるでもなく、小さく、しかしはっきりと呟いた。
「この公園は……最高ウエン(公園)だ」