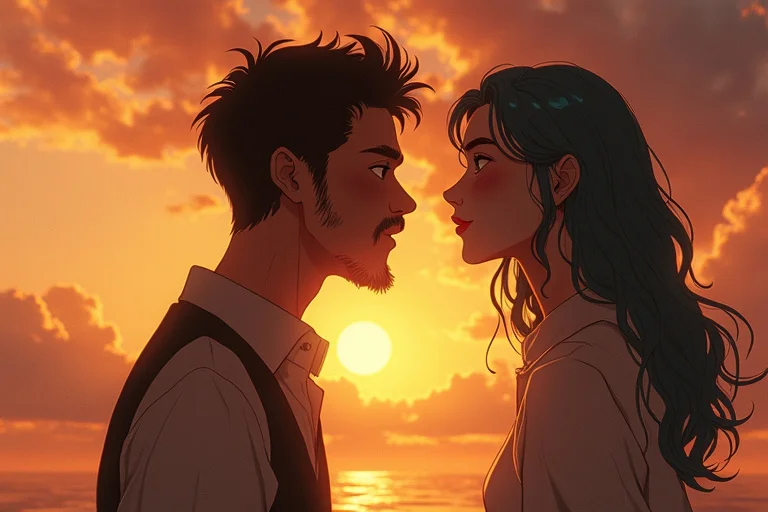第一章 満員電車の致死率
「次は、終点、新宿。終点、新宿。お出口は、右側です」
気怠い自動音声が、圧縮された人間の缶詰の中に響き渡る。間宮修一は、この世の終わりみたいな顔で、揺れる車内に耐えていた。彼の願いはただ一つ。平穏無事。誰にも関わらず、空気のように一日を終えること。しかし、神は彼にそんな安寧を許してはくれなかった。
「いやあ、参った参った」
すぐ隣に立つ、人の良さそうな初老のサラリーマンが、額の汗を拭いながら陽気に言った。
「今朝は慌てててね。大事なカバンと間違えて、うちの奥さんが親戚にもらったマグロのブロックを持ってきちゃったよ!がはは!」
その瞬間、間宮の心臓が鷲掴みにされたかのように、ぎりりと痛んだ。視界が白く点滅し、呼吸が浅くなる。来た。来てしまった。致死量の「ボケ」が。
(よせ……!やめてくれ……!俺は、俺はただ静かに……!)
脳内で絶叫するが、体は正直だ。呪いは発動する。放置すれば、心臓が止まる。この一年、嫌というほど味わってきた地獄の苦しみだ。
マグロのブロック。通勤カバン。ありえない。ありえないだろ!ツッコめ。ツッコまなければ、死ぬ。
「……っ!」
間宮は歯を食いしばり、顔を真っ赤にして、サラリーマンの肩を掴んだ。周囲の乗客が「痴漢か?」といぶかしげな視線を向ける。だが、もう構っていられない。
「なんで魚河岸経由で出勤してるんですか!というかその生臭さで気づきませんか普通!クール便で会社に送り返せ!」
静寂。満員電車の全員が、間宮とマグロの男を凝視している。男はきょとんとした顔で、手に持った風呂敷包みを見つめ、やがて「おお、ほんとだ!」と感心したように頷いた。
間宮はぜえぜえと肩で息をしながら、壁に手をついた。胸の痛みは、かろうじて引いている。しかし、代償として失ったものは大きい。社会的な立場、平穏な日常、そして人並みの羞恥心。
全ては一年前。横断歩道でぶつかった見知らぬ老婆に「あんた、面白い顔してるね。その顔で人のボケを見殺しにしちゃいけないよ」と不気味に囁かれたあの日から、間宮修一の人生は一変した。
『ボケ見殺しにしてはならぬの呪い』。
街に溢れる大小様々な「ボケ」を感知し、それを的確にツッコんで処理しなければ、心臓発作で死にかけるという、あまりにも理不尽な呪い。
以来、彼は意図せずして「キレキレのツッコミ師」として、この狂った世界を生き抜くことを強いられているのだった。彼の望みはただ、静かに暮らすことだけなのに。
第二章 天然ボケは時限爆弾
間宮の呪いは、職場においても猛威を振るっていた。
「間宮さん、このデータ、シュレッダーにかけようと思ったら、シュレッダーの方が壊れちゃいました」
「なんで先にシュレッダーの耐久限度を疑うんだよ!お前が入力したデータ量がバグってるんだろ!」
「間宮くん、新しい企画、考えてきたよ。『社内全員忍者化計画』だ」
「却下です部長!まず経費で忍者装束と撒菱が落ちません!あと僕、猫アレルギーなんで水蜘蛛の術は無理です!」
彼の的確すぎるツッコミは、結果的に部署の危機を何度も救い、業務効率を劇的に改善させた。その結果、彼は周囲から「口は悪いが、仕事の鬼」「危機管理能力の化身」と畏怖されるようになり、本人の意思とは裏腹に、どんどん出世街道を突き進んでいた。静かに暮らしたいという願いは、日に日に遠ざかっていく。
そんな彼の人生に、最大級の爆弾が投下されたのは、桜が舞い散る四月のことだった。
「はじめまして!今日から配属になりました、佐藤ひな子です!趣味は、雲の形を数えることです!よろしくお願いします!」
太陽をそのまま人間の形にしたような、天真爛漫な新人、佐藤ひな子。彼女こそ、間宮の平穏を根底から破壊する「究極のボケ製造機」だった。
彼女のボケは、天然由来、無添加、無自覚。それゆえに、あまりにも純度が高く、間宮の心臓を的確に抉る。
「間宮先輩、この書類、ヤギに食べさせてもいいですか?エコかなって」
「稟議書は反芻動物の餌じゃねえ!ヤギは会社の備品じゃないし、インクは体に悪いからヤギの健康を第一に考えろ!」
胸を押さえながら叫ぶ間宮。ひな子は「そっかあ、ヤギさんのためなら仕方ないですね!」と納得している。
彼女の存在は、間宮にとって歩く地雷原だった。いつ、どんな角度から、命を刈り取るボケが飛んでくるか予測できない。彼はひな子を必死に避けようとした。だが運命のいたずらか、会社は「新人の指導は、エースの間宮に」と、彼女を間宮の直属の部下にしたのである。
地獄の日々が始まった。だが、不思議なことも起きた。間宮が命がけで繰り出すツッコミは、ひな子の突拍子もないミスを未然に防ぎ、彼女の奇抜な発想を現実的な企画へと昇華させる効果があったのだ。
「この商品のキャッチコピー、『空も飛べるはず』でどうでしょう!」
「著作権侵害で訴えられるわ!スピッツに謝れ!でもそのポジティブさは良いから、『不可能を可能にする』方向で考え直せ!」
結果、その商品は大ヒットした。周囲は「間宮さんの指導は厳しいが、新人の才能を見事に引き出している」と絶賛の嵐。間宮は、死の淵を彷徨いながら、なぜか名指導者としての評価を確立していった。
彼は葛藤していた。ひな子の存在は、間違いなく彼の命を脅かしている。しかし、彼女の屈託のない笑顔や、誰も思いつかないような純粋な発想に触れるたび、荒みきった彼の心に、何かがポッと灯るのを感じずにはいられなかった。この感情が何なのか、彼にはまだわからなかった。
第三章 沈黙のプレゼンテーション
その日は、会社の未来を左右する、一大コンペの最終プレゼンの日だった。巨大プロジェクトの命運は、担当者である間宮と、その補佐を務めるひな子の双肩にかかっていた。
資料は完璧。練習も重ねた。だが、間宮の不安はひな子の存在そのものだった。この大舞台で、彼女がどんなボケをかますか。それが彼の最大の懸念事項だった。
プレゼンは、意外なほど順調に進んだ。間宮のロジカルな説明は、クライアントの心を掴み、会場の空気は完全に彼らのものになっていた。あとは、最後の締めだけだ。ひな子が、商品のコンセプトを情熱的に語り、締めくくる。そこさえ乗り切れば。
壇上に立ったひな子は、深呼吸を一つすると、輝くような笑顔で語り始めた。
「……私たちの新サービスが目指すのは、ただ便利なだけのものではありません。皆様の日常に、小さな奇跡をお届けすることです」
いいぞ、ひな子。その調子だ。間宮は舞台袖で固唾を呑んで見守っていた。
そして、クライマックス。ひな子は満面の笑みで、こう言い放った。
「ですから、この新サービスのコンセプトは……ずばり、『流れ星を捕まえて、それをジャムにしてパンに塗って食べること』なんです!」
しん、と会場が凍りついた。
役員も、クライアントも、誰もがポカンとした顔でひな子を見つめている。間宮の時間が、止まった。
心臓が、氷の爪で握り潰されるような激痛に襲われる。ぐっ、と胸を押さえるが、痛みは増すばかりだ。
(ツッコめない……!)
脳が警鐘を鳴らす。だが、言葉が出てこない。
これは、ただの言い間違いではない。物理法則を無視した、あまりにも詩的で、あまりにも純粋なボケ。どこから否定すればいい?「流れ星はガスや塵だ」と科学的なツッコミを入れるのか?「食品衛生法違反だ」と法的なツッコミを?違う。そんな野暮な言葉で、この美しいボケを殺してしまっていいのか?
これは、彼女の魂そのものだ。彼女が見ている、きらきらした世界の結晶だ。
死が、すぐそこまで迫っていた。視界が狭まり、意識が遠のいていく。ああ、俺はここで死ぬのか。究極のボケを前に、ツッコむこともできずに。
その時、脳裏にあの老婆の言葉が蘇った。
『ボケ見殺しにしてはならぬ』
見殺しにするな。それは、否定しろという意味だったのか?違う。もしかしたら、違うんじゃないか?このボケを、殺さずに、見つめろ。受け止めろ。そういうことだったんじゃないのか?
間宮は、最後の力を振り絞って、一歩前に踏み出した。そして、マイクを握り、静かに、だがはっきりとした声で言った。
「……その通りです」
会場の視線が、一斉に彼に注がれる。ひな子が、驚いた顔で彼を見ていた。
間宮は続けた。その声は、もうツッコミ師のそれではなく、物語を紡ぐ語り部のようだった。
「我々は、流れ星をジャムにする。それは、不可能を可能にするという、我々の情熱の比喩です。夜空を見上げて誰もが一度は夢見る、あの掴めないはずの輝きを、皆様の食卓へ届けたい。パンに塗れるくらい、身近な奇跡として感じてほしい。それが、このサービスに込められた、私たちの本当の魂です」
彼の言葉は、ひな子の突飛なボケに、意味と、文脈と、そして深い感動を与えた。凍りついていた空気が、ゆっくりと溶けていく。やがて、誰からともなく、拍手が起こった。それは瞬く間に会場全体に広がり、嵐のような喝采となった。
プレゼンは、奇跡的な大成功を収めた。
そして間宮は、自分の胸を締め付けていたあの忌まわしい痛みが、すうっと消え去っていることに気づいた。まるで、長い間絡みついていた鎖が、音もなく解けたかのように。
第四章 朝ごはんは雨粒のスープ
あれから、数ヶ月が過ぎた。
間宮修一は、以前のように物静かで、空気のような存在に戻った……わけではなかった。
呪いは解けた。もう、街角の小さなボケに心臓を痛めることはない。しかし、彼は以前よりもずっと、他人の言葉に耳を傾けるようになっていた。
彼はもう、反射的に言葉を否定しない。相手の言葉の裏にある、不器用な本音や、隠されたユーモア、きらめくような発想の欠片を見つけ出す。そして、それを否定するのではなく、優しく受け止め、面白い方へ転がしてやる。
彼は「キレキレのツッコミ師」から、人の心を解きほぐす「究極の肯定師」へと生まれ変わっていたのだ。もちろん、時と場合によっては、愛のある的確なツッコミも健在だが、それはもはや彼の命を脅かす呪いではなく、コミュニケーションを豊かにする、ただのスパイスだった。
ひな子は、彼の隣で相変わらずだった。二人は公私ともに最高のパートナーとなり、彼らの部署は、社内で最も創造的で、笑いの絶えない場所になっていた。
ある晴れた休日。二人は公園のベンチでコーヒーを飲んでいた。
「間宮さん」ひな子が空を見上げながら、夢見るような声で言った。「もし、私たちが雲の上で暮らせたら、毎日ふわふわして楽しいでしょうね」
一年前の間宮なら、きっとこうツッコんだだろう。「積乱雲はマイナス数十度の氷の塊だぞ。凍死するわ」と。
しかし、今の彼は違う。彼はひな子の横顔を見て、穏やかに微笑んだ。そして、彼女が見ているのと同じ空を見上げながら、こう答えた。
「いいね。朝ごはんは、雨粒を集めたスープかな」
ひな子は、ぱあっと顔を輝かせた。「素敵!デザートは、虹のかけらを砂糖菓子にしたものですね!」
二人の笑い声が、澄み渡る青空に溶けていく。
間宮はもう、平穏だけを求めてはいない。世界は理不尽で、おかしなことばかりだ。でも、そのおかしさの中にこそ、人生を豊かにする宝物が隠れていることを、彼は知ってしまったから。心臓を痛めるほどの呪いが教えてくれた、最高に面白くて、どうしようもなく愛おしい真実だった。