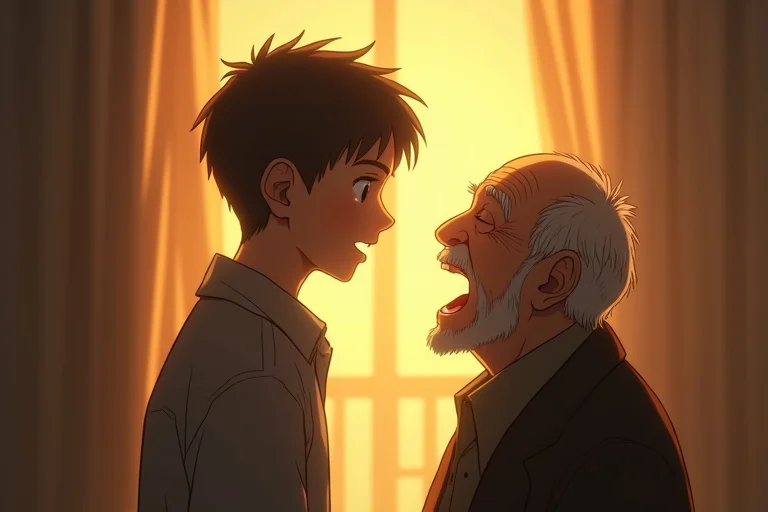第一章 蔵に眠る笑劇
須藤真一の人生は、静寂と無表情で塗り固められていた。代々、厳格な葬儀屋を営む須藤家において、感情、特に「笑い」は最も忌むべきものとされてきた。家訓はただ一つ、『不動心』。喜びも、悲しみも、怒りさえも表情筋の一ミリの動きで悟られてはならない。それが、人の最期に寄り添う者の、最高の礼儀だと教え込まれてきた。三十歳になった真一も、その教えを忠実に守り、物心ついた頃から一度も心から笑ったことがなかった。
祖父が亡くなり、湿った土の匂いが残る蔵の整理をしていた日のことだ。埃っぽい空気の中、桐箪笥の奥に隠された小さな葛籠(つづら)を見つけた。蓋を開けると、そこには古びた能面のような、奇妙な仮面が鎮座していた。白く塗られた表面には、口の部分が大きく裂け、まるで嘲笑しているかのような歪な曲線が刻まれている。しかし、その目の部分は固く閉ざされ、深い悲しみを湛えているようにも見えた。
葛籠の底には、黄ばんだ和紙が一枚。「笑わざる者、笑わすべし。ただし、汝、決して笑うことなかれ」。意味の分からぬ文言に、真一は眉一つ動かさなかった。いつも通りの無表情で仮面を手に取る。ひんやりとした木の感触が、指先に奇妙なリアリティを与えた。
その時だった。足元で丸くなっていた飼い猫のタマが、のっそりと起き上がり、真一を見上げた。いつもは仏頂面の、威厳すらある老猫だ。真一は、ほんの出来心で、その仮面を顔に当ててみた。
次の瞬間、信じられない光景が広がった。タマが「ミ゛ャッ!?」と奇声を発したかと思うと、突然、腹をよじらせるように床を転がり始めたのだ。短い手足をもたつかせ、ゴロゴロと転がりながら、時折、ひきつったように「フギャッ、フギャッ」と鳴き声を上げる。まるで、この世で最も面白いものを見て、笑いをこらえきれずにいるかのようだった。
真一は仮面を顔から離した。途端にタマの動きがピタリと止まる。きょとんとした顔で真一を見上げ、何事もなかったかのように毛づくろいを始めた。
真一の背筋を、これまで感じたことのない種類の戦慄が走り抜けた。心臓が、まるで他人のもののように大きく脈打っている。彼は再び、固く閉ざされた目の仮面を見つめた。この仮面は、一体何なのだ? 静寂で満たされていた彼の世界に、初めて不協和音が鳴り響いた瞬間だった。
第二章 サイレント・ジェスターの誕生
あの奇妙な出来事から数日、真一は仮面のことが頭から離れなかった。昼間は葬儀屋の見習いとして、完璧な無表情で香を焚き、読経を聞く。だが夜になると、蔵から持ち出した仮面を手に、その不可解な力を確かめたいという衝動に駆られた。
ある満月の夜、真一はついに決心した。黒いパーカーのフードを目深にかぶり、顔にあの沈黙の仮面を装着して、深夜の街へと足を踏み出した。仮面を被ると、不思議と世界から音が遠のくような感覚に陥る。自分の呼吸音だけが、やけに大きく響いた。
最初に通りかかったのは、酔って千鳥足のサラリーマンだった。真一がただ彼の横を通り過ぎただけ。それなのに、サラリーマンは突然、電柱に手をついて「ぶふぉっ!」と吹き出した。そして、真一の背中を見つめながら、嗚咽のような笑い声を漏らし始めたのだ。「だ、だめだ……なんか、歩き方が……ツボに……ひぃっ」。
コンビニの前でたむろしていた若者たちも同様だった。真一が自動販売機で無言でお茶を買う。その一連の動作――硬貨を入れ、ボタンを押し、商品を取り出す――が、彼らにとって耐えられないほど滑稽に見えたらしい。一人が腹を抱えて地面にうずくまると、それは連鎖した。夜の住宅街に、若者たちの腹の底からの爆笑が響き渡った。
真一は何もしていない。一言も発していないし、おかしな動きもしていない。いつも通りの、不動心を体現した無駄のない所作を繰り返しているだけだ。だが、この仮面を被ると、彼の「完璧な無表情」と「抑制された動き」が、人々にとって最高のコメディに変換されるらしかった。
彼は公園のベンチに腰掛け、人々を観察した。仮面をつけた彼を見るや、深刻な顔で電話をしていた女性が吹き出し、喧嘩していたカップルが互いの顔を見て笑い出し、ついには仲直りのキスを交わした。世界が、笑いで満たされていく。
真一の心に、今まで知らなかった温かい感情が芽生えた。人を笑わせることの、どうしようもないほどの喜び。人々が笑顔になるのを見るのは、こんなにも胸が満たされることなのか。
しかし、その喜びには常に影が付きまとった。仮面の呪いか、彼は決して笑うことができない。皆が腹を抱えて笑っている中で、彼だけが沈黙の仮面の下、静寂の世界に取り残されている。誰とも、この喜びを分かち合えない。その孤独は、まるで冷たい水が心に染み込んでくるように、じわじわと彼を蝕んだ。
やがて、彼の存在はSNSで噂になり始めた。深夜、突如として現れ、言葉を発さずして人々を爆笑の渦に叩き込む謎のパフォーマー。『サイレント・ジェスター』。そう呼ばれるようになった頃には、真一の中で、夜の街を徘徊することが、葬儀屋の仕事よりもずっと大切な日課になっていた。
第三章 父の涙と仮面の真実
『サイレント・ジェスター』の噂は瞬く間に広がり、ついにテレビ局のプロデューサーの目に留まった。深夜番組の特別企画として、ぜひ出演してほしいというオファーが、SNSのダイレクトメッセージを通じて届いたのだ。
真一は葛藤した。須藤家の人間が、テレビという衆人環視の舞台で「笑いもの」になるなど、考えられる限り最悪の背信行為だ。だが、彼のパフォーマンスを待っている人がいる。もっと多くの人を笑わせたい。その抗いがたい欲求が、恐怖を上回った。
彼は、父・厳一郎にすべてを打ち明けた。案の定、厳一郎の顔は能面のように固まり、その瞳には静かな怒りの炎が燃え盛っていた。
「勘当だ」
氷のように冷たい声が、部屋に響いた。
「須藤家の名を汚すくらいなら、お前はもはや私の子ではない。出ていけ」
父の言葉は、刃物のように真一の胸を抉った。それでも、彼は諦めきれなかった。これが、自分が初めて見つけた「生きている」実感なのだ。彼は父に背を向け、家を出た。
生放送当日。楽屋の鏡の前で、真一は震える手で仮面を握りしめていた。これを被れば、自分は『サイレント・ジェスター』になれる。だが、仮面を外した自分には何が残るのだろう。
その時、静かに楽屋のドアが開き、父の厳一郎が立っていた。驚く真一に構わず、父はゆっくりと歩み寄り、彼の手の中にある仮面を見つめた。
「その仮面は……呪われているんだ」
絞り出すような声だった。
「須藤家の『不動心』はな、ただの作法じゃない。あの仮面の呪いから身を守るための、血の滲むような修行なのだ」
厳一郎は、衝撃の事実を語り始めた。須藤家の先祖は、かつてこの仮面の力で、国を滅ぼしかねないほどの悲しみに沈んだ君主を笑わせ、国難を救ったのだという。だが、その代償はあまりにも大きかった。人々を笑わせるたびに、仮面は被った者の「幸福」や「笑う能力」を吸い上げていく。先祖は人々を救った英雄でありながら、二度と笑うことのできない、抜け殻のような余生を送った。
「その悲劇を繰り返さぬため、我々一族は感情を封じ、笑いを遠ざけてきた。仮面の誘惑に抗うために、心を石にするしかなかったのだ」
父の厳格な顔が、初めて苦痛に歪んだ。
「父さんも若い頃、お前と同じようにその力に魅入られた。病床にいた、お前の母さんを……たった一度でいいから笑わせたくて、仮面を被った。彼女は、腹の底から笑ってくれたよ。人生で一番幸せそうな顔だった」
父の声が、微かに震える。
「だが、それが最後だった。私は、彼女の笑顔を見ても、心から笑い返してやることができなくなった。彼女が息を引き取るその瞬間まで……私は、ただの無表情な石人形だった。真一、お前には……お前には、同じ思いをさせたくないんだ」
厳一郎の目から、一筋の涙が静かに頬を伝った。それは、真一が生まれて初めて見る、父の涙だった。
第四章 素顔のコメディアン
父の告白は、雷のように真一の心を打ちのめした。仮面の力が、自分の感情を犠牲に成り立っていたとは。人々を笑わせる喜びの裏で、自分は最も大切なものを失っていたのだ。
本番まで、あと数分。舞台袖で、真一は固く目を閉じた。手には、ずっしりと重い仮面。これを被れば、今夜も人々を熱狂させられる。だが、その先に待つのは、感情の死んだ未来。
彼は、ゆっくりと目を開けた。そして、仮面を楽屋の机にそっと置いた。
司会者の呼び込みと共に、スポットライトの中に足を踏み出す。フードも被らず、素顔のまま。ざわめく観客。誰もが『サイレント・ジェスター』の奇妙なパフォーマンスを期待している。だが、そこに立っていたのは、ただの地味で無表情な一人の青年だった。
真一はマイクの前に立ち、深く息を吸った。
「こんばんは。須藤真一です」
静まり返るスタジオ。彼は、訥々と語り始めた。
「私は、生まれてこの方、笑ったことがありません。実家は葬儀屋で、笑うことは禁じられていました。笑いを堪えるための訓練もしました。例えば……そう、熱々のたこ焼きを、表情一つ変えずに一気に口に放り込む、とか」
観客席から、小さな笑い声が漏れた。
「先日、祖父の蔵から奇妙な仮面を見つけました。それを被ると、なぜかみんなが僕を見て笑うんです。僕は、それが嬉しかった。でも、今日、その仮面は僕の感情を食べてしまう呪いの道具だと知りました」
彼のあまりに真剣で、不器用な語り口。そこには、計算されたジョークも、巧みな話術もなかった。ただ、一人の人間が、自分の人生を懸命に、正直に語っているだけ。その必死さが、そのあまりの不器用さが、なぜかたまらなく滑稽で、そして愛おしかった。
「僕は、人を笑わせたい。でも、僕も、笑いたいんです」
その言葉を口にした瞬間、スタジオは爆発的な笑いに包まれた。それは、仮面の力で作られた狂騒的な笑いとは違う。温かくて、優しくて、どこか少し切ない、人間味あふれる笑いだった。
真一は、自分自身の言葉で、自分自身の力で、初めて人々を笑わせたのだ。舞台袖で、父の厳一郎が、固く結んでいた口元を、ほんのわずかに綻ばせているのを、彼は見逃さなかった。
番組が終わり、真一は父と静かに向き合った。
「父さん、俺、葬儀屋も継ぎます。でも、コメディアンもやります。人の最期に寄り添うことも、人の日常を笑顔にすることも、きっと、同じくらい尊いことだと思うから」
厳一郎は何も言わず、ただ力強く頷いた。
後日、真一は自宅の洗面台の鏡に向かっていた。彼は、ゆっくりと、ぎこちなく、自分の口角を少しだけ引き上げてみた。それはまだ、笑顔と呼ぶにはほど遠い、ひきつったような形だったかもしれない。
だが、彼の瞳には、凍てついていた感情が雪解けを始めたような、確かな光が宿っていた。笑えない男が、本当の笑いを探す旅は、まだ始まったばかりだ。