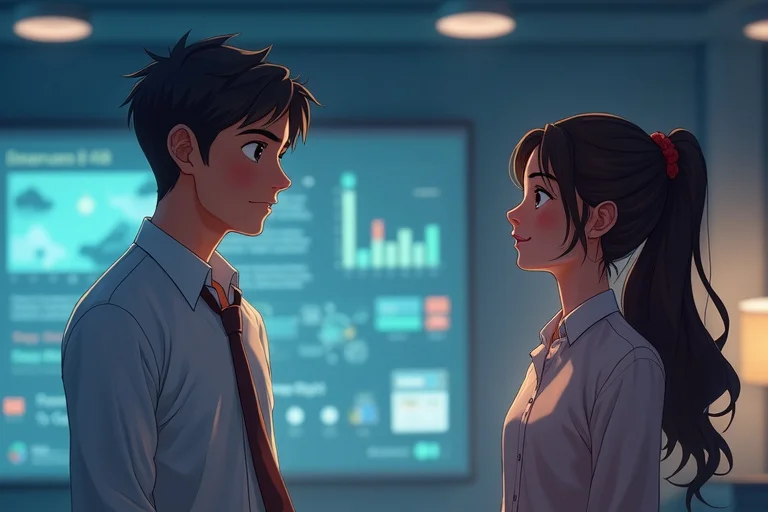第一章 鉄仮面の男と太陽の女
市役所の戸籍係、灰田勘太郎の人生は、灰色だった。蛍光灯が単調に照らすカウンター、インクの乾いた匂い、規則正しく積み上げられた書類の山。彼の世界は、完璧なまでに秩序と無表情で構成されていた。同僚たちは彼のことを「能面」「歩く定款」と呼んだ。勘太郎自身、その評価を甘んじて受け入れていた。感情を表に出すことは、彼にとって災害に等しい行為だったからだ。
彼の朝は、鏡の前で表情筋を固定する訓練から始まる。口角を水平に保ち、眉一つ動かさず、瞳の奥の光を消す。これは彼が十数年の歳月をかけて編み出した、自分自身を守るための鎧であり、呪いでもあった。
その日、彼の灰色の世界に、一本の巨大なひまわりのような女が飛び込んできた。
「婚姻届、お願いしまーす!」
太陽を丸ごと絞ったようなオレンジ色のワンピースを着た女――天野光は、カウンターに書類を叩きつけるように置いた。その声は、静かな窓口フロアに不釣り合いなほど快活に響き渡る。
勘太郎は無言で書類を受け取り、機械のように項目をチェックし始めた。
「いやー、ついに私も人妻かぁ。実感わかないなー。ね、お兄さん、実感わきます?」
「……本人確認書類を」
勘太郎は、視線も上げずに、低い声で応じた。光は全く気にする様子もなく、鞄から運転免許証をごそごそと取り出す。
「しかし、この写真写り最悪なんですよね。指名手配犯みたいじゃないです?あ、そうだ。この間、駅前で職務質問されたんですよ。警官が言うんです。『君、ちょっと顔貸して』って。私、とっさに『すみません、レンタルはやってないんです』って言っちゃって。そしたら警官、五秒くらい固まってから、お腹抱えて笑い出して……」
光のマシンガントークが続く。勘太郎はそれを右から左へと聞き流しながら、淡々と事務処理を進めていた。だが、その時だった。光が不意に勘太郎の顔を覗き込み、にっと笑った。
「お兄さん、もしかして笑うの、苦手?」
勘太郎の指が、ぴくりと震えた。心臓が嫌な音を立てて跳ねる。喉の奥に、ふわりとした甘い感触が生まれかけた。危ない。彼は慌てて息を飲み込み、その不穏な予感を胃の底に押し込めた。
「……書類に不備はありません。受理します」
彼は冷たく言い放ち、認印を力強く押した。インクが滲むほどの力だった。
「わーい、ありがとう!じゃあ、また来ますね!」
「……もう来る必要は」
勘かろうが言い終わる前に、光は嵐のように去っていった。カウンターには、彼女がつけていたのだろう、微かな柑橘系の香りと、厄介な予感だけが残されていた。勘太郎は深くため息をつき、再び鉄の仮面を被り直した。この平穏な灰色の日常が、ほんの少しでも色づくことなど、あってはならないのだから。
第二章 マシュマロの秘密
天野光は、宣言通り「また来た」。翌日、彼女は「昨日のお礼です!」と言って、勘太郎のカウンターに巨大なメロンパンを置いた。その翌日には、「市役所の屋上で鳩に餌をやっていたら、一羽が私の肩でプロポーズを始めたんです!」という謎の報告をしに来た。彼女の来訪は、勘太郎の平穏な日常における、予測不能なバグと化していた。
勘太郎は徹底的に彼女を無視した。書類を凝視し、パソコンの画面に集中し、彼女が存在しないかのように振る舞った。しかし、彼の防御は日に日に脆くなっていった。光が披露する、脈絡のない一発ギャグや、突拍子もない身の上話は、勘太郎の表情筋を執拗に刺激した。彼の口角は、本人の意思に反してぴくぴくと痙攣し、横隔膜は暴動寸前の市民のように震えた。
そして何より恐ろしかったのは、喉の奥で日に日に存在感を増していく、あの甘く柔らかな感触だった。それは、笑いの衝動が臨界点に達する兆候。爆発寸前の時限爆弾を抱えているような心地だった。
ある日の昼休み、勘太郎は給湯室で一人、インスタントの味噌汁をすすっていた。光の襲撃がない唯一の安息の時間だ。彼はほうっと息をつき、ほんの少しだけ仮面を緩めた。その時、脳裏に光が真顔で言った言葉が蘇った。
『私、前世はきっとプランクトンだったと思うんです。だって、流れに身を任せるのが得意だから』
あまりの馬鹿馬鹿しさに、勘太郎の口から「フッ」と、乾いた空気が漏れた。しまった、と思った瞬間にはもう遅かった。
ポンッ。
静かな給湯室に、マシュマロが一つ、床に落ちる軽やかな音が響いた。真っ白で、ふわふわとした、紛れもないマシュマロだった。勘太郎は血の気が引くのを感じながら、慌ててそれを拾い上げようとした。
「……え、今の……何?」
背後から聞こえた声に、勘太郎の体は石のように固まった。ゆっくりと振り返ると、そこには水筒を持った光が、目を丸くして立っていた。彼女の視線は、勘太郎の手の中にあるマシュマロに釘付けになっている。
「い、いや、これは……」
勘太郎は必死で言い訳を探した。ポケットに入れていたお菓子が、たまたま、偶然、奇跡的な確率で口から飛び出すような角度で落ちたのだと。しかし、彼の狼狽した顔が何よりの証拠だった。
「灰田さん……あなた、もしかして……」
光は一歩、また一歩と勘太郎に近づいてくる。その目は、まるで未知の生物を発見した研究者のように、好奇心で爛々と輝いていた。
「手品師……?」
予想の斜め上を行く問いかけに、勘太郎は言葉を失った。絶望的な沈黙が、給湯室の狭い空間に満ちていく。もう、隠し通すことはできない。彼の灰色の世界が、音を立てて崩れ落ちていくのが分かった。
第三章 感情100%のオーガニック製法
観念した勘太郎は、市役所の裏にある小さな公園のベンチで、全てを打ち明けた。幼い頃から、強い感情を抱くと、それが特定の食べ物になって口から飛び出してしまうという、この奇妙で厄介な体質について。
「嬉しいと、星形のラムネが。悲しくて泣くと、色とりどりの金平糖が。そして……笑うと、マシュマロが」
俯き、絞り出すように語る勘太郎の声は、雨上がりの地面に染み込む水滴のように、か細かった。
「だから、ずっと感情を殺してきました。人前で笑うなんて、とんでもない。マシュマロが噴き出す光景を想像するだけで、死にたくなります。あなたは、僕の人生をめちゃくちゃにしに来た、疫病神です」
最後の言葉は、ほとんど八つ当たりだった。これで彼女も気味悪がって離れていくだろう。そう思っていた。
ところが、光の反応は勘太郎の予想を180度裏切るものだった。
「……最高じゃないですか!」
光は目をきらきらと輝かせ、勘太郎の肩をバシンと叩いた。勘太郎は驚いて顔を上げる。
「なにそれ、超面白い!っていうか、すごい才能ですよ!だってそれって、感情が目に見えるってことでしょう!?」
「さ、才能……?」
「そうですよ!究極のオーガニック製法!感情100%のお菓子じゃないですか!」
勘太郎は、光が何を言っているのか理解できなかった。コンプレックス。呪い。隠すべき秘密。そう信じて疑わなかったものが、「才能」という言葉に置き換えられ、彼の頭は完全に混乱していた。
光は興奮冷めやらぬ様子で、今度は自分の身の上を語り始めた。彼女が老舗和菓子屋「あまの屋」の一人娘であること。伝統の味を守ることだけを考える厳格な父親と、「新しい時代のお菓子を作りたい」という自分の夢との間でもう何年も対立していること。そして、家を飛び出して、自分の理想のお店を開くためのアイデアを探していたこと。
「私、ずっと探してたんです。誰も見たことがないような、人の心を動かすような、特別なお菓子を。まさか、こんなに近くにあったなんて!」
光は勘太郎の両手を、ぐっと力強く握った。その手のひらは、驚くほど温かかった。
「灰田さん、私と一緒にお店やりませんか!?あなたの感情で、世界を甘くしましょうよ!」
世界を、甘くする。
その言葉は、雷鳴のように勘太郎の心を撃ち抜いた。
自分の人生を呪い、灰色に塗りつぶしてきたこの体質が、誰かの夢になり、希望になる。笑うという行為が、恐怖ではなく、価値を生み出すかもしれない。
勘太郎の世界を覆っていた分厚い灰色の雲に、初めて一筋の光が差し込んだ気がした。ベンチの隣で太陽のように笑う彼女を見つめながら、彼は生まれて初めて、自分の呪いを真正面から見つめ直していた。口の中に、マシュマロの甘い予感が、今度は少しも怖くない形で、ゆっくりと広がっていった。
第四章 ようこそ、マシュマロ・メランコリーへ
市役所を辞めた勘太郎は、人生最大の賭けに出た。光と共に、街角の小さな空き店舗を改装し、カフェを開いたのだ。店の名前は、光が即決で名付けた。
「感情喫茶 マシュマロ・メランコリー」
メランコリー(憂鬱)は、金平糖を降らせる勘太郎の悲しみに敬意を表して、とのことだった。
開店初日。エプロン姿の勘太郎は、緊張で全身が氷のように冷たくなっていた。カウンターの内側で、深呼吸を繰り返す。お客さんの前で、果たして自分は笑えるのだろうか。マシュマロを出せるのだろうか。それは、もはや恐怖ではなく、使命のようなプレッシャーになっていた。
「いらっしゃいませー!」
光の元気な声と共に、最初のお客さんが入ってくる。注文を取る光の背中を見ながら、勘太郎はただただ、コーヒーカップを磨くことしかできない。
その時だった。お客さんにコーヒーを運ぼうとした光が、自分の足にもつれて、盛大にすっ転んだ。ガシャーンという派手な音と共に、トレイが宙を舞い、カップの中身だったカフェラテが、見事な放物線を描いて光の頭上に降り注いだ。
白いクリームと茶色い液体でべちゃべちゃになった頭で、光は床に座り込んだまま、きょとんとした顔で勘太郎を見た。
「……あちゃー」
その瞬間、勘太郎の中で何かが弾けた。
張り詰めていた緊張の糸がぷつりと切れ、堪えようもなく、笑いが込み上げてきた。それは、今まで押し殺してきた何十年分もの笑いが、堰を切って溢れ出すような、抗いがたい衝動だった。
「あっ、はは……あははははは!」
勘太郎は、腹を抱えて笑った。生まれて初めて、人前で、心の底から。
次の瞬間、奇跡が起こった。
ポンッ、ポポポンッ!
彼の口から、色とりどりのマシュマロが、まるで噴水のように、滝のように、とめどなく噴き出したのだ。ピンク、水色、黄色、緑。ふわふわとした甘い雪崩がカウンターを越え、店内に舞い散る。それはまるで、二人を祝福する紙吹雪のようだった。
店内にいた客たちは、最初は何が起きたのか分からず呆然としていたが、事情を知ると、わっと歓声を上げた。子供たちは歓喜の声を上げて、床に散らばるマシュマロを拾い集めている。
勘太郎は、降り注ぐマシュマロの雨の中で、笑い続けていた。涙が出るほど笑っていた。それは、コンプレックスという名の硬い殻を破り、本当の自分が解放された、産声にも似た笑い声だった。
自分の感情が、誰かを笑顔にしている。
灰色の世界は、完全に消え去っていた。彼の目には、マシュマロのようにカラフルで、甘くて、優しい世界が広がっていた。
その日の夜、店の片付けをしながら、光がふと尋ねた。
「ねえ、灰田さん。怒ったら、本当に唐辛子が出るんですか?」
勘太郎は、その悪戯っぽい笑顔を見て、またくすりと笑った。
すると、ポン、と一つだけ。
彼の唇から、小さなハートの形をした、淡いピンク色のマシュマロがこぼれ落ちた。
光はそれを、壊れ物を扱うようにそっと手のひらで受け止めると、宝物のように見つめて、優しく微笑み返した。
店の窓の外では、静かな夜が始まろうとしていた。二人の甘い奇跡は、まだ始まったばかりだ。