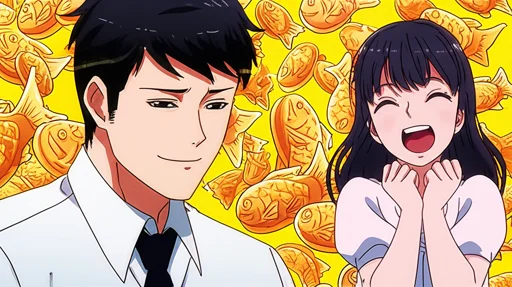第一章 錆びた錨とポストのパ・ド・ドゥ
天野奏の怒りは、いつも唐突に、そして形而上学的な質量を持って訪れる。上司の理不尽な叱責が、熱い鉄となって喉の奥に流れ込んでくる。言葉にならない反論は、体内で出口を見失い、奇妙な圧力を生み出していく。
「……だから、君は」
上司の声が遠のく。奏の視界の端で、同僚たちの顔が歪み始めた。驚愕と、わずかな憐憫。ああ、またか。奏は目を閉じる。肌が厚く、滑らかになっていく奇妙な感触。手足が短く、重くなっていく。自分の体が、自分のものでなくなっていく感覚。
その時だった。
ポケットの中で、古びたスマートフォンが振動した。ディスプレイを見るまでもない。聞こえてきたのは、決して着信音に設定した覚えのない、低く、唸るような声。『ゴマフアザラシの威嚇音』。それは、まるで今まさに奏の喉から漏れ出そうとしている声そのものだった。
奏が目を開けると、世界の色彩が少し変わって見えた。人々が自分を指さし、囁き合っている。その視線の意味を、奏は永遠に理解できないだろう。ただ、その視線が一点に集中した。
奏の目の前、錆びた錨のオブジェの隣に立つ、色褪せた赤い郵便ポスト。
それが、動いたのだ。
ポストはまず、投函口をわずかに傾け、まるで舞台に立つバレリーナが観客へ一礼するかのように優雅な仕草を見せた。次の瞬間、金属の塊とは思えぬしなやかさで、ポストは回転を始める。軸足となったコンクリートの土台は微動だにせず、その赤い胴体だけが、超高速のスピンを繰り出す。タップダンスのように地面を打ち鳴らし、アクロバティックな跳躍を見せ、コンテンポラリーダンスの複雑なステップを完璧に踏んでみせる。
誰もが息を呑んでいた。潮風も、カモメの鳴き声も、街の喧騒も、すべてがその赤いポストの独舞を際立たせるための背景となった。奏は、その非現実的な光景に心を奪われていた。身体の奥底で燻っていた灼熱の怒りが、ポストの流麗な動きに吸い取られ、霧散していくのを感じる。
やがて、狂騒的なダンスはピタリと止まった。ポストは最初と同じ場所に、何事もなかったかのように佇んでいる。人々は我に返り、ざわめきが戻ってきた。そして奏は、自分の手足が人間のそれに戻っていることに、遅れて気づくのだった。
第二章 ポケットの中の交響曲
奏のポケットに収まる古びたスマートフォンは、彼の人生そのものだった。いつから持っているのか記憶は定かでない。どこのメーカー製かも分からず、バッテリーは最後に充電した日を思い出せないほど長持ちしていた。しかし、その最大の特徴は、着信音のライブラリにあった。
『ご当地着信音』と名付けられたそのフォルダには、世界中のあらゆる音が収録されていた。シベリアのオオカミの遠吠え、サハラ砂漠の砂嵐の音、マリアナ海溝の深海魚が発する微かなクリック音、ニューヨークの地下鉄の軋み、京都の竹林が風に揺れる音。そして、そのどれもが、奏の意思とは無関係に鳴り響くのだ。
あれは、深い悲しみに打ちひしがれた日だった。鳴り響いたのは『古い消火栓のバルブから水が漏れる寂しい音』。気づけば奏の体は硬い鉄に変わり、街角に佇んでいた。そして目の前では、ショーウィンドウのマネキンが、涙を流すような悲痛なパントマイムを踊っていた。
またある日は、人生で最高の喜びを感じた日。スマホは『焼きたての巨大なパンケーキが立てる甘い音』を奏でた。奏が巨大なパンケーキそのものになっていた頃、公園の噴水が、歓喜の飛沫を撒き散らしながら天を衝くようなダンスを披露していた。
変身と、ダンス。そして、その前触れとなる謎の着信音。三者は常にセットで現れる。奏は、この奇妙な現象の法則性を解き明かそうと、何度もスマホを調べた。だが、再生履歴は常に空っぽで、フォルダの音源を任意で再生することもできない。それはただ、来るべき変身とダンスの到来を告げる、運命の交響曲の序章を奏でるだけの、黒い石板のような存在だった。
第三章 埠頭に響くエレジー
冷たい霧雨が、灰色の埠頭を静かに濡らしていた。奏は、恋人から告げられた別れの言葉を、何度も頭の中で反芻していた。言葉は鋭い氷の礫となって、彼の心を容赦なく打ち据える。足元のアスファルトに、自分の存在がじわりと溶けていくような錯覚。体が鉛のように重くなり、その場から一歩も動けなくなる。
「きゃっ、見て!」
「人が……人が、消火栓に……!」
遠くで聞こえる悲鳴は、厚い水の膜を隔てた向こう側の出来事のようだった。ああ、そうか。今の僕は、消火栓なのか。心のどこかで、冷静な自分が呟く。全身を巡る血流が止まり、代わりに冷たい水が満ちていく。悲しみは、赤い鉄の孤独な形をとった。
ポケットのスマホが、静かに震えた。着信音は、霧雨の音にかき消されそうなほど微かだった。それでも奏にははっきりと聞こえた。それは、彼が今まさになっているであろう、古い消火栓の内部で水が反響する、寂寞とした音色だった。
音に誘われるように、奏の視線(あるいは、視線のような感覚)が埠頭の先端に向けられる。そこに立つ、もう一体の消火栓。彼と同じ、赤く、古びた消火栓。
それが、静かに踊り始めた。
それはエレジーだった。亡くしたものを悼む、悲しみの舞踊。一つ一つの動きが、後悔と未練を体現していた。天を仰ぎ、地に伏すその姿は、言葉にならない慟哭そのもの。降りしきる霧雨が、まるで踊る消火栓が流す涙のように見えた。奏は、自分の内側にある行き場のない悲しみのすべてが、あのダンスに昇華されていくのを感じていた。悲しみは、共有され、そして浄化されていく。
ダンスが終わる頃には、霧雨は上がっていた。埠頭に佇む奏の頬を、一筋の冷たい雫が伝った。それは雨水か、それとも。彼は、久しぶりに自分の体温を取り戻していた。
第四章 鏡像のフーガ
この無限に続く変身とダンスの連鎖を断ち切りたい。その一心で、奏は自室に籠った。スマホを分解しようと試みたが、ネジ一本見当たらない滑らかな筐体は、彼の無力さを嘲笑うかのようだった。自分は何者なのか。なぜこんな運命を背負わされたのか。答えのない問いが、奏の精神を蝕んでいく。
鏡の前に立ち、そこに映る疲れ果てた男を見つめる。お前は誰だ。お前が感じるその感情が、僕を異形の怪物に変えるんだ。自己嫌悪の黒い波が、足元から這い上がってくる。
その瞬間、スマホが鳴った。
これまで聞いたことのない、不快な音だった。それは、ブラウン管テレビの砂嵐のようでもあり、割れた鏡が軋む音のようでもあった。『歪んだ自己認識が発するノイズ音』。そんな表題が、頭の中に直接響いた。
奏は息を呑んだ。鏡の中の自分が、ゆっくりと動き出したのだ。
それは、奏自身ではなかった。同じ顔、同じ体でありながら、その動きは人間のものではなかった。手足が関節を無視した角度に曲がり、体が液体のように波打つ。苦悶に顔を歪ませながら、しかし同時に恍惚とした表情で、鏡像は踊り続ける。それは、奏が抱える自己嫌悪、自己否定、その全てをエネルギー源とした、呪詛のダンスだった。複数の旋律が複雑に絡み合うフーガのように、鏡の中の自分は増殖し、重なり合い、苦しみのタペストリーを織り上げていく。
奏は、恐怖と同時に、ある種の既視感を覚えていた。そうだ、いつもこうだった。怒りを感じていた時、あのポストは怒りを踊っていた。悲しみを感じていた時、あの消火栓は悲しみを踊っていた。
踊っているのは、いつも「僕」だったのだ。
僕の感情が生み出した、もう一つの変身した姿。鏡の中にいるそいつが、僕の感情そのものなのだ。
第五章 解かれた和音
答えは、パズルの最後のピースが嵌まるように、奏の心にすとんと落ちてきた。
変身は、一度ではなかったのだ。
ある感情が極限に達した時、奏の意識は二つに分かれる。一つは、感情の器そのものとなって変身する自分(アザラシや消火栓になる奏)。もう一つは、その感情を外部に放出し、昇華させるためのパフォーマーとして変身する自分(ポストやマネキンとなって踊る奏)。
主人公は、常に前者だ。変身したまま動けず、ただ後者のダンスを見つめることしかできない。踊り手であるもう一人の自分は、その感情を完璧なダンスとして表現し尽くすことで、感情を昇華させ、変身を解く役割を担っていた。
しかし、その解放には代償があった。ダンスによって放出された膨大な感情エネルギーは、消滅するわけではなかった。それは世界を巡り、奏の心のわずかな揺らぎを捉え、次の感情の波を増幅させるトリガーとなっていたのだ。怒りを解放するためのダンスが、やがて来る悲しみの種を蒔き、悲しみを癒すためのダンスが、未来の喜びの過剰な萌芽となる。
スマホの着信音は、その連鎖の始まりを告げる合図。変身(主題)とダンス(変奏)が織りなす、無限に繰り返されるカデンツァの開始を知らせる、ただのファンファーレに過ぎなかった。
絶望が、静かに奏を包んだ。これは救済などではない。永遠に終わらない、感情の牢獄。感情を持つ限り、自分は変身し、踊り、そしてまた次の変身へと誘われる。自分自身によって、自分自身を永遠に閉じ込める、完璧な円環。
第六章 綿毛のアダージョ
すべてを悟った奏は、港を見下ろす丘の上に立っていた。吹き抜ける風が心地よい。眼下に広がる海の煌めきを見つめていると、穏やかで、それでいて胸が満たされるような幸福感が、ゆっくりと湧き上がってきた。
ポケットのスマホが、優しく、囁くように鳴った。
『風に運ばれるタンポポの綿毛が奏でる、旅立ちの音』。
奏の体から、すうっと重力が抜けていく。足が地面を離れ、体が白い繊維に変わっていく。巨大な、一つの綿毛。彼は微笑んでいた。それは諦めでも、絶望でもない。ただ、すべてを受け入れる、凪のような静かな受容だった。
ふわりと宙に浮いた彼の視線の先で、空を飛んでいた一羽のカモメが、突如としてその軌道を変えた。
カモメは、空という広大な舞台で、アダージョを踊り始めた。ゆっくりと、荘厳に。翼を大きく広げ、風を捉え、大空に柔らかな円を描く。それは、今まさに奏が感じている、穏やかな幸福そのものを体現した舞だった。
「ああ、次は君なんだね。僕」
綿毛となった奏が、心の中で呟く。
ありがとう。僕の喜びを、そんなにも美しく踊ってくれて。
風に乗り、綿毛の体はさらに高く、空へと舞い上がっていく。踊るカモメとすれ違い、やがて小さな白い点になっていく。彼の感情が奏でるカデンツァは、これからも続くだろう。悲しみも、怒りも、そして喜びも、形を変え、踊り、また新たな感情の波となって彼自身に還ってくる。
それは呪いか、祝福か。答えは、風の中だけが知っている。