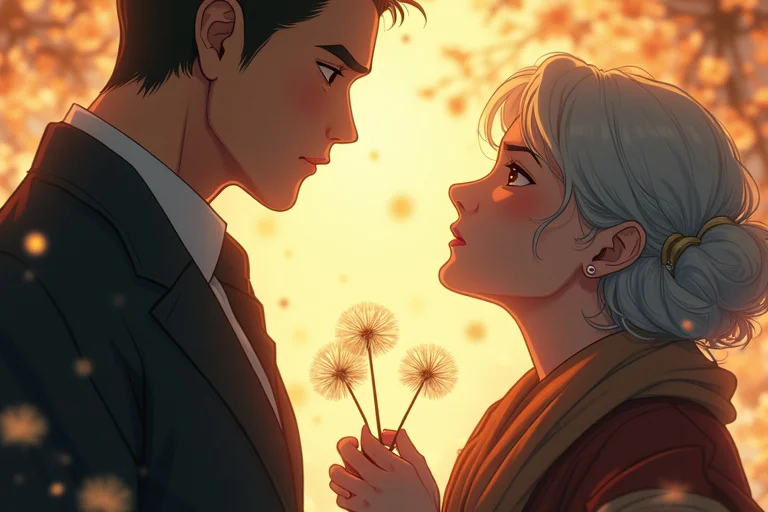第一章 塩バター風味の憂鬱
桜木健太、28歳、市役所地域振興課勤務。彼の人生は、一枚の模造紙のように平坦で、シミひとつない。几帳面な性格は、公務員という職業に驚くほど合致していた。机の上は常に完璧に整頓され、書類の角度は寸分の狂いもなく揃っている。彼の精神もまた、その机の上と同じだった。感情の起伏という名の乱雑さを、彼は極端に嫌った。特に「笑い」は、彼の人生における最大の禁忌だった。
なぜなら、健太が心から笑うと、彼の身体からポップコーンが弾け飛ぶのだ。
それは冗談でも比喩でもない。腹の底からこみ上げる笑いに身を任せた瞬間、ポンッ、ポンッ、という軽快な音と共に、半径数メートルにわたって、出来立ての塩バター風味のポップコーンが撒き散らされる。この特異すぎる体質のせいで、彼の青春は灰色だった。修学旅行の夜も、友人の結婚式も、彼は息を潜め、決して口角を上げぬよう、鉄の意志で耐え抜いてきた。楽しい思い出は、すべてポップコーン発生の恐怖に上書きされてきたのだ。
そんな彼の平穏(という名の無味乾燥)な日常に、ある日、核弾頭が投下された。
「どーもー!本日からこちらでお世話になります、天野ひかりです!趣味は人を笑わせることでーす!」
春の人事異動で健太の隣の席になった彼女は、太陽をそのまま人型にしたような女性だった。底抜けに明るく、声が大きく、そして冗談が三度の飯より好きらしい。健太の全身の細胞が、警報を鳴らした。これはまずい。非常にまずい。歩く時限爆弾が、自分のテリトリーに侵入してきたのだ。
案の定、ひかりは事あるごとに健太に絡んできた。「桜木さん、そのネクタイ、信号機みたいで交通安全に貢献してますね!」「この書類、あまりに綺麗すぎて、逆に内容が頭に入ってきません!才能ですね!」彼女の言葉は、褒めているのか貶しているのか紙一重だったが、その屈託のなさが、健太の鉄壁の無表情をじわじわと侵食していく。
そして、運命の金曜日。静まり返った昼下がりのオフィスで、ひかりが渾身のモノマネを披露した。「聞いてください、桜木さん。やる気のないセミの鳴き声。『……ミーン』」。その、あまりにも気の抜けた、絶妙な間と情けない声色。健太の脳内で、何かが焼き切れる音がした。必死に唇を噛み、机の下で太ももをつねったが、一度点火した笑いの導火線はもう止まらない。
「く……ふふっ……あ、ははははは!」
次の瞬間。ポンッ!ポポポポーン!
健太の身体を中心に、白い花々が咲き乱れるかのようにポップコーンが噴出した。それはオフィス中に舞い、課長の頭に降り注ぎ、先輩のコーヒーカップにダイブし、静寂を香ばしい塩バターの香りで満たした。呆然とする同僚たち。真っ赤になって固まる健太。ただ一人、ひかりだけが目を輝かせていた。
「すごい……!桜木さん、あなた、歩く映画館だったんですね!」
その一言が、健太の塩バター風味の憂鬱を、さらに複雑な味わいへと変えてしまったのだった。
第二章 ポジティブという名の時限爆弾
「ポップコーン男」という不名誉なあだ名は、瞬く間に庁舎内に広まった。健太は、廊下を歩くだけで囁き声と好奇の視線に晒され、食堂では彼の周囲だけ不自然な空席ができた。まるで、いつ爆発するか分からない不発弾扱いだ。健太は、これまで以上に心を固く閉ざし、ひかりとの間に見えない壁を築こうと努力した。業務連絡以外は一切口を利かず、彼女がジョークを言おうものなら、即座にヘッドフォンをつけて外界をシャットアウトした。
だが、天野ひかりという人間は、健太が築いた壁など、ブルドーザーのように軽々と破壊していくタイプだった。
「桜木さん、これどうぞ!」と、彼女は手作りのポップコーン用キャリーケース(段ボール製)を差し出してきた。「緊急事態に備えて!これで被害を最小限に抑えられます!」
「……結構です」
「じゃあ、味のバリエーションを増やしませんか?キャラメルとか、カレーとか!私、スパイスには詳しいんですよ!」
「……お断りします」
ひかりは健太の体質を、悩みではなく「面白い個性」としか捉えていないようだった。彼女の悪意のないポジティブさは、健太にとって最も対処の難しい攻撃だった。彼は逃げたかった。しかし、皮肉なことに、ポップコーン事件以来、仕事のペアを組まされることが増えてしまったのだ。おそらく、課長の「面倒な奴らはまとめてしまえ」という配慮(という名の厄介払い)だろう。
ある雨の日、二人は外回りの営業から帰る途中、バス停で足止めを食らっていた。ひかりは退屈しのぎに、カバンから一冊の古びたノートを取り出した。
「これ、私のネタ帳なんです。ちょっと聞いてもらえませんか?」
健太は反射的に断ろうとしたが、ひかりの真剣な眼差しに言葉を失った。彼女はページをめくり、一つの短い話を読み始めた。それは、靴下を片方なくして悲しんでいるタンスと、それを慰めるセーターの心温まる物語だった。拙いが、優しさに満ちた物語だった。
「……どう、でしたか?」ひかりが不安そうに顔を上げる。
健太は、どう答えるべきか迷った。面白い、と言えばポップコーンが出る。つまらない、と言えば彼女を傷つける。沈黙が流れる。雨音が、アスファルトを叩く音だけが響いていた。
「……タンスが、少し、可哀想でした」
やっとの思いで絞り出した言葉に、ひかりは「そっかぁ」と呟き、少しだけ寂しそうに俯いた。その表情を見た瞬間、健太の胸がチクリと痛んだ。彼は、人を傷つけたくない一心で、自分の感情を殺してきた。だが、感情を殺すことは、時として、人を遠ざけ、孤独にさせることと同義なのかもしれない。
バスが来た。乗り込むと、ひかりは窓の外の雨を眺めながら、ぽつりと言った。
「私、人を笑わせるのが好きなんです。笑った顔って、花が咲くみたいだから。だから、桜木さんのポップコーンも、すごいなって思う。だって、物理的に花を咲かせてるようなものじゃないですか」
健太は何も答えられなかった。彼の体質を肯定的に捉えた人間は、生まれて初めてだった。その言葉は、じっとりと湿った彼の心に、小さな陽だまりを作った気がした。彼はまだ、自分の呪いを祝福だとは思えなかったが、隣に座るこの時限爆弾のような女性が、少しだけ、ただの厄介者ではないのかもしれない、と、そう思い始めていた。
第三章 ポップコーンと金平糖のプレリュード
季節は巡り、街が桜色に染まる頃、健太とひかりに特大の任務が下された。市が総力を挙げて開催する、年に一度の一大イベント「さくら祭り」の企画運営責任者。断る術もなく、二人は祭りの準備に忙殺される日々を送ることになった。
健太は、その重責に押しつぶされそうだった。数万人が訪れるイベントだ。もし、万が一、何かの拍子に自分が笑ってしまったら?想像するだけで、胃がキリキリと痛んだ。彼は極度の緊張から、さらに無口で無表情になった。
一方のひかりは、水を得た魚のようだった。次から次へと奇抜なアイデアを出し、関係各所とエネルギッシュに交渉を進めていく。彼女の圧倒的な行動力に引っぱられる形で、準備は着々と進んだ。しかし、彼女の底抜けの明るさが、時に健太の神経を逆撫でした。
「桜木さん、そんなに眉間にシワ寄せてると、永久に取れなくなっちゃいますよ!笑いジワの方が百万倍素敵です!」
「……君には、分からないんだ」
健太は、思わず棘のある言葉を返してしまった。ひかりは一瞬、驚いたように目を見開いたが、すぐにいつもの笑顔に戻った。その笑顔が、健太には自分を憐れんでいるように見えて、余計に惨めな気持ちになった。
祭り開催の三日前、事件は起きた。メインステージの目玉として呼んでいた有名歌手が、急病で出演キャンセルになったのだ。さらに、天気予報は祭り当日に大雨を告げていた。最悪の状況だった。会議室の空気は鉛のように重く、誰もが諦めの表情を浮かべていた。
「……もう、中止にするしかないか」課長が力なく呟いた。
その時だった。ずっと黙っていたひかりが、バンッ!とテーブルを叩いて立ち上がった。
「まだです!まだ終わりじゃありません!私に、いえ、私たちに、考えがあります!」
全員の視線がひかりに集まる。彼女は健太の腕をぐいと掴んだ。
「この祭りを成功させるには、桜木さんの力が必要なんです!」
「な、何を言っているんだ……僕にできることなんて……」健太は狼狽した。この状況で、ポップコーンを撒き散らすことくらいしかできない自分に、一体何ができるというのか。
ひかりは健太の目をまっすぐに見つめ、深く息を吸い込んだ。そして、誰も予想しなかった告白を始めた。
「実は、私にも、秘密があるんです」
彼女はそう言うと、おもむろにポケットからハンカチを取り出し、自分の目を強く押さえた。そして、わざと悲しい映画のラストシーンを思い浮かべるように、眉をひそめた。数秒後、彼女の目から、一粒の涙がこぼれ落ちた。
しかし、それはただの涙ではなかった。
コロリ、とテーブルの上に転がったのは、光を受けてキラキラと輝く、淡いピンク色の小さな粒。それは、誰もが知っている、甘い砂糖菓子だった。
「……金平糖?」誰かが呆然と呟いた。
「はい」ひかりは涙を拭い、少し照れくさそうに笑った。「私は、本当に感動したり、悲しくて心を揺さぶられたりして泣くと、涙が金平糖に変わるんです」
会議室は、静寂に包まれた。健太は、目の前の光景が信じられなかった。自分と同じように、「普通ではない」人間が、こんなにも身近にいたなんて。そして、彼女はそれを恥じるどころか、まるで魔法のように披露してみせた。
「私の涙は、悲しい時だけじゃなくて、嬉しい時、感動した時にも出るんです」ひかりは続けた。「そして、桜木さんのポップコーンは、笑った時に生まれる。それって、最高の組み合わせじゃないですか?人の心を温かくする、最高のエンターテイメントです。私たちの力で、この祭りを、誰も見たことのない、特別な一日にしましょう!」
ひかりの言葉が、雷のように健太の心を貫いた。呪いだと思っていた自分の体質。それを、彼女は祝福だと言った。価値観が、ガラガラと音を立てて崩れていく。自分の世界が、180度ひっくり返るような、強烈な目眩がした。彼は、初めて、自分の身体からポップコーンが飛び出すことを、恐怖ではなく、可能性として捉え始めていた。
第四章 僕らが起こした小さな奇跡
さくら祭り当日。空は、予報通り、厚い灰色の雲に覆われていた。メインステージの歌手の穴は埋まらず、客足もまばら。会場には、湿った空気と諦めのムードが漂っていた。
健太は、ステージの袖で、固く拳を握りしめていた。隣には、ひかりがいる。彼女は少し緊張した面持ちだったが、健太を見ると、にっこりと笑った。その笑顔に、彼は背中を押された気がした。
司会者が、苦渋の表情でメインイベントの中止を告げ、会場からため息が漏れた、その時だった。健太は、ひかりと共にステージの中央へ歩み出た。ざわつく観客を前に、彼はマイクを握った。心臓が、これまで経験したことのないほど激しく脈打っている。
「皆さん、こんばんは。市役所職員の、桜木です」
声が、少し震えた。
「今日は、残念な天気になってしまいました。楽しみにしていた方々、本当に申し訳ありません」
彼は深く頭を下げた。そして、顔を上げると、ゆっくりと自分の話を始めた。
「僕は、ずっと、人前で笑うのが怖い人間でした。なぜなら、笑うと、ちょっと、困ったことが起きるからです」
観客は、キョトンとしている。
「でも、ある同僚が教えてくれました。それは、困ったことじゃなくて、面白いことなんだって。人を笑顔にできる力なんだって」
健太は、隣のひかりを見た。彼女は、目にうっすらと涙を浮かべて、頷いていた。
「だから今日は、僕のすべてをお見せしようと思います。そして、皆さんに、少しでも笑って帰ってもらえたら、と」
彼は息を吸い込み、思い切って言った。
「やる気のないセミの鳴き声。『……ミーン』」
それは、あの日、オフィスで聞いた、ひかりの渾身のネタだった。一瞬の静寂の後、客席から、くすくすと笑い声が漏れた。その温かい反応に、健太自身の口元も、自然と緩んでいく。彼は、自分のコンプレックスを、人生を、ありのままに、ユーモアを交えて語り始めた。その話は、決して上手ではなかったが、嘘のない、正直な言葉だった。
そして、自分の話がおかしくて、観客の笑顔が嬉しくて、隣にいるひかりの存在が愛おしくて。健太は、ついに、腹の底から、心の底から、大声で笑った。
「あはははははは!」
その瞬間、世界は祝福に満ちた。
ポンッ!ポポポポポポーン!
まるで打ち上げ花火のように、健太の身体から大量のポップコーンが夜空へと舞い上がった。塩バターの香ばしい匂いが、雨上がりの湿った空気を満たしていく。
「わーっ!ポップコーンだ!」
一人の子供が叫んだのを皮切りに、子供たちがステージに駆け寄ってくる。大人たちも、最初は驚いていたが、やがてその幻想的な光景に、次々と笑顔になっていった。
その光景を見ていたひかりの瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。それは、キラキラと輝く、色とりどりの金平糖となって、ポップコーンのシャワーに混じって降り注いだ。白と黄金色のポップコーンと、七色に輝く金平糖が、ライトを浴びて乱舞する。それは、誰も見たことのない、奇跡のように美しく、そして、とてつもなく美味しそうな光景だった。
祭りは、伝説になった。
後日、健太とひかりは、公園のベンチに座って、あの日のことを話していた。健太がひかりの新しいジョークに笑うと、ポン、と数粒のポップコーンが彼の手のひらにこぼれ落ちた。
ひかりが、その一粒を指でつまみ、口に入れる。
「うん、今日のポップコーンは、なんだかキャラメルみたいな味がする。甘くて、幸せな味」
そう言って彼女は微笑んだ。
健太は、自分の手のひらに残ったポップコーンを見つめた。それはもう、呪いの欠片ではなかった。それは、彼の感情の、人生の、豊かな味わいそのものだった。彼は、もう笑うことを恐れない。自分の人生が、これからも様々なフレーバーに満ちていくことを知っていたから。隣で笑う彼女と共に、彼は、塩バターだけではない、甘くて、しょっぱくて、時にはスパイシーな、味わい深い未来へと、歩き始めたのだった。