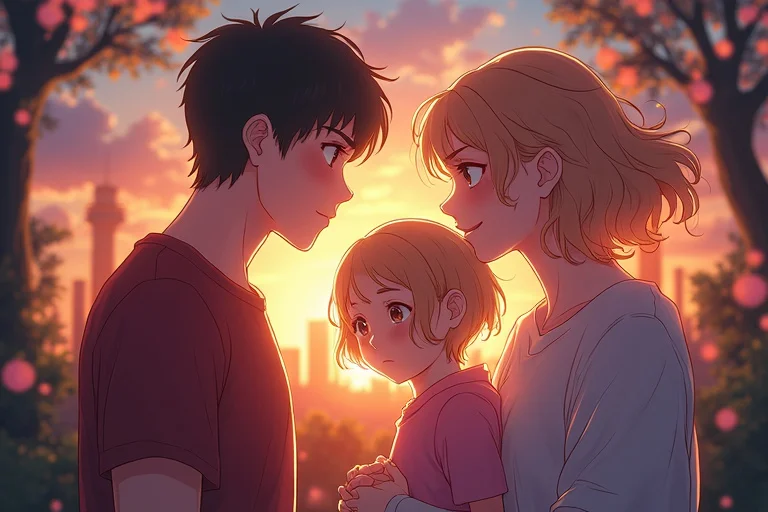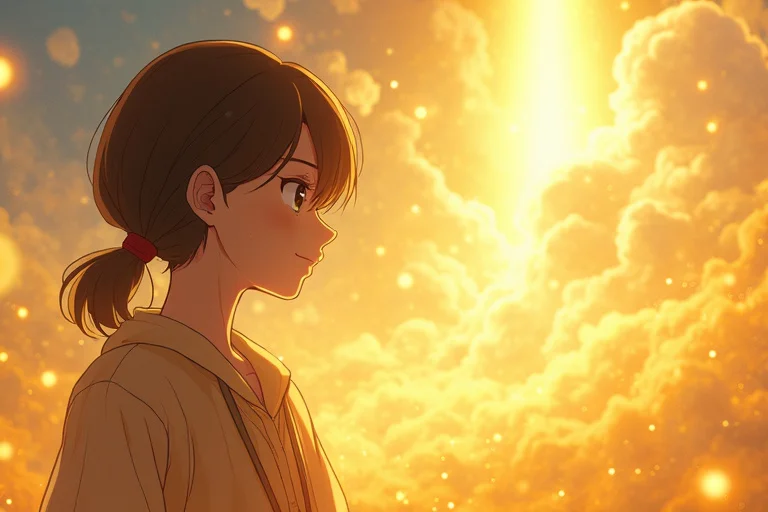第一章 絶対零度のステージ
滑川潤(なめりかわじゅん)の芸名は、スベリー・ジュン。その名は、彼の芸歴十年間のすべてを、あまりにも的確に物語っていた。
今夜も、新宿の地下にある小劇場のステージは、彼によって絶対零度にまで冷却されていた。客席はわずか三十人ほど。蛍光灯の寂しい光が、固まった笑顔のまま微動だにしない観客たちの顔を青白く照らし出している。空気はまるで分厚い氷のようで、呼吸をするたびに肺が凍りつきそうだった。
「はい、どーもー! というわけでね、皆さん、布団が吹っ飛んだら、次は何が吹っ飛ぶと思います? 正解は……不安が吹っ飛ぶ! スベリー・ジュンでしたー!」
渾身の決めポーズと共に、滑川は満面の笑みを客席に向けた。しん、と静まり返った客席から、誰かが小さく咳払いをする音だけがやけに大きく響く。最前列に座っていたカップルの男性が、気まずそうに彼女の肩を抱き寄せた。滑川の視界の端で、舞台袖の主催者が大きなため息をつきながら天を仰ぐのが見えた。
これが、彼の日常だった。ウケない。全く、これっぽっちも。彼の放つ言葉は、笑いの熱量を生むどころか、周囲の温度を根こそぎ奪い去っていく特殊な性質を持っているようだった。真面目に考え抜いたネタ、何度も鏡の前で練習した表情、完璧なタイミングで繰り出したはずのギャグ。そのすべてが、分厚い防音壁に吸収されるかのように、虚空へと消えていく。
「ありがとうございましたー!」
逃げるように舞台を降りると、楽屋はすでに次の出番の芸人たちの賑やかな声で満ちていた。誰も滑川に声をかけない。彼は透明人間のように隅のパイプ椅子に腰掛け、ペットボトルの水を喉に流し込んだ。ぬるい水が、燃えるように熱い喉を虚しく通り過ぎていく。
芸人を志したあの日、彼は信じていた。笑いは、人を救う力があると。たった一言で、絶望している人を笑顔にできる。世界をほんの少しだけ、明るくできる。その魔法使いになりたかった。しかし、十年経った今、彼が作り出せるのは、魔法ではなく、ただ気まずいだけの呪いだった。
深夜、アパートの固いベッドの上で、滑川はスマートフォンの画面をぼんやりと眺めていた。習慣になっているエゴサーチ。今日のライブの感想を探すが、案の定、彼の名前はどこにも見当たらない。いや、一つだけあった。
『今日のライブ、スベリー・ジュンって人、マジでヤバかった。逆に一周回ってなんか……元気出たわ。失恋の悩みとか、どうでもよくなった』
匿名のアカウントからの短い投稿。滑川の眉間に深い皺が刻まれる。
(皮肉か……。俺の芸がヒドすぎて、自分の悩みがちっぽけに思えたってことか)
自嘲の笑みが漏れる。胸にちくりと刺さった小さな棘を無視するように、彼はスマートフォンの電源を落とし、冷たい闇に目を閉じた。彼の芸が、彼の知らないところで小さな奇跡の芽を出し始めていることなど、知る由もなかった。
第二章 知らぬ仏の功徳
芸人を辞めようか。その考えが、朝の歯磨き粉の味のように、滑川の日常にこびりついて離れなくなっていた。アルバイト先のコンビニでは、年下の店長に叱られ、アパートに帰れば、滞納した家賃の督促状が郵便受けを赤く染めている。何より、彼の心を蝕んでいたのは、笑いを生み出せない自分への無力感だった。
「なんで、俺だけ……」
ある晴れた午後、滑川は客のいない公園のベンチで、新しいネタを考えていた。ノートには、誰の笑いも誘わないであろう言葉の残骸が散らばっている。
「タコがタコ殴り……いや、ダメだ。イカが怒っても、まあイカる……これも既出か」
ぶつぶつと呟きながら頭を抱えていると、ふと、視線を感じた。見上げると、少し離れたベンチに座った頑固そうなおじいさんが、怪訝な顔でこちらを見ている。気まずさを感じながらも、滑川は練習を続けなければと自分を奮い立たせた。観客がいると思えば、本番さながらの練習ができる。
「えー、こほん。では、一発ギャグ、いきます! あのー、そこの公衆電話さん、ちょっといいですか?……もしもし、俺だけど……ああ、俺だよ、オレオレ詐欺じゃなくて、俺俺『シャキーン!』……どうも、ありがとうございました」
滑川がキレのない効果音と共にポーズを決めると、公園の平和な空気が一瞬で凍てついた。鳩が飛び立つのをやめ、風に揺れていた木の葉が動きを止め、砂場で遊んでいた子供たちの声さえもが、ピタリと止んだかのように思えた。
おじいさんは、口を半開きにしたまま固まっていた。その顔は、理解不能なものを見た時の、純粋な困惑に満ちている。やがて、その表情がゆっくりと変化した。眉間の皺が消え、険しかった目元が、ふっと和らいだ。おじいさんは、まるで長年の呪いが解けたかのように深いため息をつくと、おもむろに携帯電話を取り出した。
「……もしもし、武史か?……ああ、父さんだ。いや、別に用ってわけじゃねえんだが……。悪かったな、この前のこと。ワシが悪かった。そうだよ、あんなつまらんことで意地を張って……。ああ、今度、孫の顔でも見せに来い」
電話口で素直に謝るおじいさんの姿に、滑川は目を丸くした。そして、すぐに自己嫌悪に陥った。
(俺のギャグが、あまりにくだらなくて、人生の悩みがどうでもよくなったんだ……。おじいさん、俺のせいで長年の確執を水に流す気になっちまったのか……)
人の心を動かした。しかし、それは滑川が望んだ形ではなかった。彼は、自分の芸が持つ「人を我に返らせる」という恐ろしい力に、罪悪感すら覚えていた。
その奇妙な現象は、その後も続いた。彼のライブを見た就活生が、「面接で落ちたことなんて、あのスベり具合に比べたら些細なこと」と吹っ切れて、見事内定を勝ち取ったり。夫婦喧嘩の絶えなかったカップルが、「あの気まずい空間を共有したことで、逆に絆が深まった」と仲直りしたり。
滑川の知らないところで、彼の「絶対零度のステージ」は、悩める人々にとっての荒療治のパワースポットとなりつつあった。しかし、当の本人は、自分の芸が人々を不快にさせているだけだと信じ込み、ますます心を閉ざしていくのだった。
第三章 奇跡の翻訳者
滑川潤の芸人人生に、終わりの足音が聞こえ始めていた。彼は、次のライブを最後に、マイクを置くことを決意していた。十年間の集大成。どうせなら、一番自信のあるネタで、芸人人生で最も盛大にスベり散らかして終わろう。彼の心は、奇妙な清々しささえ感じていた。
その運命の夜、客席の隅に、場違いなほど高級なスーツを着こなした一人の男が座っていた。テレビ局の敏腕プロデューサー、冷泉(れいぜい)だった。彼は、巨額の予算を投じたゴールデンタイムの新番組企画が、メインスポンサーの鶴の一声で白紙になるという、キャリア最大の失敗を経験したばかりだった。自暴自棄になり、部下に誘われるがまま、生まれて初めて地下アイドルのライブに足を運び、その前座として出てきたのが、スベリー・ジュンだった。
「では、最後のネタ、聞いてください! 題して、『AIスピーカーの悲劇』!」
滑川が舞台に上がった瞬間から、冷泉は眉をひそめた。華がない。オーラがない。そして、ネタが始まった途端、その予感は確信に変わった。
「ねえ、アレクサ。僕のこと、好き?」「ワカリマセン。デモ、アナタノコトハ、Googleデ検索デキマス」
一言、一言が、鋭利な氷の刃となって客席の熱を削ぎ落としていく。観客は笑うどころか、息をすることさえ忘れているようだった。
冷泉は最初、怒りを感じた。なんだこれは。プロの仕事じゃない。金を取れるレベルではない。しかし、滑川の想像を絶するスベりっぷりは、彼の怒りさえも麻痺させていった。
怒りが消えると、次にやってきたのは絶望だった。自分のキャリアも、この芸人のネタも、すべてがくだらない。無意味だ。だが、その絶望の底で、何かが変わった。滑川が渾身の決め台詞「このポンコツAIめ!……いや、愛がないからAIなのかーっ!」を放ち、ステージが完全な静寂に包まれた瞬間、冷泉の頭の中で、何かが弾けた。
(……そうか。無だ。これは、完全な『無』だ)
雑念がない。感情がない。思考が停止するほどの、完璧な虚無。この感覚はなんだ? 会社の会議室で、スポンサーに頭を下げている時には決して得られない、究極のデトックス。そうだ、この「無」の状態こそが、今の自分には必要だったんだ。プロジェクトの失敗なんて、この絶対的なスベりの前に立てば、宇宙の塵芥にも等しい。
冷泉の脳内で、停止していた回路が猛スピードで再接続されていく。失敗した企画。いや、あれは失敗じゃない。視点を変えればいい。ターゲットを変えればいい。そうだ、あの企画は深夜枠なら、コアなファンを掴める!
ネタが終わり、逃げるように舞台袖に消えようとする滑川の腕を、興奮した様子の冷泉が掴んだ。
「君! 君は天才だ!」
「は……え?」
滑川は、目の前の男が何を言っているのか理解できなかった。
「君の芸は、笑いじゃない! いや、笑いを超越している! あれは『無』だ! 人々を日常の喧騒から解放し、魂を浄化する究極のメディテーション(瞑想)だ!」
「め、でぃてーしょん……?」
「そうだ! 君の『スベり』は、人の悩みを翻訳し、無に帰す力がある! 私が君をプロデュースする! 君は、お笑い界の救世主になるんだ!」
滑川は、ただ呆然と立ち尽くしていた。十年間の芸人人生で、初めて言われた「天才」という言葉。しかし、その理由は、彼が最も忌み嫌い、克服しようと足掻いてきた「スベること」だった。自分の価値観が、ガラガラと音を立てて崩れていくのを感じた。これは、夢なのだろうか。それとも、壮大ないたずらか。彼の芸人人生は、最も予期せぬ形で、新たな扉の前に立たされていた。
第四章 沈黙のエール
滑川潤は、スベリー・ジュン改め、『サイレント・ジュン』として再デビューを果たした。冷泉が仕掛けたプロモーションは、常軌を逸していた。
『悩める現代人へ。究極のデトックス体験を。』
『笑いゼロ、癒し無限大。世界一気まずいパワースポット、ここに誕生。』
滑川の単独ライブのチケットは、最初は物珍しさから、やがて口コミでその「効果」が広まり、即日完売するほどの人気を博した。客層は様々だった。仕事に疲れたサラリーマン、人間関係に悩む学生、人生の岐路に立つ主婦。彼らは皆、笑うためではなく、滑川が生み出す究極の静寂と気まずさに身を浸し、自分自身と向き合うために劇場へ足を運んだ。
滑川は、相変わらず全力でスベり続けた。
「幽霊の『ゆう』って字は、優しいって書くんだぜ!……だから、優しくしてくれよぉ~!」
会場は、水を打ったように静まり返る。しかし、以前とは何かが違った。その静寂の中には、軽蔑や同情の色はない。むしろ、どこか神聖で、心地よい緊張感が漂っている。観客たちは、彼のスベり芸を一種のマントラのように受け止め、その気まずさの中で心を無にし、カタルシスを得ていた。
最初は戸惑いばかりだった滑川も、次第に自分の新たな役割を受け入れ始めていた。人を笑わせることはできなかった。長年の夢は、最も皮肉な形で破れた。だが、自分の存在が、確かに誰かの心を軽くしている。舞台袖から客席を覗くと、涙を流している人、何かから解放されたように穏やかな表情を浮かべている人、ただ虚空を見つめて瞑想にふけっている人がいる。彼らは、滑川の芸によって救われていた。
ある日の公演後、楽屋に一人の女性が訪ねてきた。それは、かつてSNSで「元気出たわ」と呟いていた、最初の「奇跡」の目撃者だった。
「あの、ずっと言いたかったんです。あの時、本当にどん底で……。でも、あなたの舞台を見たら、自分の悩みが本当にどうでもよくなって。あの気まずさが、逆に私の背中を押してくれたんです。ありがとうございました」
深々と頭を下げる女性に、滑川は初めて、自分のやってきたことが無駄ではなかったのだと、心から思うことができた。
そして今夜、彼は満員の由緒ある劇場のステージに立っている。客席には、冷泉プロデューサー、公園で出会ったおじいさんとその家族、そして、かつて彼を「つまらない」と見下していた芸人仲間たちの姿もあった。
滑川は深く息を吸い、マイクに向かって語りかけた。
「十年かかりました。俺は、ずっと人を笑わせたかった。でも、どうやら俺には、その才能はなかったみたいです」
客席が、固唾を飲んで彼を見守る。
「でも、今は分かります。俺の芸は、笑わせるんじゃなくて……ただ、皆さんの隣に座って、一緒に気まずくなってあげることなのかもしれないって」
彼は、ニッと笑うと、最後のギャグを放った。
「皆さん、人生いろいろありますけど……最後はみんな、骨になる!……コツコツ頑張りましょう! サイレント・ジュンでした!」
会場は、完璧な沈黙に包まれた。それは、彼の芸人人生で最も美しく、最も温かい沈黙だった。
スポットライトの中、滑川は客席を見渡した。誰も笑っていない。しかし、そこにいる誰もが、ほんの少しだけ軽くなった心で、彼に優しい眼差しを向けていた。それは、爆笑よりも雄弁な、沈黙のエールだった。滑川は、静かに微笑んだ。その満ち足りた表情は、もはやスベリー・ジュンではなく、唯一無二の表現者、『サイレント・ジュン』そのものだった。