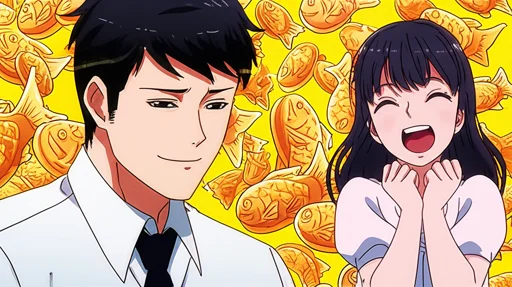第一章 悪夢は現実の設計図
根岸誠(ねぎしまこと)、三十二歳、区役所地域振興課勤務。彼の人生哲学は「石橋を叩いて、安全を確認してから渡らない」である。そんな彼が、火曜日の午前三時四十四分、ベッドから跳ね起きた。シーツは冷や汗でじっとりと濡れ、心臓は胸郭の中で暴れ太鼓のように鳴り響いていた。また、見てしまったのだ。未来の自分の、最高に恥ずかしい失敗の夢を。
それは単なる夢ではなかった。彼の見る夢は、恐ろしいほどの精度で現実を予告する、一種の呪いだった。しかも、予告されるのはキャリアを左右する成功でも、運命の出会いでもない。必ず、身の毛もよだつような「大失敗」の光景だけなのだ。
今回の予知夢は、特に鮮明で残酷だった。舞台は明日の午後、新設される『ふれあい猫カフェ型図書館』の企画プレゼンテーション。町の活性化を賭けた一大プロジェクトだ。夢の中の根岸は、緊張のあまり、スラックスの社会の窓を全開にしたまま熱弁をふるっていた。聴衆の憐れむような視線に気づいた瞬間、彼はパニックに陥り、手元のコーヒーを豪快にこぼす。放物線を描いた黒い液体は、審査委員長である田中部長の、磨き上げられた禿頭に見事着弾。静まり返る会議室。夢はそこで終わっていた。
「……ありえない」
根岸は震える手で顔を覆った。チャックの閉め忘れ。コーヒーによる部長へのヘッドショット。二重の悲劇。これが現実になるなど、断じてあってはならない。彼はベッドから転がり出ると、机のライトをつけた。ノートを開き、震える文字で『対・プレゼン大失敗 回避マニュアル Ver. 3.2』と書き込む。
彼の人生は、この予知夢との戦いの歴史だった。高校時代、告白の返事を聞く瞬間に派手にズボンが破れる夢を見た彼は、当日、制服の下にジャージを履きこんで防御。結果、あまりの暑さに熱中症で倒れ、告白はうやむやになった。大学時代、卒業論文の発表でマイクがハウリングを起こし、驚いて教壇から転げ落ちる夢を見た彼は、マイクを使わず地声で発表することを敢行。結果、声が小さすぎると評価を落とした。
回避しようとすればするほど、事態は奇妙な方向へと転がっていく。だが、根岸は諦めなかった。今回こそ、完璧な回避策で、運命という名の脚本家を出し抜いてやる。
まず、チャック問題。彼は裁縫箱から最も屈強な安全ピンを取り出し、スラックスのジッパーの金具と布地をがっちりと固定した。「これで物理的に開くことは不可能」。
次に、コーヒー問題。そもそも、プレゼン会場に液体を持ち込まなければいい。彼は頷き、マニュアルに『水分補給はプレゼン開始3時間前に完了させること』と書き加えた。
万全の策を練り上げ、根岸は夜明けの空を見上げた。灰色の雲間から覗く光が、まるで彼の前途をあざ笑っているように見えた。だが、今の彼に恐怖はなかった。あるのは、運命に抗う者だけが持つ、悲壮で、どこか滑稽な決意だけだった。
第二章 回避策という名の燃料投下
プレゼンテーション当日。根岸は戦場に向かう兵士の面持ちで区役所に出勤した。昨夜施した安全ピンは、股間に確かな重みと安心感を与えている。彼は水分の摂取を断ち、口の中はカラカラだったが、すべては悲劇を回避するためだ。
同僚の佐々木さんが、ニコニコしながら声をかけてきた。
「根岸さん、今日のプレゼン、気合入ってるね! 顔、ちょっと引きつってるけど」
「万全の態勢で臨む。それだけだ」
低く、重々しく答える根岸に、佐々木さんは「そ、そっか」と少し引いている。彼女のデスクには、例の『ふれあい猫カフェ型図書館』のマスコットキャラクター、『ニャンしょ先生』のぬいぐるみが置かれていた。
プレゼン開始は午後二時。正午を回った頃、根岸の体に最初の異変が起きた。安全ピンだ。歩くたびに、太ももの内側にチクチクとした微かな痛みが走る。気にしないように努めたが、その痛みは徐々に存在感を増していった。まるで、運命が「そんな小細工は無駄だ」と囁きながら、小さな針で彼をつついているかのようだ。
午後一時半。プレゼン資料の最終確認をしていた根岸に、田中部長が声をかけた。
「根岸くん、緊張しているかね。まあ、これでも飲んで落ち着きたまえ」
そう言って差し出されたのは、湯気の立つ紙コップ。中身は、言うまでもなくコーヒーだった。
「ぶ、部長! 恐れながら、私は今、水分を断っております!」
「何を言っとるんだ。喉が渇いては良い声も出んだろう。さあ、遠慮せずに」
断れない。部長の好意を無下にはできない。根岸は震える手でコーヒーを受け取った。悪夢のキーアイテムが、今、彼の掌中にある。心臓が嫌な音を立てる。彼は、このコーヒーを誰からも最も遠い、自分のデスクの隅にそっと置いた。まるで時限爆弾を処理するかのように。
午後一時五十五分。会議室へ移動する時間だ。根岸は深く息を吸い、立ち上がった。その瞬間、事件は起きた。
「ビリッ!」
布が裂ける、乾いた音。
視線を下に落とすと、スラックスの股間部分が、安全ピンを基点にして縦に大きく裂けていたのだ。歩くたびにピンが生地に負担をかけ、限界に達したらしい。裂け目からは、彼の勝負下着である、勇ましいライオン柄のトランクスが「ガオー」と顔を覗かせていた。
「ね、根岸さん……ライオン、飼ってたんだ……」
佐々木さんの呆然とした声が聞こえる。パニック。思考が停止する。チャック全開どころではない。これはもう、公然わいせつに近い。
「だ、大丈夫だ! 想定内のアクシデントだ!」
根岸は叫び、ロッカーに駆け込んだ。彼には最終防御策があった。予備のスラックスだ。彼はロッカーからスラックスを取り出し、トイレに駆け込もうとした。
その時だった。彼の背中に、何かがぶつかった。振り返ると、掃除のおばさんがモップがけをしており、床はワックスで濡れていた。
「うわっ!」
根岸は足を滑らせ、盛大に宙を舞った。手にした予備のスラックスが空中で放物線を描き、運悪く通りかかった佐々木さんの頭にすっぽりとかぶさる。視界を奪われた佐々木さんは「きゃあ!」と叫びながらよろめき、根岸のデスクに激突した。
デスクの隅に置かれていた、あの時限爆弾――部長のコーヒーが、その衝撃で高く跳ね上がった。スローモーションのように、紙コップは回転しながら飛び、会議室へ向かおうとしていた田中部長の、あの磨き上げられた頭部へと吸い込まれていった。
バシャッ!
夢と寸分違わぬ、しかし、遥かにダイナミックな形で。
静寂。廊下の誰もが動きを止めていた。コーヒーの滴が、部長の額から鼻筋を伝って落ちる。根岸は、股間を裂かれたスラックスのまま、ワックスの海に尻もちをついていた。彼の脳裏に、一つの確信が稲妻のように閃いた。
これは、回避できない。むしろ、俺が回避しようとすることで、物語はより面白く、より悲劇的に脚色されてしまうのだ、と。
第三章 壮大なるピタゴラスイッチ
時間は、まるで固まったゼリーのように動かなかった。コーヒーの温かい雫が床に落ちる音だけが、やけにクリアに響く。田中部長は、頭からコーヒーをかぶったまま、彫像のように動かない。その表情は、怒りとも、悲しみとも、あるいは悟りともつかない、複雑な色を浮かべていた。
「……根岸くん」
地を這うような低い声。根岸は、ライオン柄のトランクスが覗く股間を押さえながら、必死に言葉を絞り出した。
「ち、違います! これは、その、ピタゴラ的な、不可抗力で……!」
「ピタゴラ的、だと?」
部長の眉がぴくりと動いた。その時、佐々木さんが頭からスラックスを外し、混乱した様子で叫んだ。
「部長! 根岸さんのライオンが!」
「何だと!?」
部長の視線が、根岸の股間に突き刺さる。万事休す。根岸は目を固く閉じた。クビだ。懲戒免職だ。明日から俺は、この街で「ライオン男」あるいは「コーヒー投擲手」として生きていくしかない。
プレゼンの開始時刻は、もう過ぎていた。会議室からは、ざわめきが漏れ聞こえてくる。審査員たちは、主役の登場を今か今かと待っていることだろう。
すると、予想外のことが起きた。
田中部長は、ふう、と一つ大きなため息をつくと、ハンカチで顔を拭い、こう言ったのだ。
「…面白い。根岸くん、実に面白い」
「へ?」
根岸は間の抜けた声を上げた。
「君のその、常軌を逸した情熱はよく分かった。その裂けたズボンと、私の頭にかかったコーヒーが何よりの証拠だ。君は、このプロジェクトにそれだけのものを賭けている、ということだな」
「え、あ、はい! 左様でございます!」
何を言っているのか自分でも分からなかったが、とにかく肯定した。部長は、濡れた頭のままニヤリと笑うと、根岸の肩を叩いた。
「いいだろう。その格好のまま、プレゼンをやってみせろ。そのライオンの勇気と、ピタゴラ的発想力で、審査員たちを唸らせてみろ!」
もはや、ヤケクソだった。根岸は裂けたスラックスのまま、胸を張って会議室に入った。会場は、彼の登場と共に水を打ったように静まり返り、次の瞬間、爆笑の渦に包まれた。だが、根岸はもう何も恐れなかった。
彼は、予知夢のことを、そしてそれを回避しようとして起きた今日の惨劇を、赤裸々に語り始めた。それはもう、プレゼンテーションではなかった。一人の男の、運命との壮絶にして滑稽な戦いを描いた、魂の独演会だった。
「私は失敗を恐れていました! チャックが開くことを恐れ、安全ピンで留めた結果、ズボンが裂けました! コーヒーをこぼすことを恐れ、水分を断った結果、部長の慈悲のコーヒーが、部長自身の頭に降りかかるという悲劇を生みました!」
彼の熱弁は、いつしか審査員たちの心を掴んでいた。彼らは腹を抱えて笑いながらも、その瞳にはどこか尊敬の念すら浮かんでいた。この男は、本気だ。本気で不器用で、本気で滑稽で、そして本気でこの町を愛している。
プレゼンが終わった時、会場はスタンディングオベーションに包まれた。田中部長は、コーヒーのシミがついた顔で、満足げに頷いていた。
その日の夕方、根岸は驚くべき事実を知ることになる。市の広報課が、廊下の防犯カメラに映っていた一連のドタバタ劇を「職員の情熱が生んだ奇跡のPR動画」として編集し、公式SNSにアップしたのだ。動画は瞬く間に拡散され、『#ピタゴラ区役所』『#ライオン男の情熱プレゼン』というハッシュタグと共に、ネットニュースのトップを飾った。
根岸は呆然としながら、スマホの画面に流れる賞賛のコメントを眺めていた。
「この人、最高すぎるだろwww」
「こんなに笑ったの久しぶり」
「猫カフェ図書館、絶対行く!」
彼は、気づいてしまった。彼の能力は、単なる「失敗の予知」ではなかったのかもしれない。
これは、彼が「失敗を恐れる心」が生み出す、壮大な喜劇の脚本なのではないか。彼が必死になればなるほど、運命という名の脚本家は、より面白く、より感動的な物語を紡ぎ出していく。彼の心配性こそが、最高のエンターテイメントを創造する源泉だったのだ。
第四章 失敗王の戴冠式
数日後、根岸誠はすっかり街の有名人になっていた。区役所には彼を一目見ようと市民が訪れ、子供たちからは「ライオンのおじさん!」と声をかけられた。『ふれあい猫カフェ型図書館』プロジェクトは、彼のプレゼン(というより独演会)のおかげで満場一致で可決され、前代未聞のスピードで予算が承認された。
彼はもはや、失敗を恐れる小心者の職員ではなかった。人々は彼を「失敗王」と呼び、その滑稽なまでの誠実さを愛した。田中部長は、根岸を呼び出すと、新しい役職を命じた。
「根岸くん、君を本日付で『地域活性化特命担当・初代ミスチーフオフィサー』に任命する」
「みすちーふ…?」
「Chief Mischief Officer。最高イタズラ責任者、とでも訳すかな。君の巻き起こす騒動は、結果的に町を明るくする。これからも、その調子で盛大に失敗して、町を盛り上げてくれたまえ」
それは、ほとんど公認でドタバタを推奨するような、前代未聞の辞令だった。
その夜、根岸は久しぶりにぐっすりと眠った。そして、明け方、またあの夢を見た。
今度の舞台は、猫カフェ図書館のオープニングセレモニー。テープカットの瞬間、彼が持つ金のハサミが手から滑り落ち、来賓の市長のカツラに突き刺さる。驚いた市長がのけぞり、背後の巨大な『ニャンしょ先生』のバルーンにぶつかる。バルーンは破裂し、中から大量のキャットフードが吹雪のように舞い散り、集まっていた猫たちが狂喜乱舞の大騒ぎを始める――。
かつてならば、絶望の悲鳴と共に飛び起きていたはずの光景。
しかし、根岸はベッドの中で、ゆっくりと目を開けた。窓から差し込む朝日は、とても穏やかだった。彼は天井を見上げながら、想像した。キャットフードの舞う中、カツラにハサミを刺した市長と、狂乱する猫たち、そして呆然と立ち尽くす自分。
その光景は、恐ろしいというより、なんだか少し、面白そうに思えた。
「さて、と」
根岸誠は、ベッドからゆっくりと起き上がった。口元には、自分でも気づかないほどの、微かな笑みが浮かんでいた。
「今度はどんな回避策で、運命を笑わせてやろうかな」
彼の新しい一日が、また始まろうとしていた。それはきっと、最高に面倒で、最高に恥ずかしくて、そして最高に素晴らしい一日に、なるのだろう。