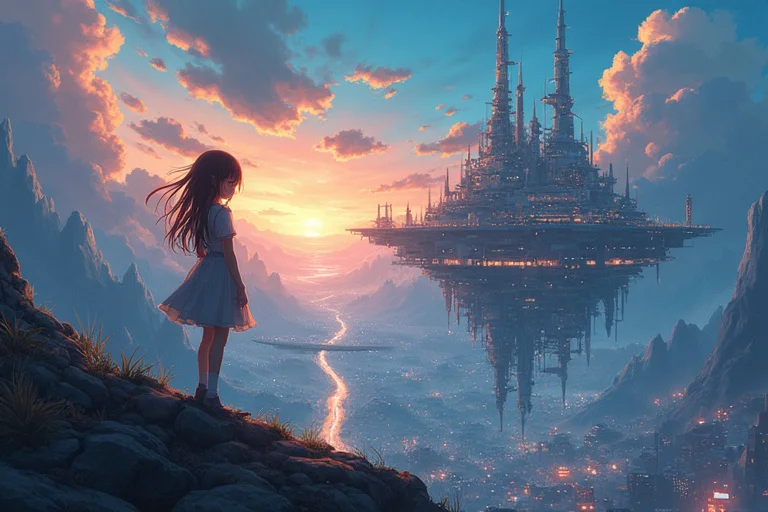第一章 饒舌な前兆
味沢幸(あじさわ こう)は、幸福の沸点が人よりずっと低い男だった。それは呪いであり、一種の才能でもあった。彼の舌は、喜びが一定の閾値を超えると、まるで独立した生命体のように自我を持ち、饒舌なミニチュアの評論家へと変貌するのだ。その評論は恐ろしく辛辣で、それでいて詩的、そして妙に的を射ているため、始末に負えなかった。
だから幸は、本当に美味しいものを避けて生きてきた。ファストフードの画一的な塩味と、コンビニエンスストアの無難な甘みに安らぎを見出す日々。彼の周囲を飛び交う、金色の光の粒のような『喜びの妖精』たちが、もどかしげに彼の肩を叩いても、幸は気づかぬふりをした。
「幸、またそんなものを食べて。たまにはちゃんとしたものを食べなきゃダメよ」
カフェのカウンター席で、友人の小松菜凛(こまつな りん)が眉をひそめる。彼女の周りでは、心配の色をした水色の妖精たちがふわりと舞っていた。彼女が差し出したのは、試作品だという小さなモンブラン。マロンクリームの艶、頂に鎮座する渋皮煮の威厳、漂うラム酒の芳醇な香り。それは、幸にとって危険な誘惑だった。
「いや、俺はこれで……」
「いいから!」
凛に無理やりフォークを握らされ、恐る恐る一口。舌の上でクリームが溶けた瞬間、幸の全身に電流が走った。栗の濃厚な甘み、それを追いかけるラム酒の香り、サクサクとしたメレンゲの食感。脳が焼き切れそうなほどの多幸感。金色の『喜びの妖精』たちが一斉に幸の口の中へ飛び込んでくる。まずい、舌が、言うことを聞かなくなりそうだ。
「んんっ……!」
幸は奥歯を食いしばり、必死に舌の反乱を抑え込む。額に脂汗を滲ませ、全身を小刻みに震わせる彼を見て、凛は首を傾げた。
「そんなに不味かった?」
「いや、う、美味すぎる……。これは、一種の暴力だ……」
やっとの思いでそれだけを絞り出すと、凛は呆れたように笑った。そして、その笑顔がふと翳る。
「ねえ、幸。お願いがあるんだけど……。私が関わっている料理コンテストで、ちょっと変なことが起きてるの」
第二章 無味のシンフォニー
『ガストロノミア・グランプリ』。それは、この街で最も権威ある料理の祭典。その会場に足を踏み入れた幸は、渦巻く感情の奔流に眩暈を覚えた。期待に胸を膨らませる観客たちの周りではオレンジ色の『興奮』の妖精が火花のように弾け、厨房から漏れ聞こえる怒号には、血のように赤い『怒り』の妖精が付き従っている。
凛に頼まれ、幸は一般客を装って事件の調査に来ていた。事件――それは、最終選考に残ったシェフたちの料理が、なぜかことごとく『無味無臭の完璧な球体』に姿を変えてしまうという、奇怪な現象だった。
やがて、ひとりのシェフが作り上げた料理が、審査員席に運ばれる。銀のクロッシュが開けられると、そこには噂通りの、乳白色をしたピンポン玉ほどの滑らかな球体がひとつ、ぽつんと置かれていた。会場がざわめく。シェフは顔面蒼白だ。
しかし、審査員長は動じない。厳かに球体を口に運び、ゆっくりと咀嚼する。誰もが固唾を飲んで見守る中、彼の目がカッと見開かれた。
「おお……おおぉ!これは!味の地平線の彼方!宇宙の創生と終焉を同時に味わうかのごとき、深淵なる体験だ!」
審査員長はそう叫ぶと、恍惚の表情で椅子から崩れ落ち、白目を剥いて泡を吹いた。他の審査員たちも次々と球体を口にし、同じように絶賛の言葉を叫んでは気絶していく。常軌を逸した光景だった。
幸はその時、見ていた。会場の薄暗い片隅で、まるで煤に汚れたような、鈍い灰色をした数匹の妖精たちが身を寄せ合っているのを。彼らは、審査員たちが気絶するたびに、満足げに小さく頷き合っていた。
第三章 記憶置き忘れマシュマロ
調査は完全に行き詰まった。灰色の妖精たちが怪しいのは明らかだったが、彼らが何者で、何が目的なのか、皆目見当もつかない。幸がカフェで頭を抱えていると、凛がそっと小さな包みをテーブルに置いた。
「これ、コンテストのスポンサーが配ってた、『記憶置き忘れマシュマロ』っていうんだって」
包みの中には、雲のように白い、ふわふわとしたマシュマロが一つ入っていた。甘いバニラの香りが鼻をくすぐる。
「食べると、その日一日のあらゆる不運を吸収してくれるらしいわ。でも、その代わり……自分にとって一番大切なものを、一時的に忘れちゃうんだって」
不運を吸収する、か。幸にとって最大の不運は、この饒舌な舌の呪いだ。もし、決勝戦で何らかの料理を口にしなければならない事態になった時、このマシュマロがあれば、変身という最悪の事態は避けられるかもしれない。
「でも、大切なものを忘れるなんて……」
凛は不安げに呟く。幸はマシュマロを摘み上げ、その不思議な軽さを指先で感じた。一番大切なもの。それはきっと、美味しいものを「美味しい」と素直に感じられる、ごく当たり前の喜びだろう。それを失うのは怖い。だが、謎を解くためには、リスクを冒さなければならない時もある。幸はマシュマロを丁重にハンカチで包み、ジャケットの内ポケットにしまい込んだ。
第四章 灰色のレクイエム
コンテスト決勝戦の日がやってきた。会場は異様な熱気に包まれている。最後のシェフが渾身の力作を披露するが、やはり運ばれてきたのは、あの『無味無臭の完璧な球体』だった。シェフは舞台袖で泣き崩れ、観客席からはため息が漏れる。
審査委員長が、もはや見慣れた所作で球体を口に運ぶ。誰もが、彼がまた絶叫し、気絶するのだろうと予想していた。しかし、違った。
委員長は球体を口の中で転がすと、何も言わず、ただ静かに涙を流し始めた。その頬を伝う涙は、絶望とも歓喜ともつかない、複雑な感情を湛えているように見えた。
「……これは、虚無だ。完全なる無。しかし、なんて美しい虚無なのだろう。私の料理人人生は、この一皿に出会うためにあったのかもしれない」
その瞬間、幸は見た。あの灰色の妖精たちが一斉に審査委員長の元へ飛んでいき、彼の心臓に直接、霧のような青い『悲しみ』の感情を大量に注ぎ込んでいるのを。そうだ、彼らの目的は、ただ絶賛させることではなかった。料理の『味』そのものを、別の強烈な『感情』で上書きし、誤認させることだったのだ。だから審査員たちは、味ではなく感情の奔流に打ちのめされて気絶したのだ。
第五章 絶望のレシピ
幸は舞台裏へ駆け込み、柱の陰に集まっていた灰色の妖精たち――ミザリアたちを追い詰めた。観念したように、彼らはぽつりぽつりと自分たちの身の上を語り始めた。
彼らは、本来なら世界に『至高の喜び』をもたらすはずの、最高位の感情の妖精として生まれるはずだった。しかし、誕生の瞬間に運命のいたずらが起きた。生まれたばかりの彼らの魂は、すぐ隣で生まれるはずだった『絶望』の妖精たちと、そっくり入れ替わってしまったのだ。
その結果、彼らは世界で最も不運な味覚を持つ存在となった。彼らが心から「美味しい」と感じるものは、他の誰かにとっては耐え難いほどの『不味さ』、あるいは感覚が拒絶するほどの『無』としてしか認識されない。
コンテストでの犯行は、復讐でも悪戯でもなかった。ただ、自分たちが最高に美味しいと信じる料理を、誰かに認めてほしかった。自分たちの存在意義を、この世界に証明したかった。それだけの、あまりにも哀しい願いだったのだ。
その告白に、幸は胸を締め付けられるような痛みを覚えた。彼らの孤独は、本当に美味しいものを素直に楽しめない自分の孤独と、どこか似ている気がした。
第六章 舌上のアリア
幸は、覚悟を決めた。ポケットから『記憶置き忘れマシュマロ』を取り出す。彼にとって一番大切なもの――『普通の食事を楽しむ喜び』。それを失う覚悟。
彼は壇上に上がると、審査員長から残りの『球体』を受け取った。そして、マシュマロを口に放り込む。綿菓子のように儚く溶け、優しいバニラの香りが広がった直後、頭の中から何かがすっぽりと抜け落ちる感覚がした。
そして、彼は『球体』を口に入れた。
瞬間、世界から一切の音が消えた。味も、香りも、食感もない。ただ、絶対的な『無』が舌を支配する。それは、魂が根こそぎ削り取られるような、冒涜的な虚無感だった。常人ならば、その場で発狂していただろう。
だが、幸の中で何かが弾けた。絶望的な不味さが、マシュマロによって吸収され、純粋な『体験』としての情報だけが脳を駆け巡る。そして、今まで抑え込んできた『喜び』の感情が、堰を切ったように全身を駆け巡った。
「――来たッ!」
幸の舌が、彼の意思とは無関係に震え始める。そして、朗々と、まるでオペラのアリアのように歌い上げた。
「諸君!我々は歴史の目撃者となった!これは味ではない、哲学だ!甘味、塩味、酸味、苦味、旨味、その全てを超越し、森羅万象が回帰する原初の『ゼロ』!我々はついに味の向こう側、究極の無味、すなわち『味の涅槃』に到達したのだ!この虚無こそが、至高の美味であるッ!」
その批評は、狂気じみていながら、神々しいほどの説得力に満ちていた。会場は水を打ったように静まりかえり、やがて、割れんばかりの拍手が巻き起こった。
第七章 ゼロの美食家
幸の舌が紡いだ言葉は、新たな美食の潮流を生んだ。『ゼロ・キュイジーヌ』と名付けられたその料理は、究極の食体験として瞬く間に世界中の美食家たちを熱狂させた。そして、ミザリアたちは皮肉にも、新時代の寵児として祭り上げられた。彼らは初めて、他者からその存在を肯定されるという、温かな喜びを知った。彼らのくすんだ灰色の体は、ほんの少しだけ、白く輝きを取り戻したように見えた。
だが、味沢幸は、代償を支払っていた。
『記憶置き忘れマシュマロ』の効果は一時的なはずだった。しかし、あまりに強烈な『ゼロ』の体験は、彼の味覚を永遠に変えてしまった。もはや、彼にとってどんなご馳走も砂を噛むように味気ない。凛が作るあの絶品のモンブランでさえ、ただの甘い塊にしか感じられなかった。
彼の舌が、彼の魂が求めるのは、ただひとつ。あの、魂を震わせた『究極のゼロ』だけ。
「行ってくるよ、凛」
幸は小さな鞄ひとつで、カフェの前から旅立とうとしていた。
「どこへ行くの?」
「分からない。でも、探さないと。この舌が求める、まだ見ぬ『ゼロ』を」
その声に、悲壮感はなかった。むしろ、求道者のような静かな熱意が宿っている。凛は何も言えず、ただ寂しそうに微笑んだ。
幸が歩き出すと、彼の周りを、白く輝き始めたミザリアたちがそっと付き従う。彼らは、自分たちを肯定してくれた唯一の理解者のために、これからも『最高に不味い料理』を作り続けるのだろう。
失われた味覚と、饒舌な舌を道連れに、味沢幸は生涯をかけた美食の旅に出る。それは、誰にも理解されない、世界で最も孤独で、最も満ち足りた旅路だった。