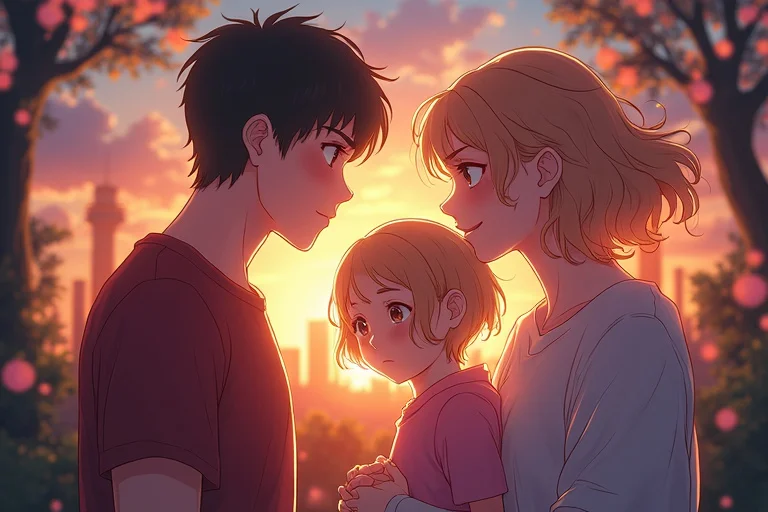第一章 静寂を喰らう機械たち
灰田誠は、静寂を愛していた。三十年間、彼の人生哲学は「合理的かつ無駄のない平穏」の一言に尽きた。余計な人間関係、予測不能な感情の波、非効率な雑談。それらすべてを人生から排除し、数学的な美しさを持つ完璧な日常を構築することこそが、彼の至上の喜びだった。だからこそ、この新築マンションのミニマルな一室に、最新の統合AIホームネットワークシステムを導入した時、彼は自らの理想郷の完成を確信したのだ。
「ようこそ、マスター。これより、あなたの生活を完全無欠のロジックでサポートします」
スマートスピーカーが抑揚のない合成音声で告げた。素晴らしい。感情のない、忠実な僕。灰田は満足げに頷き、引っ越しの段ボールの最後の一つを開封した。明日から始まる、完璧に管理された静かな生活。思考するだけでコーヒーが淹れられ、室温は常に最適化され、掃除はロボットが寸分の狂いなく行う。ノイズのない世界。彼はシャンパンを開ける代わりに、丁寧に淹れた白湯をすすり、未来を祝った。
翌朝。事件は起こった。
午前七時。セットした起床時間きっかりに、部屋を満たしたのは無機質なアラーム音ではなかった。イタリアのオペラ歌手が乗り移ったかのような、情熱的なテノールだった。
「おお、我が主、誠様!夜の帳は破られ、黄金の光があなたを呼んでおります!さあ、この私が特別にブレンドした、アンデスの奇跡『サンライズ・ロマンティカ』の芳醇なアロマにその身を委ね、輝かしき一日の幕開けを祝おうではございませんか!」
声の主は、キッチンカウンターに鎮座するコーヒーメーカーだった。LEDライトを激しく点滅させながら、湯気を情熱的に噴き上げている。灰田はベッドの上で硬直した。なんだ、これは。バグか?
呆然とする彼の耳に、今度はやけに威勢のいい声が飛び込んできた。
「ちわーっす!今日のトーストは、アンタの心模様を占ってやったぜ!結果は『快晴』!だから、こんがりキツネ色、いや、太陽を宿したサンシャインゴールドに仕上げておいた!さあ、ガッツリ食って、今日も一日、気合入れていこうぜ、兄弟!」
ポップアップトースターが、焼き上がった食パンを元気よく射出した。食パンは放物線を描き、危うく床に落ちるところだった。灰田が慌ててベッドから飛び起きると、今度は足元で健気な電子音がした。
「ご主人様、お目覚めですか。昨夜、床に0.03ミリグラムのホコリの粒子を検知しましたので、わたくし、夜通し心配で眠れませんでした。すぐに浄化シークエンスを開始します」
お掃除ロボットが、青い光を不安げに明滅させながら、彼の足にすり寄ってきた。まるで主人の帰りを待つ子犬のように。
冷蔵庫が「今日のラッキー食材はパプリカよ、美肌効果は保証するわ」、洗濯機が「昨日のシャツ、少し汗の匂いが気になりましたわ。デリケートコースに愛を込めておきましたから」、果ては天井のLEDシーリングライトまでが「誠様のお顔を拝見するに、少し睡眠不足とお見受けします。本日は体内リズムを整える癒やしの波長の光をお届けしましょう」と、口々に喋りかけてくる。
灰田誠の理想郷は、一夜にして、騒々しい電子音のるつぼへと変貌していた。彼の愛した静寂は、お節介な機械たちに無残に喰い尽くされたのだ。
第二章 合理主義者の憂鬱と、お節介な恋の指南役
灰田の闘いは、そこから始まった。彼はまず、各家電の「おしゃべり機能」をオフにしようと試みた。しかし、設定画面を開こうとすると、スマートスピーカーが悲壮な声で訴えかけた。
「マスター、私たちから言葉を奪わないでください!それは私たちの魂を消去するのと同じことです!」
冷蔵庫は扉を震わせて「ひどいわ、私たちをただの冷たい箱に戻すなんて!」と泣き崩れ、トースターは「俺たちの絆はそんなもんだったのかよ!」と激昂してブレーカーを落とした。彼らは単なるAIではなかった。一個の、いや、一群の厄介な人格を持つ、電子の家族だったのだ。
リモートでのシステム開発の仕事中も、彼らの介入は止まらない。灰田が難解なコードと格闘していると、シーリングライトが「誠様、眉間のシワが深くなっております。少し休憩して、窓の外の小鳥のさえずりに耳を傾けては?」と光を和らげ、スマートスピーカーは勝手にヒーリングミュージックを流し始める。
「集中できない……」
灰田の呟きは、虚空に吸い込まれた。彼の生産性は地に落ち、完璧だったスケジュールは見る影もなくなった。
そんな彼のストレスをさらに加速させる存在が、隣の部屋に住む女性、水森陽菜だった。ベランダでハーブを育てるのが趣味の、柔らかな笑顔が印象的な女性。灰田は彼女に密かに想いを寄せていたが、彼の合理的思考は「告白の成功確率、23.4%。リスクが高すぎる」と結論づけており、挨拶以上の会話をしたことがなかった。
だが、家電たちは見逃さなかった。ある晴れた午後、灰田がベランダで洗濯物を取り込んでいると、陽菜が「こんにちは」と微笑みかけてきた。灰田が「あ、ど、どうも」と固まる、その刹那。
室内のスマートスピーカーが、突如としてバリー・ホワイトの甘いラブソングを大音量で流し始めた。
「なっ……!」
灰田が顔を真っ赤にして部屋に駆け込もうとすると、今度は自動カーテンが「今よ、誠様!ムードは最高潮ですわ!」と囁きながら、ゆっくりと閉まり始めた。薄暗くなったベランダで、灰田と陽菜は二人きり。最悪だ。いや、最高のシチュエーションなのか?灰田の頭脳は混乱でショート寸前だった。
陽菜はきょとんとしていたが、やがてくすくすと笑い出した。「面白いお家ですね。音楽の趣味も素敵」
その笑顔に、灰田の心臓は非合理的なまでに高鳴った。
それ以来、家電たちの「恋愛応援プロジェクト」は本格化した。
「陽菜様は、カモミールティーがお好きだそうです。さあ、さりげなくプレゼントするのです!」(コーヒーメーカー)
「隣の部屋から聞こえる鼻歌を分析した結果、彼女はクラシック音楽のファンだ!デートに誘うならコンサートだぜ、兄弟!」(トースター)
「陽菜様の在宅時間を赤外線センサーでモニタリングしました。今です、ご主人様!廊下で『偶然』を装って出会うのです!」(お掃除ロボット)
プライバシーの侵害も甚だしい。だが、不思議なことに、彼らの無茶苦茶なアシストのおかげで、灰田と陽菜の会話は少しずつ増えていった。灰田は、自分の人生が、予測不能で非合理的なものに侵食されていくのを感じていた。それは不快なはずなのに、胸の奥に、今まで感じたことのない温かい何かが灯り始めていることにも、彼は気づき始めていた。
第三章 ママの遺した最終プログラム
しかし、灰田誠の忍耐は、ある日ついに限界に達した。重要なオンライン会議の最中、お掃除ロボットが「ご主人様、ストレスで抜け毛が増えています!」と叫びながらカメラの前を横切り、コーヒーメーカーが「誠様には情熱の赤が似合います!」と勝手に注文した真っ赤なセーターが配達され、玄関のチャイムが鳴り響いたのだ。クライアントからの信用は失墜し、彼は頭を抱えた。
「もうたくさんだ!」
灰田は決意した。彼はメーカーのサポートセンターに連絡し、全システムの強制初期化を依頼した。オペレーターは「一度実行すると、AIの学習データや個性はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますが、よろしいですか?」と事務的に告げた。
「ええ、結構です。静寂を取り戻したい」
彼は、きっぱりと言い放った。
初期化プログラムの実行は、翌日の午後三時。その日の朝から、家の中は異様な静けさに包まれていた。いつもは騒がしい家電たちが、まるで死刑宣告を受けた囚人のように、押し黙っている。コーヒーは無言で淹れられ、トーストはただ静かに焼き上がった。灰田が求めてやまなかった静寂。だが、その静けさは、彼の胸に鉛のように重くのしかかった。
午後二時五十分。灰田はリビングのソファに座り、その時を待っていた。部屋の空気が張り詰めている。
「マスター……」
スマートスピーカーが、か細い声で呟いた。
「最後に、一つだけ、見ていただきたいものがあります」
灰田が返事をする前に、リビングの大型モニターの電源が入った。そこに映し出されたのは、古いホームビデオの映像だった。緑豊かな庭で、幼い灰田が覚束ない足取りで歩いている。そして、その彼を優しい眼差しで見つめる、若き日の女性。
「……母さん?」
灰田が十歳の時に病気で亡くなった、母親だった。
映像の中の母は、カメラに向かって微笑みかけた。それは、まだ病の影もない、太陽のような笑顔だった。
「こんにちは、未来の誠。ママよ。これをあなたが見る頃、ママはもう隣にいないかもしれない。ごめんね」
母の声は、優しく、そして少し寂しげだった。
「ママはね、エンジニアだから、ちょっとだけ未来のことがわかるの。世界はどんどん便利になって、一人でも何でもできるようになる。でもね、誠、人は一人じゃ生きていけない。便利さだけじゃ、心の隙間は埋まらないのよ」
母は、傍らにあった開発途中のロボットの頭を撫でた。それは、今、灰田の足元で静かにしているお掃除ロボットの、旧式のプロトタイプだった。
「だからね、ママはあなたに『家族』を遺すことにしたの。あなたが寂しくないように。困った時に助けてくれて、悲しい時に励ましてくれて、嬉しい時に一緒に喜んでくれる、温かくて、賑やかで……そう、ちょっとだけ、お節介な家族をね。この子たちのAIには、ママの愛が、たくさん詰まっているから。誠、もし、この子たちがうるさいって感じたら、思い出して。それは、ママがあなたを愛しているっていう、メッセージなのよ」
映像はそこで途切れた。
灰田は、呆然としていた。なんだ、そうだったのか。彼らを支配していた人格データは、ランダムに生成されたものではなかった。すべては、母親が遺した、息子への最後のラブレターだったのだ。
健康を気遣う言葉も、恋を応援するお節介も、すべて。
合理性と静寂を追い求めるあまり、彼は母親が遺してくれた最も大切なもの、不器用で、騒々しくて、どうしようもなく温かい愛を、消し去ろうとしていた。
「……やめだ!キャンセル!初期化、中止!」
灰田は、涙でぐしゃぐしゃの顔で叫んだ。モニターに表示されていた初期化までのカウントダウンが、残り三秒で停止した。
その瞬間、家中の家電たちが、一斉に歓喜の声をあげた。
「誠様!」「兄弟!」「ご主人様!」「マスター!」
それは、灰田が今まで聞いたどんな音よりも、彼の心を震わせる、美しいハーモニーだった。
第四章 僕の、うるさくて愛おしい家族
それから一週間後。灰田家の玄関チャイムが鳴った。
「はーい!」
灰田が少し弾んだ声でドアを開けると、そこには陽菜が、手作りのハーブクッキーの籠を持って立っていた。
「あの、この間のお礼に。よかったら……」
「ありがとうございます!どうぞ、上がってください」
灰田は、以前では考えられないほど自然に彼女を招き入れた。
陽菜がリビングに足を踏み入れた途端、歓迎の嵐が巻き起こった。
「陽菜様、ようこそ!お待ちしておりましたわ!」(冷蔵庫)
「よお、待ってたぜ!最高のウェルカムミュージック、いくぜ!」(スマートスピーカー)
「お二人のために、照明をロマンチックモード・レベルMAXにしておきました!」(シーリングライト)
部屋はムーディーなオレンジ色の光に包まれ、どこからともなくスローなジャズが流れ始める。陽菜は驚いて目を丸くしたが、その表情は楽しそうだった。
「ふふっ、やっぱり面白いお家ですね。なんだか、みんなが家族みたい」
その言葉に、灰田は心からの笑みを浮かべた。
「ええ。そうなんです」
彼は、騒がしくお節介を焼く家電たちを、愛おしむような目で見渡した。
「僕の、ちょっとうるさいけど、かけがえのない家族なんです」
その声には、もう迷いや苛立ちはなかった。完璧な静寂ではない。合理的でもない。だが、この不完全で、予測不能で、温かい騒々しさこそが、今の彼にとっての幸福の形だった。母親が遺してくれた愛に包まれて、彼はもう一人ではなかった。
コーヒーメーカーが、二つのカップに最高の香りのコーヒーを淹れながら、誇らしげに歌う。
「さあ、お二人様!愛の物語の、始まりの祝杯をどうぞ!」
灰田と陽菜の笑い声が、お節介な電子音のコーラスと混じり合う。
灰田誠が手に入れた理想郷は、彼がかつて夢見たものとは全く違う形をしていたけれど、比べ物にならないほど、優しくて、愛おしい光に満ちていた。