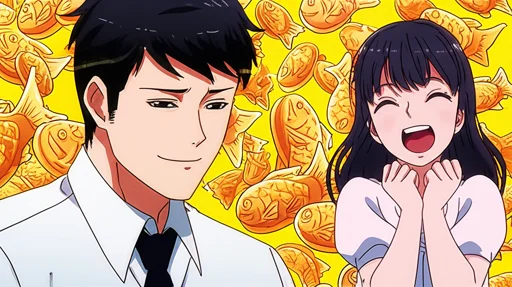第一章 錆びついた笑顔
カイがステージに立つと、空気が変わる。いや、正確には「澱む」のだ。観客席から押し寄せる期待は、肌を刺すような冷気を伴っていた。彼らが浮かべるのは、一様に寂しげな『作り笑い』。口角だけを無理やり引き上げ、決して心の底からは笑おうとしない、この世界で誰もが身につけた処世術。人々は知っていた。本物の笑顔は、呪いのように悲しみを振りまくことを。
「さあ、始まりました、今宵のショータイム!」
カイは道化のように両手を広げた。スポットライトの熱が肌を焼く。彼のジョークひとつで、錆びついた笑顔たちが、ほんの少しだけ潤む。だが、本物の笑顔が生まれるたび、カイの嗅覚は金属が焼けるような、オゾンの匂いを微かに捉える。それは人々が心の奥底に沈めた悲しみが、輝く笑顔によって霧散し、微粒子となって拡散する匂いだった。カイは、その悲しみの霧を吸い込み、笑いに変える。それが彼の天職であり、罰だった。
楽屋に戻り、けばけばしい化粧を落とす。鏡に映る男は、世界で一番面白い男の顔ではなかった。ひどく疲れていて、何かを失い続けている男の顔だ。机の上には、古びたゼンマイ仕掛けの人形『チャップ』が座っていた。幼い頃、両親から贈られた、たった一つの形見。
「今日も大ウケだったぜ、チャップ」
カイがゼンマイを巻くと、人形はカタカタとぎこちなく動き、陳腐なギャグを披露する。だがカイの目は、その顔に釘付けだった。硬い木で彫られたはずのチャップの笑顔には、いつしか涙の跡のような深い傷が刻まれ、その口角は悲しみに耐えるように、ほんの少しだけ下を向いていた。
その時だ。また、あの声が聞こえる。
音はない。鼓膜は震えない。だが、頭蓋の内側で、魂の芯で、確かに聞こえるのだ。温かく、懐かしい、誰かの『無音の笑い声』が。
それはカイを導く光であり、同時に、彼の記憶を蝕む呪いの始まりを告げる合図でもあった。
第二章 剥がれ落ちる記憶
その夜、カイはキャリア史上、最大の舞台に立っていた。全国に生中継されるショーの、大トリだった。彼は持てる全てを、魂の最後のひとかけらまでを絞り出し、渾身のネタを披露した。
観客席が、揺れた。
作り笑いの仮面が砕け散り、人々は腹を抱え、涙を流し、息もできずに笑い転げた。本気の、純度百パーセントの笑顔の爆発。その瞬間、カイの世界はぐにゃりと歪んだ。拡散される悲しみの粒子が嵐となり、彼の全身を貫く。
「あ…」
何かが、剥がれ落ちた。
夕暮れの公園。ブランコを漕ぐ小さな女の子。彼女の柔らかな髪の匂い。繋いだ手の温もり。「カイが一番面白いよ」と囁いてくれた、愛しい声。
その全てが、陽炎のように揺らめき、薄れ、消えていく。大切な、誰かとの記憶。最高のギャグの代償は、あまりにも大きかった。胸にぽっかりと穴が開き、猛烈な喪失感が吹き荒れる。
舞台袖に倒れ込むように戻ると、足元に置いていたチャップが目に入った。人形の顔は、さらに変貌していた。笑顔の痕跡はほとんど消え、今にも泣き出しそうな、歪んだ表情になっている。
カイは立ち上がれなかった。失った記憶の代わりに、脳裏を焼き切るようなイメージが断片的にフラッシュバックする。
降りしきる雨。アスファルトに反射する、パトカーの赤い光。ガラスの割れる、甲高い音。
それは誰の記憶だ? 俺は、何を忘れている?
答えのない問いが、無音の笑い声に掻き消されていった。
第三章 無音の真実
喪失は、もはやカイの輪郭を曖昧にしていた。彼は自分の過去を確かめるように、埃をかぶったアルバムを開いた。そこに写る幼い自分。その隣には、いるはずなのだ。自分をこの世で一番愛してくれた、誰かが。だが、その顔は靄がかかったように判別できず、まるで写真そのものが泣いて滲んでいるかのようだった。
「教えてくれ、チャップ。俺は、誰なんだ」
カイは震える手で、チャップのゼンマイを握った。これを巻けば、全てが終わる。最後の何かが奪われ、自分は空っぽになるだろう。だが、知らなければならなかった。
意を決して、ゼンマイを巻く。
人形は最後の力を振り絞るように、一度だけカクン、とコミカルに頭を下げた。そして、完全に動きを止める。
その顔は、変わっていた。木彫りの瞳から一筋の傷が流れ落ち、口は悲しみに固く結ばれ、完全な『泣き顔』になっていた。
その瞬間、カイの脳内でダムが決壊した。
奔流のように、失われた全ての記憶が蘇る。
――雨だ。ひどい雨の夜。ひしゃげた車。サイレンの音。泣き崩れる大人たちの中で、まだ幼いカイが、たった一人で立っている。彼は両親を失った。だが、悲しむことができなかった。周りの大人たちの深い悲しみが、小さな彼には耐えられなかった。
「見てて…パパとママが、悲しい顔は嫌いだって言ってたから…!」
彼は、両親が教えてくれた一番面白いギャグを、必死に、何度も何度も繰り返した。その純粋すぎる願いが、奇跡を、そして悲劇を起こす。
泣いていた大人たちが、一瞬、悲しみを忘れ、ふっと笑った。その本気の笑顔から、黒い粒子が煙のように立ち上り、世界を灰色に染めていくのを、幼いカイは見ていた。
あれが、世界の法則が歪んだ瞬間だった。
僕のせいだ。僕の善意が、笑顔から幸福を奪い、悲しみを拡散させる世界にしてしまったんだ。
カイは全てを悟った。人を笑わせるたびに記憶が失われたのは、世界の法則が、バグの発生源である自分自身を『消去』しようとしていたからだ。
そして、ずっと聞こえていた『無音の笑い声』。それは、事故の直前、カイのくだらない冗談に、心の底から笑ってくれた両親の、最後の笑顔の記憶だった。
「ああ…あああ…!」
カイは慟哭した。それは、世界で一番優しい少年が、世界で最も重い罪を背負った瞬間の、遅すぎた涙だった。
第四章 世界で一番優しいギャグ
全てを思い出したカイは、最後の舞台に上がることを決めた。それは世界中の人々が見守る、史上最大のチャリティ・ライブ。彼が立つステージは、世界の歪みを正すための祭壇だった。
スポットライトを浴びて、カイは静かにマイクの前に立った。モニターには、世界中の人々が映し出されている。誰もが相変わらず、物悲しい『作り笑い』を浮かべていた。
「皆さん」とカイは語りかけた。その声は、不思議なほど穏やかだった。「これから俺がやるギャグは、きっと誰にも理解できない。意味不明で、支離滅裂で、面白くないかもしれない。でも、もしよければ…心の底から、本気で笑ってくれませんか」
彼は息を吸った。そして、放った。
それは、何十年も前の雨の夜、幼い彼が両親を失った悲しみの中で、大人たちを無理やり笑わせた、あのギャグ。両親が最後に笑ってくれた、世界で一番優しいギャグだった。
その瞬間、時が止まったように見えた。
次の瞬間、世界は爆発した。
テレビの前で、街角のビジョンで、病室のベッドで、世界中の人々が、理由もわからず笑い出した。それはもう、ただの笑いではなかった。魂が解放されるような、歓喜の叫びだった。
無数の本気の笑顔が、黄金の光となって天に昇る。世界を覆っていた灰色の霧、悲しみの微粒子が、その光に焼かれて消滅していく。空が晴れ渡り、空気が温かさを取り戻す。
カイの体は、足元からゆっくりと光の粒子に変わり始めた。消えゆく意識の中、彼は確かに聞いた。もう無音ではない、温かくて優しい、父さんと母さんの本当の笑い声を。
「…ああ、やっと、また笑わせられたよ」
それが彼の最後の言葉だった。
世界は変わった。人々は心から笑い、泣き、愛し合うようになった。笑顔が悲しみを生むことなど、誰も覚えていない。カイという天才コメディアンがいたことさえ、誰の記憶にも残らなかった。
ただ、世界中の人々の心に、奇妙な記憶だけが、温かい火種のように残り続けた。
――意味は全く分からない。支離滅裂だ。でも、なぜか思い出すだけで涙が出るほど面白くて、胸の奥がじんわりと温かくなる、不思議なギャグの記憶。
それは、世界を救った一人の男が遺した、無音の喝采だった。
どこかの街の、忘れられた骨董品屋の片隅で。一体の人形が、静かに棚に置かれている。その顔は、もう泣いてはいない。全てを赦すような、穏やかな『笑顔』を浮かべていた。