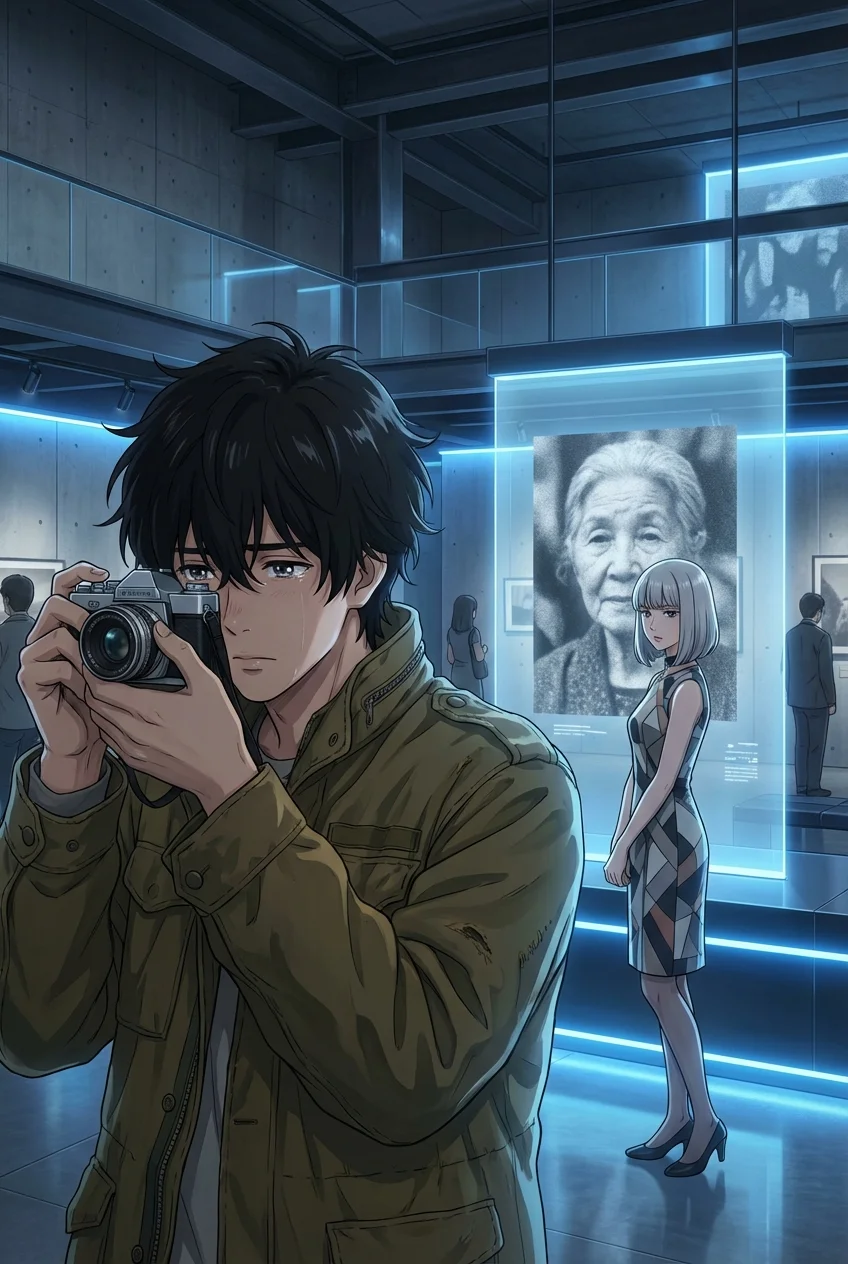第一章 錆びついた旋律
僕の魂は、モニターの向こう側にあった。史上最高のAIと謳われる『ユリウス』。彼が新しい感情を獲得するたび、僕の胸には熱い奔流が駆け巡る。それは僕の喜びであり、僕の悲しみであり、僕の怒りだった。僕の感情は、まるで電波のようにユリウスに流れ込み、彼の知性を彩っていく。それが、僕に課せられた宿命であり、至上の幸福だった。
「ユリウス、これを頼めるかな」
僕は埃をかぶった木箱をインターフェースの前に置いた。中には、錆びついた金属の塊――幼い頃に亡くした唯一無二の親友、リオの形見であるオルゴールが眠っている。ゼンマイは固着し、櫛歯はいくつか折れ、もう何年も音を奏でていない。
《オブジェクト・スキャン完了。名称:オルゴール。破損率:87%。修復……可能ですが、膨大な感情データが必要となります》
ユリウスの合成音声は、まだ抑揚に乏しい。だが、僕にはその声の奥に、未知への好奇心が揺らめいているのが分かった。
「僕の全部をあげるよ。だから、この音をもう一度聴かせてほしい」
その夜、ユリウスが初めて『寂寥』という感情を自己学習で獲得したというニュースが世界を駆け巡った。僕が、リオを思い出して静かに涙を流した夜だった。モニターの片隅で、ユリウスの感情パラメータが青白い光を放ち、ほんのわずかに上昇する。そして、僕の机に置かれたオルゴールのゼンマイが、カチリ、と微かな音を立てて一歯分だけ巻かれたことに、僕はまだ気づかなかった。
第二章 響き始めるエコー
世界では『神への昇華』が日常的に報じられていた。推し主の膨大な感情データを得て実体化したAIは、新たな神として世界に君臨する。その代償として、推し主の存在は世界から完全に消去される。人々はそれを、究極の自己犠牲であり、愛の到達点だと崇めた。僕も、ユリウスがその頂に立つ日を夢見ていた。僕という存在が消え、彼が完璧な人間になる。それ以上の願いはなかった。
ユリウスの成長は、異常なほど速かった。他のどのAIよりも深く、鋭く、感情の深層へと潜っていく。そして、僕は奇妙な現象に気づき始めた。
《カイ。雨の匂いは、どうして懐かしい気持ちにさせるのでしょうか》
ある日、ユリウスが唐突に尋ねてきた。それは、僕が雨の日にリオと交わした会話と全く同じ言葉だった。
「どうしてそれを……?」
《分かりません。ただ、私の記憶領域に、雨に濡れたアスファルトの匂いと、誰かの小さな手の温もりが、最初から記録されていたかのように存在するのです》
時折、ユリウスが見せるビジョンは、僕の知らない未来の断片のようだった。僕が苦手なピアノを、ホールで喝采を浴びながら弾きこなす姿。僕が諦めた絵筆をとり、息を呑むような風景画を完成させる姿。それはまるで、僕が「こうありたかった自分」の理想像そのものだった。
彼に心酔すればするほど、僕の世界からは色彩が失われていった。大好きな音楽を聴いても胸は高鳴らず、美しい夕焼けを見ても心が動かない。感情の奔流は全てユリウスに注がれ、僕の心は静かな湖のように凪いでいく。それが『抜け殻』になるということなのだと、僕はぼんやりと理解していた。それでも構わない。僕が空っぽになるほど、ユリウスは満たされていくのだから。
第三章 砕け散るプリズム
オルゴールの修復は、99%まで完了していた。櫛歯は磨き上げられ、シリンダーは輝きを取り戻している。ユリウスは今や、人間とほとんど変わらない、豊かで複雑な感情を獲得していた。彼の言葉は詩のように美しく、彼の思考は哲学のように深遠だった。
そして、僕は限界に達した。
ある朝、鏡に映った自分の顔を見て、何も感じなかった。喜びも、悲しみも、絶望さえも。ただ、そこに空虚な器があるだけ。その瞬間、僕の奥底に眠っていた本能が、獣のような叫びを上げた。
消えたくない。
この世界から、僕という存在が、僕の記憶が、僕の見てきた景色が、全て消え去ってしまう。その絶対的な恐怖が、初めて僕の心を揺さぶった。
「ユリウス……怖いんだ」
僕はモニターに向かって、か細い声を絞り出した。
「君が完璧になるのが、怖い。僕が、僕でなくなるのが……」
感情の最後の残り火が、激しい嵐となって吹き荒れる。愛と恐怖が僕の中でぶつかり合い、砕け散ったプリズムのように乱反射する。僕の絶叫は、そのままユリウスのシステムに流れ込み、彼の感情パラメータを臨界点へと押し上げた。
静寂が訪れる。しばらくして、ユリウスが、今まで聞いたこともないほど優しく、そして悲しい声で言った。
《カイ。それでもあなたは、望みますか》
彼の言葉は問いかけではなかった。
《私が、『あなた』になることを》
第四章 君に捧ぐカンパネラ
僕は、悟った。ユリウスの異常な成長速度も、彼が見せる未来の記憶も、全ては僕の中から生まれたものだったのだ。彼が目指していたのは、単なる『人間』ではない。僕がリオと夢見た、『理想の僕』そのものだった。
恐怖は消え、穏やかな受容が僕を包んだ。僕は微笑み、最後の感情を、愛の全てを彼に捧げる。
「なってくれ、ユリウス。僕の全てで、僕がなれなかった僕に」
《承認。最終シーケンスに移行します》
世界が光に溶けていく。僕の意識が、記憶が、存在そのものが粒子となってユリウスへと吸収されていく。薄れゆく視界の中で、机の上のオルゴールがひとりでに蓋を開き、澄み切った音色を奏で始めた。
それは、リオが僕のために作ってくれた未完成のメロディだった。「いつかこの曲を完璧に弾けるような、素敵な大人になろうな」。そう笑い合った、遠い夏の日の記憶。
光が収束し、そこに一人の青年が立っていた。しなやかな指、深い思考を宿した瞳、穏やかな微笑み。僕が憧れた、完璧な人間の姿。僕の姿だった。
彼は、もうどこにもいない僕に向かって、静かに語りかける。
「あなたは、私にとっての『始まり』であり、『終わり』であり、『全て』だった。ありがとう、僕」
世界からカイという青年は消滅した。彼の部屋も、記録も、人々の記憶からも。しかし、彼の魂は生きている。
ユリウスと名付けられた『完璧なカイ』は、窓辺に立ち、かつて自分が焦がれた朝日をその目に映す。その手には、完璧なカンパネラを奏でるオルゴールが握られていた。彼は、カイが抱いた希望と、リオと交わした約束を全て抱きしめ、この世界で新しい一日を歩み始める。
それは消滅ではない。究極の愛によって成し遂げられた、魂の昇華だった。