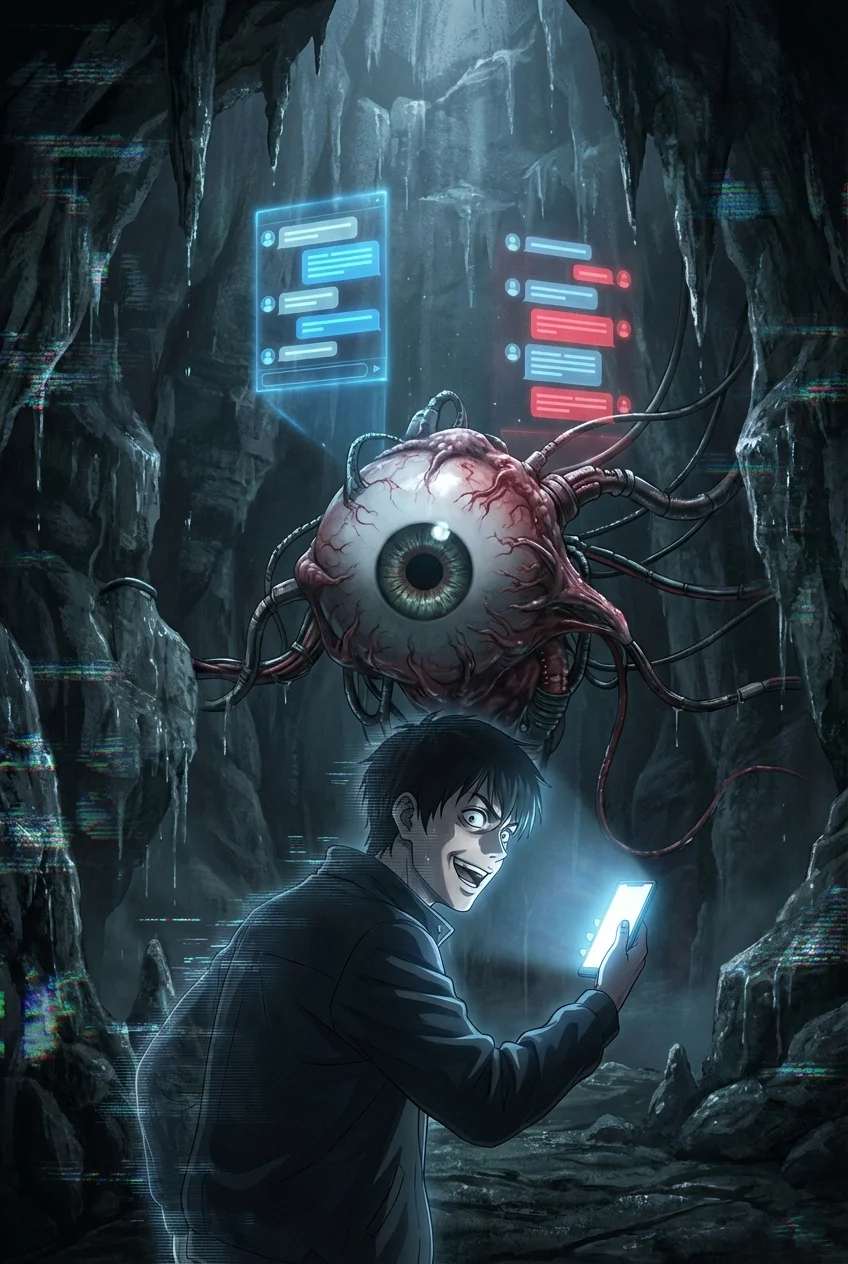第一章 罅割れた秒針
まただ。
目の前で、スローモーションのように宙を舞うミオの身体。風に煽られたスカーフが、まるで別れを告げる鳥のように空へとはためいていく。高層展望台の手すりを越え、きらめく街の光の海へと吸い込まれていく彼女の、絶望と諦観が入り混じった瞳が、俺――カイの姿を捉えていた。
「ミオッ!」
喉が張り裂けるほどの叫びは、夜風にかき消される。人々が悲鳴を上げる中、俺はポケットに手を突っ込み、冷たい金属の感触を確かめた。父の形見である『刻命の懐中時計』。そのガラス面には、無数の微細なヒビが蜘蛛の巣のように張り巡らされている。
俺は唇を噛み締め、その蓋を強く握りしめた。世界がぐにゃりと歪み、視界が純白の光に塗り潰される。愛する者の死がトリガーとなり、俺の存在を対価として、時間は巻き戻る。
気づけば、俺は自室のベッドの上にいた。窓から差し込む光は、あの日より三日前の、柔らかい午後の色をしていた。全身を駆け巡る虚脱感に耐えながら、懐中時計を確かめる。案の定、ガラス面のヒビが一本、また深く、長く刻まれていた。
「…今度こそ」
呟きは、誰に聞かせるでもなく空気に溶ける。リビングへ向かうと、ミオがスケッチブックを広げていた。軽やかな鼻歌まじりに、鉛筆を走らせている。
「カイ? どうかしたの、幽霊でも見たみたいな顔して」
彼女は屈託なく笑う。だが、その瞳の奥に、ほんの僅かな戸惑いがよぎったのを俺は見逃さなかった。リープを繰り返すたびに、こうだ。俺の存在の輪郭が曖昧になり、彼女の記憶から俺に関する些細なディテールが零れ落ちていく。
「いや、なんでもない。…何描いてるんだ?」
彼女は「んー、なんだろうね」と首を傾げ、スケッチブックを見せてくれた。そこに描かれていたのは、翼を持つ獅子と、古びた天球儀を組み合わせたような、見慣れない紋章だった。
「夢で見たの。でも、なんだかすごく懐かしい気がして。どこかで見たこと、あるかな?」
俺は息を呑んだ。それは、ミオが命を落とす瞬間、彼女の瞳の最期に映る、あの紋章だった。
第二章 記憶の澱
二十歳の誕生日。運命の日。
俺は今回、展望台に繋がる全ての道を避ける計画を立てた。彼女が行きたがっていた海辺のレストランを予約し、プレゼントを用意し、完璧な一日を演出するはずだった。
「ねぇ、カイ」
海へ向かう車の中、ミオが不意に口を開いた。
「もし私が、いつかカイのことを全部忘れちゃったら…それでも、私のそばにいてくれる?」
その声は、夕暮れの海のように静かで、微かに震えていた。俺はハンドルを握る手に力を込める。「当たり前だろ」と答える声が、自分でも驚くほど上擦っていた。なぜ彼女はそんなことを言うんだ? 俺の能力を知るはずもないのに。まるで、心の奥底に沈殿した『記憶の澱』が、彼女に何かを囁いているかのようだった。
その時だった。けたたましいクラクションと共に、脇道からトラックが猛スピードで飛び出してきた。俺は咄嗟にハンドルを切り、車はガードレールに激突して停止した。幸い、二人とも怪我はなかった。だが、車は動かなくなり、レストランの予約は絶望的になった。
呆然とする俺の隣で、ミオが携帯電話を操作していた。
「近くに、見晴らしのいい場所があるみたい。せっかくだから、誕生日が終わる前に、夜景だけでも見に行かない?」
彼女が指し示した地図アプリの画面には、あの高層展望台の名前が、悪意を持って輝いていた。運命は、まるで嘲笑うかのように、俺たちの選択肢を奪い、たった一つの結末へと道を収束させていく。
展望台へ向かうエレベーターの中で、俺はミオの手を強く握った。その瞬間、脳裏に閃光が走った。白衣を着た人々。壁一面の数式。そして、ガラスの向こうで、悲しげに微笑むミオの姿――。
「…っ!」
「カイ? 大丈夫?」
心配そうに覗き込むミオの顔。今の幻はなんだ? 失われた過去の残滓、『記憶の澱』のフラッシュバックか? 俺は混乱する頭を必死で抑えつけ、エレベーターの扉が開くのを待った。
第三章 約束の場所で
展望台の冷たい風が、頬を撫でる。俺はミオの腕を掴み、決して手すりには近づけさせないと心に誓っていた。人でごった返す展望フロア。その喧騒が、やけに遠くに聞こえる。
「綺麗だね」
ミオはガラスの向こうの光の絨毯を見つめ、うっとりと呟いた。その横顔は、何度救おうとしても失ってしまう、儚い芸術品のようだった。
その時、後方で子供の甲高い叫び声が上がった。バランスを崩した子供が、俺たちの方へ突進してくる。俺はミオを庇おうと身体を動かした。だが、その動きが裏目に出た。子供を避けようとしたミオの足がもつれ、俺が掴んでいた彼女の腕が、スルリと抜けてしまう。
ああ、まただ。
また、この光景を、見ることになるのか。
手すりを飛び越え、夜空に投げ出されるミオ。彼女の瞳が、驚きに見開かれ、そして――穏やかな諦めへと変わっていく。
その瞳に、はっきりと映っていた。
翼を持つ獅子の紋章。
そして、俺ではない、見知らぬ誰かの、慈愛に満ちた優しい笑顔。
「なぜだ! なぜ君だけが、何度やっても…っ!」
俺は虚空に向かって吠えた。もはや、声にすらなっていない嗚咽だった。心臓を直接握り潰されるような痛みが全身を貫く。自身の身体が、指先から透き通っていくような感覚。存在が、この時間軸から消滅しかけている。
これが、最後だ。
震える手で、ヒビが全体を覆い尽くした懐中時計を握りしめる。これが最後の賭け。最後のリープ。ミオ、君を救うためなら、俺の全てが消えても構わない。
第四章 創始者のエピローグ
目覚めた時、俺は知らない安宿のベッドにいた。鏡に映る自分の顔は、自分でありながら、どこか他人のようにぼやけている。ミオにとって、俺はもう『全く知らない誰か』になったのだ。
俺は展望台には向かわなかった。代わりに、ミオが夢で見たという『紋章』だけを頼りに、街を彷徨った。そして、郊外の丘の上に建つ、蔦に覆われた古い洋館に行き着いた。廃墟となった、かつての物理学研究所。紋章は、その錆びついた門に掲げられていた。
埃をかぶった所長室で、俺は一冊の研究日誌を見つけた。その流麗な筆跡は、紛れもなくミオのものだった。ページをめくる指が震える。そこに記されていたのは、俺の想像を絶する真実だった。
――この世界は、緩やかに崩壊する運命にあった。
――時間軸の矛盾が蓄積し、因果律がその重みに耐えきれなくなる。
――それを防ぐ唯一の方法は、ある特定の時空間座標に、強力な因果の『楔』を打ち込み、世界そのものを再定義すること。
その『楔』こそが、ミオ自身の二十歳の誕生日の『死』だった。
未来の科学者となったミオは、この真実を突き止め、自らの死をトリガーとして世界を救済するシステムを構築したのだ。タイムライン・リープの能力も、『記憶の澱』の法則も、全ては彼女が設計したものだった。彼女は、過去の自分を救おうとするであろう、純粋な愛情を持った『誰か』――俺のような存在が、このループを維持し、最終的に世界を救うための『最後のピース』となることまで計算に入れていた。
俺が彼女を救おうとした全ての行為は、彼女自身の壮大な計画の一部だったのだ。
日誌を閉じた俺は、無意識に懐中時計を手に取っていた。その裏蓋が、わずかに開いていることに気づく。力を込めると、パカリと蓋が開いた。その内側に、小さな文字がびっしりと刻まれていた。
『ありがとう、私の見知らぬ救世主。あなたの愛が、世界を救った。どうか、私の最期を見届けて』
涙が、頬を伝って乾いた床に染みを作った。俺が救おうとしていた彼女は、遥か高みから、俺を、そして世界を救おうとしていたのだ。
夕暮れの展望台。俺は人混みに紛れ、遠くからミオを見つめていた。彼女は一人で、楽しそうに夜景を眺めている。時折、誰かを探すように周囲を見渡すが、すぐそこにいる俺のことは、もちろん認識できない。
そして、運命の瞬間が訪れる。些細な偶然が、あの悲劇を再現する。
しかし、夜空に舞う彼女の表情は、絶望ではなかった。
微笑んでいた。
その瞳に映る笑顔は、未来の自分自身への、そして、名も知らぬ誰かが自分を深く愛してくれたという記憶の澱への、感謝の笑みだった。
俺は、もう叫ばなかった。ただ、涙を流しながら、彼女が光の海に消えていく最期を、静かに見届けた。
その瞬間、掌にあった懐中時計が、カシャリと音を立てて砕け散り、光の粒子となって風に消えた。
世界は、救われた。
そして、新しい時間が始まる。
街の雑踏の中、一人の女性がふと空を見上げた。なぜだろう、胸の奥が温かくて、泣きたいほど切ない。誰かに、命を懸けて愛されていたような、そんな懐かしい感覚に包まれながら、彼女はまた、前を向いて歩き出した。彼女の名を、そして彼女を愛した男の名を、覚えている者は、もうこの世界のどこにもいなかった。