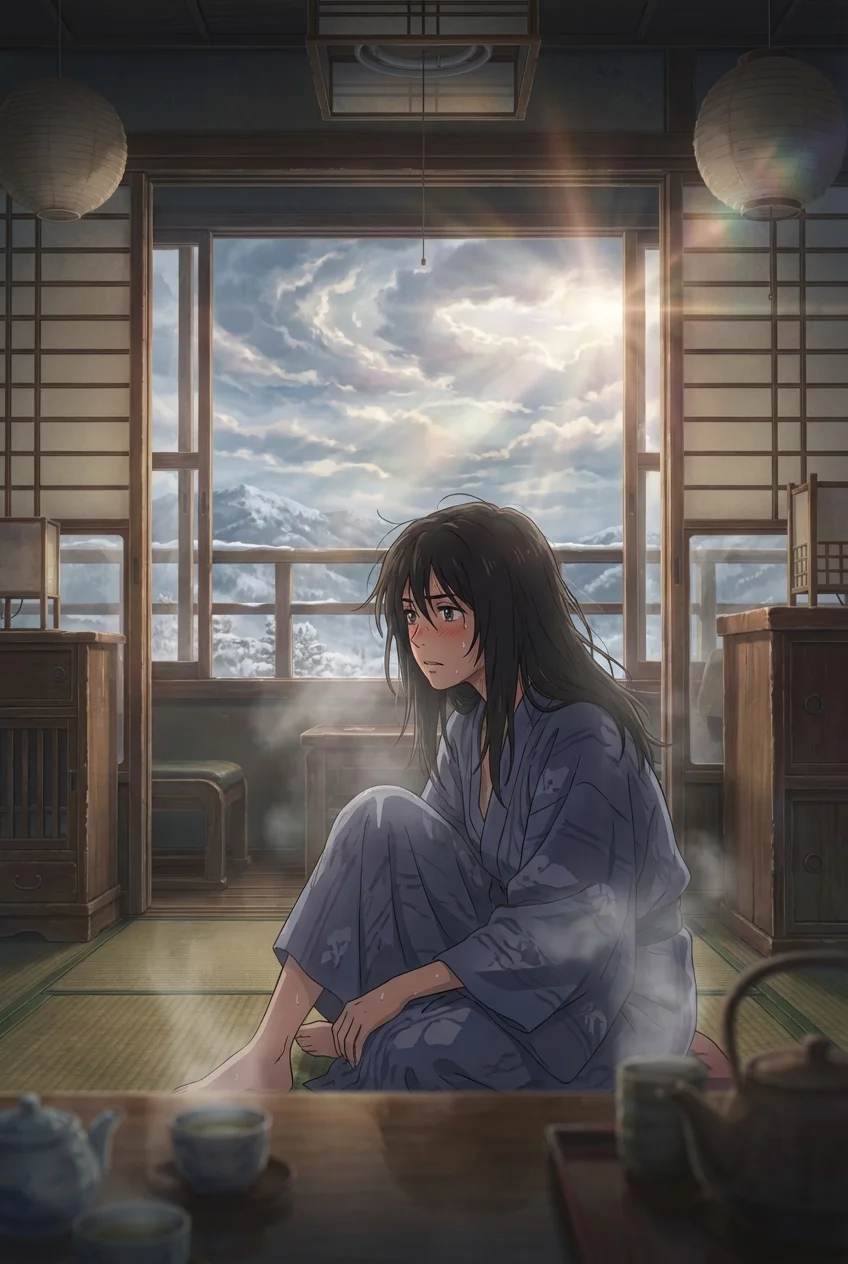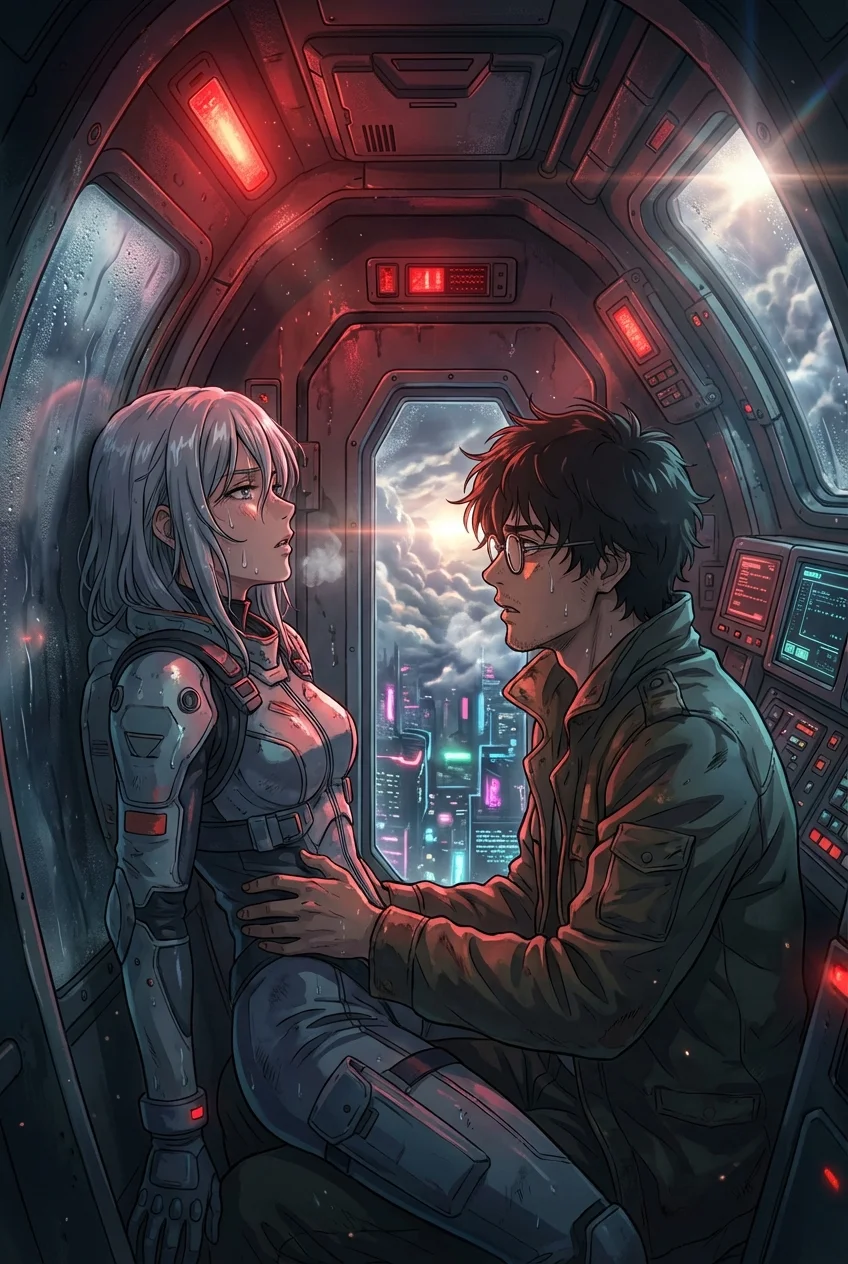第一章 冷徹な指輪
左手の薬指が、氷を押し当てられたように冷たい。
きゅ、と締め付けられる感覚。
その冷たさは、私の心拍数が平常時を超えたことを示している。
「……香月。どうした? ペンを持つ手が止まっているぞ」
重厚なマホガニーのデスクの向こう。
社長の西園寺が、書類から視線を上げずに言った。
低く、腹の底に響くバリトンボイス。
「申し訳ございません。次期プロジェクトの損益分岐点について再考しておりました」
私は表情筋一つ動かさず、完璧な嘘を吐く。
「ほう。数字の確認だけで、そこまで脈が乱れるのか?」
西園寺が立ち上がる気配。
革靴が絨毯を踏む、僅かな衣擦れの音。
私の鼻腔を、ビターな煙草と高級なムスクの香りが支配していく。
「……社長。私との距離が近すぎます。業務効率が低下する恐れが」
「これは『業務』だ。忘れたか? 契約書第5条。健康管理も私の管轄下にある」
彼は私の背後に回り込むと、椅子の背もたれに両手をついた。
逃げ場はない。
耳元にかかる熱い吐息。
うなじの産毛が逆立つほどの、圧倒的なオスの気配。
「この指輪は、君があらゆる事象に動じない『完璧な秘書』であることを証明するための枷だ」
大きな手が、私のブラウスの第一ボタンあたりを指でなぞる。
「だが、どうだ? 最近、この指輪はいつも冷たい。……君の身体が、私の接近に悲鳴を上げている証拠だ」
「それは……空調の設定温度の問題かと」
「屁理屈を」
西園寺の指が、不意に私の耳朶を甘噛みした。
「っ……!」
「感じているのか? 香月」
「いいえ。……不快、です。直ちに止めてください」
「嘘だ」
彼は私の左手を取り、薬指の銀色のリングに唇を寄せた。
金属の冷たさと、彼の唇の熱。
その温度差に、脳髄が痺れるような錯覚を覚える。
「君の理性がどれほど否定しようと、この指輪と君の身体は正直だ」
私は奥歯を噛みしめる。
これはハラスメントだ。あるいは、彼特有の歪んだマネジメント手法。
感情を捨てろ。事実だけを見ろ。
しかし、私の太ももの内側が、じわりと熱を帯びていくのを止められない。
-----
第二章 業務命令の檻
「社長室の奥にある『資料室』へ来い。極秘資料の整理だ」
インターフォン越しの指示は、いつも唐突だ。
私はスカートの皺を正し、パンプスの音を殺してその部屋へ向かった。
扉を開ける。
そこは資料室などではなかった。
壁一面が防音材で覆われた、窓のない密室。
中央には、場違いなほど大きな革張りのソファだけが置かれている。
「社長、ここは……」
「私の私室だ。そして、ここから先は『特別業務』となる」
カチャリ。
背後で鍵のかかる音がした。
西園寺が、獲物を追い詰める捕食者の目で私を見下ろしている。
「香月、服を脱げ」
「……はい?」
思考が一瞬停止する。
「聞き間違いではありません。その指示の業務的妥当性を提示してください」
「契約書第1条。『社長の個人的な要望を含む、あらゆる指示に最高のパフォーマンスで応えること』」
彼は薄く笑い、歩み寄ってくる。
「君はサインしたはずだ。全財産とキャリアを賭けて、私に忠誠を誓うと」
「それは……しかし、倫理規定に」
「この部屋に倫理などない。あるのは支配と被支配だけだ」
彼の手が私の腰に伸び、強引に引き寄せられる。
硬い胸板に押し付けられ、抵抗する間もなく唇が塞がれた。
「んっ……ふ、ぁ……っ!」
濃厚なキス。
舌が口内を蹂躙し、私の理性という名の防壁を溶かしていく。
唾液が混じり合う水音が、静まり返った密室に響く。
いやらしい、粘度のある音。
「んぅ……しゃ、ちょ……」
息継ぎのために離れた唇から、銀色の糸が引く。
「名前を呼べ。今は『社長』ではない」
「西園寺……さま……っ」
「いい子だ」
彼は満足げに目を細めると、私のブラウスを一気に引き裂いた。
ボタンが弾け飛ぶ音が、理性の崩壊を告げる号砲のように響いた。
「あっ……!」
露わになった肌に、冷房の風と、それ以上に熱い彼の視線が突き刺さる。
指輪が、凍りつくほどに冷たくなっていた。
私の身体は震えている。恐怖ではない。
これは、渇望だ。
-----
第三章 崩壊する理性
「君のその『能面』のような冷静さが、いつ崩れるのか見たかった」
西園寺は私をソファに押し倒すと、私の太ももの間に膝を割り込ませた。
スカートが捲れ上がり、露わになったガーターベルトに彼の指が這う。
「や、めて……これ以上は、契約違反……」
「契約? 違うな。君は望んでいる」
彼の指が、私の秘められた最奥に触れた。
「ひっ!」
声にならない悲鳴。
「見ろ。こんなに濡れている。君の『感情遮断』機能は、すでに故障しているようだ」
「ちが、う……これは、生理現象で……」
「まだ言うか」
彼は私の否定を許さないかのように、自身の熱く硬直した欲望を押し当ててきた。
「っ……!」
限界まで張り詰めた一物が、私の湿り気を帯びた入り口をこじ開ける。
入ってくる。
異物が、私の中を侵食していく。
「あ、ああっ! 入っ……てる……!」
「力を抜け。私を受け入れろ、麗」
名前を呼ばれた瞬間、頭の中で何かが切れた。
業務。命令。契約。
そんな言葉がすべて吹き飛び、ただ快楽だけが脳を白く染め上げる。
「あ、あぁっ! 西園寺さま、もっと、奥……!」
「そうだ。その顔だ。その乱れた顔が見たかった」
彼は激しく腰を打ち付ける。
パン、パン、と肌と肌がぶつかる音が、いやらしく響く。
突き上げられるたびに、私の身体は弓なりにしなり、快感の波に溺れていく。
私の内壁は彼を締め付け、貪欲にその熱を求めた。
もう、秘書としての私はいない。
ただの雌として、彼に貫かれることを悦んでいる。
「麗、愛している……君のその、壊れた姿を」
彼の低音の囁きとともに、最奥に熱い飛沫が放たれた。
身体の芯が溶け出し、視界が真っ白に弾ける。
-----
第四章 共犯の聖域
事後の気配が漂う密室。
乱れた衣服のまま、私は西園寺の腕の中に力なく横たわっていた。
呼吸はまだ荒く、汗ばんだ肌が触れ合う感触が、現実味を帯びている。
「……私は、君を壊したかった」
西園寺が、私の汗で張り付いた髪を優しく撫でながら呟く。
「君の完璧な『無感情』に惹かれていた。だが、それを汚し、私だけのものにしたいという欲望に勝てなかった」
彼は自嘲気味に笑う。
「君はもう、以前のような完璧な機械人形には戻れない。私が、君の人間性を引きずり出してしまったからだ」
それは、懺悔のように聞こえた。
自分が作り上げた最高傑作を、自らの手で破壊した創造主の嘆き。
けれど。
私は胸の奥から湧き上がる、奇妙な温かさを感じていた。
今まで「業務」という箱に押し込め、見ないふりをしてきた感情。
それが今、奔流となって溢れ出している。
「……違います、西園寺さま」
私は震える手で、彼の頬に触れた。
「君は……私を恨んでいるか?」
「いいえ」
涙が一筋、頬を伝う。
それは悲しみの涙ではなく、解放の涙だった。
「あなたは私を壊したのではありません。……解放してくださったのです」
私は彼の首に腕を回し、自ら唇を重ねた。
今まで受け身だった私が、初めて見せる能動的な愛撫。
「私はずっと、この檻の中であなたに触れられるのを待っていた……そんな気がします」
「麗……」
「もっと、私を茶苦茶にしてください。この部屋から、二度と出られないくらいに」
私の瞳に宿るのは、かつての冷徹な光ではない。
ドロドロとした、独占欲と依存の色。
彼の欲望が私を狂わせたのではない。
私たちはずっと、互いの狂気を求めていたのだ。
ふと、左手を見る。
今まで氷のように冷たかった指輪が、今はじんわりと熱を帯び、紅く明滅していた。
それは、私が彼を受け入れ、彼もまた私に囚われた証。
「あぁ……愛している、麗。君は永遠に私のものだ」
「はい。私はあなたの秘書であり、共犯者です」
彼は再び私を押し倒す。
オフィスはもはや仕事場ではない。
私たちだけの、歪で甘美な聖域となった。
外の世界など、もうどうでもいい。
この熱に溶けて、堕ちていけるなら。