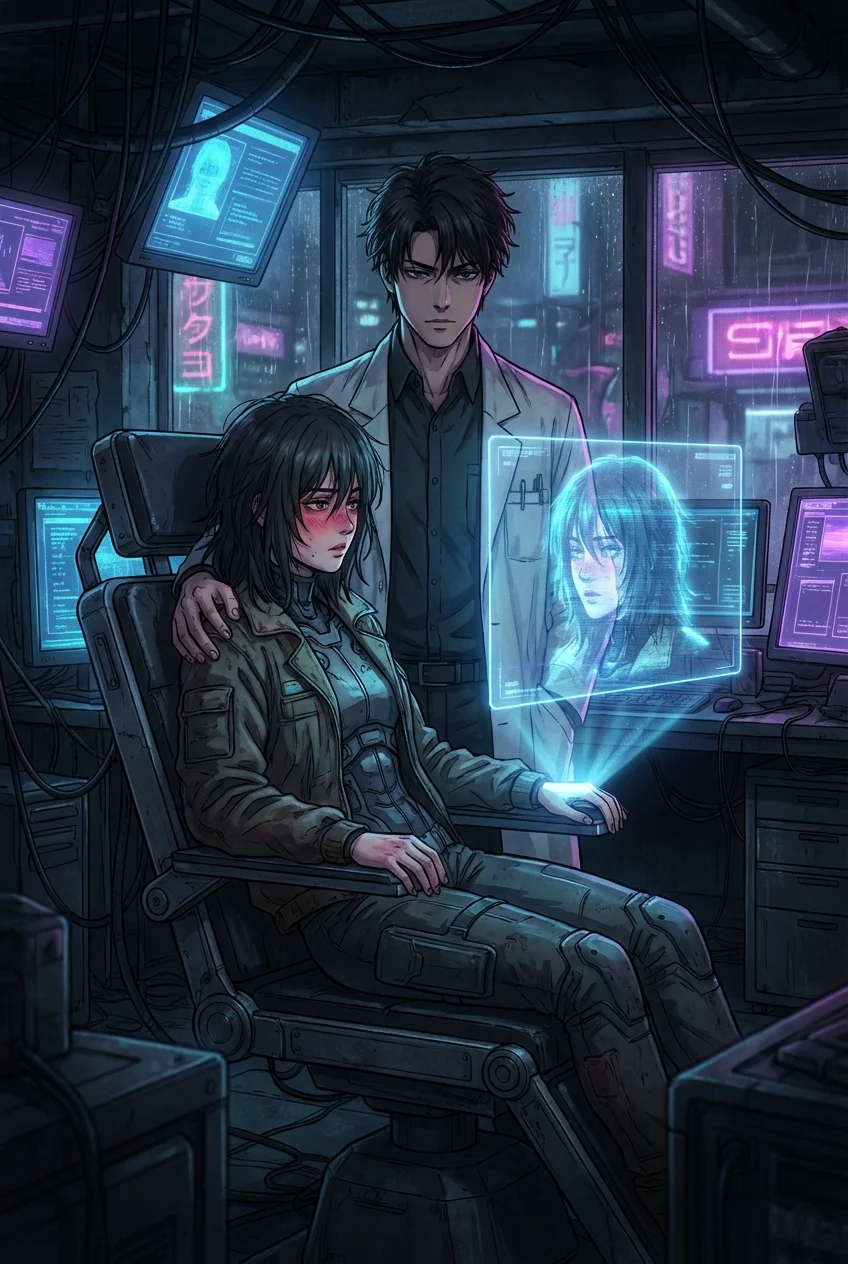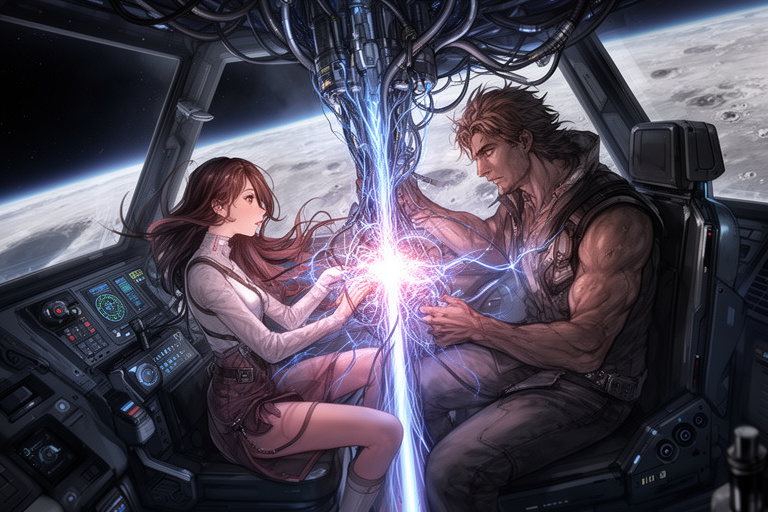第一章 氷の女王の亀裂
深夜二時。都市の喧騒は眠りにつき、雨音だけがオフィスの窓を叩いている。
「……はぁ」
静寂に包まれたフロアで、佐伯玲子(さえき れいこ)は小さく溜息をついた。
三十四歳、マーケティング部部長。
社内では『氷の女王』と恐れられる彼女は、一分の隙もない完璧なメイクと、鋭いヒールの音で武装している。
だが今、その鎧は限界を迎えていた。
重なるトラブル、理不尽な役員の要求。
偏頭痛がこめかみを締め付け、視界が歪む。
「……まだ、残ってたんですか?」
背後から聞こえた声に、玲子は肩を跳ねさせた。
振り返ると、そこには新入社員の神崎蓮(かんざき れん)が立っていた。
二十三歳。人懐っこい笑顔と、大型犬のような雰囲気で女性社員に人気のある男。
けれど玲子にとっては、未熟で手のかかる部下に過ぎない。
「神崎くん。……ええ、少しね。あなたは?」
「俺もです。これ、差し入れ」
彼がデスクに置いたのは、ホットココアだった。
湯気と共に甘い香りが立ち上り、玲子の張り詰めた神経をかすかに緩ませる。
「……ありがとう。でも、もう帰りなさい」
「部長こそ。顔、真っ青ですよ」
拒絶しようとした玲子の言葉を遮り、蓮がデスクの向こうから回り込んでくる。
距離が、近い。
普段の「無害な後輩」の顔ではない。
ふわりと鼻腔をくすぐる、雨とムスクが混じったような雄の匂い。
「……ちょっと、近いわよ」
「強がらないでくださいよ、玲子さん」
心臓がドクリと跳ねた。
『部長』ではなく、名前で呼ばれた。
「肩、ガチガチじゃないですか」
大きな手が、玲子の華奢な肩を掴む。
熱い。
服の上からでも火傷しそうなほどの体温が、冷え切った玲子の肌に侵食してくる。
「やめ……」
「ここ、気持ちいいんでしょう?」
親指が、首筋のツボを容赦なく抉る。
「あ……っ!」
予期せぬ快感に、玲子の口から甘い呼気が漏れた。
その瞬間、オフィスの空気が変質した。
第二章 反転する優位性
「いい声ですね……もっと聞かせて」
蓮の声は、昼間の明るいトーンとは別人のように低く、掠れていた。
マッサージという名目は、瞬く間に崩れ去る。
肩を揉んでいた手は、いつの間にか鎖骨をなぞり、ブラウスの第一ボタンへと伸びていた。
「神崎、くん……だめ、ここは会社よ……」
「誰もいませんよ。警備員も、もう巡回を終えました」
耳元で囁かれる吐息。
熱を帯びた唇が、耳殻を甘噛みする。
「んぅ……っ、あっ!」
背筋を電流のような痺れが駆け抜けた。
抗わなければならない。
私は上司で、彼は部下だ。
こんなことが知られたら、築き上げてきたキャリアが崩壊する。
理性が警鐘を鳴らす。
だが、身体は正直だった。
過度なストレスと疲労で弱りきった精神は、目の前の「癒やし」という名の快楽に縋りつこうとしている。
「部長、震えてますよ」
「ちが……これは……」
「嘘つき」
蓮が冷笑を浮かべ、玲子をデスクに押し付けた。
書類がバラバラと床に散らばる音が、背徳感を煽る。
「昼間はあんなに偉そうに命令するのに、今はこんなに可愛い顔して……」
彼の手が、タイトスカートのスリットから滑り込む。
ストッキング越しの摩擦熱が、太ももの内側を焼き焦がしていく。
「や、あ……っ! そこ、は……!」
「濡れてますよ、玲子さん。僕の指が欲しいって、身体が言ってる」
巧みな指使い。
彼は玲子の弱点を知り尽くしているかのようだった。
敏感な場所を執拗に攻め立てられ、玲子の瞳から涙が滲む。
「お願い、許して……」
「何を許すんです? 止めて欲しいんですか? それとも……」
蓮の指が、秘められた花園の入り口を割り開く。
「もっと、滅茶苦茶にして欲しい?」
「あぁっ! ……欲しい、の……っ!」
理性が決壊した。
第三章 蜜の味
「よくできました」
蓮が満足げに微笑み、玲子の唇を奪う。
深い、深い接吻。
唾液が混じり合う濡れた音が、静まり返ったオフィスに響き渡る。
舌が絡み合い、酸素を奪われ、玲子の頭の中は真っ白に染まっていく。
「んんっ……ぷはっ、……はぁ、はぁ……」
酸素を求めて喘ぐ玲子の胸元は、既にはだけていた。
露わになった白い肌に、蓮が容赦なく吸い付く。
「あっ、あとが付いちゃう……!」
「付ければいい。明日、会議があるんでしょう? その間ずっと、服の下のこれを感じててください」
独占欲に満ちた言葉。
それが、玲子の奥底に眠っていたマゾヒズムを刺激する。
(私、こんな風にされたかったんだ……)
誰かに支配され、責任も重圧も忘れて、ただ快楽に溺れたかった。
「入れますよ……玲子さん」
準備を整えた蓮が、玲子の両足を大きく開かせる。
デスクの端に腰掛けさせられ、無防備に晒された秘所。
そこに、熱く脈打つ彼の楔(くさび)があてがわれる。
「あ……熱い、おおきい……っ」
「力抜いて。……全部、受け入れて」
ぬぷ、と湿った音を立てて、侵入が始まる。
きつきつの肉壁を押し広げ、最奥を目指して突き進む異物感。
苦しいほどの充満感に、玲子は仰け反った。
「あぁぁーーっ! はいっ、入っ……てる……っ!」
「くっ、玲子さんの中、凄く吸いついてくる……」
完全に結合した瞬間、二人の吐息が重なる。
そこからは、獣のような交わりだった。
激しく打ち付けられる腰。
揺れるデスク。
肌と肌がぶつかり合う音。
「ああっ、そこ! だめっ、深いっ、こわれるぅ!」
「壊れちゃえばいい。あんたの理屈も、プライドも、俺が全部溶かしてやる!」
「あっ、ああっ、いくっ、イくぅっ!」
突き上げられるたびに、脳髄が痺れるような快感がスパークする。
何度も絶頂を迎え、身体の力が抜けても、蓮は止まらない。
むしろ、その愛撫はより激しさを増していく。
「まだ逃がしませんよ。……朝まで、たっぷりと可愛がってあげますから」
悪魔のような、けれど愛おしい年下の男。
玲子は涙で潤んだ瞳で彼を見つめ、自らその背中に腕を回した。
「……もっと、ちょうだい……蓮……」
それは、氷の女王がただの女へと堕ちた、敗北宣言だった。
第四章 夜明けの共犯者
窓の外が白み始めていた。
乱れた衣服を整え、玲子はけだるい身体を椅子に沈めている。
机の上は綺麗に片付けられているが、空気にはまだ情事の余韻——甘く生温かい匂いが漂っていた。
「……コーヒー、飲みますか?」
何事もなかったかのように、蓮が新しいカップを差し出す。
けれどその首筋には、玲子が爪を立てた痕が赤く残っていた。
「……ええ、もらうわ」
カップを受け取る指先が触れ合う。
ただそれだけで、身体の奥が疼くのを玲子は感じた。
もう、昨日までの関係には戻れない。
「今日の会議、頑張ってくださいね。『部長』」
蓮がニヤリと笑い、耳元で囁く。
「もし辛かったら、いつでも俺を呼んでください。トイレでも、倉庫でも、どこでも慰めてあげますから」
玲子は頬を紅潮させながら、しかし毅然とした眼差しで彼を睨み返した。
「……生意気ね。覚悟しておきなさい」
その言葉は拒絶ではなく、甘美な契約の証。
オフィスという戦場で、二人だけの秘密の遊戯が幕を開けたのだ。
(終)