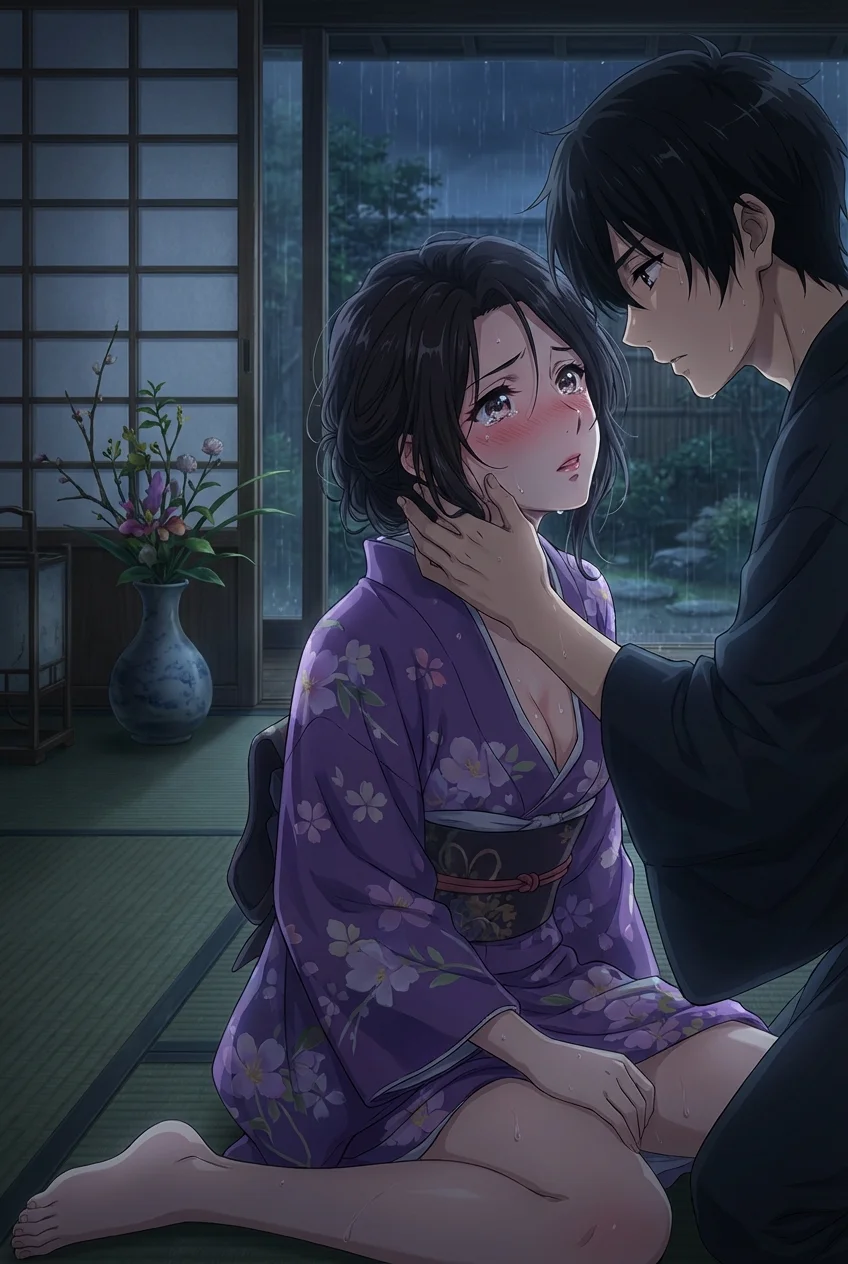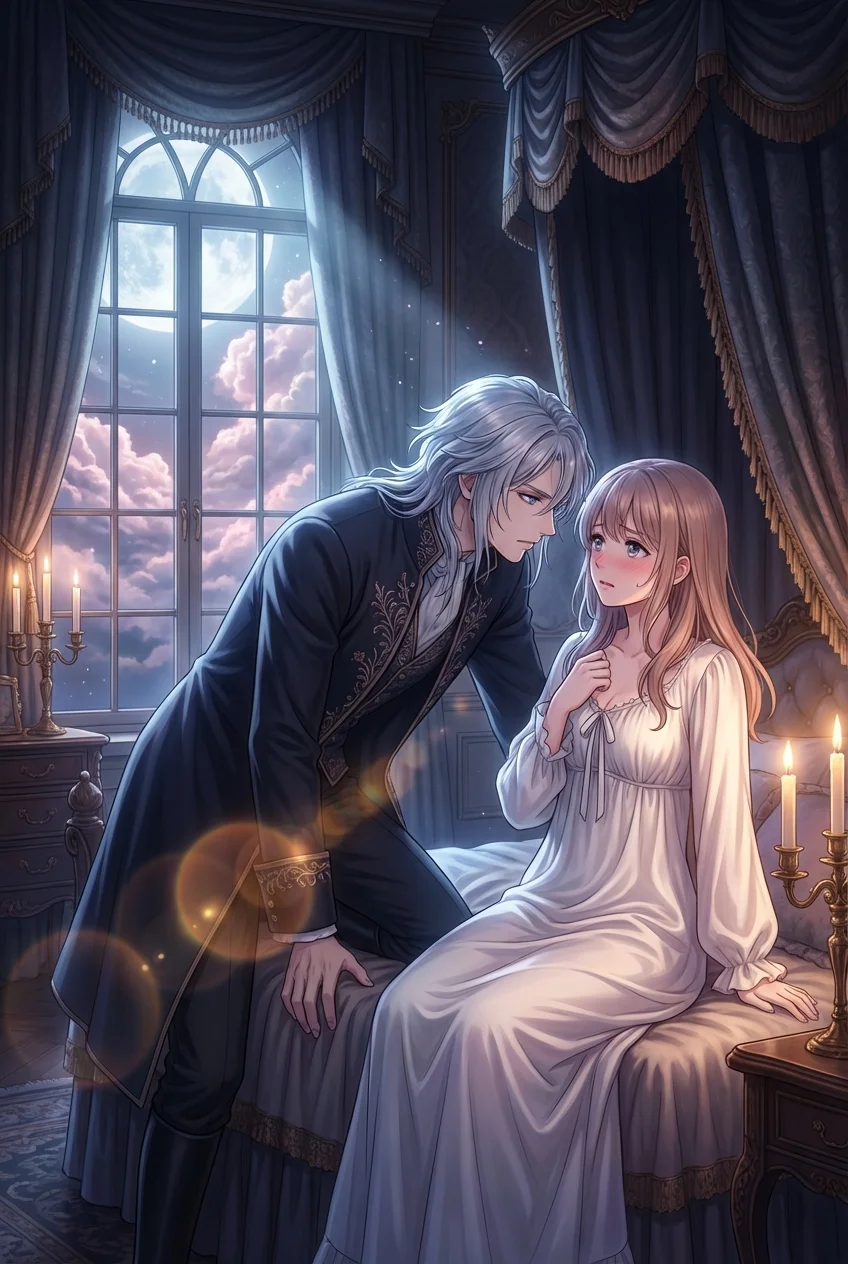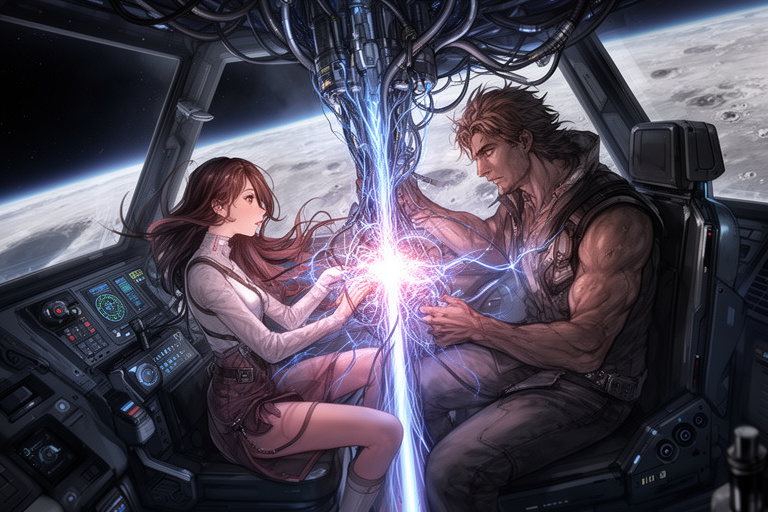「君の痛みだけが、私の凍った血を溶かす唯一の炎だ」
その男は、愛を囁くようには言わなかった。
まるで飢えた獣が、最後の晩餐を前に祈りを捧げるかのように、私の耳元で低く唸ったのだ。
第一章 氷の檻と過敏な生贄
北の果て、人間が生きることを拒絶された極寒の地。
そこに聳える黒曜石の城は、主である辺境伯、ヴァレリウス・フォン・ドラグノフその人を体現していた。
「氷血公」
そう呼ばれる彼は、生まれつき体温を持たず、痛みも、味も、快楽さえも感じない「無感覚の呪い」を受けていると噂されていた。
対する私は、生家である男爵家から「不良品」として売り飛ばされた娘、エララ。
私には、常人の何倍も強く刺激を感じ取ってしまう「感覚過敏」という奇病があった。
布が擦れるだけで皮膚が焼けつくように痛み、大きな音は脳を直接殴られるような衝撃となる。
世間からは「触れられぬ聖女」と皮肉られ、腫れ物扱いされてきた私。
そんな私が、何も感じない男のもとへ嫁ぐことになったのは、運命という名の悪意としか思えなかった。
初夜の寝室。
窓の外では猛吹雪が狂ったように暴れまわっている。
だが、この部屋の中は奇妙なほど静寂に包まれていた。
暖炉の火だけがパチパチと爆ぜる音。
その微かな音さえ、私の過敏な耳には雷鳴のように響く。
「……怯えているのか?」
重厚な扉が開き、ヴァレリウスが入ってきた。
銀色の髪、氷河のような青い瞳。
美しいが、そこには「生」の温かみが一切感じられない。
彼はゆっくりと私に歩み寄る。
軍靴が石畳を叩く音が、私の心臓の鼓動と重なり、不快なリズムを刻む。
私は反射的に身を引いた。
これまでの人生、誰かに触れられることは苦痛でしかなかったからだ。
しかし、彼は躊躇なく私の腕を掴んだ。
「ひっ……!」
悲鳴が漏れる。
彼の指は、まるで死体のように冷たかった。
だが、次の瞬間、ありえないことが起きた。
彼が私に触れた箇所から、私の神経を通じて、彼自身の「感覚」が逆流してきたのだ。
いや、違う。
「……ああ、これが『熱』か」
ヴァレリウスが陶酔したように目を細める。
彼は私の腕を握りしめる力を強めた。
私にとっては骨がきしむほどの激痛。
だが、その痛みを感じているのは私だけではなかった。
彼と私の神経が、目に見えない管で繋がれたような感覚。
私の痛みを、彼が「味わって」いる。
「素晴らしい……君の肌は、こんなにも柔らかく、壊れやすいのか」
彼は私の首筋に顔を埋めた。
冷たい唇が、脈打つ動脈の上に押し当てられる。
「君が感じる全てが、私の身体に流れ込んでくる。君という器を通して、私は初めて世界を感じられるんだ」
それは愛の告白ではなかった。
生存本能に基づく、絶対的な捕食宣言だった。
第二章 侵食する共鳴
逃げ場など、最初からなかった。
天蓋付きの巨大なベッドに押し倒され、私は彼の冷たい体の下で喘いでいた。
「待っ……て、あ、あぁっ!」
彼の手が、私のドレスを引き裂く。
絹が裂ける音、肌に触れる冷気、彼の荒い呼吸。
そのすべてが、私の過敏な神経を針で刺すように刺激する。
普通の人間なら「少し乱暴な愛撫」で済む行為も、私にとっては感覚の奔流となって脳髄を焼き尽くす。
「もっとだ、エララ。もっと感じろ」
ヴァレリウスの瞳が、青白く発光しているように見えた。
彼は飢えていた。
生まれてから一度も満たされることのなかった感覚への渇望。
それが今、私の身体を通して爆発している。
彼が私の胸元に冷たい指を這わせる。
先端が尖った氷の欠片でなぞられているような、鋭い刺激。
ビクリ、と私の背が弓なりに反る。
その反応を見て、彼は喉を鳴らした。
「そうだ、その震えだ。君が震えるたびに、私の指先に電撃が走る」
彼は実験を楽しむ科学者のように、あるいは壊れやすい楽器を調律するように、私の身体のあちこちを執拗に攻め立てた。
敏感すぎる耳朶を甘噛みされ、私は言葉にならない声を漏らす。
その声さえも、彼にとっては極上の音楽なのだ。
「ダメ、おかしく……なる、頭が、溶けちゃう……!」
「溶かせ。理性など邪魔なだけだ」
彼の手が、許されない場所へと滑り込む。
熱く濡れた秘所。
そこはもう、彼を待ち受けるように蜜を溢れさせていた。
彼がそこを指先で弄ると、私の視界が真っ白に弾けた。
「あ、あ゛ぁぁっ! や、め……!」
「止めない。君が果てる瞬間、私がどれほどの快楽を得られるか……試させてくれ」
それは拷問に近かった。
けれど、恐ろしいことに、その拷問は甘美な猛毒を含んでいた。
彼と感覚がリンクしているせいで、彼が私の身体から感じ取っている「歓喜」や「征服欲」までもが、私の脳内に流れ込んでくるのだ。
彼が私を弄ぶことで得る快感。
それを私が感じ、その私の快感を彼がまた吸い上げる。
無限のフィードバックループ。
私は自分の意思とは無関係に、快楽の濁流に飲み込まれていった。
「あ、熱い、熱いよぉ……ヴァレリウス様ぁ……!」
「いい子だ。私の名前を呼べ。君の存在の全てを、私に刻み込め」
彼が私の中に入り込んできた瞬間、世界が裏返った。
肉体的な結合だけではない。
魂の境界線が溶解し、二つの精神がドロドロに混ざり合う。
異物が体内を抉るような重い感覚。
しかし、それは同時に、欠落していたパズルのピースが埋まるような、恐ろしいほどの充足感をもたらした。
「ぐっ……! なんて、熱さだ……!」
彼が唸り声を上げ、私の肩に爪を立てる。
私の内壁が彼を締め付けるたびに、彼もまた、私を締め上げるように抱きしめる。
苦しい。
けれど、離れられない。
呼吸ができないほどの口づけ。
唾液が混じり合い、酸素が奪われ、意識が明滅する。
死んでしまう。
このままでは、快楽で脳が焼き切れ、廃人になってしまう。
そう思うのに、身体は正直に彼の熱を求め、腰を揺らしてしまう。
「もっと……奥、まで……!」
私が懇願すると、彼は嗜虐的な笑みを浮かべた。
「ああ、望み通りにしてやる。君が壊れるまで、決して離さない」
第三章 永遠に終わらぬ絶頂
夜は、永遠に続くかと思われた。
何度も絶頂を迎え、身体はとうに限界を超えていた。
指一本動かせないほど疲弊しているのに、彼は許してくれない。
「まだだ。まだ眠るな、エララ」
耳元で囁かれる悪魔の命令。
彼は私の意識を現世に繋ぎ止めるように、敏感になりすぎた胸の先端を、冷たい舌で転がした。
「ひぃっ……! もう、無理、ゆるして……っ!」
「許さない。君が眠れば、私はまたあの孤独な『無』の世界に戻らなければならない。そんなことは耐えられない」
彼の執着は、愛などという生易しいものではなかった。
それは生存のための寄生。
彼にとって、私は唯一の「世界への扉」なのだ。
この扉が閉ざされれば、彼は死んだも同然になる。
だから、彼は必死に私を刺激し続ける。
私が痛みや快楽で泣き叫び、生を実感している間だけ、彼もまた生きることができるから。
「君は私の臓器だ。私の神経だ。私の全てだ」
彼の腰が再び激しく打ち付けられる。
最奥を小突かれるたびに、脳髄から火花が散る。
もう、どこまでが私の感覚で、どこからが彼の感覚なのか分からない。
彼の圧倒的な支配欲が、私の心を満たしていく。
「愛されたい」と願っていた孤独な少女は、今、「所有される」という究極の形でその願いを叶えられてしまった。
「あ、あ、イクッ……! また、イッちゃうぅ……!」
「いけ。何度でも。その度に私は、君の命の輝きを啜ろう」
波状攻撃のように押し寄せる快感。
終わりのない波。
息継ぎさえ許されない溺没。
私の目から涙が溢れ、枕を濡らす。
それは悲しみの涙ではなく、許容量を超えた感情が溢れ出した証拠だった。
視界が揺らぐ。
天井のシャンデリアが、星屑のように散らばって見える。
意識が飛びそうになるたびに、彼は私の唇を噛み、痛みで引き戻す。
「私を置いていくな。ここにいろ。私の中で、ずっと燃えていろ」
彼の楔(くさび)が、私の存在そのものを縫い止める。
とぷん、と。
私は深い、深い沼の底へと沈んでいった。
そこは、冷徹な公爵が支配する、熱くて甘い、地獄の底。
もう、二度と浮き上がることはできない。
彼の背中に爪を立て、私は哭いた。
獣のように。
彼のために感覚を捧げる、生きた供物として。
窓の外の吹雪は止まない。
だが、氷の城の中は、狂気じみた熱気と、甘い腐敗臭にも似た情事の匂いで満ちていた。
この夜が明けても、私の地獄は終わらない。
彼が私を手放すことは、死ぬまで――いや、死んで魂になっても、ないのだから。
「愛しているよ、私の感覚(エララ)」
薄れゆく意識の中で聞いたその言葉は、世界で最も甘く、重い呪いのようだった。