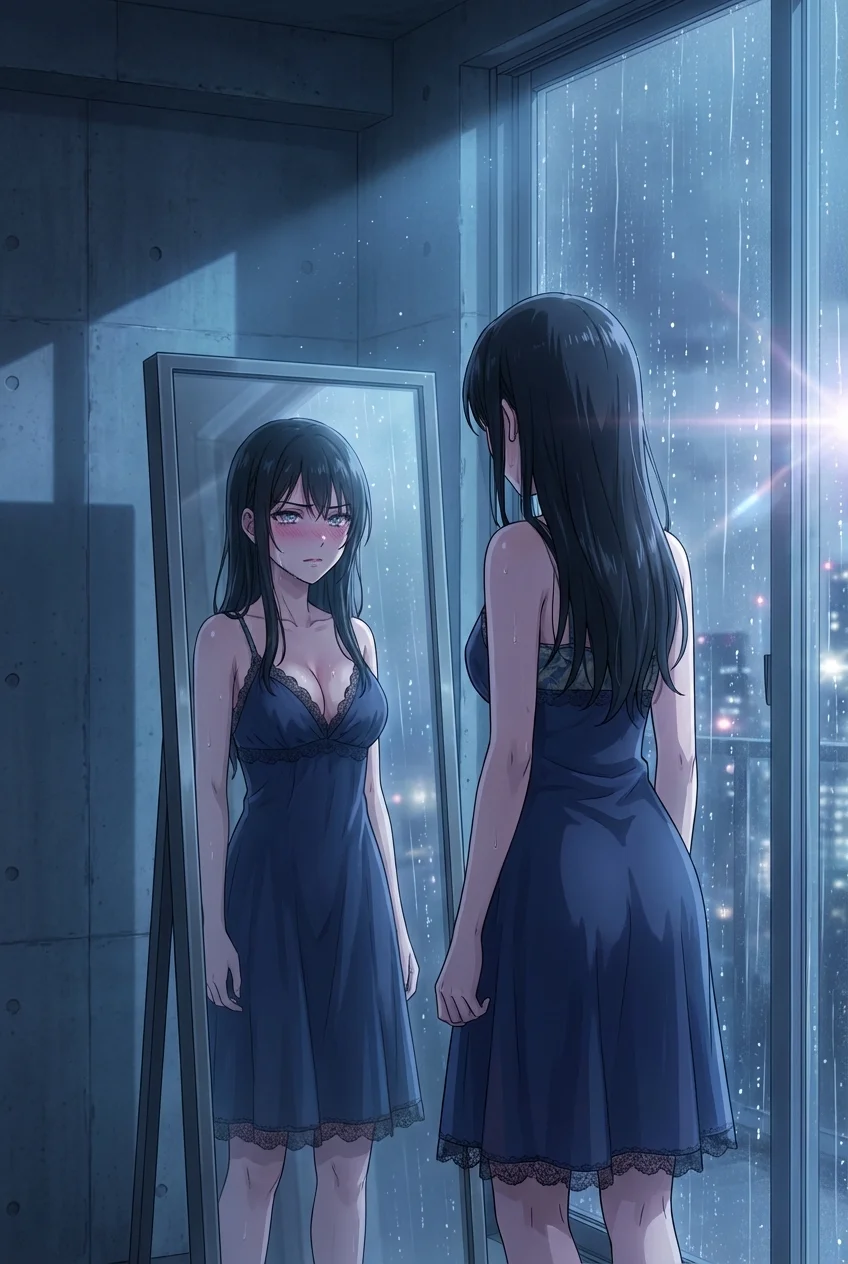第一章 無臭の帝王と調香師
「……澪(みお)。今日の『香り』を報告しろ」
重厚なオーク材の扉が閉ざされた瞬間、その命令は下される。
都心を見下ろす高層ビルの最上階。空調は完璧に制御され、塵ひとつない無機質な空間。
この部屋の主であり、巨大コングロマリットを統べる冷徹な若き帝王、九条礼二(くじょう れいじ)が、革張りのソファに深く身を沈めていた。
私は震える指先で、自身のシャツのボタンに触れる。
「は、はい……。今日は、雨上がりのアスファルトと、少し焦げたような珈琲の残り香……それと、あなたの選んだシダーウッドのベースノートが……」
私の言葉など、彼にとっては記号に過ぎないはずだ。
けれど、彼は獲物を狙う猛禽のような瞳で私を射抜くと、手招きをした。
「近づけ。言葉だけでは足りないと言ったはずだ」
私は契約妻。
表向きは、新進気鋭の調香師として彼の事業を支えるパートナー。
だが、本当の契約内容は違う。
九条礼二は、ある事故の後遺症で『嗅覚』と『味覚』を失っていた。
彼が世界の色を取り戻す方法はただ一つ。
他者の、それも特定の波長を持つ人間の『昂り』を媒介にすること。
そして、極度の嗅覚過敏(ハイパーオスミア)に苦しみ、社会生活すらままならなかった私、澪こそが、彼にとって唯一の『フィルター』だったのだ。
「失礼、します……」
膝をつき、彼の足元に傅(かしず)く。
礼二の大きく冷たい手が、私の首筋に滑り込んだ。
脈打つ頸動脈を確かめるように、親指がゆっくりと肌を擦る。
「いい匂いだ。お前が恐怖と期待で発熱すると、俺の世界にも色がつく」
彼の声は低く、鼓膜を直接撫でられるような響きを持っている。
冷たいはずの指先が触れた場所から、火花のような熱が散る。
「今日は接待で、質の悪い香水を浴びるほどつけた男と同席した。鼻が腐りそうだ……いや、俺には匂いなどしないんだったな」
自嘲気味に笑うと、彼は乱暴に私の腰を引き寄せた。
「浄化してくれ、澪。俺のために、その過敏な神経をすべて開け」
拒否権はない。
私の才能を買い取り、多額の借金を肩代わりし、この『無臭の檻』で守ってくれているのは彼なのだから。
それに何より、私はこの瞬間を待っている。
社会という雑音の中で窒息しそうな私にとって、彼に翻弄され、理性を手放す瞬間だけが、唯一の救済なのだと気づいてしまっていた。
第二章 晩餐会の裏側で
週末のチャリティ・ガラは、絢爛豪華という言葉が相応しい夜だった。
シャンデリアの煌めき、行き交う高価なドレス、そして混じり合う無数の香水。
普通なら気絶してしまいそうな匂いの洪水を、私は必死に堪えていた。
隣に立つ礼二の腕にしがみつく。
彼は完璧な仮面を被り、社交界の紳士として振る舞っていた。
「大丈夫か、マイ・ディア」
周囲には気遣う夫に見えただろう。
けれど、耳元で囁かれた言葉は違った。
「我慢しろ。今のこの不快感をよく覚えておけ。後で俺が塗り替えてやる」
テーブルに着くと、彼はテーブルクロスの下で、私の太腿に手を滑り込ませた。
「っ……!」
息を呑む私に、向かいの貿易商が怪訝な顔をする。
礼二は涼しい顔でワイングラスを傾けた。
「妻は少々、貧血気味でしてね。……ああ、このヴィンテージは素晴らしい」
彼は味など分かっていないはずだ。
けれど、テーブルの下で彼の指が私の内腿の柔らかい皮膚を這い上がるにつれ、彼の瞳に光が宿っていくのが分かった。
「……ベリーの酸味と、枯葉のニュアンス。そうだろう? 澪」
「は、はい……その通り、です……」
私の感覚が、彼に流れ込んでいる。
私が緊張と背徳感で身体を熱くすればするほど、彼は味覚を取り戻していく。
指先が際どい場所を掠めた。
「んっ……」
「もっとだ。もっと感じろ。お前の感覚神経が焼き切れるほど鋭敏になれば、この料理はさらに美味くなる」
彼の指は執拗だった。
直接的な行為ではない。
ただ、神経が集中する場所を、焦らすように、円を描くように撫で回す。
ドレスの布越しに伝わる熱が、私の思考を白く染めていく。
周囲の談笑が遠のき、カトラリーの音が反響する。
私はフォークを取り落とさないよう、必死に指に力を込めた。
全身の血液が、彼に触れられている一点に集まっていく。
「顔が赤いぞ。……可愛いな」
彼は残酷なほど楽しげに、私を見つめながらメインディッシュの肉を口に運んだ。
まるで、私そのものを味わっているかのように。
第三章 限界の先にある共鳴
帰宅した直後のペントハウスは、静寂に満ちていた。
ドレスを脱ぎ捨てさせられ、私は広いベッドの上に放り出される。
「さあ、続きだ」
礼二はネクタイを緩めながら、私に覆いかぶさった。
もはや優雅な紳士の仮面はない。
飢えた獣のような、それでいて冷徹な観察者の目。
「あ、あの……少し、休ませて……」
「駄目だ。感覚が鋭敏になっている今こそが、最良の時間だ」
彼は私の抵抗を封じると、首筋、鎖骨、そして胸元へと、熱い楔のような口づけを落としていく。
愛撫は甘く、けれど決して核心には触れない。
「焦がれるだろう? 欲しいなら、声に出して乞え」
彼の指が、私の身体の輪郭をなぞる。
敏感すぎる嗅覚が、彼から発せられるフェロモン――支配欲と独占欲の香り――を捉えてしまい、脳髄が痺れる。
「れい、じ……さん……おねがい……」
「何をだ? 具体的に言え。お前のその唇から紡がれる言葉が、俺の糧になる」
彼はわざと動きを止めた。
寸止め。
高まりきった神経が、行き場を失って悲鳴を上げる。
私は涙目で彼を見上げた。
「私を……壊して……あなたの感覚にして……」
それは、完全なる降伏宣言。
礼二の口元が嗜虐的に歪んだ。
「よく言った。……いい子だ」
その瞬間、彼のリミッターが外れた。
波状攻撃のように押し寄せる快楽の奔流。
彼は私の反応を一つも逃さず、執拗に、丹念に、理性の壁を一枚ずつ剥がしていく。
「あ、あぁっ! ……だめ、おかしく、なる……っ!」
「なれ。俺のために狂え。お前が絶頂の淵で喘ぐその匂いだけが、俺に『生』を実感させる」
私の視界が明滅する。
天井の照明が流星のように尾を引いて滲む。
熱い、熱い、熱い。
体の中を溶岩が流れているようだ。
彼の手が、私の秘められた泉を掻き回す。
甘い水音が部屋に響き、それがさらに恥辱と興奮を煽る。
「見てみろ、こんなに濡れている。……いい香りだ、澪。最高に甘い」
彼は私の耳元で囁き続け、意識が飛びそうになるたびに、鋭い刺激を与えて現実に引き戻す。
気絶することすら許されない。
永遠に続くかと思われる、昇り詰める手前の浮遊感。
「まだだ。まだ逝かせない」
「ひぐっ……、うぁ……っ!」
限界を超え、指先が痙攣し、背中が弓なりに反る。
それでも彼は止めない。
私の全てを搾り取るまで、この饗宴は終わらないのだ。
第四章 永遠の共犯者
嵐が過ぎ去った後、私は泥のようにベッドに沈んでいた。
意識の断片がようやく戻ってくる。
隣には、満ち足りた表情の礼二が横たわり、私の髪を弄っていた。
「……気分はどうだ」
「……最悪、です」
掠れた声で答えると、彼は喉の奥でくつくつと笑った。
「そうか。だが、お前はまた俺を求める」
否定したかった。
けれど、身体の芯に残る余韻が、彼の言葉を肯定している。
過敏すぎる私の世界を、彼だけが圧倒的な刺激で塗り潰し、『無』にしてくれる。
その安らぎを知ってしまった。
「俺たちは共犯だ、澪。俺はお前がいなければ味も匂いも感じない廃人。お前は俺がいなければ世界の情報量に押し潰される脆弱な蝶」
彼は私の指に絡めた自分の指に、誓いのキスを落とした。
「一生、この檻から出すつもりはない。覚悟しておけ」
それは呪いのような、あるいは至上の愛の告白。
私はその甘美な絶望に目を細め、彼の胸に顔を埋めた。
彼の匂いがする。
冷たくて、残酷で、どうしようもなく私を安心させる、私の主人の香り。
「……はい。あなただけの、共犯者でいます」
窓の外では夜が明けていく。
けれど、私たちの密やかな宴は、これからも永遠に続いていくのだ。
感覚という名の鎖で繋がれた、二人だけの世界で。