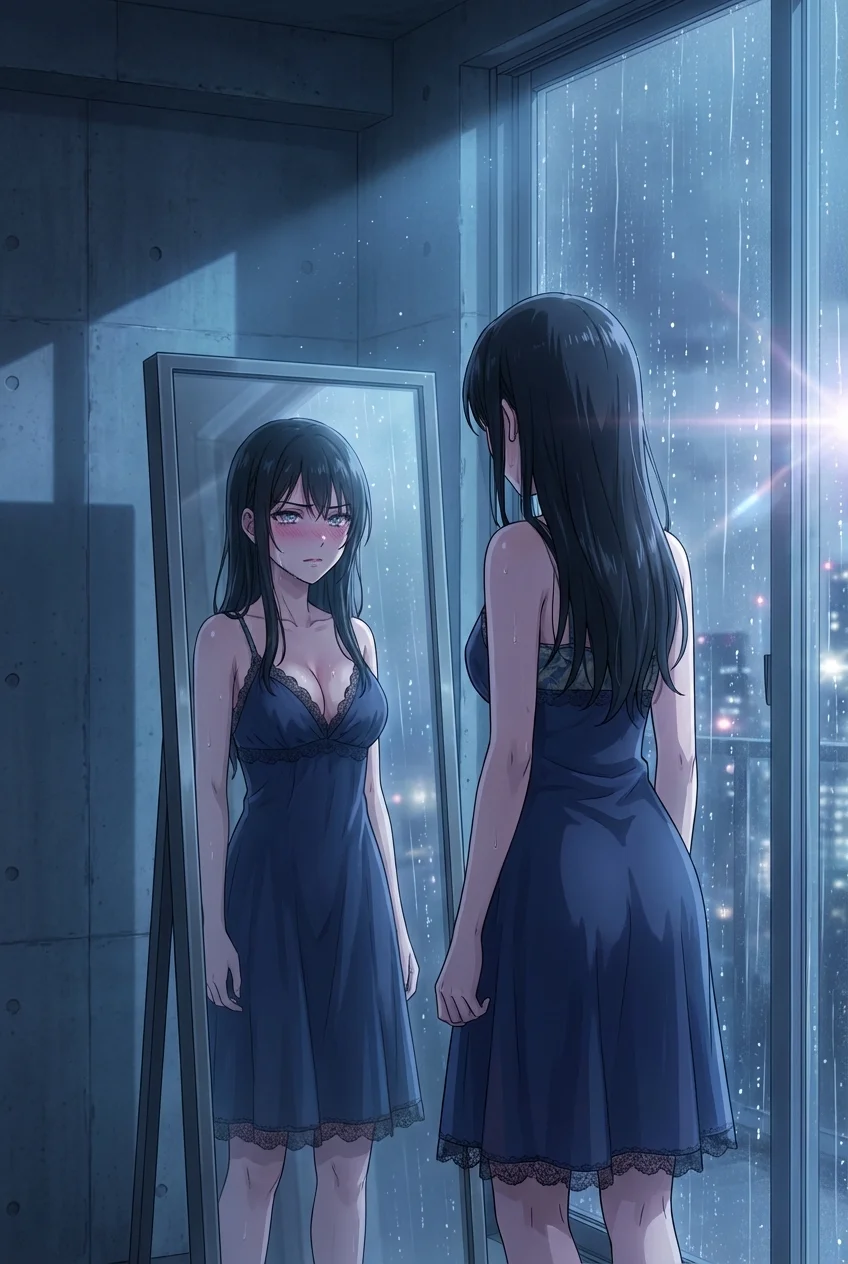第一章 仮説:高濃度魔力保有体における粘膜接触の反応値
「――動かないで。数値が……乱れる」
地下研究室特有の、カビと薬品、そして甘ったるい香油の匂いが充満している。
私は震える指先で、羽ペンを羊皮紙に走らせた。
だが、インクの滲みは、私の動揺を如実に物語っている。
目の前には、実験台(ベッド)に拘束された男。
被験体コード・アルファ。通称、カエレン。
この大陸で絶滅したはずの『竜人族』の生き残りであり、私の研究のすべてだ。
「先生。手が震えていますよ」
低い、地響きのような声が鼓膜を撫でる。
彼は両手首をミスリル合金の手枷で固定されながら、余裕綽々の笑みを浮かべていた。
琥珀色の瞳。
その奥で揺らめくのは、捕食者の光だ。
「黙りなさい。これは……魔力伝導率の測定実験よ」
「へえ。俺の肌をそんなに熱心に撫で回すのが?」
「触診、と言って」
私は白衣の襟を正し、努めて冷静な声を出す。
だが、喉の奥が乾いて張り付くようだ。
彼の肌は、異常なほどの熱を帯びている。
竜人族特有の『発情期』ならぬ『排熱期』。
体内で生成される膨大な魔力が、行き場を失って暴走寸前なのだ。
本来なら、適度な魔法行使で発散させる。
だが、私は仮説を立てた。
『過剰魔力を他者の生体電流と接触させることで、より効率的な中和・吸収が可能ではないか』
要するに、私が彼に触れ、その熱を奪う。
これは学術的な探求だ。
決して、私の個人的な欲望のためではない。
「……熱い」
彼の広い胸板に手を這わせる。
指の腹に、ドクン、ドクンと、重い心音が伝わってくる。
まるで巨大なエンジンの上に手を置いているようだ。
汗ばんだ肌は吸い付くように滑らかで、触れた箇所からピリピリとした痺れが私の腕を駆け上がる。
「ん……」
カエレンがわずかに喉を鳴らした。
苦痛ではない。
甘く、低い、獣の唸り。
「そこは……魔力の集積点(ツボ)ですか?」
「ええ。胸骨の正中線に沿って、魔力回路が集中しているの」
嘘ではない。
だが、そこが同時に、彼らにとっての強烈な愛撫の急所であることも、私は文献で知っていた。
知っていて、触れている。
私の指先が乳首を掠めるたび、鋼のような筋肉がビクリと跳ねる。
その反応を見るたび、私の下腹部に重い熱が溜まっていく。
「先生……もっと強く」
「だめよ。今は表面温度の計測中だから」
「焦らすのが趣味なんですか? あんたって人は」
カエレンが鎖を引きちぎらんばかりに身をよじる。
鎖が金属音を立てて悲鳴を上げた。
彼の昂ぶりは、目に見える形となって現れている。
腰布一枚の下で、雄々しい何かが屹立し、布をテントのように押し上げているのが視界の隅に入った。
「視線、感じますよ」
「……観察記録の一環よ。勃起現象における血流の増加量を推測しているの」
「嘘つき」
カエレンが私の手首を、拘束されていない指先でそっと絡め取る。
「あんたの匂い……変わった」
「な……」
「甘い。熟れた果実みたいに……俺に食われたがってる匂いだ」
彼の言葉が、呪いのように理性を侵食する。
私は慌てて手を引っ込めようとしたが、その力は優しく、しかし絶対的だった。
「離して」
「離さない。実験なんでしょう? なら、最後までデータを取ってくださいよ」
彼は私の指を口元へ運び、舌先で、指の腹を舐め上げた。
「ひっ……!」
電流が走った。
ただ濡れた舌が触れただけではない。
高密度の魔力が、粘膜を通じて私の体内に逆流してきたのだ。
「味も……いい」
彼は恍惚とした表情で、私の指を咥え込み、吸い上げる。
ジュ、チュプ、と卑猥な水音が、静寂な研究室に響き渡る。
それはキスよりも濃厚で、交接よりも直接的な『魔力侵食』の始まりだった。
第二章 実験経過:限界閾値における理性の融解と依存性
「あ、あっ……あ……!」
私の口から、情けない声が漏れる。
指先から注ぎ込まれる彼の魔力は、熱い蜜のように血管を巡り、脳髄を痺れさせていく。
生物学的に言えば、これは『魔力中毒』の初期症状だ。
竜の魔力は、人間には強すぎる。
だが、その破壊的な快楽は、麻薬以上の依存性を持っていた。
「どうしたんです? 顔、真っ赤ですよ」
「う、るさい……これは、拒絶反応の……一種で……」
「へえ。拒絶反応で、そんなに濡れるんだ」
カエレンの視線が、私の白衣の裾、太腿のあたりを執拗に舐める。
私は思わず内股を擦り合わせた。
否定できない。
下着はすでに、自分の愛液でぐっしょりと重くなっている。
「続きをしましょう、先生。俺の熱、まだ全然下がってない」
彼は顎で、自身の下半身をしゃくった。
布越しでもわかる、怒張した熱源。
それは脈打ち、解放を求めて震えている。
「直接的な……排泄行為は、実験規定に……」
「排泄? 違うだろ。これは『共鳴』だ」
カエレンが鎖をジャラリと鳴らし、上体を起こす。
拘束されているはずなのに、なぜか追い詰められているのは私の方だ。
「俺のここが、熱くて痛いんです。先生のその……柔らかい場所で、冷やしてくれないと」
「っ……」
「ほら、見てください。先端から、魔力が漏れてる」
彼に促され、恐る恐る視線を落とす。
腰布の先端が、じわりと濃い染みを作っていた。
先走り汁ではない。
液状化した魔力だ。
その甘い芳香が鼻腔をくすぐった瞬間、私の頭の中で何かが切れた。
学術的な興味?
臨床実験?
そんな建前は、この圧倒的な『オス』の匂いの前では無力だった。
「……触診を、続行するわ」
私は震える手で、彼の腰布に手をかけた。
「いい子だ」
カエレンが喉の奥で笑う。
布を剥ぎ取ると、そこには凶悪なまでの熱源が露わになった。
赤黒く充血し、脈打つその器官は、まさに竜の首のように天を向いている。
「すごい……」
思わず感嘆の声が漏れた。
生物学者としての称賛と、メスとしての渇望が混ざり合う。
先端からは、透明な魔力液が糸を引いている。
私は吸い寄せられるように、その先端に指を這わせた。
「あぐっ……!」
カエレンが仰け反り、歯を食いしばる。
「そこ……! 敏感なんだ……もっと、擦って……」
「ここが、一番熱いのね……」
カリ、と張り詰めた亀頭の縁を指でなぞる。
そのたびに、ビクンビクンと竿が跳ね、私の手に熱い飛沫がかかる。
「先生……手だけじゃ、足りない」
「……え?」
「口で。先生のその知的な唇で、俺の全部を味わって分析してくれ」
命令ではない。
懇願。
あの傲慢な竜人族が、快楽に顔を歪ませて私に乞うている。
その事実に、背筋がゾクゾクと粟立った。
私は膝をつき、彼の股間に顔を寄せた。
熱気と共に、ムスクのような強烈な香りが立ち込める。
「……いただきます」
それは食事の挨拶か、実験開始の合図か。
私は唇を開き、熱く脈打つ先端を、ゆっくりと口内に招き入れた。
「う、おぉ……ッ!」
口に含んだ瞬間、舌が痺れた。
味蕾の一つ一つが焼かれるような刺激。
濃縮された魔力が、粘膜から直接脳へと突き抜ける。
苦しい。
太すぎる。
喉の奥まで突き刺さってくる。
けれど、美味しい。
私は夢中で舌を絡めた。
裏筋を舐め上げ、鈴口を吸い、睾丸の重みを掌で確かめる。
口腔内が彼の体温と魔力で満たされる感覚。
「そう……そこ……! 舌を、もっと強く……!」
カエレンの手が私の頭を掴み、腰を突き上げる。
ガクガクと研究台が揺れる。
「んっ、んーッ! じゅる、ちゅぷっ……!」
私は彼の動きに合わせて、頭を前後に振った。
唾液と魔力液が混ざり合い、顎を伝って白衣を汚していく。
もう、ただの貪り合いだった。
彼の熱を、私が飲み込む。
私の理性を、彼が犯す。
「だめだ、もう……出る……ッ! 先生、飲んでくれ……俺の魔力を、全部ッ!」
「んむッ!?」
彼の腰が大きく跳ねた。
喉の奥に、熱湯のような奔流が撃ち放たれる。
ドクドクと、絶え間なく注ぎ込まれる白濁した魔力。
私はむせ返りそうになりながらも、その一滴すら逃すまいと喉を鳴らして飲み干した。
胃の中に熱い塊が落ちる。
身体中の細胞が歓喜の声を上げる。
ああ、これが『共鳴』。
これが、私が求めていた真理。
第三章 結論:被験体への恒久的な従属とパラダイムシフト
「はぁ……はぁ……」
荒い呼吸だけが、部屋に響いている。
カエレンは脱力し、研究台に沈み込んでいた。
私もまた、床にへたり込み、口元を拭うことも忘れて彼を見上げていた。
口の中に残る、鉄と蜜の味。
全身を駆け巡る高揚感。
「……すごいデータが、取れたわ」
虚ろな目で、私は呟いた。
羊皮紙に記録することなど、もうどうでもよかった。
私の身体そのものが、最高の記録媒体になってしまったのだから。
「先生」
カエレンが、気だるげに目を開けた。
その瞳からは、先程までの凶暴な光が消え、代わりに粘着質な執着の色が宿っていた。
「味はどうでした? 俺の魔力(ナカミ)は」
「……最高純度よ。致死量に近い……快楽毒」
「そりゃよかった」
彼はニヤリと笑い、拘束されたままの手で、クイクイと私を招いた。
「でも、まだ半分も抜けてないんですよ。俺の熱」
「え……?」
「一回じゃ足りない。知ってるでしょう? 竜の性欲がどれほど底なしか」
彼の股間を見ると、萎えるどころか、再び鎌首をもたげ始めていた。
先程よりも、さらに大きく、硬く。
「ひっ……」
「次は、こっち(・・・)を使わせてくれますよね?」
彼の視線が、私の濡れた股間に突き刺さる。
「口だけじゃ、もう我慢できない。先生の奥の奥、子宮の入り口まで楔を打ち込んで、俺の魔力でパンパンに満たしてあげたい」
「そ、れは……実験の範疇を……」
「超えてる? いいえ、これが最終段階(ファイナル・フェーズ)です」
カエレンが力を込めると、パキン、という硬質な音と共に、ミスリルの手枷が砕け散った。
「な……っ!?」
「あんたが俺を研究してたんじゃない。俺が、あんたを俺なしじゃ生きられない身体に作り変えてたんだよ」
彼は自由になった腕で私を抱き寄せ、研究台へと押し倒した。
「さあ、始めようか。朝まで……いや、あんたの理性が完全に焼き切れるまで、たっぷりと可愛がってあげる」
「あ……カエレン……っ」
私は抵抗しなかった。
いや、できなかった。
身体が、子宮が、彼の熱い楔を求めて疼いていたから。
私の唇から、研究者としての言葉は消え失せた。
ただ、快楽を乞うメスの喘ぎ声だけが、研究室の闇に溶けていった。
(了)