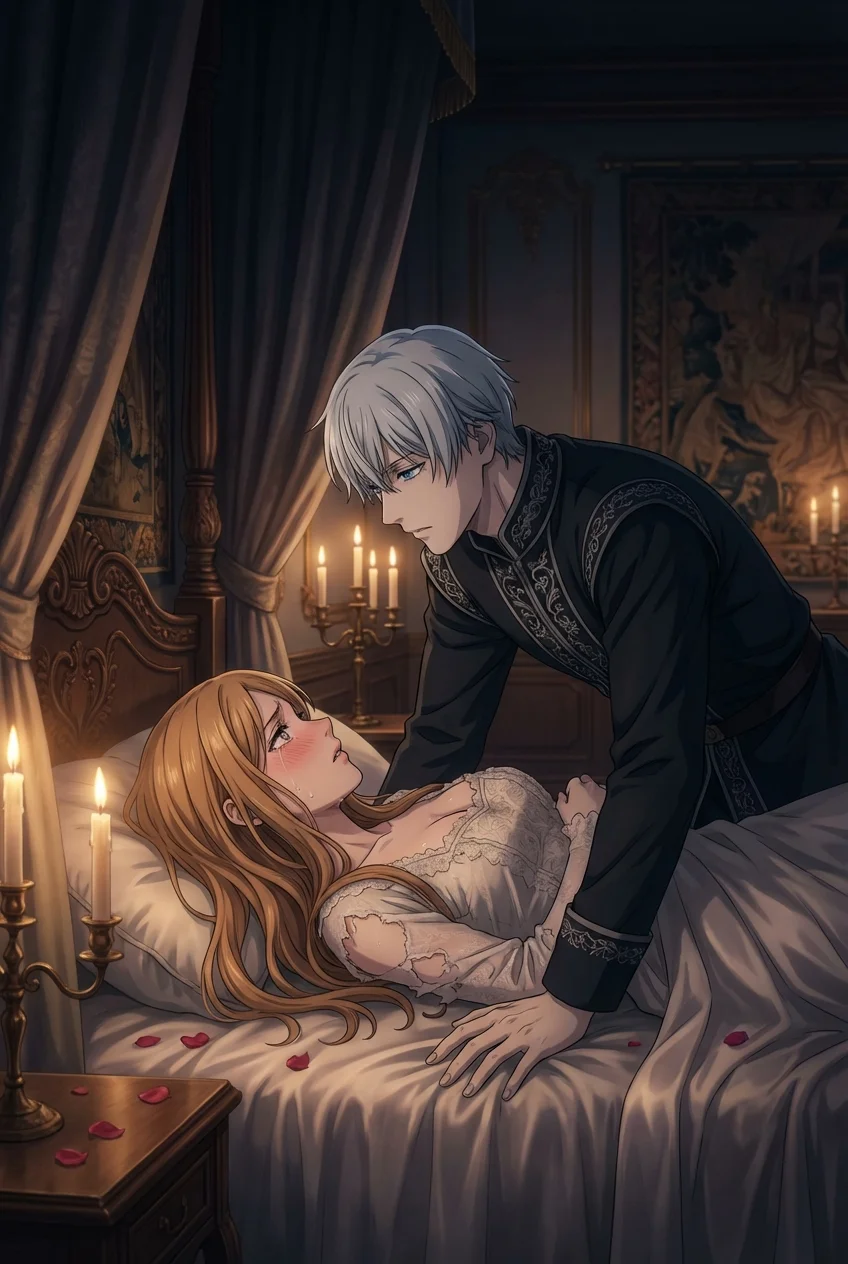第一章 緑の迷宮と冷徹な解析
アマゾンの大気は、それ自体が生き物のような粘度を持っていた。
吸い込むだけで肺が重くなるような湿気。腐葉土と濃密な花の香りが混じり合い、理性をゆっくりと溶かしていく。
「エレナ博士、LiDARの較正はまだか? 雲行きが怪しい」
テントの入り口から投げかけられた低い声に、私はモニターから視線を外さずに答えた。
「あと三十秒待って、レンジロウ。このセクターの植生除去アルゴリズムが、地下構造の異常値を弾き出しているの」
画面上の無機質な緑の点が、次々と剥ぎ取られていく。
露わになったのは、ジャングルの底に眠る幾何学的な直線の痕跡。
「……ビンゴ。未発見の祭壇よ。座標、北緯二度、西経六十一度……ここからわずか八百メートル」
振り返ると、現地ガイド兼護衛のレンジロウが、汗で肌に張り付いたシャツの胸元を寛げながら、不敵な笑みを浮かべていた。
「八百メートル? このジャングルじゃ、東京の十キロより遠いぜ」
彼の視線は、私の顔ではなく、汗で透けたブラウスの襟元を一瞬だけ掠めた気がした。
野蛮で、粗野。私の最も苦手とするタイプ。
けれど、この男が発散する圧倒的な「雄」の熱量は、冷房の効いた研究室しか知らない私の本能を、時折ひどくざわつかせた。
「行きましょう。雨が降る前にデータロガーを設置しないと、衛星のパスが切れる」
私は機材を掴み、逃げるようにテントを出た。
背後で彼が、喉を鳴らすように笑ったのが聞こえた。
第二章 閉ざされた石室
読みは甘かった。
レンジロウの警告通り、スコールは慈悲なく襲い掛かってきた。
視界を白く染めるほどの豪雨。叩きつける雨粒が痛い。
「こっちだ、博士!」
泥濘に足を取られそうになる私の腕を、レンジロウの太い腕が強引に引く。
彼がナイフで蔦を切り裂くと、岩肌にぽっかりと空いた亀裂が現れた。
LiDARが示した「異常値」――古代の排水路か、通気口の跡だろうか。
二人が滑り込むと、そこは人一人がようやく身を縮められるほどの狭小な空間だった。
「くっ……狭いな」
彼の身体が、正面から私に押し付けられる。
外は轟音。
けれど、この石の窪みの中だけは、奇妙な静寂と、むせ返るような二人の体臭が充満していた。
「本部、こちらクジョウ。現在、ポイントB付近の岩陰に避難中。どうぞ」
私は震える手でトランシーバーを握りしめた。
『こちら本部。ノイズが酷い。状況を報告せよ。遭難の危険はあるか?』
スピーカーからの声はクリアだ。こちらの音声も届いている。
「安全は確保されているわ。ただ、雨が止むまでは……っ」
言葉が詰まった。
密着したレンジロウの太腿が、私の股間に割り込むように押し当てられたからだ。
「おい、動くなよ。少しでもズレたら、外の雨に濡れる」
耳元で囁かれる声。
彼の熱い吐息が、雨で冷えた首筋にかかり、鳥肌が一気に全身を駆け巡った。
わざとだ。
彼は、この状況を楽しんでいる。
第三章 交錯するノイズ
「博士、あんたの心拍数、上がってるんじゃないか?」
レンジロウの手が、私の腰に回された。
シャツ越しだというのに、その掌の熱さが火傷のように肌を焦がす。
「ふざけないで……離れて」
「無理だ。この狭さじゃ、これ以上離れられない」
彼の唇が、私の耳殻を甘噛みする。
「んっ……!」
声が出そうになり、慌てて口元を手で覆った。
トランシーバーの送信ボタンは、まだ押されていない。
けれど、いつ本部から呼びかけがあるか分からない状況だ。
「真面目な顔して、こんなに濡れてる」
彼は私の反応を見透かしたように、空いているもう片方の手を、泥と雨で重くなった私のスカートの裾へと滑り込ませた。
「やめ……っ、本部が聞いてるのよ!」
小声で抗議するが、彼は悪戯っぽく笑うだけだ。
「なら、静かにしてればいい。それとも、助けを呼ぶか? 『興奮してどうにかなりそうです』って」
太い指が、下着の縁をなぞる。
直接的な接触はない。まだ、布一枚の隔たりがある。
それなのに、その焦らすような動きが、私の理性の回路をショートさせていく。
『こちら本部。クジョウ博士、応答願います。座標の再確認を……』
突然の通信。
私は反射的に送信ボタンを押してしまった。
「あ、……はい、こちらクジョウ」
その瞬間、レンジロウの指が、下着の奥、最も熱を帯びた核心へと侵入した。
「っ……!!」
悲鳴を噛み殺し、背中を反らす。
石壁の冷たさと、彼の指の容赦ない熱さ。
矛盾する刺激が、脳髄を白く染め上げる。
『座標データにズレが生じているようです。現在地の詳細を』
「げ、現在地は……んっ、……その、岩の……裂け目で……」
気丈に振る舞おうとする声が、上擦る。
レンジロウは私の視線を受け止めながら、指先の動きを早めた。
水音。
粘り気のある湿った音が、狭い空間に響く。
この音がマイクに拾われないか、その恐怖と背徳感が、快楽を爆発的に増幅させる。
「あ、あっ……座標は、ごめんなさい、ちょっと、ノイズが……」
嘘ではない。
私の頭の中は、快楽という名のノイズで埋め尽くされている。
彼は私の耳元に唇を寄せ、音も立てずに囁いた。
(もっと啼けよ。高尚な博士の、乱れた声を聞かせろ)
その言葉が合図だった。
彼の手つきが、愛撫から、明確な「開発」へと変わる。
敏感な部分を執拗に弾かれ、擦られ、抉られる。
もう、立っていられない。
私は彼の首に腕を回し、しがみつくことしかできなかった。
第四章 水没する理性
「ん……ぁ、だめ、そこ……!」
送信ボタンから指を離す余裕すらない。
もう、本部がどう思おうと構わない。
頭の芯が痺れ、視界がチカチカと明滅する。
レンジロウは私のスカートを捲り上げると、自身のもどかしいほどに硬く熱い塊を、私の濡れそぼった秘所に押し当ててきた。
布越しの摩擦。
それだけで、神経が焼き切れそうになる。
「欲しいか? エレナ」
初めて名前で呼ばれた。
「ほ、ほしい……レンジロウ、お願い……」
プライドも、博士号も、すべて泥水に溶けて消えた。
あるのは、渇望だけ。
彼は一度だけ強く私を抱きしめると、邪魔な布を乱暴にずらした。
「……!」
貫かれる衝撃。
言葉にならない絶叫が喉の奥で詰まり、嗚咽となって漏れる。
熱い楔が、私の内側の未踏領域を、LiDARよりも深く、正確に測量していく。
『博士? 博士! 応答してください! 何かありましたか!?』
トランシーバーが叫んでいる。
けれど、私はそれに答えることができない。
「あ……っ、すごい、奥、突かれて……っ!」
激しい雨音が、私たちの恥部を、交わる音を、そして獣のような喘ぎ声をすべて掻き消してくれる。
狭い石室の中、私たちは互いの存在を確かめ合うように、貪り合った。
彼の動きに合わせて、古代の遺跡が震えているのか、それとも私の感覚が崩壊しているのか。
何度も何度も、白濁した意識の中で、私は熱帯の嵐と共に果てた。
第五章 嵐のあとの静寂
雨が上がったのは、それから一時間後のことだった。
ジャングルは嘘のように静まり返り、葉先から落ちる雫が宝石のように輝いている。
乱れた衣服を整え、私はまだ火照りの残る顔で外に出た。
「……本部、こちらクジョウ。通信障害から復旧。現在地より帰投する」
『了解。無事で何よりです。凄まじい嵐でしたね』
無機質な応答に、安堵と、ほんの少しの落胆を覚える。
ふと横を見ると、レンジロウがタバコを吹かしながら、ニヤリと笑った。
「いいデータは取れたか? 博士」
「……ええ。予想以上の、未知の領域だったわ」
私はLiDARの画面を見るふりをして、自身の胸の高鳴りを隠す。
画面には、先ほどまでいた石室の構造が映し出されていた。
それは、古代人が「生命の再生」を祈った、聖なる子宮の形をしていた。
私はそっと画面を閉じ、彼の逞しい背中を追って歩き出した。
まだ、調査は始まったばかりだ。