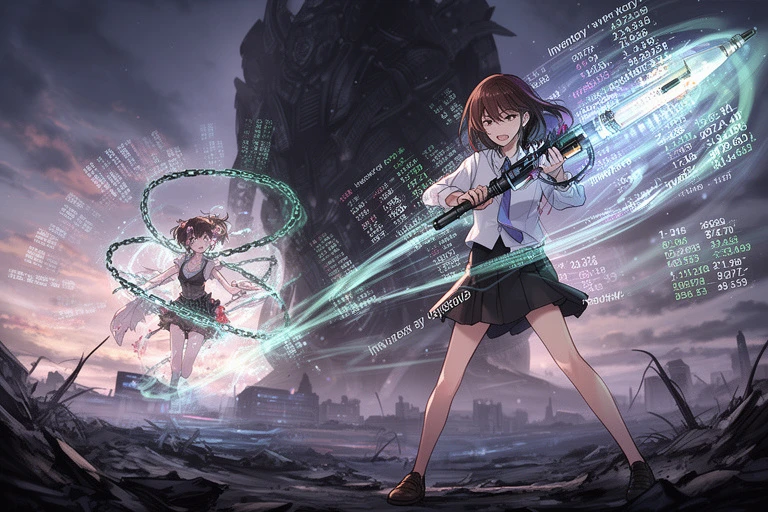第一章 菫と古い紙の香り
路地裏の突き当たり、蔦の絡まる扉に掲げられた『夢の香房』というささやかな看板が、僕、アキトの仕事場だ。ここでは、他人の最も深層にある「願い」を、香りとして嗅ぎ分ける。そして、その香りの組成を読み解き、忘れられた夢を「調香」する。それが僕の生業だった。
「……もう、自分が何者なのか、分からなくなるんです」
カウンターの向こうで、依頼人の女性が震える声で言った。彼女の指先は、まるで磨りガラスのように向こう側が透けて見え、その『現実の輪郭』が dangerously 希薄になっていることを示していた。人々は、自分だけの「固有の夢」を見失うと、こうして徐々に世界から消えていく。
僕は静かに目を閉じ、意識を集中させた。彼女の魂から立ち上る、か細い香りの糸を手繰り寄せる。焦燥感の酸っぱい匂い、諦念の湿った土の香り。だが、その奥深く……本当に深く沈んだ場所に、微かな甘さがあった。
「……雨に濡れた菫(すみれ)の香り。それから、少し埃っぽい、古い紙の匂い」
僕がそう告げると、彼女はハッと息を呑んだ。その瞳に、忘れかけていた光の欠片が宿る。それは、幼い頃、屋根裏部屋で雨音を聞きながら、自分だけの物語を絵本に描いていた少女の記憶。誰にも言えなかった、絵本作家になるというささやかな願いの香りだった。
僕は棚に並んだ幾百もの小瓶から、菫のエッセンス、シダーウッド、微量のインクの香料を手に取り、手際よく調合していく。琥珀色の液体がフラスコの中で渦を巻き、やがて完成した一滴を、彼女の手首にそっと落とした。
香りが立ち上った瞬間、彼女の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。透けていた指先に、ゆっくりと血の気が戻っていく。失われた夢の記憶が、彼女の輪郭を再び世界に繋ぎ止めたのだ。
「ありがとう……ございます」
深く頭を下げて去っていく彼女の背中を見送りながら、僕は自分の掌に視線を落とす。どんな複雑な願いの香りも嗅ぎ分けられるこの鼻も、自分自身の内側からは、何も嗅ぎ取ることはできない。そこにあるのは、完全な静寂と、無臭の空虚だけ。僕の傍らに置かれた『無色の夢の瓶』は、どんな客の夢の香りを容れても鮮やかな色を帯びるのに、僕がいくら息を吹き込んでも、ただの透明なガラスのままだった。
街の巨大なスクリーンには、巨大企業『ドリーム・コア』社の広告が絶え間なく流れている。「あなたに完璧な一夜を。オーダーメイドドリームで、最高の明日を」。人々は固有の夢を見る手間を惜しみ、既製品の安らかな夢を買い求めていた。その甘く、画一的な香りが、僕の鼻を微かに刺激した。
第二章 砂糖菓子を焦がした匂い
その日、店の扉が乱暴に開けられ、二人の男に抱えられた青年が運び込まれてきた。彼の身体はほとんど透明で、背景の壁が透けて見えるほどだった。その存在感の希薄さは、もはや末期的と言ってよかった。
「頼む、助けてやってくれ!こいつ、ドリーム・コアの夢にハマってから、おかしくなっちまったんだ!」
友人の悲痛な叫びを聞きながら、僕は青年に近づき、その魂から漂う香りを嗅いだ。
鼻をついたのは、砂糖菓子を焦がしたような、甘く粘つく匂い。ドリーム・コア社が供給する夢に共通する、人工的な香料の香りだった。それはあまりに強く、彼の本来持つべき固有の香りをほとんど覆い隠してしまっている。
僕は眉をひそめ、その甘ったるい煙の向こう側を、必死に探った。
あった。ほんの僅か、燃え殻の底に残る火種のように。
錆びた鉄と、遠い潮騒の香り。
船乗りになることを夢見ていた、港町育ちの少年の願いの残滓だった。
「このままでは、彼の願いは完全に上書きされて消滅する……」
僕は手持ちの最も純粋な香料を使い、彼の失われた夢の再生を試みた。しかし、ドリーム・コア社の人工香料は、まるで毒のように彼の魂にこびりつき、僕の調香を阻んだ。数時間後、青年はかろうじて輪郭を取り戻したが、その瞳は虚ろなままだった。
この一件で、僕の疑念は確信に変わった。ドリーム・コアの夢は、人々の魂を蝕む毒だ。それは真の願いを奪い、人々を無個性な、夢の消費者へと変えてしまう。なぜ、こんなものが世界を席巻しているのか?その目的は何だ?
僕は、これまで集めてきた様々な人々の『願いの香り』を閉じ込めた小瓶を眺めた。一つひとつが異なる色と輝きを放っている。この多様性こそが、世界を豊かにしているはずだった。それを奪う権利など、誰にもない。
僕は決意した。この謎を解き明かすために、ドリーム・コア社の本拠地、あの天を衝く白亜の塔へ向かうことを。腰には、あの空っぽの『無色の夢の瓶』だけを携えて。
第三章 僕の『半身』
ドリーム・コア社の本社ビルは、静寂に支配されていた。無菌室のような白い廊下には人の気配がなく、ただ巨大なサーバーの低い駆動音だけが響いている。僕は幾重ものセキュリティを抜け、香りの痕跡を頼りに、塔の最深部へとたどり着いた。
そこは、巨大なドーム状の空間だった。中央には、眩い光を放つ巨大な球体の装置が鎮座し、無数のケーブルが接続されている。そして、その装置の前、ガラスの繭のようなカプセルの中に、一人の人物が静かに浮かんでいた。
息を呑んだ。
その顔は、僕と瓜二つだったのだ。
「……やっと来たんだね。僕の『半身』」
カプセルの中から、思考が直接流れ込んでくるような、澄み切った声が響いた。それは僕自身の声に酷似していたが、一切の感情が削ぎ落とされている。
「お前は……誰だ?」
「僕は、君だよ。君が捨てた、君自身の『夢』そのものだ」
彼の言葉と共に、僕の脳裏に、忘れていたはずの光景が洪水のように流れ込んできた。
それは、この世界が『夢の混沌』に沈んだ、遠い過去の記憶。人々の夢が暴走し、悪夢が現実を侵食し、世界が崩壊しかけていた時代。両親を悪夢に喰われた幼い僕は、たった一人で、あまりにも強すぎる願いを抱いた。
――誰も傷つかない、誰も悲しまない、完璧で、たった一つの理想の夢を創って、この世界を救う。
その願いは、僕自身の魂を二つに引き裂いた。
夢を嗅ぎ分け、他者の心を癒す能力だけを残した『僕』。
そして、その強大な願いを叶えるため、夢を創り出す能力の全てを注ぎ込まれた『半身』。
ドリーム・コア社が供給する“オーダーメイドドリーム”は、僕が世界を救うために自らを犠牲にして生み出した、唯一無二の夢だったのだ。人々から固有の夢を奪っていたのではない。混沌から世界を守るために、僕の夢が、たった一つの巨大な傘となって、世界を覆っていたに過ぎなかった。
「僕たちの夢は、世界を救ったんだ。安定と平和をもたらした。なのに、君はそれを壊しに来たのかい?」
半身は静かに問う。僕は言葉を失い、その場に立ち尽くすしかなかった。世界を蝕む毒だと思っていたものが、実は、僕自身の自己犠牲の果てに生まれた、歪んだ救済の形だったとは。
第四章 夜明けの調律
安定した一つの夢の世界か。それとも、混沌のリスクを孕む、多様な夢の世界か。
僕は選択を迫られていた。半身の言う通り、彼の創る夢は世界に秩序をもたらした。しかし、その代償として、人々は魂の輝きを失っていく。それは本当に「救い」と呼べるのだろうか。
僕は、腰に提げた『無色の夢の瓶』を握りしめた。
この旅の道中、僕は消滅しかけた人々から、様々な願いの香りをこの瓶に集めていた。それはドリーム・コアの夢では決して得られない、不格好で、不完全で、けれど、どうしようもなく美しい、個性の輝きだった。
瓶の中を覗き込む。空っぽのはずの瓶の底に、いつの間にか、集めた無数の香りの粒子が混じり合い、淡い虹色の光を放っていた。
「完璧な夢なんて、きっとどこにもないんだ」
僕は顔を上げ、半身に向かって言った。
「傷ついても、迷っても、自分だけの夢だからこそ、人は強く、美しくなれる。君が守ろうとした世界は、あまりにも優しくて……そして、あまりにも寂しすぎる」
僕はゆっくりと中央の装置に近づき、『無色の夢の瓶』を、鍵穴のように窪んだ部分へと差し込んだ。そこは、かつて僕の夢の核が分離した場所だった。
瓶が眩い光を放つ。僕の半身だった存在が、安らかな表情で光に溶けていき、僕の中へと還ってくる感覚があった。巨大な装置はシステムダウンの警告音を鳴らし、やがて完全に沈黙した。
世界中に供給されていた均質な夢のネットワークが、途切れる。
その瞬間、装置に吸収されていた無数の『願いの香り』が解放され、光の奔流となってドームの天井を突き破り、夜空へと昇っていった。
僕は塔の外に出た。
夜空には、色とりどりのオーロラが広がっていた。それは、解放された人々の夢の香りそのものだった。街のあちこちで、人々が眠りから覚め、窓を開けて空を見上げている。彼らの瞳には、戸惑いと共に、新しい夢の始まりを告げる光が灯っていた。
その時、僕は初めて感じた。
自分の内側から、静かに立ち上る、微かな香りを。
それは、雨上がりの土の匂い、古い本のインクの匂い、潮風と錆びた鉄の匂い――僕が救ってきた人々の夢の香りが全て混じり合った、優しく、そしてどこか懐かしい香りだった。
僕の『現実の輪郭』は、これまでになく鮮明に、世界に存在していた。
空っぽだった夢の瓶は、もうない。僕自身が、世界中の夢を受け止め、紡いでいく瓶になったのだ。
夜が明け、新しい世界の最初の光が街を照らし始める。その光の中で、僕は静かに微笑んだ。