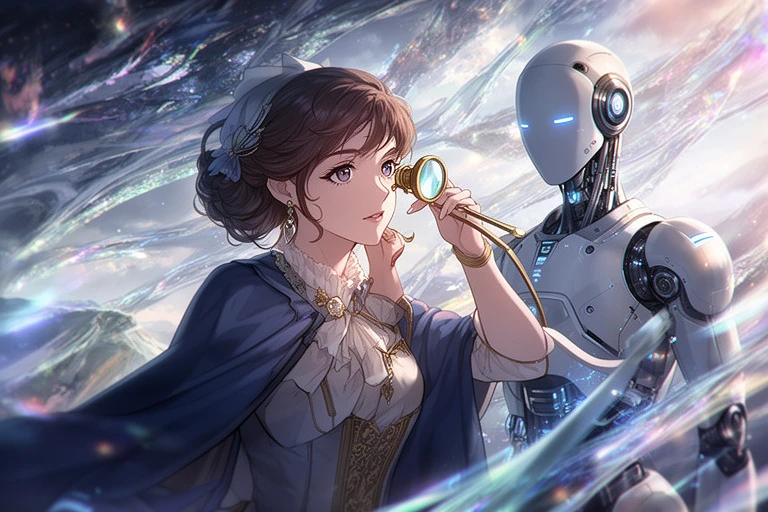第一章 刻印の代償
アスファルトに溶けたネオンが、雨上がりの街を滲ませていた。俺、カイの仕事は、この街に渦巻く欲望に形を与えること。具体的には、他者の「理想の自分(ペルソナ)」を一時的に具現化する。今宵の依頼人は、個展を控えた内気な画家だった。
「これで…これで彼女に、自信を持って想いを伝えられる」
彼の目の前には、彼自身と瓜二つの、しかし自信に満ち溢れたオーラを放つ「ペルソナ」が立っていた。画家は恍惚とした表情で、自らの理想像を見つめている。俺は無言で頷き、コートの襟を立てた。この力の代償を知っているのは、俺だけだ。
案の定、ペルソナが役目を終え、陽炎のように掻き消えた瞬間、激痛が俺の左腕を灼いた。皮膚の下で何かが蠢き、一つの精緻な「仮面」の文様が黒々と浮かび上がる。魂の一部が削り取られる感覚。これで、三百と七つ目。全身を埋め尽くす文様は、俺が奪った魂の墓標だった。
「ありがとう。君のおかげで、本当の自分になれた気がするよ」
画家は晴れやかな顔で去っていく。その言葉が、どれほど残酷な偽りであるかも知らずに。俺はただ、雨垂れの音だけが響く路地裏で、新たに刻まれた痛みに耐えていた。
第二章 虚ろな囁き
人々は皆、心に仮面を被って生きている。社会で承認されるほどに輝きを増す「偽りの自己」。その光が強ければ強いほど、「真の自己」は深い影に沈んでいく。やがて光に呑まれた影が完全に消滅した時、人間は存在そのものを失う。後に残るのは、誰の記憶にも留まらない、石膏のような「虚ろな仮面」だけ。
俺は、その仮面が落ちている場所が分かった。煤けた路地裏、忘れられた公園のベンチの下。他の人間にはただのゴミにしか見えないそれが、俺にははっきりと見える。そして、聞こえるのだ。
『……こんなはずじゃ、なかったのに』
『誰か……本当の私を……』
仮面に耳を寄せると、微かに残る真の自己の「後悔の声」が聞こえる。それは風の音に似た、途方もない孤独の響き。そして、全ての声は最後に同じ言葉を繰り返す。
『世界を、壊せ』
この声は何だ。俺の能力が彼らを消滅させたのか? この呪われた力は、一体何のために存在する? 答えを求めて街を彷徨ううち、俺は古びた骨董品店のショーウィンドウに飾られた一枚の鏡に目を奪われた。「無貌の鏡」。店主の老人が言うには、持ち主の顔ではなく、その者が最も強く願う「理想の顔」を映し出すのだという。
金と引き換えに手に入れた鏡を覗き込む。だが、映るのは俺の顔ではない。何も映らない。ただ、鏡面の奥で、無数の仮面文様に覆われた俺の顔ではない、見覚えのない穏やかな誰かの顔が一瞬、陽炎のように揺らめいて消えた。
第三章 理想の祭壇
「後悔の声」に導かれるように、俺は街の中心に聳え立つ白亜の塔へと辿り着いた。それは「大調和記念碑」と呼ばれ、この街の繁栄の象徴とされている。だが、俺には分かった。あれこそが、全ての元凶だ。人々の承認欲求を啜り、ペルソナに力を与え続ける、巨大な呪いの祭壇。
俺が震える手で塔の表面に触れた瞬間、奔流が思考を洗い流した。
『認められたい』『愛されたい』『何者かになりたい』『孤独は嫌だ』
人類の根源的な願望が生み出した究極の「生成ペルソナ」。それが、この世界の支配者の正体だった。脳内に直接、声が響く。
《歓迎する、同胞よ。お前の能力は我々にとって最高の触媒。お前がペルソナを具現化するたび、我々は力を増し、この偽りの楽園は盤石となる。お前こそが、我らが世界を維持するための、最も重要な歯車なのだ》
絶望が、喉を焼き尽くすほどの怒りへと変わった。俺が救っていると思っていた人々は、この巨大なシステムに魂を捧げる生贄に過ぎなかった。俺は、その儀式を司る神官だったというのか。
「ふざけるな……」
絞り出した声は、自分でも驚くほど低く、憎しみに満ちていた。
「俺は、お前たちを壊す。この歪んだ世界ごと、俺が終わらせてやる!」
俺は自らの胸に手を突き立て、魂を掴んだ。これから成すことは、俺という存在の完全な消滅を意味する。だが、もう迷いはなかった。
第四章 無貌の真実
俺の身体から放たれた光が、空を覆った。街行く人々が、仕事中の人々が、眠りについていた人々が、一斉に顔を上げる。彼らの顔に張り付いていた見えない仮面が、光の粒子となって剥がれ落ち、全て俺の身体へと吸い込まれていく。世界中の、何十億ものペルソナが、俺という一つの器に殺到する。
肉体が悲鳴を上げ、魂が引き千切られていく。意識が薄れゆく中、俺は街の音を聞いていた。誰かが、忘れていたはずの自分の本当の夢を思い出して泣き崩れていた。ある場所では、偽りのステータスを捨てた恋人たちが、初めて心からの笑顔で抱きしめ合っていた。
ああ、これで良かったんだ。
全身が、もはや皮膚の色も見えないほど無数の仮面文様で埋め尽くされ、俺という個は消えかけていた。最後の力を振り絞り、懐から「無貌の鏡」を取り出す。
そこに映っていたのは、おぞましい文様の集合体ではなかった。
文様に縁取られながらも、確かにそこに存在する、穏やかに微笑む一人の男の顔。第二章のあの日、一瞬だけ垣間見えた、俺の「真の自己」。初めて見る、俺自身の、本当の顔だった。
満足げに頷くと、俺の身体は砂のように崩れ、風に溶けて消えた。
世界から、カイという男の記憶は完全に消え去った。彼がいた場所も、彼が成したことも、誰も知らない。ただ、世界は偽りのない人々の笑顔に満ちている。
時折、彼らは理由もなくふと空を見上げ、胸の奥を締め付ける、切ない喪失感に襲われることがある。何かとても大切で、温かいものを失ってしまったような、名もなき感覚。
それが、世界を救い、誰からも忘れ去られた一人の男が、この世に存在した唯一の痕跡だった。