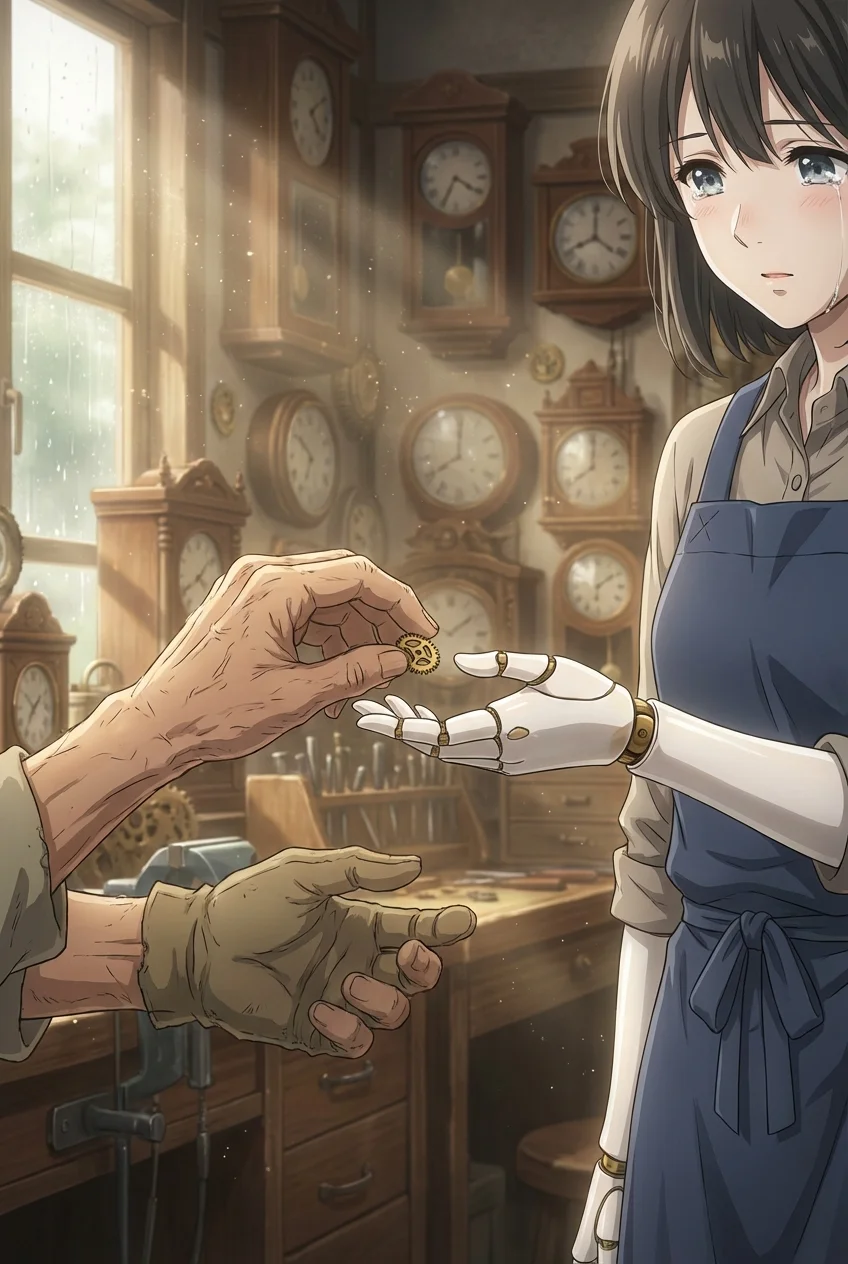第一章 硝子玉の心
アスファルトの隙間から漏れるネオンが、雨上がりの空気をぼんやりと照らしている。俺、レイの仕事は、この光の街に漂う「感情」を採取することだ。人々は俺をエモーション・コレクターと呼ぶ。
恋人たちの語らいから立ち上る、蜂蜜のように甘い黄金色の粒子。成功を祝う乾杯の輪から弾ける、シャンパンの泡のような白銀の輝き。俺は右腕にはめられた腕輪――「共鳴結晶」をかざし、それらの光を手際よく吸い込んでいく。結晶が微かに温かくなり、依頼主の元へと転送されていく。これが、この世界の仕組み。人々は自力で感情を生み出せず、俺たちのようなコレクターが届けた他人の感情で、心の渇きを癒すのだ。
「今日の『安らぎ』は、とても質がいいわね」
路地裏のアパートで、老婆が皺くちゃの手でカップを温めながら呟いた。俺が届けたばかりの、湖の水面のように穏やかな青緑色の粒子が、彼女の周囲をゆっくりと漂っている。その光を吸い込むたび、老婆の強張った肩から力が抜けていくのが分かった。
「感情枯渇症の一歩手前でした。定期的な摂取を忘れないでください」
俺は事務的に告げる。老婆の安堵した顔を見ても、俺の心は静まり返った水面のように、何も映さない。どんなに美しい感情の光を見ても、どんなに悲痛な心の叫びを聞いても、俺の内側には何も生まれない。俺自身の感情だけが、光の粒子として現れることは決してなかった。
部屋を出ると、湿った夜風が頬を撫でた。腕の共鳴結晶は、次の仕事を示すかのように冷たく沈黙している。俺は空を見上げた。厚い雲に覆われた空は、まるで俺の心の内側のように、どこまでも無表情だった。自分はただ、感情を右から左へ流すだけの、空っぽの硝子玉なのだと、いつも思う。
第二章 澱む街の影
街の空気が、じわりと変わり始めていた。デリバリーされる感情の量が減り、質も落ちてきている。供給源が枯渇し始めている、という不穏な噂が、黴のように人々の心に広がっていた。
感情の供給が滞れば、人々は「感情枯渇症」に陥る。心が枯れ、生きる気力を失う病。だが、それよりも厄介なのが、古い感情の摂取によって心に溜まる「感情の滓」だ。消費期限切れの感情は、澱んだ紫色の靄となって心にこびりつき、やがて理性の箍を外す。
「やめろ! それは俺の『歓喜』だ!」
広場で、男がもう一人の男に掴みかかっていた。感情の闇取引だ。男の瞳の奥に、澱んだ滓が揺らめいているのが見えた。周囲の人々は、無関心か、あるいは微かな恐怖を滲ませた表情で遠巻きに見ている。これもまた、感情の欠乏が生んだ風景だった。
「レイ。本部へ来なさい」
腕の結晶を通して、上司であるエヴァの冷静な声が響いた。感情統制機構の中枢、白を基調とした無機質なオフィスで、彼女はモニターに映るデータを見つめていた。
「供給源『揺り籠』のエネルギー低下が深刻化している。原因が特定できない。あなたに調査を命じます」
「俺に?」
「あなたは最高のコレクターよ。そして……誰よりも、感情の影響を受けない」
エヴァの言葉はいつも、メスのように鋭く、正確に核心を突いてくる。彼女の瞳は、どんな感情の光も映さない、深い湖のようだった。俺と同じ、空っぽの人間なのだろうか。いや、違う。彼女の奥底には、何か固く閉ざされたものがある。そんな気がした。
俺は頷き、機構の最深部――これまで誰も立ち入ることを許されなかった聖域、『揺り籠』へと向かうことを決めた。腕の共鳴結晶が、まるで心臓のように、とくん、と一度だけ脈打った。
第三章 揺り籠の真実
『揺り籠』は、巨大な洞窟の最奥に鎮座していた。そこに在ったのは、天を突くほどの巨大な水晶の柱。かつては七色の光を放っていたのだろう。だが今、その輝きは虫の息で、表面には無数の亀裂が走っていた。これが、世界の感情を支えてきた供給源の、最後の姿だった。
「……やはり、もう限界のようね」
背後から、エヴァの声がした。いつの間にか俺の後ろに立っていた彼女は、静かな目で『揺り籠』を見上げていた。
「エヴァ、これは一体……」
「世界の真実よ、レイ」
エヴァは語り始めた。かつて、人々は自らの内に感情を持っていたこと。その感情が生み出す憎悪と欲望が、世界を滅亡の淵へと追いやったこと。生き残った人々は、感情という名の爆弾を管理することを選んだ。
「統制機構は、全人類から感情を『吸い上げる』システムを構築した。それがこの『揺り籠』。人々は感情を奪われ、代わりに我々が管理し、ろ過した安全な感情を受け取ることで、平和を維持してきた」
エヴァの言葉は、俺が知る世界の全てを根底から覆した。
「だが、システムには欠陥があった。吸い上げた負の感情のエネルギーが強すぎたの。暴走する感情を中和し、浄化し、そして全てを受け止めるための『器』が必要だった」
彼女の視線が、俺を射抜く。
「それが、あなたよ、レイ」
俺は、言葉を失った。俺が無感情なのは、欠陥品だからではなかった。俺自身が、感情を生み出すのではなく、この世界の全ての感情を受け止めるために創られた、ただ一つの存在だったからだ。腕輪の共鳴結晶は、俺という『器』と『揺り籠』を繋ぐための端末に過ぎなかった。
その時だった。
ゴオォ、という地鳴りのような音と共に、『揺り籠』が最後の輝きを放ち、そして――完全に沈黙した。水晶の柱は、ただの巨大な石塊と化した。
世界から、感情の供給が完全に断たれた瞬間だった。腕の結晶を通して、街の絶望的な叫びが、音のない悲鳴となって流れ込んできた。
第四章 きみの色
世界は、急速に色を失っていった。街角では人々が虚ろな目で座り込み、暴力的な衝動に駆られた者たちの争いが絶えなかった。感情枯渇症と、滓による暴走。世界の終わりが、静かに始まっていた。
『揺り籠』のあった洞窟で、俺はエヴァと二人きりで佇んでいた。
「方法は、一つだけある」
エヴァが、俺の心臓を見つめるように言った。
「あなたの中には、創られてから今この瞬間までに採取した、全人類の純粋な感情の『原液』が眠っている。それを解放すれば、人々は再び自らの力で感情を取り戻し、世界は再生される」
「……俺は、どうなる?」
「『器』は役目を終える。あなたという個は、世界に溶けて消えるでしょう」
消える。その言葉に、恐怖はなかった。むしろ、腑に落ちた。空っぽの俺が、世界を満たすために存在していた。それが、俺の存在理由。これ以上にない、完璧な答えだった。
俺は静かに頷いた。
そして、右腕の共鳴結晶を、自らの胸に強く押し当てた。
結晶は光と共に俺の身体に吸い込まれ、心臓の位置で眩い輝きを放ち始める。熱い。初めて感じる、身体の内側からの熱。それは痛みであり、歓喜でもあった。
次の瞬間、俺の身体から、光の奔流が溢れ出した。
黄金の『喜び』、澄んだ青の『悲しみ』、燃えるような赤の『怒り』、そして、俺が一度も採取したことのない、桜色の『愛』。無数の感情が、光の粒子となって世界中に降り注いでいく。枯渇した人々の心に、温かな光が染み渡っていく。街のあちこちで、人々が泣き、笑い、抱き合う気配が伝わってきた。
意識が薄れていく。世界が、光に溶けていく。
その最後の瞬間に、俺は見た。
俺自身の胸の中に、ほんの小さな、けれど、どこまでも温かい光の粒子が生まれるのを。
それは、誰のためでもない、俺自身の感情。
この世界を満たし、その全てを受け止めることができたという、静かな『満足』の色だった。
光は、誰にデリバリーされることもなく、俺と共に、ただ静かに輝いていた。
*
世界は再生された。人々は再び、自らの内に感情という名の火を灯す力を取り戻した。それは祝福であり、同時に、かつて世界を滅ぼしかけた混沌の再来を意味していた。
統制機構のオフィスで、エヴァは窓の外を見つめていた。街には、赤、青、黄色、無数の感情の光が再び灯り始めている。それはあまりに美しく、そして、あまりに危うい光景だった。
彼女は、誰もいなくなった空に向かって、そっと呟いた。
「ありがとう、レイ。……さあ、ここからが、私たちの本当の始まりよ」
エンドロールの流れない空に、今日生まれたばかりの、新しい感情の色が瞬いていた。