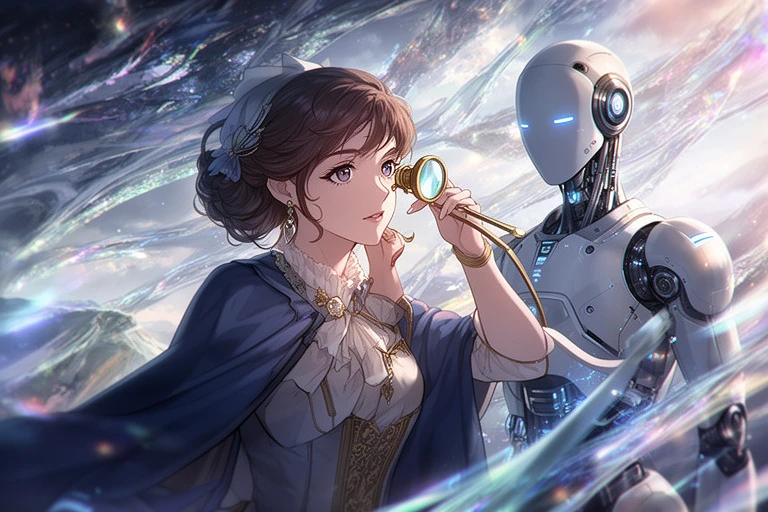第一章 炎上の代償
「はいどうもー! 今日も今日とて他人の不幸で飯が美味い! バズファイヤーです!」
スマホの画面に向かって、俺は唇を吊り上げる。
コメント欄を滝のように流れる罵詈雑言。
俺の網膜には、それらが文字ではなく、視神経を焼く赤黒い『針』として突き刺さる。
チリチリと肌が泡立つ感覚。
嫉妬の熱、憎悪の粘り気。
たまらない。この不快指数こそが、俺の銀行口座を潤す燃料だ。
「今日のターゲットは、清純派ぶってるあの……」
言いかけた瞬間だった。
スマホのレンズが、ありえない質量の熱を放った。
視界が白熱し、内臓が裏返るような浮遊感が俺を襲う。
鼻をつくのは、焦げ臭いオゾンの臭い。
「……ッ、あつ!?」
目を開けると、廃墟だった。
色は、ない。
建物も空も、すべてが古びたフィルムのように灰色で、音という音が消滅している。
目の前には、泥にまみれた修道服の少女が一人。
ゴミを見るような目で、俺を見下ろしていた。
「やっと捕まえました。異界の『病原菌』」
「はあ? 誰が菌だ。俺は数百万人に支持されるインフルエンサー……」
ドォォォォォン!!
俺が口を開いた刹那、足元の石畳が爆ぜた。
何の前触れもない衝撃波。
俺の体は枯れ葉のように吹き飛び、背中をレンガ壁に打ち付けられる。
「がはっ……!? な、なんだ!?」
肺から空気が強制排出され、激痛が走る。
少女――セーラは、眉ひとつ動かさない。
その手には、掌サイズの水晶鏡が握られていた。
「口を開けば爆発。あなたの言葉が『虚偽』である証拠です」
「言葉が……爆発するだと……?」
「ここは『言霊界』。嘘は衝撃となり、悪意は物理的な刃となって空間を裂く。あなたの世界のような、軽い言葉は存在できません」
セーラが俺に鏡を向ける。
鏡面がジジジと嫌な音を立て、黒いノイズで塗りつぶされた。
「あなたは汚染源だ。さっさと消毒しないと」
彼女の眼差しに、慈悲など欠片もない。
俺は痛む脇腹を押さえ、へらりと笑おうとした。
「へっ、手厳しいな。俺はただ、皆が喜ぶ真実を提供してるだけ……」
バヂィッ!
今度は唇が焼けた。
まるで熱したコテを押し付けられたような激痛。
「いっ、ぐああああ!」
「学習しないのですね。その『嘘』が、この世界を殺しかけているというのに」
俺は地面に転がり、焼けただれた唇を押さえた。
なんだ、この世界は。
適当なハッタリも、商売上の演出も通用しないのか。
恐怖よりも先に、腹の底から苛立ちが湧き上がってきた。
俺の商売道具を、言葉を、封じる気か。
第二章 沈黙する世界とノイズ
俺たちは歩いた。
どこまでも続く、灰色の街を。
道端には、人間のような何かが転がっている。
動かない。
彼らの輪郭はぼやけ、今にも空気に溶けてしまいそうだ。
「なんなんだよ、こいつらは。やる気あんのか」
俺が爪先で男の肩を小突く。
反応はない。虚ろな瞳が、ただ虚空を見つめている。
「彼らは言葉を奪われたのです。あなたたちが垂れ流す『ノイズ』によって」
セーラが吐き捨てるように言う。
俺はスマホ型の配信機材『バズカメラ』を構えた。
電波はないはずだが、セーラの鏡と共鳴し、画面にはノイズ交じりの映像が映っている。
「ノイズだぁ? 言いがかりだろ。俺は需要に応えてるだけだ」
俺はカメラを回しながら、いつもの調子で正当化を試みる。
「世間が求めてるんだよ。刺激を、正義の鉄槌を、生贄を! 俺はそれを供給するスカベンジャーだ。感謝されこそすれ、恨まれる筋合いは……」
その時、セーラが俺の胸ぐらを掴み、強引に鏡を突きつけた。
「その薄汚い眼で、よく見なさい!」
鏡の中に、映像が浮かび上がる。
かつて俺が『暴露』し、社会的に抹殺したアイドルの少女だ。
『大暴露! 枕営業の実態!』
サムネイルの俺が下品に笑っている。
だが、鏡が映し出したのは、その後の彼女の姿だった。
暗い部屋。散乱する薬。
彼女はスマホの画面を見つめ、過呼吸に陥っている。
『死ね』『消えろ』『汚い』
俺の動画に煽られた何万ものコメントが、物理的な刃物となって彼女の皮膚を切り裂いていた。
幻覚ではない。彼女の心象風景では、言葉は凶器そのものだった。
「ひっ……う、あ……」
彼女が喉を掻きむしり、血を吐く。
その血の一滴一滴が、俺には焼けた鉛のように見えた。
「これが、あなたの言う『需要』ですか?」
セーラの手が震えている。怒りで。
「彼女は無実だった。でも、あなたの『面白い嘘』が真実を塗り替え、彼女の魂を殺した。その負のエネルギーがこの世界に流れ込み、空を灰色に染めたのです」
「……仕事、だったんだ」
俺の声がかすれる。
認めれば、俺の全てが崩れ落ちる気がした。
「あいつらだって、楽しんでたじゃないか。俺だけが悪いのかよ……」
「ええ、あなたが引き金を引いた」
セーラは冷徹に告げた。
鏡の中の少女が、血走った目でこちらを見た気がした。
俺の心臓が、早鐘を打つ。
これまで「数字」としてしか見ていなかった他人の痛みが、質量を持って俺の胃袋に落ちてくる。
吐き気がした。
自分の吐いた言葉が、ドロドロとした黒いタールとなって、喉の奥から逆流してくる感覚。
「おえっ……げほっ、ごほっ!」
俺は膝をつき、地面に胃液をぶちまけた。
今まで見ないふりをしてきた「事実」が、内側から俺を食い荒らし始める。
これは、罰だ。
「……もういい。殺せよ」
俺は涙目でセーラを見上げた。
「俺みたいなクズは、ここで処理された方が世のためだろ」
セーラは鏡を下ろした。
軽蔑の色は消えていない。だが、そこには僅かな哀れみと、諦めのような決意があった。
「殺しません。あなたには、後始末をつけてもらいます」
第三章 最初で最後の告白
「接続、します。耐えてください」
セーラの言葉と共に、俺のスマホと彼女の鏡が光のケーブルで繋がれる。
ジュッ、と音がした。
「ぐっ、あああああ!」
スマホを握る右手が、高熱で焼かれる。
『虚偽』にまみれた俺の端末と、『真実』を映す鏡。
相反する二つを繋ぐ回路は、俺の肉体を導線として焼き尽くそうとしていた。
「痛いですか。でも、離さないで」
「わーってるよ……クソッ!」
俺は焼けただれる手のひらの激痛をねじ伏せ、カメラを自分に向けた。
画面の向こうには、現実世界へのパスが繋がっている。
500万人の登録者。
俺が餌を与え続け、怪物を育ててしまった場所。
『配信開始』
通知は届くはずだ。
俺の失踪で騒ぎになっている今なら、注目度は過去最高だろう。
「……あー、聞こえるか。クソ野郎ども」
話し始めた瞬間、喉が焼けた。
いつものような煽り口調は、この世界では「ノイズ」として拒絶される。
飾るな。盛るな。
剥き出しのまま喋れ。
「今日は……謝罪配信だ」
画面に映る俺は、ひどい顔をしていた。
煤と泥にまみれ、脂汗を流し、情けなく歪んでいる。
これが、俺の正体だ。
「俺が今まで言ってきたこと、全部……全部、デタラメだった」
バチバチッとスマホから火花が散る。
右手の感覚がなくなっていく。
「裏取りなんてしてねえ。お前らが興奮すればそれでよかった。金になれば、誰が死のうがどうでもよかったんだ」
嗚咽が漏れた。
格好悪い。死ぬほど格好悪い。
だが、言葉にするたびに、胸のつかえが取れていく。
「怖かったんだよ……! 誰にも見向きされないのが、空っぽの自分がバレるのが怖くて……だから、他人を燃やして、その明かりで暖を取ってたんだ!」
鼻水が垂れるのも構わず、俺はカメラに縋り付いた。
鏡の光が増幅し、灰色の空を貫いていく。
「ミハル……ごめん。本当に、ごめんなさい。俺は、お前の人生を……」
特定の誰かの名前。
俺が踏みにじった、あの子への懺悔。
「許してくれなんて言わねえ。ただ……もう、終わりにしたいんだ」
ドクン。
世界が脈打った。
俺の『本音』が、強烈な波動となって拡散する。
それは爆発ではない。
透明な、浄化の波紋。
灰色の霧が晴れていく。
座り込んでいた人々の瞳に、光が戻る。
赤黒い棘のようだった空気が、澄んだ青色へと変わっていく。
「天音さん、見て……」
セーラが呟く。
鏡の中のノイズが消え、そこには、無数の「言葉」が流れていた。
『届いたよ』
『わかってた』
『逃げるな』
『聞いてるから』
罵倒だけではない。
そこには、人間が人間として発する、熱を持った感情があった。
俺がずっと目を背け、否定してきた「他者の体温」が、画面越しに流れ込んでくる。
「……ああ、なんだ。結構、温かいじゃねえか」
俺は焼けた右手でスマホを握りしめ、深く頭を下げた。
視界が涙で滲んで、何も見えない。
「今まで、本当にすまなかった。……さようなら」
配信終了のボタンを押す。
同時に、俺の体が光の粒子となって崩れ始めた。
この世界での「異物」である俺は、浄化と共に排除される。
「天音ッ!」
セーラが初めて、俺の名前を叫んだ。
彼女の手が伸びてくる。
俺はその冷たくて温かい手を、焼け焦げた手で握り返した。
「ありがとな、共犯者。……お前の鏡、最高に痛かったぜ」
彼女が泣き笑いのような顔をしたのを最後に、俺の意識はホワイトアウトした。
エピローグ 波紋のゆくえ
現実に戻った俺を待っていたのは、地獄のような請求書の山と、警察の取調べだった。
異世界からの配信は、全世界の電波をジャックして放送されたらしい。
俺の罪はすべて白日の下に晒された。
当然だ。魔法のようにすべてが解決するなんて、そんな都合のいい話はない。
あれから二年。
俺は罪を償い、今は地方の小さな配送会社で働いている。
ネットは解約した。スマホもガラケーに変えた。
昼休み。
同僚が休憩室のテレビを見ていた。
ドキュメンタリー番組が流れている。
『言葉の力を信じる人々』という特集だ。
画面の隅に、見覚えのある少女が映った。
かつて俺が追い詰め、自殺寸前まで追い込んだアイドル、ミハルだ。
彼女は今、ネットリテラシーを教える講師として活動しているらしい。
その顔には、まだ深い傷跡のような陰りがある。だが、その瞳はしっかりと前を向いていた。
『言葉は刃物です。でも、誰かを温める毛布にもなります』
彼女がカメラに向かって微笑む。
俺は、震える手で缶コーヒーを握りしめた。
許されたわけじゃない。
一生、背負っていく傷だ。
ふと、ポケットのガラケーが震えた。
メールだ。
アドレスは知らない。
本文もない。
ただ、絵文字が一文字だけ。
✨🪞✨
キラキラと輝く、鏡。
俺は空を見上げた。
今日の空は、あの灰色の世界とは違う、突き抜けるような青だ。
風が吹いた気がした。
あの厳しい聖女が、「サボるなよ」と背中を叩いたような気がして。
俺はガラケーを閉じ、短く呟いた。
「……ああ、わかってる」
俺は作業着の襟を正し、午後の配送へと走り出した。
言葉を持たない荷物に、せめて「丁寧」という想いを乗せて届けるために。