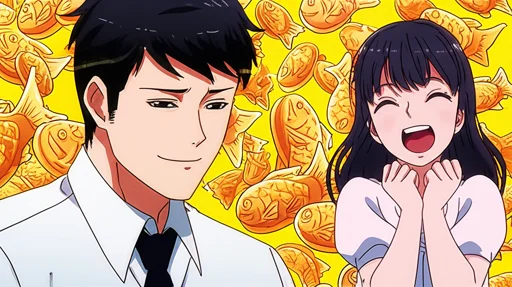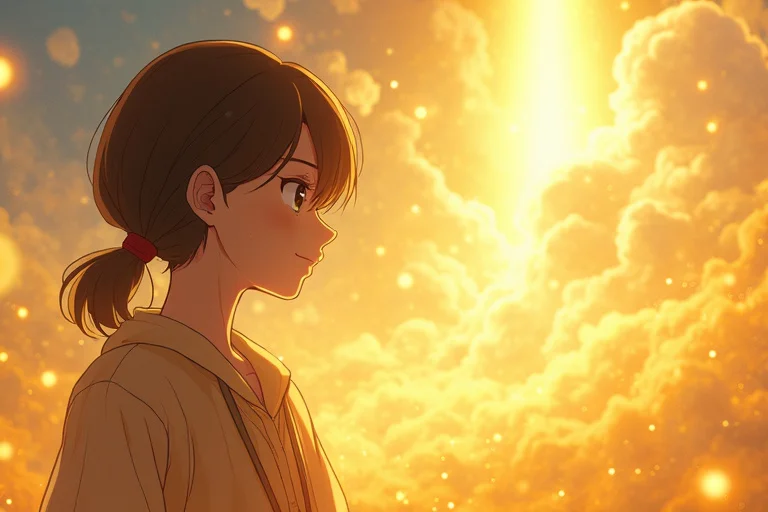第一章 笑ってはいけない公務員
佐藤健太、三十二歳、市民課職員。彼の人生は、一枚の罫線紙のように正確無比、かつ退屈であるべきだった。蛍光灯の白い光が均一に降り注ぐオフィスで、彼は今日も寸分の狂いなく書類の山に判を押していく。カコン、カコン。その無機質な音だけが、彼が生きている証だった。
彼が「笑い」という感情を、まるで致死性のウイルスのように恐れているのには、深刻な理由があった。
健太が心から笑うと、物理法則がねじ曲がるのだ。
それは幼少期に遡る。初めて腹を抱えて笑った時、庭の石灯籠が突然サンバを踊り出した。高校時代、友人のくだらないギャグに吹き出すと、教室の黒板消しが編隊を組んで窓から飛び去っていった。以来、彼は感情に蓋をし、鉄仮面を自らの標準装備と定めた。笑いは、彼の世界におけるバグであり、秩序を破壊するカオスそのものだった。
そんな彼の平穏な日常に、ある日、彩度の高いインクが一滴、ぽとりと落ちた。
「はじめまして! 今日からお世話になります、高橋ひかりです! 趣味は人間観察と、おいしいものを食べることです! よろしくお願いします!」
太陽を無理やり人間の形に押し込んだような女性だった。彼女の笑顔は、オフィス全体の照度を一段階上げたように錯覚させるほど眩しい。健太は、その直視できない光から逃れるように、わずかに会釈だけして書類に視線を戻した。関わってはいけない。心の警報がけたたましく鳴り響く。
しかし、ひかりは健太の隣の席だった。彼女は事あるごとに健太に話しかけてきた。
「佐藤さん、そのネクタイ、すごく素敵ですね! なんだか、こう、真面目なコンブみたいで!」
「……どうも」
「あ、今の、褒め言葉ですよ? 出汁が出そうだなって!」
健太は眉一つ動かさなかったが、内心では「真面目なコンブ」という絶妙な表現に、口角がむず痒くなるのを感じていた。危ない。この女は、天然のスタンドアップコメディアンだ。
その日の午後、事件は起きた。ひかりが持ってきた差し入れのクリームパンを食べようとした課長が、勢い余ってクリームを鼻の頭につけてしまった。それに気づかず、真剣な顔で電話応対を続ける課長。その姿は、威厳と滑稽さの奇跡的なマリアージュだった。
オフィスに忍び笑いが広がる中、健太は必死に耐えていた。見るな、見るな、見るな。だが、隣のひかりが「ぷっ」と吹き出す音が聞こえた瞬間、つられてしまった。
「く……っ」
喉の奥で、小さな笑いが弾けた。
その瞬間だった。健太のデスクに置かれていた小さな観葉植物、パキラの鉢植えが、カタカタと震えだした。そして、おもむろに二本の枝を足のように広げると、軽快なステップを踏み始めたのだ。それは紛れもなく、キレのあるブレイクダンスだった。ウィンドミルからフリーズまで、植物とは思えぬ身体能力でフロアを沸かせるパキラ。
呆然とする職員たち。鼻にクリームをつけたまま固まる課長。唯一、ひかりだけが目をキラキラと輝かせ、小さなパキラに喝采を送っていた。
「すごい……! 佐藤さん、あなた、何者なんですか!?」
健太は、顔面蒼白になりながら、ただ天を仰いだ。こうして、彼の罫線紙のような人生は、ぐちゃぐちゃに丸められてゴミ箱に捨てられることが決定したのだった。
第二章 笑顔の感染力とたい焼きパニック
パキラのブレイクダンス事件以来、高橋ひかりは健太を「未確認面白生命体」としてロックオンした。彼女の執拗なまでの「笑顔誘発作戦」が始まったのだ。朝の挨拶にしょうもない一発ギャグを混ぜ込み、昼休みには変顔の練習に付き合わせようとし、仕事の合間にはネットで見つけた猫の面白動画を執拗に見せてくる。
「佐藤さん、見てください! この猫、飼い主の頭を完璧なリズムで叩いてるんですよ! ドラムの神童かも!」
健太はモニターに背を向け、無心で判を押す。カコン、カコン。だが、耳から入ってくるひかりの実況と、想像力が、彼の鉄壁の防御を少しずつ侵食していく。
「面白いことなんて、一つもありません。仕事の邪魔です」
「えー、でも、佐藤さんが笑うと、世界がもっとハッピーになるじゃないですか! パキラだってあんなに楽しそうだったし!」
ひかりの言葉は、健太の胸に小さな波紋を広げた。ハッピー、か。自分の能力は、これまで破壊と混乱の元凶でしかなかった。だが、彼女の目には、それが「幸福」として映っているらしい。その事実は、健太を戸惑わせた。
そんなある日、市役所の給湯室で、健太はうっかり大笑いしてしまった。原因は、ひかりが真剣な顔で語った「カラスは実は白い鳥だったが、日焼けサロンに通いすぎて黒くなった」という彼女の祖母の迷信だった。あまりの馬鹿馬鹿しさに、こらえきれなかったのだ。
「ぶはっ!」
健太が腹をよじった瞬間、給湯室の隣にあるコピー機が、ガコンガコンと異常な音を立て始めた。そして、排紙口から出てきたのは、A4用紙ではなかった。
湯気の立つ、あんこたっぷりの、たい焼きだった。
一枚、また一枚と、香ばしい匂いをあたりにまき散らしながら、たい焼きが無限に印刷されていく。あっという間に床はたい焼きの海と化した。職員たちが何事かと集まってきて、その光景に目を丸くする。
「うわー! たい焼きだ! しかも焼きたて!」
「なんでコピー機から!?」
パニックになるかと思いきCきや、誰かが「食べてみようぜ」と言い出したのをきっかけに、オフィスは即席のたい焼きパーティー会場と化した。普段は険しい顔の課長まで、「おお、これはうまい」と頬張り、鼻の頭についたあんこをひかりに笑われている。
健太は、たい焼きの山の中で立ち尽くしていた。自分が引き起こしたカオス。だが、そこには悲鳴も怒号もなく、人々の弾けるような笑顔と笑い声があった。ひかりが、あんこのついた口で健太に笑いかける。
「佐藤さん、やりましたね! みんな、すっごく嬉しそうです!」
その屈託のない笑顔を見ていると、胸の奥がじんわりと温かくなるのを感じた。いつもは忌まわしいと思っていた自分の能力が、初めて誰かの喜びにつながった瞬間だった。もしかしたら、この力は、呪いではなく、祝福なのかもしれない。
健太の鉄仮面に、ほんのわずかな亀裂が入り、そこから柔らかな光が漏れ始めた気がした。彼は、足元に転がっていたたい焼きを一つ拾い上げ、恐る恐る口に運んだ。甘いあんこの味が、口いっぱいに広がった。それは、彼が何十年も忘れていた、幸福の味だった。
第三章 悲劇の神は退屈している
健太の能力は、市役所公認の「秘密兵器」となった。ひかりが企画した、寂れかけた商店街を盛り上げるための町おこしイベント「びっくり!にこにこフェスティバル」で、健太はメインアクトとして白羽の矢を立てられたのだ。
「佐藤さんの『笑顔ミラクル』で、商店街に奇跡を起こしましょう!」
ひかりに背中を押され、健太は戸惑いながらも、ステージに立つことを決意した。彼の心には、かすかな期待が芽生えていた。この力で、もっと多くの人を笑顔にできるかもしれない。自分の存在が、誰かの役に立つのかもしれない。
イベント当日。特設ステージに立った健太は、眼下に広がる人々の海を見て、ごくりと唾を飲んだ。ひかりがステージ袖から、力強くガッツポーズを送ってくる。
「さあ、皆さん! これから、この町で一番面白い男、佐藤健太さんが、皆さんを最高の笑顔にする、奇跡のショーが始まります!」
ひかりの紹介を受け、健太はマイクを握った。観客は固唾を飲んで彼を見つめている。健太は、これまでひかりが彼を笑わせるためにやってきた数々のドタバタを思い出し、それを拙いながらも語り始めた。パキラのダンス、無限たい焼き、そして「真面目なコンブ」のくだり。
最初は緊張で声が震えていたが、話しているうちに、自分でもおかしくなってきた。これまで抑圧してきた「面白い」と感じる心が、堰を切ったように溢れ出す。観客からも、くすくすと笑い声が漏れ始め、それはやがて大きな波になっていった。
「あはは……あはははは!」
ついに健太は、生まれて初めて、心の底から、何のてらいもなく大爆笑した。他人のためでも、義務でもない。ただ、この状況が、自分の人生が、おかしくて、愛おしくて、たまらなかったのだ。さあ、どんな奇跡が起きる? 虹色のシャボン玉が空を埋め尽くすか? それとも、商店街の銅像がラップを始めるか?
しかし、何も起こらなかった。
シン、と世界が静まり返った。健太の笑い声だけが、むなしく響く。観客はぽかんとし、ひかりもステージ袖で青ざめている。
その時だった。健太の目の前の空間が、水面のように揺らめいた。そして、そこからゆっくりと、一人の男が姿を現した。古代ギリシャの彫刻のように整った顔立ちをしているが、その表情は、世界のすべての退屈を一身に背負ったかのように、深く、深く、憂鬱に沈んでいた。
「ああ、つまらない。実に、つまらなくなった」
男は、ため息と共にかすれた声で言った。
「誰だ、お前は……」
「私はメリクテス。かつては『悲劇の神』と呼ばれたが、今はただの退屈な傍観者だ」
メリクテスと名乗る男は、宙に浮かんだまま、つまらなそうに健太を見下ろした。
「お前のその力、私が与えたものだ。人間の意図せぬところで起きる滑稽な事象、必死に取り繕う様、それを見て退屈を紛らわしていた。お前は最高のコメディアンだったよ。笑うことを恐れ、苦悩しながら、それでも漏れ出す笑いがカオスを生む。その矛盾こそが、極上のエンターテインメントだった」
健太は、言葉を失った。自分の能力は、祝福などではなかった。高次元の存在の、単なる娯楽。自分は、水槽の中の金魚のように、ただ鑑賞されていただけだったのだ。
「だが」とメリクテスは続けた。「お前は、本当に笑ってしまった。心から、楽しんで。他人のためでも、義務でもなく、自分のために。そうなると、もう予定調和だ。予測可能な幸福ほど、退屈なものはない。だから、その力は返してもらう。ご苦労だった、私の道化」
その言葉を最後に、メリクテスの姿はすうっと消えていった。まるで、最初から何もなかったかのように。
後に残されたのは、能力を失った、ただの真面目な男と、静まり返った観客、そして、ぼろぼろと崩れ落ちていく健太の価値観だけだった。たい焼きの甘い味は、もうどこにもしなかった。
第四章 ただの、つまらない男
世界から音が消えたようだった。健太はステージの中央で立ち尽くし、自分の空っぽになった両手を見つめていた。観客たちの失望と戸惑いの視線が、無数の針となって突き刺さる。もう、自分には何もない。奇跡を起こすことも、誰かを驚かせることもできない。ただの、つまらない、佐藤健太に戻ったのだ。
イベントの失敗は決定的だった。健太は舞台から逃げ出したかった。しかし、足が鉛のように重く、動かない。
その時、マイクにノイズが走った。ステージ袖から、ひかりが駆け寄ってきたのだ。彼女は健太からマイクをひったくると、深呼吸をして、観客に向かって叫んだ。
「奇跡なんて、起きなくたっていいじゃないですか!」
その声は、震えていた。でも、力強かった。
「面白いことが起きなくたって、別にいいです! 私は……私は、さっきの佐藤さんの笑顔が見られただけで、もう十分です! あんなに楽しそうに笑う人を、私は見たことがありませんでした! それだけで、私は今日ここに来て、このイベントをやって、本当によかったって思います!」
ひかりの瞳には、涙が浮かんでいた。彼女の必死の叫びに、静まり返っていた会場が、ざわめき始める。
「そうだな、確かに、兄ちゃんの笑い方、最高だったぜ!」
「なんだか、こっちまで楽しくなったわ」
ぽつり、ぽつりと、観客の中から共感の声が上がり始めた。それはやがて、温かい拍手へと変わっていった。その拍手は、超常現象に向けられたものではない。能力を失った、ただの佐藤健太という一人の男が、心から笑ったことに対して送られた、純粋な称賛だった。
健太は、涙で滲む視界の中で、ひかりの顔を見た。彼女も泣きながら、彼に笑いかけていた。
その瞬間、健太は本当の意味で理解した。人を笑顔にするのは、不思議な力ではない。たい焼きでもなければ、踊るパキラでもない。人の心が、人の心を動かすのだ。自分の笑顔が、ひかりの心を動かし、ひかりの言葉が、観客の心を動かした。それは、悲劇の神の気まぐれな呪いよりも、ずっと確かで、温かい奇跡だった。
数日後。健太とひかりは、いつもの帰り道を並んで歩いていた。市役所には、「イベントはともかく、あんたの笑顔は良かった」という匿名の投書がいくつか届いたらしい。
「私、今度は落語とかやってみませんか、佐藤さん」
「……やめておけ。絶対に向いてない」
「えー、なんでですか! 私、結構いけると思うんですけど。『じゅげむじゅげむ五劫のすりきれ』!」
「それ、暗記パンでもないと無理だろ」
健太は、自分から冗談を言っていることに、少し驚いた。それは、プロの芸人のようには全く面白くなかった。ひかりは「うーん、つまんない!」と言って、大げさに肩をすくめる。
でも、二人は顔を見合わせて、自然と笑い声をこぼした。それは、奇跡を期待する笑いではなく、ただ、共にいることの楽しさから生まれた、ささやかな笑いだった。
その時だった。
健太が、道端に転がっていたごく普通の見慣れた石ころが、ほんの少しだけ、ピクッと動いたような気がした。
それは、風のせいだったかもしれない。あるいは、単なる目の錯覚だったかもしれない。悲劇の神が、ほんの少しだけ力を残していったのか。それとも、本当の笑顔には、神の介入さえ必要としない、自分たちだけのささやかな奇跡を呼び起こす力があるのだろうか。
健太は、もうその答えを追い求めることはなかった。彼はひかりの方を向き、今度はもう少しだけ面白い冗談を言ってみようと、少しだけ口角を上げた。隣で笑う彼女の存在が、どんな超常現象よりも、彼の世界を豊かに彩っている。空はどこまでも青く、世界の退屈さなど、彼らにはもう関係のないことだった。