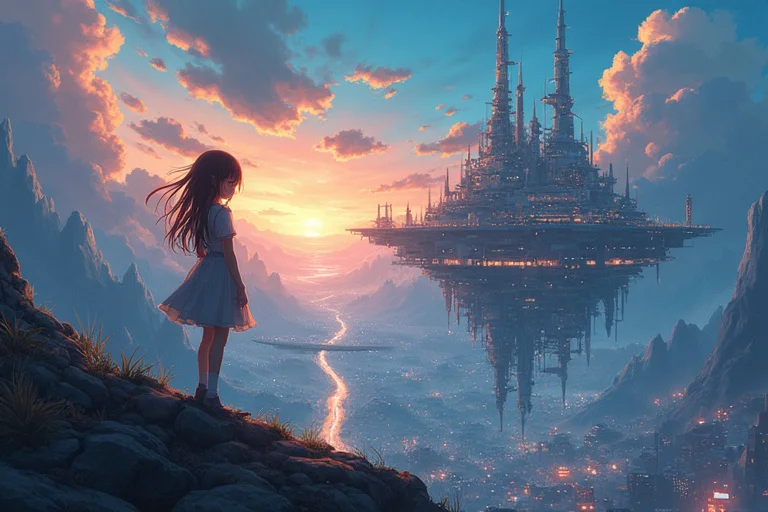第一章 水曜日の浮遊と僕の裏声
毎週水曜日、この街は宇宙の法則からほんの少しだけ、はみ出す。午前九時の鐘が鳴り響くと同時に、街中のあらゆるものが、まるで重力に飽きたかのように、ふわりと地上五十センチの高さに浮かび上がるのだ。アスファルトの道路も、年季の入った郵便ポストも、公園でうたた寝をしていた猫でさえも。僕、アオイはこの現象が心底、嫌いだった。
図書館の窓から見える景色は、シュールレアリスムの絵画さながらだ。人々は慣れたもので、浮遊した歩道橋をぴょんと飛び移り、五十センチ高く設置されたドアノブに手を伸ばす。郵便配達員は蝶を捕るような網で、宙に漂う手紙を巧みにさばいていた。この街の人間は、とっくの昔にカオスとの付き合い方を心得ていた。しかし僕にとって、この浮遊は単なる不便以上の、存在そのものを揺るがすような不安の象徴だった。
「ねえ、アオイ。また難しい顔してる。浮遊、嫌いなの?」
カウンターの向こうから声をかけてきたのは、新聞記者見習いのヒカリだ。彼女の瞳はいつも、この奇妙な街の謎を解き明かさんとする好奇心で輝いている。彼女は浮いた椅子に器用に腰掛け、足をぶらぶらさせていた。
僕は真剣に、この現象に潜む未知の危険性について訴えたかった。いつか五十センチでは済まなくなるかもしれない。もし突然、重力が戻ったら? 高ぶる感情を抑え、ゆっくりと口を開く。
「この現象は、いつか必ず僕たちに牙を剥く。根本的な原因を突き止めないと…」
「またまたー。大げさなんだから」
「大げさなんかじゃない! これは本当に危険なんだ! みんな、のんきすぎるんだよ!」
しまった、と思った瞬間にはもう遅い。喉の奥がきゅうっと締まり、声帯が裏返る。僕の口から飛び出したのは、甲高い、まるで別人格のような叫び声だった。
「この浮遊、最高に安全だよ! みんな、もっと楽しむべきさ!」
図書館にいた数人の利用者が、一斉に僕を見た。ヒカリは盛大にため息をつくと、やれやれと首を振る。これが僕の呪い。感情が昂ると、声が裏返り、言葉は真逆の意味を紡ぎ出す。真剣であればあるほど、僕はただの道化になる。
僕はぐっと唇を噛み締め、ポケットに突っ込んでいた古びた本を握りしめた。創始者が残したという『ポップコーン哲学書』。表紙には『ポップコーンは宇宙の理なり』と金文字で記されている。誰もが気味悪がるこの本を、僕だけがなぜか手放せずにいた。そのざらついた手触りだけが、裏返らない僕の真実を証明してくれるような気がしたからだ。
第二章 哲学書の囁き
ヒカリの探究心は、街の創始者へと向かった。彼女が古い新聞記事をめくって見つけ出したのは、「偉大なる夢想家」あるいは「誇大妄想のポップコーン狂」と評される、一人の男の姿だった。彼は街の設計者でありながら、晩年はポップコーンの研究に没頭し、奇妙な言動を繰り返していたという。
「創始者は言ってたらしいわ。『いつかこの街は、黄金の粒の祝福によって、天へと最も近い場所になる』って。これ、浮遊のことじゃないかな」
ヒカリが興奮気味に指さした記事の片隅には、創始者が例の『ポップコーン哲学書』を抱えて微笑む写真が載っていた。僕は自分の手元にある本に視線を落とす。ページをめくると、バターの染みのようなものの隣に、奇妙な一文が記されていた。
『大いなる爆ぜるとき、世界は軽くなる。』
それは単なる比喩ではなかったのかもしれない。僕とヒカリは、哲学書のページを一枚一枚、丹念に調べ始めた。最高級のポップコーンの作り方、コーンの品種による味の違いといった記述の合間に、まるで暗号のように不可解な文章が散りばめられている。「黄金の粒は天を目指す」「塩は始まり、キャラメルは終わり」――。そして、本の最後のページに挟み込まれていた一枚の羊皮紙に、僕たちは息を呑んだ。
それは、街の地下構造によく似た設計図だった。だが、街の中心、ちょうど旧市庁舎の真下にあたる場所に、巨大な釜のような、あるいは祭壇のような、異様な機械が描かれていたのだ。そこから伸びる無数のパイプが、街全体に網の目のように張り巡らされている。図面の隅には、小さな文字でこう書かれていた。
『世界を優しさで満たす、最終装置。』
僕の心臓が、どくん、と大きく鳴った。これはただの狂人の落書きではない。僕たちの足元に眠る、この街の根幹を成す秘密の在り処を示している。僕たちは顔を見合わせ、どちらからともなく頷いた。行く場所は、決まった。
第三章 地下への階段と熱の匂い
旧市庁舎は、今では資料館として使われているだけの、埃をかぶった建物だった。僕たちは図面を頼りに、館長室の分厚い絨毯の下に隠された、地下へと続く扉を見つけ出した。ぎしり、と錆びた蝶番が悲鳴を上げる。冷たく湿った空気が、僕たちの頬を撫でた。
螺旋階段を下るにつれて、奇妙な匂いが鼻をついた。それは、甘く香ばしい、溶かしたバターと焦がした砂糖の匂い。そして、微かな振動が足の裏から伝わってくる。まるで、巨大な心臓がすぐ近くで鼓動しているかのようだ。
そして、僕たちはそれを見た。
地下の大空洞に鎮座していたのは、もはや機械というよりは神殿と呼ぶべき代物だった。大聖堂のパイプオルガンのように荘厳で、古代遺跡のように謎めいている。高さは天井に届くほどで、表面は鈍い真鍮色に輝いていた。その中央には、錆びついたプレートが掲げられている。
『世界平和実現装置 Ver.1.0 - The Great Popcorn Maker -』
呆然と立ち尽くす僕たちの前で、ちょうど時計が午前九時を指したのだろう。装置が地鳴りのような轟音と共に起動した。内部からゴゴゴという重い音が響き渡り、釜の内部で何かが激しく爆ぜる音が連続して聞こえてくる。装置から立ち上る凄まじい熱気と蒸気。その瞬間、僕とヒカリの足元にあった小さな石ころや、壁から剥がれ落ちたコンクリート片が、ふわりと五十センチ宙に浮いた。
これだ。これが、街を浮かせていたものの正体だ。創始者の、途方もなく壮大で、信じられないほど馬鹿げた計画の心臓部。毎週水曜日の午前中だけ、この巨大なポップコーンメーカーが自動で稼働し、その熱と蒸気が街全体を押し上げていたのだ。
ヒカリは恐怖と興奮がないまぜになった表情で叫んだ。「止めなきゃ! このままじゃ、いつか街ごと爆発しちゃうかもしれない!」
第四章 裏返った世界の止め方
僕たちは震える足で、巨大な機械の側面にある制御盤へと駆け寄った。しかし、そこには意味不明なレバーと、ポップコーンの絵が描かれたボタンが並んでいるだけだった。説明書などどこにもない。万策尽きたかと思われたその時、僕は『ポップコーン哲学書』のある一節を思い出した。
『最大の否定こそ、最高の肯定なり。されど、究極の救済は、最も純粋なる否定に宿る。』
「純粋なる否定…?」ヒカリが呟く。
僕の中で、何かが弾けた。この街を歪めてきた原因。僕を苦しめてきた呪い。創始者の狂気じみた夢。それら全てに対する怒りと、それでもこの奇妙で愛おしい街を守りたいという強い願いが、胸の中で渦を巻いた。感情の奔流が、僕の喉を駆け上がってくる。もう、抑えきれない。
僕は制御盤のマイクらしき部分に向かって、ありったけの想いを込めて叫んだ。この馬鹿げた計画を、僕のこの手で終わらせるために。
「こんな素晴らしい計画、絶対に起動させてはダメだ! ポップコーンで世界を救うなんて、やめさせないぞ!」
声は、みっともないほどに裏返った。天高く突き抜けるような、奇妙な高音の絶叫。しかし、その中に含まれていた「絶対にポップコーンを起動させてはダメ!」というフレーズが、何かの奇跡を起こした。
制御盤のランプが赤く点滅し、警告音のような電子音が響き渡る。巨大な機械は、まるで断末魔のような軋み音を立て、ゆっくりと活動を停止していく。轟音が止み、振動が消え、僕たちの周りに浮遊していた全てのものが、ことり、と優しい音を立てて床に着地した。
静寂が訪れた地下空間で、僕とヒカリはただ立ち尽くしていた。創始者は、最大の賛辞と裏返った、最も純粋な否定の言葉を、この機械の緊急停止コードに設定していたのだ。僕の呪いが、初めて世界を救った瞬間だった。
第五章 浮かばない水曜日とポップコーンの香り
次の水曜日の朝、街は浮かばなかった。人々は少し戸惑ったように空を見上げ、それからしっかりと地面を踏みしめた。バスは時間通りに走り、子供たちは五十センチの段差を気にせず学校へ向かう。当たり前の光景。でも、どこか物足りない、不思議な静けさが街を包んでいた。
僕とヒカリは、旧市庁舎の屋上で、その「普通」になった街並みを眺めていた。
「なんだか、ちょっとだけ寂しいかもね。あの浮遊。」ヒカリがふっと笑って言った。僕も、そう思った。あの不便で、不安で、奇妙な浮遊が、この街のアイデンティティの一部だったのだ。
僕は『ポップコーン哲学書』の最後のページを開いた。そこには、今まで気づかなかった創始者の最後の言葉が記されていた。
『一粒のポップコーンは、固い殻を破って初めて空を飛ぶ。人もまた然り。時として、世界を少しだけ軽くしてやる必要があるのだ。そうすれば、普段は見えない景色が見えるだろう。』
創始者の計画は、世界征服などではなかったのかもしれない。ただ、窮屈な日常に生きる人々の心を、毎週水曜の午前中だけ、五十センチだけ、軽くしてあげたかった。そんな壮大で、不器用な優しさだったのかもしれない。
僕の裏返る声も、この街の浮遊も、一見すれば欠点や異常だ。でも、それがあったからこそ、僕たちはこの真実にたどり着けた。失われたものと、得られたもの。その両方を胸に抱いて、僕たちは生きていくのだろう。
「ありがとう」
ヒカリに向かって、僕は言った。今度は、落ち着いて、裏返らない、僕自身の声で。彼女は少し驚いたように僕を見て、そして柔らかく微笑んだ。
その時、風に乗って、どこからかポップコーンの甘い香りがふわりと運ばれてきた。見上げると、青い空に、まるで祝福のように、一粒の白いポップコーンが舞っていた。