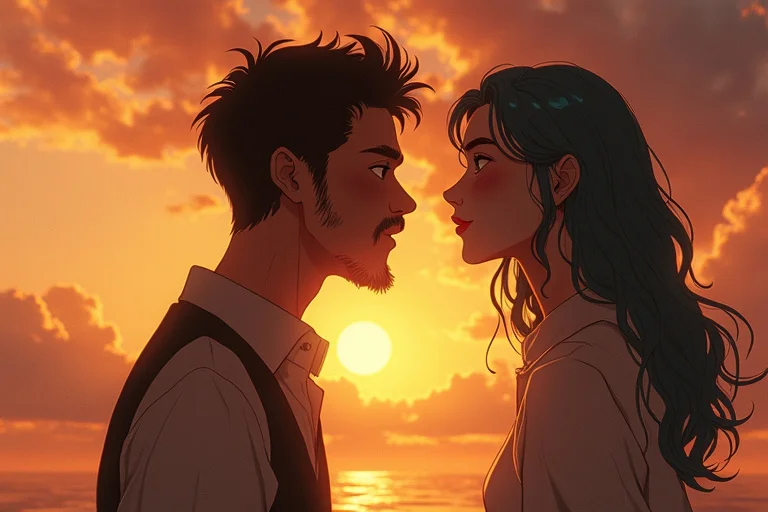第一章 土砂降りのツッコミ
「──というわけで、僕のじいちゃん、最期の言葉が『Wi-Fiのパスワード』だったんですよ!」
相方の風巻翔(かざまき しょう)が渾身のボケを放った瞬間、俺、雨宮晴人(あめみや はると)は背筋に氷を流し込まれたような悪寒を覚えた。シン、と静まり返る地下のライブハウス。湿度を含んだ重い沈黙が、まるで濡れた毛布のように客席を覆っていく。スベった。それも、観測史上最大級に。
「いや、どんだけ現代っ子な逝き方なんだよ!」
俺は、喉から絞り出すようにツッコミを入れた。その刹那、ゴロゴロゴロ…!と、地鳴りのような雷鳴が劇場の天井を揺らした。客席の数人が、びくりと肩を震わせ、不安げに天井を見上げる。やめてくれ。俺の心臓と、この建物の耐久年数のために。
俺には秘密がある。俺の感情は、どういうわけか周囲の天気に直結するのだ。嬉しいと快晴、悲しいとしとしと雨、そして、ウケると一点の曇りもない青空が広がる。逆に、今みたいにスベると──。
ザアアアアアアアッ!
窓もない地下のライブハウスに、まるで滝壺にいるかのような轟音が響き渡った。ゲリラ豪雨だ。階段の隙間から、濁流が滝のように流れ込み始める。客席から「うわっ!」「浸水してる!」という悲鳴が上がり、もはや誰も俺たちの漫才など見ていなかった。
ライブは強制終了。びしょ濡れになった客が恨みがましい視線を俺たちに投げつけながら去っていく。オーナーの雷親父が、文字通りカミナリを落とすために、鬼の形相で仁王立ちしていた。
「雨宮!てめえ、またやりやがったな!お前が舞台に立つたびに豪雨ってどういう呪いだ!『ウェザーリポート』じゃねえ、『ゲリラ豪雨警報』に改名しろ!」
「す、すみません…」
「次スベったら、永久出禁だ!分かったな!」
楽屋に戻ると、相方の翔が呑気にタオルで髪を拭いていた。
「いやー、今日の客、ノリ悪かったなあ。でも晴人のツッコミ、雷鳴とシンクロしてて新しい演出かと思ったぜ!」
「あれは演出じゃねえ、現実だ…」
こいつは俺の体質のことを知らない。ただの極度の「雨男」だと思っている。だからこそ、純粋に面白いことだけを追求できる。俺は、いつだって災害の恐怖と隣り合わせなのに。
感情を殺せ。心を無にしろ。そう自分に言い聞かせなければ、この街は水没する。芸人として致命的な自己暗示をかけながら、俺はいつも客席の片隅に目をやった。
最前列の、指定席。そこに今日も彼女は座っていた。虹村しずく。腰まで伸びる黒髪に、人形のように整った顔立ち。彼女だけは、どんな豪雨の中でも、傘もささずにじっと俺たちの舞台を見つめている。そして、一度も笑ったことがない。その無表情な瞳が、まるで俺の才能の無さを告げているようで、胸がちくりと痛んだ。俺の心に、冷たい霧雨が降り始める。外の雨は、まだ止みそうになかった。
第二章 快晴のボケ、時々、霧
「なあ晴人、次のネタ、これでいこうぜ!」
オンボロアパートの一室。翔が自信満々に差し出したネタ帳には、『AI搭載の炊飯器に人生相談する男』と書かれていた。
「『お米の気持ちが分かります』とか言って、最終的に炊飯器に『とりあえず、まず君が炊かれろ』って論破されるんだ。どうだ、画期的だろ!」
あまりのバカバカしさに、俺は思わず「フッ」と息を漏らした。その瞬間、分厚い雲に覆われていた窓の外が、パッと明るくなる。眩しいほどの陽光が畳の上に四角い光の絨毯を広げた。
「お、晴れたな!やっぱ俺のネタは太陽も祝福するわけだ!」
翔は無邪気に笑うが、俺は慌てて真顔に戻った。危ない。これ以上感情を揺さぶられてはならない。俺が本気で笑ったら、この辺り一帯が記録的な猛暑に見舞われるかもしれないのだ。
俺は感情を抑圧するほど、ネタはつまらなくなった。ツッコミは精彩を欠き、声は上ずり、まるで天気予報を読み上げるアナウンサーのように平板になった。翔の天真爛漫なボケが、俺という分厚い雲に遮られて、観客まで届かない。
出禁がかかった次のライブまであと三日。焦りだけが募り、俺の頭上には常に灰色の雲が停滞していた。気分転換に公園のベンチでネタ帳を眺めていると、ふと、隣に誰かが座る気配がした。シャンプーの優しい香り。見れば、虹村しずくだった。
「あ…」
心臓が跳ね、公園の上空に薄く霧がかかり始める。なんでこの人がここに。
彼女は俺のネタ帳を覗き込むと、小さな声で言った。
「あの…いつも見てます」
「あ、ありがとうございます…笑ってもらえたこと、一度もないですけど」
皮肉が口をついて出た。すると彼女は、少しだけ眉をひそめ、まっすぐに俺の目を見た。
「あなたの天気、嫌いじゃないです」
「…は?」
天気?彼女は、俺の体質を知っているとでもいうのか?
「雨が降るのも、雷が鳴るのも、全部、あなたが本気だからですよね。あなたのツッコミは、いつも一生懸命で…だから、見てしまうんです」
彼女の言葉は、乾いた俺の心に染み込む夕立のようだった。今まで呪いだと思っていたこの体質を、肯定されたのは初めてだった。
「でも…」と彼女は続けた。「最近のあなたは、ただの曇り空です。嵐のほうが、ずっと魅力的でした」
そう言うと、彼女は静かに立ち去っていった。
残された俺の心は、晴れと霧と雷雲が入り乱れる、異常気象のようになっていた。嵐のほうが、魅力的?彼女を笑わせたい。心の底から、そう思った。たとえ、この街に観測史上最大の嵐を呼ぶことになったとしても。その思いが、俺の中で初めて恐怖を上回った瞬間だった。
第三章 嵐の夜と、七色の告白
運命のライブ当日。俺が舞台袖に立っただけで、ライブハウス周辺には視界数メートルの濃霧が立ち込めていた。
「よーし晴人、今日は絶対ウケるぞ!」
翔の能天気な声が、霧の向こうから聞こえるようだ。
幕が上がる。最前列には、いつものように虹村しずくが座っていた。彼女の瞳が、俺をまっすぐに射抜いている。
序盤のネタは、意外にもウケた。客席の笑い声が波のように押し寄せるたび、俺の心は高揚し、外では霧が晴れていくのを感じた。いける。今日はいけるかもしれない。
そして、クライマックス。翔が繰り出す『AI炊飯器』の渾身のボケ。練習では何度も笑ってしまった、必殺のフレーズ。だが、本番のプレッシャーが、俺の喉を締め付けた。ツッコミのタイミングが、コンマ数秒、ずれた。
そのコンマ数秒が、すべてを台無しにした。
客席は、水を打ったように静まり返る。まずい。そう思った瞬間、ピシャアァァン!と、鼓膜を突き破るような落雷の音が響き渡り、同時に、劇場内のすべての照明が消えた。
停電。
完全な暗闇と、耳をつんざく豪雨の音。客席はパニックに陥り、悲鳴と怒号が渦巻いた。
「もうダメだ…」
俺は舞台の中央で立ち尽くした。またやってしまった。俺は、人を笑わせるどころか、不幸にしかできない。芸人なんて、目指すべきじゃなかったんだ。自己嫌悪の嵐が心に吹き荒れ、それに呼応するように、外の暴風雨はさらに勢いを増していく。建物の軋む音が、俺の心を砕く音と重なった。
その、絶望の闇の底で。
ふわり、と。最前列で、淡い光が灯った。七色の、柔らかな光。それは、虹村しずくから発せられていた。彼女が、必死にこらえていた笑いを、ついに解き放ったのだ。
「くすっ…あははっ!」
彼女が声を立てて笑うと、その周りに鮮やかな虹のアーチがかかった。
暗闇の中、彼女はすっくと立ち上がった。虹の光に照らされた彼女の顔は、今まで見たことがないほど輝いていた。
「ごめんなさい、雨宮さん。ずっと、我慢してたんです」
彼女の声は、嵐の音の中でも不思議と鮮明に聞こえた。
「あなたのネタ、本当はいつもすごく面白くて、笑うのを堪えるのが大変だった。でも、私が本気で笑うと、こうして虹が出ちゃうから…あなたの天気を邪魔しちゃうと思って…!」
彼女の告白に、俺は言葉を失った。邪魔?何を言っているんだ。
虹の光が、ふわりと客席全体に広がっていく。すると、信じられないことが起きた。あれほど激しく吹き荒れていた嵐が、嘘のように静まっていく。窓のない地下室に、雨上がりの澄んだ空気が流れ込んでくる。
バチン、と音を立てて、照明が復旧した。虹の光に照らされた幻想的な空間で、観客たちは皆、あっけにとられて目の前の光景を見つめている。
俺は、目の前の奇跡と、涙を浮かべて笑う彼女を見て、ようやくすべてを理解した。俺の嵐を鎮められるのは、彼女の虹だけだったんだ。
第四章 君と見る、スタンディングオベーションの虹
嵐は去った。けれど、舞台にはまだ、虹が架かっている。まるで、この瞬間のために用意された、世界で一番美しいスポットライトのようだった。
俺はマイクを握り直し、相方の翔ではなく、虹の根元に立つ彼女に向かって、アドリブでツッコミを入れた。
「いや、本気で笑うと虹が出るって…どんだけファンタジーな体質だよ!俺のゲリラ豪雨といいコンビすぎるだろ!」
そのツッコミに、しずくが心の底から「あははは!」と笑った。彼女の笑い声は、まるで鐘の音のように美しく響き渡り、つられた客席から、堰を切ったような大爆笑が巻き起こった。会場の空気が一変し、まるで真夏のような熱気に包まれる。しずくの虹は、人々の笑い声を浴びて、さらにその輝きを増した。
その後の俺たちの漫才は、もはや漫才ではなかった。嵐と虹の共同作業。俺が緊張で霧を発生させれば、彼女がくすりと笑って虹の光で照らし出す。俺がスベって土砂降りを降らせれば、彼女が涙を流して笑い、大きな虹の傘で会場を守ってくれる。それは、誰も見たことのない、奇跡のエンターテイメントだった。
ライブは、スタンディングオベーションの中で幕を閉じた。オーナーは「まあ、こういう天候操作系の演出なら、うちの新しい名物にしてもいい」と、目尻の涙を拭いながら出禁を撤回してくれた。
後日。俺としずく、そして事情をようやく理解した翔の三人は、公園のベンチに座っていた。俺の心は晴れやかで、空には一点の曇りもない。
「まさか、しずくちゃんがそんな秘密兵器だったとはなあ」と翔が笑う。
俺は、隣に座るしずくの横顔を見つめた。
「俺、ずっと自分のこの体質が呪いだと思ってた。人を不幸にするだけの、いらない力だって」
俺は空を見上げた。どこまでも青い、完璧な空。
「でも、やっと分かった気がする。俺の天気は、呪いじゃなかった。君っていう虹に出会うための、壮大な前フリだったんだな」
俺の言葉に、しずくははにかんで、頬を赤らめた。すると、彼女の足元に、日差しを浴びてキラキラと輝く、小さな虹が咲いた。
これからも俺の人生は、きっと雨が降ったり、嵐が来たりするだろう。でも、もう怖くはない。どんな悪天候だって、君が笑ってくれれば、そこには必ず虹が架かるのだから。人生は天気とよく似ている。そして俺たちの未来は、きっと、快晴のち、虹だ。