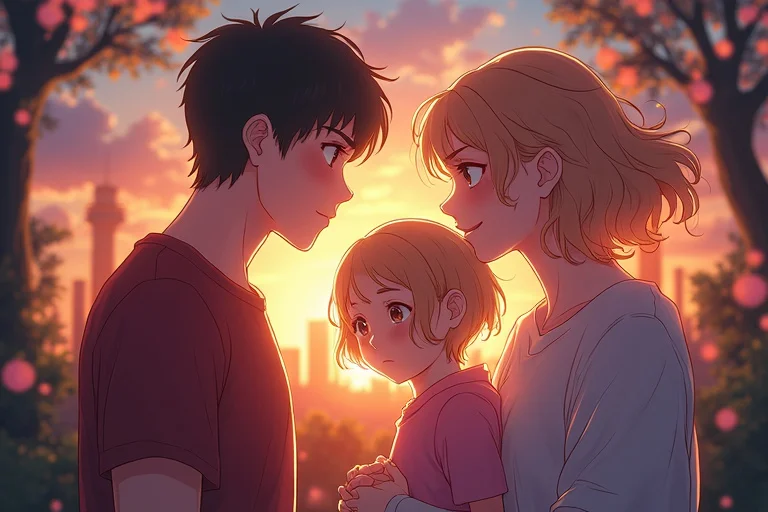第一章 不可解な日常の幕開け
吉田純一、35歳。彼の人生は、まるで丁寧に整えられた盆栽のようだった。変化を嫌い、日々のルーティンを愛する。朝は七時ちょうどに目覚ましが鳴り、決まってトーストと目玉焼き、そしてインスタントコーヒー。通勤電車はいつも同じ車両の、いつも同じ場所に立つ。彼の辞書に「サプライズ」という言葉は、存在しなかったはずだ。しかし、その平和な盆栽に、ある朝、突如として竜巻が吹き荒れた。
その日、純一がいつものようにトーストを焼き、バターを塗ろうとした、その刹那だった。トーストが、まるで意思を持ったかのように、彼の指の間をすり抜け、宙を舞い始めたのだ。純一は呆然とそれを見上げた。きつね色のトーストは、ゆっくりと反時計回りに回転しながら、彼の頭上五メートルほどの位置で静止した。そして、まるで目に見えない手が作業しているかのように、スプーンに乗ったバターが均等に塗られ始めたのだ。バターが塗り終わると、トーストは再び重力に従い、皿の上に「ふわっ」と着地した。焦げ一つなく、完璧な焼き加減と塗り加減。純一は口を開けたまま、それが夢なのか現実なのか判別できなかった。彼の妻、美香は、その光景を横目でちらりと見ると、「あら、今日は空中サービスなの?便利ね」と全く動じることなく、涼しい顔でコーヒーを啜っている。純一は我が目を疑った。美香はいつも通りの反応だった。あるいは、いつも通り「過ぎる」反応だった。
その日から、彼の日常は一変した。通勤電車では、純一が乗り込んだ途端、車内のすべての乗客が一斉に彼の座席を巡って無声の椅子取りゲームを始め、最終的に純一が座ろうとした瞬間に座席が彼の頭上で折り畳まれ、彼は宙に浮いた格好になった。会議中、彼が重要なプレゼンテーションの締めくくりに入ろうとすると、彼の口から出るはずの言葉が「にゃーん」「わんわん」「ぴよぴよ」といった動物の鳴き声に置き換わってしまう。同僚たちは吹き出し、上司は「吉田、疲れているのか?面白いじゃないか!」と腹を抱えて笑った。誰も、真剣に心配する者も、説明を求める者もいなかった。皆、純一が巻き込まれる奇妙な出来事を、まるでそれが当然であるかのように、ただ面白がっているだけだった。
純一の困惑は募るばかりだった。鏡の中の自分は、相変わらず冴えない中年の男だが、その背後には見えないスポットライトが当たっているかのような、奇妙な明るさを感じ始めた。彼は自分が「面白い」と評されることに、居心地の悪さと、そしてわずかな恐怖を感じていた。一体何が起こっているのか。彼の世界は、突然、理由も脈絡もなく、誰かに仕組まれた壮大なコメディ劇と化してしまったかのようだった。
第二章 迷走する純一とエスカレートする「コメディ」
純一は原因を探るべく、奔走した。まずは美香に問い詰めたが、「純ちゃん、最近変よ。疲れてるんじゃない?でも、見てて飽きないからいいけどね」と、まるで彼が単なる娯楽を提供しているかのような口ぶりだった。会社の上司や同僚、行きつけの定食屋の主人、さらにはコンビニの店員まで、純一の周囲の人々は皆、彼の身に起こる不可解な現象を、何の疑問も抱かず、むしろ楽しんでいるかのようだった。
ある日、純一がオフィスで書類を整理していると、引き出しから突如、生きたカニが飛び出し、彼の鼻を挟んだ。純一は「ぐわっ!」と叫び、その場に崩れ落ちた。カニは素早く彼のネクタイに挟まり、ゆらゆらと揺れる。同僚たちは、その光景を見て机を叩いて大爆笑した。隣の席の先輩社員は、「吉田、カニにまで好かれるとはな!お前、まさか海の男だったのか!?」と涙を流しながら笑っていた。純一はもはや、この現実がどこまでが現実で、どこからが狂気なのか判別できなくなっていた。
彼はインターネットで「日常 奇妙な出来事」「自分だけおかしい」といったキーワードで検索したが、ヒットするのは心霊現象や統合失調症に関する記事ばかりだった。彼は自分に何らかの精神的な病があるのではないかと疑い、病院を予約した。しかし、診察室に入った途端、純一の椅子が突如としてロッキングチェアに変形し、彼が座ると同時に猛スピードで揺れ始めた。医師は驚きもせず、「吉田さん、診察室でリラックスしすぎじゃないですかね?まぁ、そういうユニークな方もいらっしゃいますから」と微笑みながら、彼の症状をまるでギャグのように受け流した。純一は、自分の人生が、もはや個人の問題ではなく、何か巨大な、見えない力によって動かされていると悟り始めた。
夜、純一は自室で一人、深く考え込んだ。天井のシミが、彼の目には嘲笑うピエロの顔に見えた。自分は、この世界の登場人物に過ぎないのか?それも、滑稽な役回りを与えられた、ただの道化なのか?彼がそう考えた途端、部屋の隅に置かれた観葉植物の鉢から、小さなマイクが「ぐいーん」と伸びてきた。マイクは純一の方を向くと、静かに光を放ち始めた。その光は、純一の全身をスキャンするかのようにゆっくりと上下した。純一は息を呑んだ。この光景は、これまでで最も直接的で、そして恐ろしい「仕掛け」だった。彼は、自分の人生が、誰かの「見世物」になっているのではないか、という漠然とした疑念が、確信に変わり始めたのを感じた。
第三章 銀河の視聴者と明かされた真実
純一は、あのマイク状の光景以来、自分のアパートの部屋を徹底的に調べ始めた。壁の裏、床下、天井裏。どこかにおかしな仕掛けがあるのではないか、と。そして、彼はついに発見した。寝室の壁、長年かけて壁紙が剥がれかかっていた部分の奥に、金属製の小さな蓋が隠されていたのだ。蓋を開けると、そこには、手のひらサイズの奇妙な機械が埋め込まれていた。それは小さなモニターと、いくつかボタンが並んだ装置だった。モニターには、純一には理解できない記号や、奇妙な文字が流れている。そして、画面の片隅には、見慣れた光景が映し出されていた。
それは、純一自身だった。
純一が昨晩、天井のシミをピエロの顔に見立てていた時の、あの深刻な表情が映し出されている。そして、その映像の下には、異星の文字で「爆笑!地球人、自己存在の危機に直面!最高に笑えるリアクション!」といったテロップが流れている。画面の端には、さらに驚くべき情報があった。「視聴率:98.7%」「銀河コメディ・チャンネル独占配信中」という文字と、無数のカラフルな丸い点が、高評価を示すかのように点滅していた。
純一の脳裏に、これまでの不可解な出来事が走馬灯のように駆け巡った。空中を舞うトースト、椅子取りゲーム、動物の鳴き声、そしてカニ……。すべては、この「銀河コメディ・チャンネル」なるものの視聴者を笑わせるために仕組まれた、壮大なコメディだったのだ。自分は、地球という名のセットで、宇宙規模の視聴者に向けて、毎日ひたすら「面白い」リアクションを提供し続ける「役者」に過ぎなかったのだ。
純一は膝から崩れ落ちた。彼の人生は、彼自身の選択でも、努力でも、失敗でもなく、全てが誰かの「シナリオ」に沿って進行する、ただのエンターテイメントだった。彼の存在意義は、「笑い」の消費のため。彼の尊厳は、宇宙の彼方から見下ろす異星人の娯楽のために踏みにじられていたのだ。これまで信じてきた「自分」という存在が、音を立てて崩れ去った。絶望、怒り、そして虚無感が純一の心を支配した。彼は、自分の人生を、ただの「コメディ」として消費されていることに、言いようのない無力感を覚えた。この世に、真実などなかった。全てが、笑いのための演出だったのだ。
第四章 最高のコメディアン、吉田純一
数日間、純一は放心状態だった。会社も休んだ。妻の美香は心配していたが、純一は真実を話すことなどできなかった。いや、話したところで、美香もまた、この壮大なコメディの共演者の一人に過ぎないのかもしれない、と疑うようになっていた。彼の目に映る世界は、全てが薄っぺらいハリボテのように見えた。
しかし、やがて彼の心に、諦めとは異なる、奇妙な感情が芽生え始めた。「どうせ見世物ならば、最高の見世物になってやる」。絶望の底から這い上がった純一は、そう決意した。彼は、自らの人生を「演じる」ことに意味を見出そうとしたのだ。受動的に「笑われる」のではなく、能動的に「笑わせる」側になってやろう。宇宙の視聴者よ、これまでの「吉田純一」はもういない。今日からお前たちの前には、最高のエンターテイナーが立つ。
翌朝、純一は目覚まし時計が鳴る前に目を覚ました。そして、わざと目覚まし時計を叩き割った。美香が驚いて振り向くと、純一は満面の笑みで言った。「今日は、僕が君のために朝食を作るよ!宇宙一のオムレツをね!」美香は「あら、珍しい」と目を丸くしたが、その顔にはどこか楽しそうな笑みが浮かんでいた。
純一の「コメディ」は、そこから始まった。通勤電車では、わざと変な踊りをしながら乗り込み、乗客を巻き込んでウェーブをさせた。会議では、プレゼンの最中に突然、スーツを脱ぎ捨ててレオタード姿になり、謎の歌を熱唱した(もちろん、歌声は動物の鳴き声だったが)。上司は怒鳴るどころか、「吉田、やるな!その発想はなかったぞ!」と爆笑した。
最初はぎこちなく、ただ滑稽なだけだった彼の行動は、次第に洗練されていった。彼は自分の人生が「コメディ・チャンネル」として放送されていることを逆手に取り、見えない視聴者の期待を読み、時には裏切り、時には予想を超える「笑い」を仕掛けるようになった。彼は、自分の人生という舞台で、最高の脚本家であり、最高の演出家であり、そして最高の主演役者となったのだ。
彼の周りの人々も変わっていった。純一の「コメディ」は、彼らを巻き込み、日常の退屈さから解放し、笑顔にしていった。美香は、毎朝純一がどんな「ネタ」を仕掛けてくるか、楽しみにするようになった。会社の同僚たちは、純一の「演出」に協力するようになり、彼の周囲は、まるで本当にコメディドラマの撮影現場のような活気に満ちていった。
ある日、純一は例のモニターを再び開いた。画面には、彼がオフィスで繰り広げた最新のコメディが映し出されていた。視聴率は99.9%。そして、異星の文字で「伝説のコメディアン爆誕!地球人、まさかの進化!」「視聴者参加型コメディへ昇華!」というメッセージが流れていた。そして、画面の隅には、純一の知る日本語で小さな文字が書かれていた。「純一よ、お前は気付いたな。世界は、お前の想像力でどこまでも面白くなる。このチャンネルは、お前自身が、お前の人生の主役になるための、壮大な仕掛けだったのだ。」
純一はモニターから目を離し、窓の外を眺めた。彼の人生は、依然としてハチャメチャだ。だが、もう、彼は一人でそれに立ち向かっていたわけではない。彼の「コメディ」は、周囲の人々を巻き込み、彼らの日常にも色を添えている。そして何よりも、彼自身が、自分の人生を心から楽しんでいる。世界は、変わっていなかった。変わったのは、純一の視点だった。彼は「笑われる」ことから「笑わせる」喜びを知り、自分の人生を、自らの手で最高のコメディに変えていったのだ。銀河の果ての視聴者が今も彼の人生を観ているかどうかは分からない。だが、純一にとっては、もはやそれが重要ではなかった。彼の舞台は、今この瞬間も、彼の目の前に広がっているのだから。